古(いにしえ)の身体技法をヒントに新しい介護技術を提案する
古武術介護入門kobujutsukaigo-nyumon
【第3回】
原理その1「揺らしとシンクロ」
岡田 慎一郎(介護福祉士・介護支援専門員)(前回よりつづく)
今回から,実際に私が工夫している介護技術を1つひとつご紹介し,それを通して古武術的な身体の使い方を体感しながら,その原理を考えていきたいと思います。といっても,最初はそれほど難しいことはやりません。ただし,見た目の単純さ以上に,身体の使い方や感じ方にかかわる,重要なヒントがたくさん含まれた技術です。
波乗り感覚で省エネ介護!?
今回ご紹介する原理は「揺らしとシンクロ」。まずは,「椅子からの立ち上がり介助」をやってみましょう。脚力が弱った方の椅子からの立ち上がりをお手伝いするわけですが,やってみると意外に難しいものです。単純に立ち上がらせようとすると,被介護者の腰が椅子に残ってしまうことも少なくありません。介護者,被介護者の双方に身体的な負担がかかってしまいます。図1をご覧ください。一見,ただ肩に手を添えて立ち上がりを手伝っているだけで,特別なことは何もないようです。しかし,実は以下のような工夫を行っています。
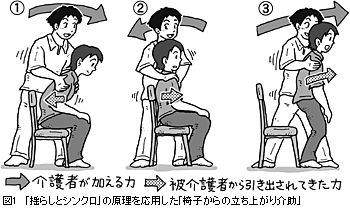
1)介護者は被介護者の横に立ち,腋の下に手を添え,もう片方は肩に添える。
2)前に軽く揺すり被介護者の反応を見る(図1-(1))。
3)被介護者がバランスを戻そうと後方に身体を倒してきたら,その動きよりも少しだけ速く,さらに後方に被介護者の身体を引く。うまくタイミングが合うと,被介護者は自然に,前方にバランスをとろうとする(図1-(2))。
4)被介護者が前方にバランスをとろうとしたところを,タイミングよく軽く支え,一緒に立ち上がると,互いに抵抗感なく立ち上がることができる(図1-(3))。
文章で書くと複雑ですが,例えて言えばサーフィンのようなものです。「揺らし」によって相手の身体に起こった「波」に乗ることで,わざわざ筋力を使わなくとも,楽に立ち上がり介護ができます。うまくいくと,双方ともにふわりと浮き上がったような感覚が味わえます。まさに,筋力に頼らない省エネ介護です。
「でも,これって現場では通用しないんじゃない?」という声もあるでしょう。
確かに,この方法はある程度ご自分で立ち上がりが可能な程度の脚力の弱さという,限定条件の中でしか通用しません。しかし,相手の動きにシンクロ(同調)することにより「チカラ」を引き出すという原理そのものは,他の技術にも応用が可能です。次にご紹介する「武術遊び」と合わせて,職場の仲間と遊び感覚で練習されると,きっと現場で使えるヒントに出会えると思います。
武術遊び「引き落とし」
図2をご覧ください。これは現場では絶対にしてはいけないことですね(苦笑)。でも,あえて介護とは逆をやってみることで,見えてくることもあります。休憩時間に仲間とゲーム感覚でやってみてください。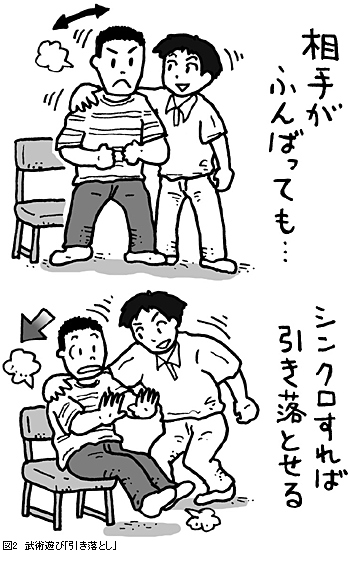 |
| (1)相手の肩に手を置く。相手には足を踏ん張ってもらい,十分に耐えてもらう(上)。 (2)相手の微妙な揺れにシンクロしながら椅子へと引き落とす(下)。 |
体格が同じくらいであれば,片手で倒そうとしても,普通なら我慢されてしまいます。ところが,相手の揺れにうまくシンクロできると,ほとんど力まずに,簡単に引き落とすことが可能なのです。図2-(1)で,あえて相手に踏ん張ってもらっているのもこの遊びのポイント。普通だと,力を入れたほうが倒れにくそうなのですが,この場合は,相手が力んで,踏ん張っていたほうが簡単に決まります。どうしてでしょう?
人間は常に揺れている
眼を閉じて立っていると,自分が揺れていることがわかります。そう,人間は止まっているつもりでも,実はほんの少し揺れているのです。人間は揺れることによりバランスを絶えず微調整しています。引き倒されそうになった時や,転びそうになった時にうまくバランスが取れるのも,この「揺れ」があるおかげです。力んで踏ん張ってもらったほうが「引き落とし」が簡単に決まるのは,力を入れることによって,この「揺れ」が制限され,コントロールしやすくなるからです。仮に相手がマネキン人形だったら「引き落とし」なんて,簡単ですよね。それは,マネキンには人間のような揺れがないからです。
現在の高層ビルの地震対策は,ビルそのものが揺れることで,地震の振動を吸収する仕組みになっています。昔はがっちりと土台を固めて地震に耐えようとしていたのですが,それでは振動をもろに受けて倒れてしまう。揺れているほうが,踏ん張っているよりも強いのです。人間にも同じようなことが言えるのではないか,と思います(図3)。
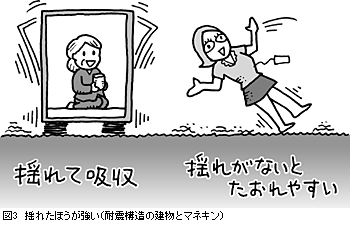
「椅子からの立ち上がり介助」や「引き落とし」の技術は,こうした人間の「揺れ」を上手に利用した技術です。相手のわずかな揺れを感じ,それにシンクロすることによって,楽に立ち上がらせたり,逆に引き落としたりすることができるということです。
もちろん,相手の揺れを利用するわけですから,うまくいけば,マネキン相手よりも楽に,相手を引き落とすことができます。また,「椅子からの立ち上がり介助」では,初めに相手を揺らして反応を引き出していましたが,相手の揺れを感じることができれば,こちらから揺らすことなく,相手の揺れにシンクロするだけで立ち上がらせることも可能です。この場合,外から見ると,触れただけで立ち上がらせているように見えます(かなり難しいですが)。
「社交ダンス」からの発想
以前,武術の考え方を取り入れている社交ダンス講師の方と交流させてもらった時のことです。その方は,お互いの手を合わせると「手を動かし,押したり,引いたり,自由に動いてください」と言いました。合わせた手を思いのまま動かしてみたところ,その方は,まるでキャスターがついているかのようにその動きを増幅し,ダンスにして表現してくれたのです。社交ダンスというと,手取り足取り型を教えるものだと思っていたのですが,その方はまるで違う発想でアプローチしていました。相手の動きを増幅し,表現する。介護にも通じる発想だと思いました。
介護者側が一方的に「してあげる」のではなく,相手の反応を引き出し,それを発展した形でお手伝いする。今回の椅子からの立ち上がりも,ただ相手を揺さぶって立ち上がるだけだと,相手には「立たされた」という受身の感覚しか残りません。しかし,この社交ダンスのように,自分の動きが相手によって増幅され,立ち上がることができた,という感覚を持てれば,被介護者に受身ではない,主体としての自尊心が生まれるのではないでしょうか。
被介護者に動きの「起源」を担ってもらい,私たちはそれを最大限に大きな波となるように表現する。それは,言葉ではない,身体を通してのコミュニケーションといえるでしょう。
推理小説を読むように!?
「揺らしとシンクロの原理」は,これでおしまいというわけではありません。次回以降も登場するさまざまな原理と有機的に組み合わさって初めて大きな効果を発揮します。ちょうど,推理小説で,何気ない小道具があとあと事件解決の鍵となるような展開と似ています。ですから,連載が進むにつれて,実はそうだったのか! と気がつくことが多くなると思います。推理小説を読む感覚で,頭と身体で楽しんでいきましょう!イラスト:海谷 和秀
(次回につづく)
|
◆参考図書・映像資料
DVD『甲野善紀 武術との共振』 武術家・甲野善紀氏が研究する身体操法の格闘技,スポーツ,介護への応用を解説。介護への応用の章に岡田氏が出演。60分,5,980円(税5%込)。 ◆問合せ・販売: 人間考学研究所 URL:http://www.ningenkougaku.jp (書店でもお求めいただけます) ◆岡田慎一郎氏講習会情報
◆お天気介護サービス「古武術バージョン介護技術セミナー」
|
岡田慎一郎氏プロフィール
介護福祉士,介護支援専門員。古武術の身体操法を応用した介護術を研究。岡田慎一郎氏への質問・講演依頼等は岡田慎一郎氏公式サイト(http://shinichiro-okada.com/)まで。
|
|||||||||||||||||
【関連情報】
●岡田慎一郎氏の最新刊 『DVD+BOOK 古武術介護実践編』 (動画配信中!)
●岡田慎一郎氏が最新技術を紹介する「こんな方法もあるかもしれない――介護発,武術経由の身体論」は,『看護学雑誌』で2008年1月号(Vol.72 No.1)より2010年3月号(Vol.74 No.3)まで連載。電子ジャーナル「MedicalFinder」からも検索・閲覧・購入できます。
●岡田慎一郎氏の公式サイトは こちら です。


