MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


日本救急医学会,厚生労働省,総務省消防庁 監修
日本救急医学会メディカルコントロール体制検討委員会 編集
《評 者》雪下 國雄(日本医師会常任理事)
まさにメディカルコントロール 『必携』
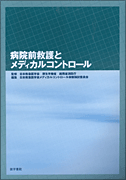 とかく外国から直輸入のカタカナ文字は,充分に理解されないまま独り歩きしがちだ。ともすれば「メディカルコントロール」(以下,MC)もその仲間に入りかねない。本書はその危機を救うために登場した救世主と言っては大げさだろうか。
とかく外国から直輸入のカタカナ文字は,充分に理解されないまま独り歩きしがちだ。ともすれば「メディカルコントロール」(以下,MC)もその仲間に入りかねない。本書はその危機を救うために登場した救世主と言っては大げさだろうか。
MCがはじめて公の場に登場したのは,厚生省(当時)「病院前救護体制のあり方に関する検討会」においてである。以来,病院前救護とMCは表裏一体のものとされ,特に救急救命士の業務拡大の際には,必ずMCがその前提条件とされてきた。
しかるに,わが国では医師の具体的指示等のMCに相当する行為が当然実践されていなければならないはずなのに,オフラインを含めたMC体制の体系的な整備が不充分なままにいたずらに時が過ぎてしまった。
MCを体系的に理解できる
厚生省における検討会の提言やその後の救急救命士の業務拡大を受け,MC協議会の立ち上げを中心にオンライン・オフラインのMC体制の整備が真剣に取り組まれるようになった。
しかし,MC協議会という「器」をこしらえても,これに盛る料理がてんでんバラバラでは,意味がない。指示体制,実習,事後検証,再教育等を首尾一貫して実施していくためには,MCの体系的な理解が必要なのである。
本書では,総論,次いでオンラインMC,オフラインMCにそれぞれ章を与え,具体例を交えながら詳細に説明している。わが国の病院前救護とMCをおおよそ網羅し,かつ合理的に項目立てた構成となっており,体系的な理解を得ることができる。特に,MCの両輪の一方に位置しながら,影が薄くなりがちなオフラインMCにも,相当のページを割いていることは注目に値する。
医療と救急のコラボレーション
医療と救急の連携が,病院前救護体制の全般にわたって重要なことは論を俟たない。
そう思いながら読み進めていると,「現場出動型救急医療と消防救急との連携」としてドクターカー・ドクターヘリシステムを説明している章に目が留まった。救急患者の救命,社会復帰には,医師による病院前救護活動が重要であることは言うまでもない。しかし,これらのシステムを完全に構築している地域は稀で,仮に構築していても医師が実際に現場に出動する例は当然限られている。つまり,医療サイドと救急サイドとの相互の連携と役割分担なくしてドクターカー・ドクターヘリシステムは成立し得ない。
救急救命士の業務拡大(気管挿管・薬剤投与)に伴う病院実習でも同様である。本書でも指摘の通り,救急救命士の病院実習が,未だ国民に広く理解されているとは言えず,また医師の臨床研修医制度も必修化された今日,加えて救急救命士の病院実習の継続には医療サイドの絶大な熱意と協力が必須である。
最終章に至っては「コラボレーションとコミュニケーション」として,「さらに一歩深めた連携をとる」ための説明を展開している。そしてなにより,本書の構成自体が医療と救急の見事な「コラボレーション」をなしていて,両サイドの連携を重視していることに編者の慧眼がうかがい知れる。
医師会の役割
本書では,ドクターカーシステムの項で,地域医師会が救急医療機関をコントロールする立場にあり,その役割の重要性と個々の利害を越えて地域住民の生命を守るという本来の立場を自覚すべきであるとしている。
誠にその通りで,地域医師会には非常な重圧をかけて恐縮だが,ドクターカーシステムに限らず,MC体制に中心的な役割を果たして欲しい。
MC体制整備の「必携本」
MCは,救急患者の生命に深くかかわり,国民の救急医療に対する信頼を左右するもので,正しく理解し,実践されなければならない。
これまでにも,MCについて多くの研究,議論が行われてきたが,体系的に理解できる参考書は不思議と少なかった。本書は,小林国男先生はじめ多くの叡智の集大成であり,病院前救護とMCに必要十分な知見を得られる,まさに「必携本」といえる。また,随所に地域の具体例が盛り込まれており,この類の図書にありがちな硬直化,抽象化を避けるための努力が施されている。
わが国の救急医療体制の一翼を担う方々はもとより,研究者,学生,マスコミ関係者等もぜひ本書を熟読し,活用されることを希求するものである。


脇口 宏 編集
《評 者》五十嵐 隆(東大大学院・小児医学)
こどもの感染症診療に必要な 知識と智恵にあふれた良書
 現代の小児科医は小児科学の中のsubspecialityを1つか2つ,自分の専門領域と定めている。しかし,どのようなsubspecialityを専門とする小児科医であっても,多くの小児科医は「麻疹を診断できなくては小児科医の資格はない」と考えている。
現代の小児科医は小児科学の中のsubspecialityを1つか2つ,自分の専門領域と定めている。しかし,どのようなsubspecialityを専門とする小児科医であっても,多くの小児科医は「麻疹を診断できなくては小児科医の資格はない」と考えている。
「麻疹」を含め,こどもが罹患するさまざまな感染症を診ることができないと,たとえあるsubspecialityの分野で秀でた業績があっても,小児科医としては尊敬してもらえない。おそらく専門分化のより進んだ内科ではそのようなことはないであろう。ここに,感染症に対する内科医と小児科医の差があると,私はかねてから思っている。
実際にprimary careを担当することが比較的少ない大学病院の小児科医であっても,内科医に比べればさまざまな感染症に遭遇する機会が多い。また,総合病院小児科や実地医家として働く小児科医は,毎日こどもの感染症に遭遇している。
こどもは成人に比べると感染症に罹患しやすく,集団生活の場を通じての感染の機会も多いからである。こどもはさまざまな感染症を経験することで,未熟であった免疫系を次第に強化していく。小児科医にとって感染症を的確に診断し治療することは小児科医が小児科医たる極めて重要な基本である。
『こどもの感染症ハンドブック』はこどもの感染症を診察するうえで必要な知識と智恵にあふれた良書である。本書では,重要なこどもの感染症が具体的にわかりやすい表現で丁寧に記載されている。
主要症状別に感染症が分類されて記載されている点も,読者にとっては大変に親切である。一般小児科医はもちろんのこと,小児科研修医も本書を無理なく読んで比較的短時間で重要な要点と最新の情報を得ることができる。こどもを診察する機会のある内科や耳鼻科の医師にも本書が診療上の大きな助けとなるはずである。
第2版では,旧版よりも技術的進歩の見られる迅速診断と治療薬に大幅な充実が図られており,感染症新法の改訂にも内容を対応させている。また,従来の抗菌薬・抗ウイルス薬とは違う感染症の治療戦略として,バクテリオファージ療法が紹介されており,21世紀の感染治療の夢も熱く語られている。
明日の診療に役立つ本書を,1人でも多くの医師にお読み戴きたいと考え,本書を推薦する。


寺澤 捷年 編
《評 者》佐賀 純一(佐賀医院)
高齢化社会に朗報を もたらす好著
 寺澤捷年先生編集の本が出たというので,待ってましたとばかりに飛びついた。と言うのも,漢方関係の書物を山と積みながら五里霧中という有り様であった時に寺澤先生から『症例から学ぶ和漢診療学』(医学書院)をお送りいただき,厚い霧が一気に晴れた快感を覚えた経験があるからだ。
寺澤捷年先生編集の本が出たというので,待ってましたとばかりに飛びついた。と言うのも,漢方関係の書物を山と積みながら五里霧中という有り様であった時に寺澤先生から『症例から学ぶ和漢診療学』(医学書院)をお送りいただき,厚い霧が一気に晴れた快感を覚えた経験があるからだ。
そこで今回の書物を一読してみたところ,直ちに次のことを実感した。それはこの書物が和漢医学を志す者の必読書となるであろうことは論を俟たないが,むしろこれまで漢方をさほど重要視していなかった西洋医学偏重の先生方にショックを与えるのではないか,従来の治療法の根本的見直しを迫ることになるのではないかということである。
なぜかと言えば,高齢者の抱える多様な訴えに対して適切に対応できる治療法は,西洋医学の領域全体を見渡しても実に寥々たるものであって,医者自身が困り果てているというのが実情だからだ。患者さんがしびれ,意欲の低下,気力の喪失,冷え,手足のほてり,かゆみ,かすみ目などを訴えると「年だから仕方がないですよ」と言いながら実は,西洋医学の無力を告白しているに過ぎないという事実に気付いている医師は少なくない。
ところが和漢薬は,そのような患者さんの訴えに正面から取り組む術を備えている。この書物には,それらの事例が具体例をもって系統的に示され,しかもチャート図を用いて最も適切な方剤を検索するシステムが開示されている。
例えば多発性脳梗塞に併発した「睡眠時呼吸障害」の患者さんに対して「西洋医学的アプローチの現状」という一節を設けてその治療法と限界を明快に解説しながら,他方,こうした事例に対してどの和漢薬を用いるべきか,それらはどのように奏効したかということについて使用経験をふまえて詳細に解説し,しかも,それらの方剤を選択するための手順を図式化して提示しているのである。
こうした編集方法は全編を貫いており,西洋医学と和漢診療学の相違がひと目でわかるばかりでなく,高齢者独特の多様な病態に対して,和漢薬こそが,切り札となり得る力を十分に保有しているという事実を再認識させてくれる。
このように,特筆すべき症例は全編にわたっていて枚挙にいとまがないが,「性的逸脱行動」に関する症例報告は劇的である。ひと目をはばからぬ自慰行動によって家族や介護職員を困惑させていた高齢の男性が,桂枝加竜骨牡蛎湯によって救われたという事例は,人間存在の業の深さ,哀れさ,心理の複雑さを見せつけると共に,和漢薬の秘めている底知れぬ力を暗示しているように思える。
ともかくも,この書物は医学界のみならず,高齢化社会にまたとない朗報をもたらすものであり,その意味で,和漢診療学が高齢化社会全体に大きな貢献をなし得る不可欠の存在であるということを,胸がすくばかりに見事に証明してみせた必携の好著である。


WM臨床研修サバイバルガイド小児科
吉村 仁志 監訳
《評 者》宮坂 勝之(国立成育医療センター 手術・集中治療部長)
チーム医療に必要な 実践に即した内容
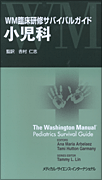 本書の序文で監訳者は,「翻訳していてワクワクした」と述べている。その気持ちが十分に伝わってくる。おそらく今では指導役となっている訳者たちが,自分自身の研修時代を考え,こんな本があったらよかったと思いながら翻訳されたのだと思う。
本書の序文で監訳者は,「翻訳していてワクワクした」と述べている。その気持ちが十分に伝わってくる。おそらく今では指導役となっている訳者たちが,自分自身の研修時代を考え,こんな本があったらよかったと思いながら翻訳されたのだと思う。
米国で小児科レジデント研修を開始する医師が,毎日持ち歩くことを前提に編集された本であるが,日本語版では,訳者による注釈や解説に日本の医療との相違が懇切丁寧に説明されていることに,その思いが込められている。さすがは,今,卒後臨床研修で大人気の沖縄県立中部病院のスタッフが関わった内容だと実感できる。ところどころのカタカナ日本語は仕方がないが,監訳者が原稿全体に丁寧に目を通していることが明らかで,文体も整い誤植も少なく,とても読みやすい。
血液疾患・腫瘍性疾患の章に,目的を持って白血病を記載していないことでもわかるように,優先度をつけた効率的なチーム医療実践の重要性が根底に流れており,これは日本の臨床医療で大いに欠けていることである。これからの医療では,限られた資源のなかで有効なチーム医療の実践が求められる。それには優先度をたてた医療の実施が重要であるが,皆保険制度の日本の医療ではそうした視点が今まで欠けていたように思う。
本書は,研修に際しての心がけの記載,サインアウト(申し送り)に際しての簡潔さの強調,そして申し送りを終えたら明日に備え速やかに帰宅しよう,などチーム医療を行ううえで重要な,通常の教科書ではカバーできない研修の実践に即した内容に満ちている。
こうした本が上級研修医,専門研修医のレベルでまとめられていることに米国医療の層の厚さを感じさせる。サバイバルマニュアルとしての役割に加え,小児医療の考え方の整理に役立ち,周辺領域の医師や指導的な立場の医師にとっても大いに役立つ内容である。
A5変・頁364 定価3,360円(税5%込)MEDSi
