MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


吉岡 成人,和田 典男,伊東 智浩 著
《評 者》大澤 佳之(おおさわ胃腸科内科クリニック院長)
内分泌代謝疾患への 想像力を補ってくれる1冊
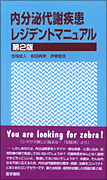 この本はコンパクトにまとまっている。新書サイズで270ページ程の容量は,忙しくなかなか時間がとれない実地医家にとって本を手に取ってみる1つのきっかけになる。初老と言われる年齢に足を踏み入れた田舎の開業医としては,実際のところ久しぶりに通読した1冊になった。著者らは,研修医や卒後3-5年くらいの内科専攻レジデントを読者として想定して,このマニュアルを執筆したと思うのだが,大昔の研修医にとっても,とてもよくできた1冊と実感した。私と同年代の内科医にもぜひとも薦めてみたい。そういうわけで,一開業医の感想に終始するのをお許しいただきたい。
この本はコンパクトにまとまっている。新書サイズで270ページ程の容量は,忙しくなかなか時間がとれない実地医家にとって本を手に取ってみる1つのきっかけになる。初老と言われる年齢に足を踏み入れた田舎の開業医としては,実際のところ久しぶりに通読した1冊になった。著者らは,研修医や卒後3-5年くらいの内科専攻レジデントを読者として想定して,このマニュアルを執筆したと思うのだが,大昔の研修医にとっても,とてもよくできた1冊と実感した。私と同年代の内科医にもぜひとも薦めてみたい。そういうわけで,一開業医の感想に終始するのをお許しいただきたい。
内分泌疾患に関しては,医学生時代には,比較的容易に頭に入ったものであった。ホルモンのフィードバック機構や理論に基づいた負荷試験などは理路整然としており,臨床感覚に未熟な学生にも比較的理解しやすい。一方,代謝疾患の代表といえる糖尿病に関しては,わかったようなわからないような感じで卒業した。糖尿病に関してはやはりわかっていなかったことが後でわかったが,その後の糖尿病臨床医としての経験の中で,疾患に対する理解を深めていった。一方,わかっていたはずの内分泌疾患に関しては,実際の臨床を行ううえでいろいろと問題があった。一般内科に紛れ込んでくる内分泌疾患を見つけるのはなかなか困難なものである。最も一般的な内分泌疾患は甲状腺疾患であるが,それさえもなかなか診断に至らないことも多い。頻脈,発汗,やせ,眼球突出,甲状腺腫を呈する典型的な甲状腺機能亢進症はむしろ少ないくらいである。
本書の前半は,内分泌疾患に当てられている。日常診療に流されていく中で,内分泌疾患を拾い上げていく第一のコツは,まず,その疾患を思い起こすことであるのは言うまでもないだろう。しかし,一般開業医における長年の外来の中で,ついつい疾患を見逃している場合も多いと思う。本書のおかげでしばらくはまた内分泌疾患を想定しての日常診療ができそうに感じた。
基本中の基本であるが,甲状腺の触診を忘れないようにしよう。下垂体副腎系の疾患では,身体所見や一般検査成績から,疾患を想起することが重要なのであるが,とりわけ初診時の直感が大事ということであろうか。二次性高血圧症を拾い出すのはやはり難しそうだ。開業医の外来で,PRA/PACの測定をどこまで行えばよいのだろう。発作性の高血圧症で,ワンポイントでのカテコラミン採血も行ってみなければならないか。即,副腎CT検査を行って,褐色細胞腫を探すのは,どうなんだろうか。少々乱暴か。副甲状腺疾患を想定しての外来診療も必要だ。不定愁訴の患者でも,一度は血清Caを測定するようにしなければ。
本書の後半は,代謝性疾患である。糖尿病の記述がその主たるものである。一般内科においての糖尿病の診療は先の内分泌疾患とは少々違ったものになる。疾患を拾い上げるのはさほど重要なことではない。眼の前に存在する糖尿病患者を診て判断しなければならないことは多い。糖尿病の病型,血糖コントロールの状況,薬剤治療の選択,治療の評価,などであるが,本書の記述は大変よくまとまっている。しかし,糖尿病への考え方が身についている年配の専門医にはとてもよいのだが,レジデントや糖尿病非専門内科医にとっては,記述がいささかまとまりすぎているかもしれない。限られた紙面の都合上,仕方のないことなのではあるが。
最後になるが,本書の随所にちりばめられた貴重な症例が読者の疾患への想像力を補ってくれて,side memoもとても役に立つ。研修医やレジデントだけでなく,ベテラン内科医にも一読を薦めたい好著である。


Linda Wilson-Pauwels,Elizabeth Akesson,Patricia Stewart,Sian Spacy 著
高倉 公朋 監訳
齋藤 勇,寺本 明 訳
《評 者》河瀬 斌(慶大教授・脳神経外科)
解剖の知識が臨床に どう役立つかを明確に示し, 読者の興味をかき立てる
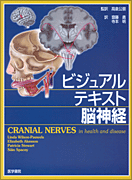 近年の情報の氾濫とともに,かつて限られていた数の医学書もうなぎ上りに増加している。日本の教科書や参考書はとかくつめ込み主義的な構成になっており,読者の興味をかき立てたり,どこにその知識が必要なのかを示したりしているものは少ない。
近年の情報の氾濫とともに,かつて限られていた数の医学書もうなぎ上りに増加している。日本の教科書や参考書はとかくつめ込み主義的な構成になっており,読者の興味をかき立てたり,どこにその知識が必要なのかを示したりしているものは少ない。
教科書や解剖書も御多分に洩れない状況である。本書も一見神経系の系統解剖書に見えるが,実はそうではない。系統解剖にありがちな,「何のためにこれを覚えるのか?」という疑問を各章冒頭に「症例」という患者のプレゼンテーションをすることで,知識が臨床の場でどのように役立つかを明確に示し,読者の興味をかき立てている。これはやはり日本の執筆者も見習うべきであろう。
解剖図では神経の6種の機能(一般知覚,内臓知覚,特殊知覚,体性運動,鰓運動および内臓運動)がそれぞれ色刷りで示されており,一目瞭然となっている。解剖図自体もカラーで理解しやすく,立体的に描いてある。さらにそれを元にして「症例問題」が作られており,読者の知識を問うことによって,記憶の整理をさせている。そして最後には患者の診察法までを写真や図で解説するという念の入れ方である。
このように基礎と臨床の知識を一緒にして実地に役立てることは,大変重要でプラクティカルである。私自身もこの本を読んで再教育される点が数多くあるほど内容が豊富でわかりやすい。したがって本書は学生や研修医のみならず,専門医にとっても有益な本であるといえる。


山科 章,近森 大志郎 編
《評 者》西村 重敬(埼玉医大教授・循環器内科)
難しい心電図判読を学ぶ
若手医師に最高の指導医が
手をさしのべる
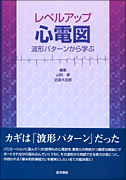 2004年度は,医師卒後研修制度改革がスタートした年となった。後で振り返れば,あの年が教育・研修制度の大きな変換点であったという年になるであろう。山科教授が序で述べておられるように,その研修目標は,「プライマリ・ケアの基本的な診察能力(態度,技能,知識)を身につけること」である。そのプログラムの中で循環器科領域においては,経験すべき症状・病態として胸痛,動悸,呼吸困難など,緊急を要する症状・病態としてショック,急性心不全など,経験すべき循環器領域の疾患として,心不全,狭心症,心筋梗塞,不整脈(主要な頻脈性,徐脈性不整脈),弁膜症(僧帽弁膜症,大動脈弁膜症),動脈疾患(動脈硬化,大動脈瘤)があげられている。これらは,診療する機会の高い(common)病態と疾患である。その診断にあたっては,病歴,身体所見が最重要であり,加えて心電図検査は不可欠である。医師には,プライマリ・ケアに必要な一定レベル以上の心電図診断能が求められていることを意味する。
2004年度は,医師卒後研修制度改革がスタートした年となった。後で振り返れば,あの年が教育・研修制度の大きな変換点であったという年になるであろう。山科教授が序で述べておられるように,その研修目標は,「プライマリ・ケアの基本的な診察能力(態度,技能,知識)を身につけること」である。そのプログラムの中で循環器科領域においては,経験すべき症状・病態として胸痛,動悸,呼吸困難など,緊急を要する症状・病態としてショック,急性心不全など,経験すべき循環器領域の疾患として,心不全,狭心症,心筋梗塞,不整脈(主要な頻脈性,徐脈性不整脈),弁膜症(僧帽弁膜症,大動脈弁膜症),動脈疾患(動脈硬化,大動脈瘤)があげられている。これらは,診療する機会の高い(common)病態と疾患である。その診断にあたっては,病歴,身体所見が最重要であり,加えて心電図検査は不可欠である。医師には,プライマリ・ケアに必要な一定レベル以上の心電図診断能が求められていることを意味する。
心電図は難しくまだまだ不明な点が残されている。誤解を恐れずに言えば,単心筋細胞の電気的現象モデルから,ST変化,T波変化は十分に説明できない。また,不整脈の発生機序を説明する心臓電気生理学的仮説のすべてが証明されたものではない。そのために,学生や研修医の中には,厳密さを求めるあまり,心電図診断はあいまいであると,敬遠しがちな者がいる。心電図判読のある部分は,パターン認識で経験によらざるを得ないのが実情なのである。それだからこそ,かつて(私の研修医の頃)は,心電図判読の力をつけるためには,「心電図をまず判読し,次に先輩医師から教えを受け,その心電図をファイルし,症例を積み重ねながら学べ」と言われた。
本書は,最高級の指導医が,膨大な症例の中から最適の症例を厳選,分類し,「さあ,この症例の心電図を判読しながら勉強しよう」と手をさしのべてくれているように感じる本である。構成は,心電図提示,病歴等の臨床所見,本質的な質問と解答,解説,チェック項目の確認からなっている。なによりもすばらしいのは,心電図所見の臨床的意義をどのように判断し患者を診ていくのか,という視点が貫かれていることである。この点が,これまでの心電図診断演習本との最大の違いである。
医学生,初期臨床研修を受けている医師,内科研修中の医師,循環器専門医をめざしている医師に加えて,救急疾患の診療にたずさわっている医師やコメディカルの方々にも,本書を強く推薦する。ただし,読んでいく際の注意点は,編集・著者らの長年の指導経験から得られた,学習者の誤りやすい点等が,キーワード,表にさりげなくまとめられているので,一字一句を理解していくことである。


福嶋 敬宜 編
福嶋 敬宜,二村 聡,太田 雅弘,入江 準二 執筆
《評 者》多賀須 幸男(多賀須消化器科・内科クリニック院長)
読めば必ず 「病理に強い臨床医」になれる
 4名の著者はいずれも臨床のレジデントを経て病理学の研修過程を修了し,内外の臨床病院の病理学科で経験を深め,難関と言われる日本の病理専門医・細胞診専門医の資格を取得した新時代の臨床病理医たちである。
4名の著者はいずれも臨床のレジデントを経て病理学の研修過程を修了し,内外の臨床病院の病理学科で経験を深め,難関と言われる日本の病理専門医・細胞診専門医の資格を取得した新時代の臨床病理医たちである。
「I.入門編:病理診断の使い方を知る」(42頁),「II.基礎編:病理に強い臨床医といわれる」(157頁),「III.応用編:病理診断を研究に活かす」(17頁),「IV.資料編:いつでも参照」(28頁)という各編のタイトルから想像できるようにユニークな構成であり,しかもわかりやすい文章とシェーマで解説されている。
病理をはじめて最初に戸惑うのは,「異形成」,「髄様」,「肉芽」などの,わかったようでわからない用語である。ウイルヒョウの病理総論の系譜を継ぐ日本の病理学には,形而上学的な響きを残す用語をかみ砕いて説明する習慣がなく,おいそれと質問しがたい雰囲気が今も漂っている。推測するに著者らも修行時代に体験したこの悩みを次世代にさせたくないというスタンスで編集され,成功している。恥ずかしながら「篩状」,「脱分化」,「オルガノイド・パターン」などの正確な意味を,本書で初めて知った。
現在の臨床医の多くは,手術材料や生検組織がどのような過程を経て病理報告書ができあがるのか知らないのではなかろうか。本書では正確な診断を得るための材料の取り扱いや病理医とのコミュニケーションについて,手を取るように説明されている。胆管癌や膵癌の切除材料の正しい処理方法や特殊染色の選び方などを初めて知った。
「FAQ」,「ここがホット」,「耳より」と題した28のコラムに「EBウイルス関連胃癌」,「パニン」,「MUC蛋白」等々の最新の話題の解説があり,入門書にはないサービス精神が溢れている。「結節内結節」に相当する所見が50年前の剖検レポートで「肝細胞がunruhig」と記載されていたことを懐かしく思い出した。診断名の時代的変遷についても詳しく,とくに肝の病理用語の最近の大きな変化に驚かされた。
索引が充実し参照ページが完備し,そのうえ裏表紙にその要点を掲載している編集者の気配りが本書の利用価値を倍増している。造本の最終工程に行われるこの作業は手抜きになりやすいものである。カラー写真でなくより技術を要する白黒写真を用いたのも,AFIP(Armed Forces Institute of Pathology)の図譜に迫ろうとする著者たちの心意気とみた。
国立がんセンター時代に病理の心得をたたき込まれた筆者は,標本を必ず観察し患者にも顕微鏡を覗かせて,そこにひろがる別世界の美を分かつことにしている。本書を読めば必ず「病理に強い臨床医」になって,新しい視界を開いてくれる。


精神医学講座担当者会議 監修
山内 俊雄,小島 卓也,倉知 正佳 編
広瀬 徹也,丹羽 真一,神庭 重信 編集協力
《評 者》秋元 波留夫(金沢大名誉教授)
専門医にも役立つ 精神医学の エンサイクロペディア
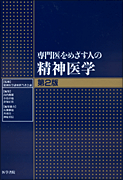 本書は,1998年,全国の大学で精神医学講座を担当する教授諸君の企画,監修で出版された『専門医のための精神医学』の改訂第2版である。題名が『専門医をめざす人の精神医学』と改められている。
本書は,1998年,全国の大学で精神医学講座を担当する教授諸君の企画,監修で出版された『専門医のための精神医学』の改訂第2版である。題名が『専門医をめざす人の精神医学』と改められている。
日本精神神経学の長年の懸案であった精神科専門医制度がいよいよ2005年から実施されることになり,専門医をめざす人は学会が規定するところの「精神科専門医認定試験」を受験しなければならないことになった。この改訂版はこの画期的ともいうべきわが国の精神科専門医制度の出発にそなえて,精神科専門医として,クライエントから信頼されるに足る人格,診療技能の向上に資するための拠りどころとなるマニュフェストを意図して編纂されたものであり,単なる教科書,手引き書,minimum requirementsではない。
この本の内容は,1.精神医学を学ぶための基本的な知識と態度,2.精神症状とその捉え方,3.診断および治療の進め方,4.症状性を含む器質性精神障害,5.精神作用物質使用による精神および行動の障害,6.てんかん,7.心理・生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群,8.統合失調症,統合失調型障害および妄想性障害,9.気分(感情)障害,10.神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害,11.成人の人格障害および行動の障害,12.精神遅滞および心理的発達の障害,13.小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害,14.乳幼児,児童および青年期の精神医学的諸問題,15.コンサルテーション・リエゾン精神医学,サイコオンコロジー,16.精神科救急,17.自殺の問題,18.生物学的治療,19.精神療法,20.社会的治療,社会復帰を援助する治療,の20章からなり,752頁の大冊である。
執筆者も115人という多数にのぼり,医学生用の教科書とちがって,エンサイクロペディアの観がある。それだけに,精神医学・医療の現状を批判し,未来を展望する主体的な視点に乏しいのがいささか物足りない。しかし,それはこの本の欠点ではない。これまできわめて不備であった精神科卒後臨床研修制度が改善され,2004年度から精神科の研修が必須となり,精神科卒後教育の整備充実が求められているが,この本はそのためにも役立つにちがいない。
いまわが国で求められているのは,さまざまなスティグマと差別の横溢する社会に生きている精神を病む人たちへの医学的援助者としての自覚を持つ精神科専門医である。日本精神神経学会の専門医制度がそのために役立つようになることを私は期待するが,この「専門医をめざす人の精神医学」は「めざす人」だけではなく,精神科専門医の生涯学習に役立つために,さらに改訂され,版を重ねることを期待したい。
B5・頁752 定価18,900円(税5%込)医学書院
