対談
「やがて来る日のために」――訪問看護ドラマ化の舞台裏
山田太一氏(脚本家)
佐々木静枝氏(訪問看護ステーション北沢管理者)
弊社発行の雑誌『訪問看護と介護』は来年創刊10年目を迎える。1月号では特別企画「中と外からみた訪問看護の魅力」の1本として,脚本家の山田太一氏と訪問看護師の佐々木静枝氏(訪問看護ステーション北沢管理者)との対談を掲載している。山田氏と訪問看護のつながりとは…。
来春3月,訪問看護をテーマとした特別ドラマ「やがて来る日のために」がフジテレビ系列で放送される。脚本は「岸辺のアルバム」「ふぞろいの林檎たち」など多くの話題作をてがける山田太一氏。キャストも市原悦子さん,柄本明さんなど,豪華な顔ぶれだ。深く,温かみのある人物描写に定評のある山田氏が描く訪問看護の現場とは,どのようなものなのだろうか。
ドラマ制作にあたって山田氏からの取材を受けた訪問看護師の佐々木静枝氏は,「たくさんの人に訪問看護を理解してもらう絶好の機会」と考え約1年にわたる取材に協力したという。ドラマのねらい,さらには訪問看護の魅力について語り合った対談の一部を以下に紹介する。
「看護のリアリティ」を求めた脚本
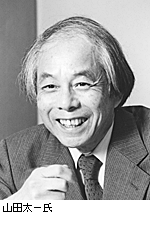 山田 僕と佐々木さんとの出会いは,そもそもは,フジテレビの「金曜エンタテイメント」という2時間ドラマの枠で,市原悦子さん主演でドラマを作らないか,という話が来たところからはじまります。今回は局から訪問看護師のドラマはどうだろうという提案があったんです。訪問看護についてはほとんど無知だったのですが,明日にも世話になるかもわからない歳ですし,これは知っておくにこしたことはないと思いました。そういうわけで,佐々木さんのところにお邪魔してお話を聞いたことがご縁になっているんです。
山田 僕と佐々木さんとの出会いは,そもそもは,フジテレビの「金曜エンタテイメント」という2時間ドラマの枠で,市原悦子さん主演でドラマを作らないか,という話が来たところからはじまります。今回は局から訪問看護師のドラマはどうだろうという提案があったんです。訪問看護についてはほとんど無知だったのですが,明日にも世話になるかもわからない歳ですし,これは知っておくにこしたことはないと思いました。そういうわけで,佐々木さんのところにお邪魔してお話を聞いたことがご縁になっているんです。
佐々木 たまたまうちの訪問先のお客様が,ドラマのプロデューサーとお知り合いで,担当看護師を通して「訪問看護のドラマをつくりたいので,どなたか協力してくれる人はいないだろうか」というお話があったんですよね。それでプロデューサーが私のところにいらしたのが,もう1年以上前になるでしょうか。そこからのおつき合いですね。
山田 取材をしてみると,やはりいろいろなケースがあって,訪問看護というのは深いですね。
佐々木 そう思われました?
山田 ええ。私の想像力より事実のほうがずっとすごいなと思いました。こっちがどうあがいたって,事実には勝てません。ただ,実際のエピソードというのは,そのまま使うとご迷惑になるケースもあるので,むしろ生の事実は避けていますが。
佐々木 シナリオを見せていただいた時,けっこう自分の経験と重なるように思いました。事実ではないとわかりつつも,つい自分の出会ってきたケースを思い出して,当てはめて読んでしまいました。
山田 人はあまり変わらないということでしょうか。
 佐々木 在宅療養している方は別に特異なのではなく,あくまでも生活の延長線上で療養生活をされているからだと思います。それできっと私たちから見ても自然なせりふや場面として書かれているのかなと思いました。そういう普遍性もあるお話だと思います。シナリオを書くに当たって,医療や看護を扱うことで苦労された点はありますか?
佐々木 在宅療養している方は別に特異なのではなく,あくまでも生活の延長線上で療養生活をされているからだと思います。それできっと私たちから見ても自然なせりふや場面として書かれているのかなと思いました。そういう普遍性もあるお話だと思います。シナリオを書くに当たって,医療や看護を扱うことで苦労された点はありますか?
山田 ケアの実際については,僕はよくわからないんですよ。技術をシナリオに詳しく書く能力はないので,そこは医療の専門家の指導に従おうと割り切りました。このドラマは看護にリアリティがないとだめですから,専門家頼りです。
死が出てくる話をドラマにすると,言い方は悪いですが,盛り上がりが早いというか,書き手としては楽なんです。人間はみな死ぬわけですから,そこにはたくさんのドラマがありますよね。だけど,それをいわば商売に使うというのは,ちょっと避けたいというか,それを出せば楽だけど,そのように病気や死を利用するのはたしなみがないような,はしたないような感じがしてね。それで,なるべくそういうことはしないようにと思ってきたのですが,今回の作品には,ぎっしりと入っています。ですから,このドラマで貯金を全部使ってしまったな。
佐々木 この「やがて来る日のために」というタイトルは,誰にでも訪れる,最期の日々ということでしょうか。
山田 そう。その日のために働いている人という意味もありますし,患者の立場からでも使える言葉だと思います。
佐々木 取材されてみて,ご自分もいつか訪問看護に世話になるかもしれないとおっしゃいましたが,安心して任せられそうな現場でしたか?
山田 それはもう,なるべくなら在宅で死にたいと思いましたね。どうしても年をとってくると自宅の空気というのは,過去の塊でしょう。汚れやシミも,雨戸のきしみも,細かく私を支えてくれています。その過去から離れて白い壁の病院に行き,そこで死ななければならないというのは,相当さびしいことですね。過去なんかに拘らない人もいるでしょうけれど,おおむねは過去に取り囲まれていたいと思うのではないでしょうか。僕なんかは,自宅の音,気配,他人との距離,本や絵のあるところで死にたいと思いますね。
この対談の全文は,『訪問看護と介護』2005年1月号(10巻1号)に掲載されています。ドラマは来春3月にフジテレビ「金曜エンタテイメント」枠にて放送予定。
