臨床研修必修化目前で
求められるプライマリ・ケア指導医の養成
日本家庭医療学会特別教育ワークショップ開催


日本家庭医療学会による特別教育ワークショップ「地域におけるプライマリ・ケアの卒後・生涯教育プログラム作成」が,伴信太郎氏(名大・日本家庭医療学会長)のコーディネートのもと,さる4月19-20日の両日,東京大学において開催された。来年から必修化される卒後臨床研修には「地域保健・医療」がカリキュラムに含まれ,プライマリ・ケアに求められる臨床能力の養成が重視されている。こうした背景から本ワークショップでは,伴氏の他,生坂政臣氏(千葉大),大滝純司氏(東大),岡田唯男氏(亀田メディカルセンター),大西弘高氏(マレーシア・国際医科大),斉藤康洋氏(国立病院東京医療センター),藤沼康樹氏(北部東京家庭医療学センター),松村真司氏(松村医院)がファシリテーターを務めて議論を展開。イギリスにおけるGP(General Practitioner)教育システムを参考にした,日本の診療所医師が「日本版GP」の研修指導医となるための,具体的な卒後・生涯教育プログラム作成が試みられた。
英国のGP養成カリキュラム
伴氏は冒頭の挨拶で,「総合する専門医」としての家庭医養成のためには,大学以外の施設とどのように連携をとっていくかが重要と指摘。卒後4年次に診療所においてトレーニングを行なう英国のGP教育カリキュラムが参考にしやすいとし,「本ワークショップで,日本型カリキュラム作成のための問題提起をしていただきたい」と方向付けた。続いて,特別講師として招かれたニール・ジャクソン氏(London Deanery)が,英国におけるGP卒後教育について説明するとともに,卒後教育マネジメントを基本業務とするLondon Deaneryの働きを紹介した。
さらに,斎藤康洋氏(国立病院東京医療センター)が英国の研修病院を見学した経験から,英国のGP養成カリキュラムについて紹介。GP研修医はVT(Vocational Training)と呼ばれる,週に1度のレクチャーとケースディスカッション主体の勉強会への70%以上の出席が義務付けられている点など,特徴的なカリキュラムにも言及した。
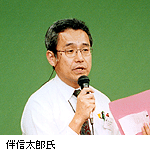

ガイドライン作成も視野に
 グループワークでは,「わが国の診療所医師がGP研修指導医となるために学ぶべきことは何か?」をテーマに議論。教育技術,研修医の生涯学習促進など,グループごとに選んだ話題について,卒後・生涯教育プログラムの作成にむけて話し合った。
グループワークでは,「わが国の診療所医師がGP研修指導医となるために学ぶべきことは何か?」をテーマに議論。教育技術,研修医の生涯学習促進など,グループごとに選んだ話題について,卒後・生涯教育プログラムの作成にむけて話し合った。
伴氏は,弊紙のインタビューに対し,本ワークショップでの議論と日本家庭医療学会でのプログラム作成委員会での議論とをあわせて,いずれは学会として研修,生涯教育のガイドラインを作っていければと話している。
(本ワークショップの模様は,下記参加体験記も参照のこと)


よいプログラムができると確信
金信浩(千葉大学医学部附属病院 総合診療部) 今回ニール・ジャクソン先生の講演を通して,英国ではDeaneryという国家機関の管理のもと,GP研修医が診療所で1年間マンツーマンの外来教育を受けると知り,日本のシステムとの相違に驚きました。こうした英国の現状を参考に,ワークショップでは5つのグループに分かれ,「日本の診療所医師がGP研修指導医となるための具体的な卒後・生涯教育プログラム」の作成を試みました。いかに良い指導医を育てるかという課題は,未熟な私が考えるにはとても難しいことと思いましたが,真剣に議論される同じ班の先生方のご意見を聞きながら,自然に私も議論に加わるようになりました。
今回ニール・ジャクソン先生の講演を通して,英国ではDeaneryという国家機関の管理のもと,GP研修医が診療所で1年間マンツーマンの外来教育を受けると知り,日本のシステムとの相違に驚きました。こうした英国の現状を参考に,ワークショップでは5つのグループに分かれ,「日本の診療所医師がGP研修指導医となるための具体的な卒後・生涯教育プログラム」の作成を試みました。いかに良い指導医を育てるかという課題は,未熟な私が考えるにはとても難しいことと思いましたが,真剣に議論される同じ班の先生方のご意見を聞きながら,自然に私も議論に加わるようになりました。
思わず身を乗り出して
私が所属したB班では「研修医の生涯学習の指導方法」をテーマに選び,GP研修医に生涯学習を促し指導する能力を,いかに指導医に身に付けてもらうかを課題としました。最初に一般・個別目標を決め,利用可能な資源・組織形態という順にスムーズに決めることができました。しかし,教育方略におけるカリキュラム作成の段階に議論が進むと,次々に難題があがりました。財政的な予算はどうするか? 誰が講師をするのか? どれくらいの頻度で行なうのか? 評価はどのようにするのか? など具体的になればなるほど問題が噴出しました。2日間の議論の末どうにか最終的に,研修カリキュラムとして年3回の講習会の案を作成することができました。具体的には第1回目に生涯学習についての講義,第2回目はロールプレイを用いた成人学習の理論と実践の基礎,第3回目は指導現場をビデオ撮影し行なう検討会,そして全過程が終了したのち認定証を発行するという内容になりました。
話し合いの中では,県または学会主導によるGP育成機関の発足,模擬患者ならぬ模擬研修医を使ったロールプレイの研修など,次々にユニークで斬新なアイデアが出され感心させられました。エキサイトしてくると座っていたはずの班全員が,立ち上がり身を乗り出しているのに気付き,顔を見合わせ笑う一幕もありました。
