| 連載(6) | 新医学教育学入門 | 教育者中心から 学習者中心へ |
カリキュラムって何だ(前編)-顕在的か潜在的か | ||
| 大西弘高 国際医学大学(マレーシア)・医学教育研究室上級講師 | ||
真野律子さんは何事も決められたとおりにしないと気がすまない性格の医学部1年生。大学に入学し,オリエンテーションでもらったシラバスに,帰宅後早速目を通しました。すると,「一般目標」「個別目標」として,非常に細かな項目が並んでおり,「こんなにたくさんのことを学ばないといけないのか……」と少し恐ろしい感じがしました。
心待ちにしていた統計学の授業
真野さんの母は5年前,ある薬剤の治験に参加し,副作用の後遺症に今も悩まされています。母が「治験の説明をした先生は,『副作用は動物実験で何パーセント』とか言ってたけど,私にとっては100%やわ。とにかく,律子は,患者の気持ちがわかる医者になってね」と言ったことが胸に響きました。シラバスの「統計学」の部分につい目がいきましたが,よくわからない言葉が羅列されています(表)。でも,「統計パッケージの利用を含めた具体的な扱い方」という部分に惹かれて,授業を心待ちにしていました。さて,統計学の授業は,通常の大教室での講義でした。「コンピュータルームで統計パッケージを試しに使うことはできる」という説明がありましたが,講義ではt検定,U検定,F検定の原理が黒板にすらすらと書き連ねられていき,例題を解くばかりでした。必死でノートをとり,コンピュータルームで実際に試してみようとしますが,そもそもコンピュータを使った経験がほとんどなく,途方に暮れてしまいました。指導教官に質問に行っても,「まず表計算ソフトぐらい使えないとねぇ」と困った顔。周囲の友人たちは,「統計学は最後に公式を書いた紙を持ち込んで試験さえできたらいいらしいよ。先輩から過去問もらったから心配いらないし」と気楽な様子ですが,母の言葉がズシリと胸に響いている真野さんは何だか納得できませんでした。
その時,コンピュータルームに,同級生の表働数美さんがやってきました。別の大学で心理学部を出た表働さんは,統計手法を用いて卒論のための研究もしてきたそうです。「授業はあまりわからないけど,昔やってた勉強が真野さんの役に立つかなと思って来てみたよ」そう言うと,早速コンピュータからSPSS(R)*を開き,授業でやったデータを入力して,答えを確認し始めました。すると,答えは一瞬で出るではありませんか。(先生が黒板に書いていた内容って何だったの?)真野さんは,何だか腑に落ちない気がしました。
| 表 | |
|
カリキュラムとは
curriculumという語は,currere(走る)というラテン語から派生しました。走るコース,走ったコースを表すようです。また,履歴書を英語でcurriculum vitaeと言いますが,curriculumは履歴という意味も持っています。教育学的には,カリキュラムという用語が,個々の学習者が学び,経験した内容すべてを表すと考えられています。カリキュラムを前もって綿密に計画するための“カリキュラム開発(curriculum development)”は教育学の根幹をなすものです。しかしカリキュラム開発は綿密に行なわれても,計画したとおりの内容が学習されていないという問題点が指摘される機会が増えています。計画されたカリキュラムは“顕在的カリキュラム(manifest curriculum)”と呼ばれ,それ以外の場で学習者が経験した内容を指す“潜在的カリキュラム(hidden curriculum)”と区別されています。カリキュラムを“教育プログラム”や“教育課程”という用語に置き換えて用いていたこともありますが,この2つはいずれも顕在的カリキュラムを指しており,潜在的カリキュラムを含まないものと考えるべきです(図)。
真野さんが大学で経験したことを,このカリキュラムの枠組みで見ていきましょう。シラバスに書かれた内容は顕在的カリキュラムを表しています。本来,ここに書かれた内容を最大限学生が習得できるように授業や実習を組むべきですが,それがなされていない印象があります。さらに,教官/教員の思惑とはかけ離れたところで学生たちは「単位さえ取れればいい」というような安易な考えに流されがちです。
教育者側がよく誤るのは,「教えたことは学んでいるだろう」と勝手に理解することです。これを“履修主義”と呼び,授業をした,単位を出したという表面上の実績だけを重視する姿勢が伺えます。これに対し,「1人ひとりの学生は何を学習しているか」を観察し,最大限習得させようとする考え方を“習得主義”と呼びます。教育者が履修主義に陥ると,教えた内容が学ばれていない可能性が高まり,顕在的カリキュラムよりも潜在的カリキュラムの占める割合が大きくなりますし,授業やシラバスの内容自体も軽視される風潮が生まれるでしょう。
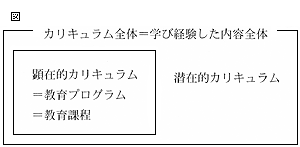
今回のシナリオの問題点
真野さんが納得できなかったのは,(1)「統計パッケージの利用を含めた具体的な扱い方」について教えてくれたのは,表働さんであり,担当教官ではなかったこと
(2)講義よりも,コンピュータルームで実際にやってみることの方が目標に到達できそうなこと
(3)シラバスに並んでいる目標が単なる“お題目”となっており,機能していないこと
でした。
これらはすべてカリキュラム開発の部分で取り沙汰すべき問題点と言えます。次回,後編でもう一度潜在的カリキュラムだけを取り上げて述べたいと思います。
(この項つづく)
*SPSS(R):統計パッケージの1つ。元はstatistical package for social scienceの略。
