MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


医学生が学ぶべき内容と最新の知識を盛り込んだ教科書
標準血液病学池田康夫,押味和夫 編集
《書 評》外山圭助(東医大名誉教授)
 私が慶應義塾大学病院に勤務していた1970年代,病棟に勤務する若い医師が好んで勉強に用いていた本がSamuel Rapaport著の“Introduction to Hematology”であった。この書はB5判程度の本であるが,最新の血液学の知識を網羅し,実際にベッドサイドでも役に立つ知識が満載されていて,かつ,価格も適当であった。たまたま,台湾の大学で講義する機会を得たが,ここで使われている教科書もこの本であった。このような臨床の医師にも,学生にも有用である本にその後なかなか遭遇することがなく(その一端の責任は教職にあった私自身の怠慢にもあるが),そのような教科書の出現を期待すること久しかったが,今回その渇望する血液学書が出版されて誠に喜ばしい。それは『標準血液病学』である。
私が慶應義塾大学病院に勤務していた1970年代,病棟に勤務する若い医師が好んで勉強に用いていた本がSamuel Rapaport著の“Introduction to Hematology”であった。この書はB5判程度の本であるが,最新の血液学の知識を網羅し,実際にベッドサイドでも役に立つ知識が満載されていて,かつ,価格も適当であった。たまたま,台湾の大学で講義する機会を得たが,ここで使われている教科書もこの本であった。このような臨床の医師にも,学生にも有用である本にその後なかなか遭遇することがなく(その一端の責任は教職にあった私自身の怠慢にもあるが),そのような教科書の出現を期待すること久しかったが,今回その渇望する血液学書が出版されて誠に喜ばしい。それは『標準血液病学』である。
最新の基本知識から治療法まで
本書は医学生を対象として学ぶべき基本的事項と最新の知識を盛り込んだ教科書をめざし,同時に医師として備えるべき知識と能力に関する最近のホットな議論を踏まえた内容をめざしたと,序に記載されているが,内容はまさにそのとおりである。血液学の各分野の専門家がそれぞれの得意とするところを担当されたので,血液学に関する最新の基本知識が網羅されている。特に造血機構やサイトカインの基礎知識,造血器腫瘍の分子生物学的病因,血栓性疾患の病態生理など新しい知見が記載されており,各疾患の発症病態など興味を喚起する点が多い。さらに臨床に役立つように貧血疾患,出血性疾患,血栓性疾患へのアプローチを示し,また種々の疾患の新しい診断基準も示されており,新しい悪性リンパ腫のWHO分類も記載されている。その上,予後に関して,あるいは,一般に教科書では記述の少ない治療法まで述べられているのはきわめて実用的である。血液標本のカラー写真をふんだんに掲載
その上,血液学の診断の基礎となる各種疾患の血液標本のカラー写真がふんだんに掲載されていることや,多くの重要な検査方法が示され,さらに血液検査の基準値まで記されているのも親切である。また本書には,血液臨床で非常に重要な輸血に関して,基礎から適応,手技,副作用までも入っていることは,他の教科書に見られることの少ない便利な点でもある。しかも,B5判のソフトカバーで索引まで入れて320頁という中に,よくもこれだけの豊富な内容が詰め込まれたものと感心する。編者および各著者のご努力の賜物である。また,英文,邦文の索引はなかなか便利にできており,価格もリーズナブルであるのはうれしい。しかし,あえて不満をあげれば,カラー写真では悪性貧血の多分葉好中球は周辺の赤血球が典型的でない。また,T細胞性白血病の細胞やhairy cell leukemiaなどはもう少し典型的な白血病細胞を示したほうが,学生に対しては親切である。骨髄線維症でもHE染色のみでなく,銀染色の写真も示されたほうが望ましい。また,50頁左段の「3)ヘモグロビンM症」の見出しは誤りである。
上記に無理に不満を述べたが,全体にはすばらしい教科書で,これだけ内容のある教科書はあまりないのではないだろうか。学生のみならず,内科医あるいは血液を専攻しようという若い医師にも必携の書であると考える。
B5・頁320 定価(本体4,500円+税) 医学書院


腫瘍学をはじめて学ぶ医学生に最適の教科書
がんの細胞生物学R.G.McKinnell,R.E.Parchment,他 著/阿部達生,三澤信一 訳
《書 評》北川知行(癌研究会癌研所長)
腫瘍学のエッセンスを伝える
 この教科書は,ミネソタ大学の学部学生(undergraduate students)のために作られたものであるが,大変バランスよく,そして正確に,現代腫瘍学ないし腫瘍生物学のエッセンスを伝えている良書である。冒頭にがんに罹患された人たちの手紙を10通ほど紹介してある。感動的な文章で病気としてのがんの実像を伝え,学生たちが腫瘍学を学んでいくためのよい動機づけとなっている。
この教科書は,ミネソタ大学の学部学生(undergraduate students)のために作られたものであるが,大変バランスよく,そして正確に,現代腫瘍学ないし腫瘍生物学のエッセンスを伝えている良書である。冒頭にがんに罹患された人たちの手紙を10通ほど紹介してある。感動的な文章で病気としてのがんの実像を伝え,学生たちが腫瘍学を学んでいくためのよい動機づけとなっている。
著者の1人のMcKinnel教授は,この30年にわたって続いているミネソタ大学の腫瘍生物学講義の最初からの推進者であるが,1960年代に有名なLuckeの蛙腎がん細胞核を除核した正常卵に移植し,完全なオタマジャクシが発生することを確かめた先駆的な研究者である。
博士は,「腫瘍学は生物学で学べないことを教えてくれる。例えばがんの浸潤と転移は現代生物学では扱えないし,実際講義もされない。しかしこの現象の解明から生物の発生過程あるいは成育個体中にみられる細胞移動のメカニズムが明らかにされる」と考えている。この卓越した見識と人類を悩ませるがんを克服したいという情熱が,学部学生のためにこれほど充実した腫瘍学講義を行ない,また学生たちを惹きつけてきた力の源であろう。
腫瘍学は基礎・臨床・社会医学のすべてを包摂する
翻って日本の医学部学生への腫瘍学講義の現状を見ると,いろいろ問題がある。ほとんどの大学で,腫瘍学講義は病理学教室が中心となって行なわれているのであるが,しばしば講義内容が旧く,形態診断学に片寄り過ぎ,急速に展開している現代分子腫瘍学の成果を咀嚼しバランスよく講義に取り入れているとは言い難い。生化学,衛生学,微生物学等々の教室が,互いに連携なく,つまみ喰い的に腫瘍学講義をしており,そこには重複や欠落がある。臨床腫瘍学の講義はほとんどない。そもそも腫瘍学は,基礎医学,臨床医学,社会医学のすべてを包摂しており,医学部学生に医学・医療における総合的思考,社会的アプローチの重要性を理解させる上での最良の教科であるが,現状ではその機会が十分生かされていないのである。よい教科書が得がたいのも問題である。本書の出現は,その点でも誠に喜ばしいと言える。腫瘍学ないし病理学を受講する日本の医学部の3-4年生は,ちょうどアメリカの学部学生の上級に当たると思われるので,本書は日本の医学生の教科書として誠によく適合していると言える。
本書の価値に着目され,邦訳を完成された関係者の慧眼とご努力に敬意を捧げたい。
B5変・頁384 定価(本体5,000円+税) 医学書院


新しい感染症の時代に必須の項目を盛り込んだテキスト
標準感染症学齋藤 厚,那須 勝,江崎孝行 編集
《書 評》猪狩 淳(順大教授・臨床病理学)
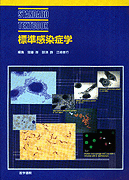 栄養状態や衛生環境の改善,予防接種の普及,抗菌化学療法やワクチン療法の進歩により,「感染症はもう恐くなくなった」,「感染症はもはや過去の病気となった」という認識に傾き,感染症は解決済みの疾患であるかの錯覚に陥った。現に,「感染症科」を標榜する病院が少なくなり,医科系大学の学生教育でも感染症の講義時間数は極端に減少した。そのため,感染症を専門とする医師は少なくなり,感染症を知らないまま卒業してしまう医学生が増えるという,困った現象が一時期ではあるが起こった。
栄養状態や衛生環境の改善,予防接種の普及,抗菌化学療法やワクチン療法の進歩により,「感染症はもう恐くなくなった」,「感染症はもはや過去の病気となった」という認識に傾き,感染症は解決済みの疾患であるかの錯覚に陥った。現に,「感染症科」を標榜する病院が少なくなり,医科系大学の学生教育でも感染症の講義時間数は極端に減少した。そのため,感染症を専門とする医師は少なくなり,感染症を知らないまま卒業してしまう医学生が増えるという,困った現象が一時期ではあるが起こった。
感染症の臨床に重点を置く
ここ10数年来,院内感染症,日和見感染症,耐性菌による難治感染症が増加し,さらに,新興感染症や再興感染症が世界各国で出現し,社会的問題に発展している。かかる事例を機会に,再び,感染症に対する関心が高まり,その予防対策の重要性が改めて認識されることとなった。このたび,医学書院より標準教科書シリーズの1つとして『標準感染症学』が発刊された。本書は,編集者が述べているように,感染症の臨床に重点を置き,臨床的視点に立脚して,今やわが国の感染症学をリードする新進気鋭の方々によって執筆されている。本書は真に時宜を得た感染症学の著書である。
本書の内容を簡単に紹介すると,大きく3つの柱から成り立っている。すなわち,感染症に関する基礎知識,感染症各論,臓器別感染症である。第 I 章の感染症に関する基礎知識は,まず感染症の成立に係る寄生体と宿主との関係,生体の防御機構について,次に,感染症診断の進め方,そして治療と予防,疫学へと順序だてて解説されている。この章は感染症を理解する上で絶対に知らなければならないこと,基本的な事項が述べられている。この項は本書の特徴の1つと言えるであろう。
第 II 章の感染症各論は,現在私どもが日常診療上知っていなければならない感染症,社会的にあるいは公衆衛生上問題になっている感染症を10項目ほどあげている。これらは新しい感染症の時代に対応するためには必須ともいうべき事項である。第Ⅲ章の臓器別感染症は,ただ感染症の羅列ではなく,日常診療で見る頻度が高い主要感染症を中心に解説されている。
感染症への理解を助ける
標準教科書シリーズは医師国家試験出題基準を満たすことを目標として,これまでさまざまな医学領域の好著が出版されており,本書もそれに準拠したもので,医学生の感染症の教科書としては最適である。しかも文章は平易であり,図や表が随所で使われており,理解を助ける役目を果たしていることは大変よい。本書は医学生のみならず研修医,感染症を専門とする方々にも最適であり,感染症学の教科書として,参考書として推薦したい好著である。B5・頁400 定価(本体5,500円+税) 医学書院


日本の研修医に最も重要なマニュアル
内科レジデントマニュアル 第5版聖路加国際病院内科レジデント 編集
《書 評》谷口純一(熊大附属病院・総合診療部)
研修医の強い味方
 毎年春になると新しい研修医がやってくるのであるが,彼ら・彼女らに接すると自分が研修医の頃が思い出され,さまざまな気持ちが沸き起こってくる。必ずしも上級医がいつもバック・アップしてくれるとは限らず,特に患者が急変・重症化した時こそそばにいなかったことが多かったかもしれない。別に“マーフィーの法則”などではなく,今思い返してみれば,ただ単に急変・重症化の早期サインを見落としていたり,予測が不十分であったり,また自分があわてていて連絡が後手に回っていただけということが多かったのではないかと,情けなくも恥ずかしい状況であったと思う。
毎年春になると新しい研修医がやってくるのであるが,彼ら・彼女らに接すると自分が研修医の頃が思い出され,さまざまな気持ちが沸き起こってくる。必ずしも上級医がいつもバック・アップしてくれるとは限らず,特に患者が急変・重症化した時こそそばにいなかったことが多かったかもしれない。別に“マーフィーの法則”などではなく,今思い返してみれば,ただ単に急変・重症化の早期サインを見落としていたり,予測が不十分であったり,また自分があわてていて連絡が後手に回っていただけということが多かったのではないかと,情けなくも恥ずかしい状況であったと思う。
そんな時,そんな自分を一番現実的に助けてくれたのは,『内科レジデントマニュアル』であり,『ワシントン・マニュアル』であった。今回『内科レジデントマニュアル』が第5版に改訂されるに当たり,自分が研修医の頃に使っていた旧第2版を久しぶりに引っぱり出し,比較してみた。大変驚いたことは,ベーシックでスタンダードな部分は何ら変わっていないことと,その一方で,その他のところは大幅に進化しており,新しい項目や知見も加わり,より実際的になっていることである。研修医の時大変お世話になり役に立ったが,今の自分にとっても参考になるところが多々ある。
より高次の医療を実現するための武器
自分もやがて上級医となり,研修医向けの簡単なマニュアルを作ることも経験したが,非常に大変な作業であったのを記憶している。“マニュアルを作る場合,(1)分解,(2)急所の明確化,(3)理解,(4)例解,(5)図解,(6)改訂の時期の明示と改訂責任者名の明記などがポイントである。そして,マニュアルというものは高度知識社会での基盤的道具であり,それに従い,知識を身につけた上で,それを超えた自分の仕事を創造することができる”という文章を最近読んだ。『内科レジデントマニュアル』はまさにそのようなポイントを踏まえて作成されており,主として内科の救急的諸問題に対し,“基盤的道具”としてはもちろん,より高次の医療を実現することが可能なポテンシャルを持った“武器”であると改めて再認識させられた。そもそも本書は日本の『ワシントン・マニュアル』をめざして作られ始めたと聞いたことがあるが,『ワシントン・マニュアル』が救急の現場や,日本の医療状況に必ずしもそぐわない面もあり,特に救急の現場の研修医には使いにくい場合もあるように思われる中で,本書は日本の研修医にとって最も重要なマニュアルであると言えるだろう。自戒の意も込め,1人でも多くの研修医が,このマニュアルに触れ,活用し,そしてマスターした上で,これを超えるより高次で,国際的な医療を展開していってくれることを切に希望してやまない。また,不断の努力で非常に優れたものを作りあげていった聖路加国際病院内科の新・旧のレジデント諸兄に敬意を表するとともに,今後もより効率的でユニークで正確なものを継続して作っていっていただきたいと願う。
B6変・頁396 定価(本体3,300円+税) 医学書院
