今年度の看護婦国家試験を振り返って
山内豊明(大分県立看護科学大学・助教授)出題基準提示後初の国家試験
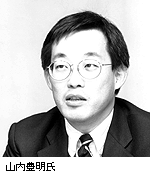 今年2月に行なわれた第89回看護婦国家試験(3月30日に合格発表,参照)は,1999年6月に厚生省から看護婦国家試験出題基準(以下,出題基準)が出されてから初めてのものであった。出題基準は,「看護教育のあり方を拘束するものではない」とされながらも,「看護教育課程の卒業生のほぼ全員が看護婦国家試験を受験するという事実を踏まえると,看護教育の方向性に大きく影響を与えるものであることに疑いの余地はなかろう」という真部の主張1)には同感である。
今年2月に行なわれた第89回看護婦国家試験(3月30日に合格発表,参照)は,1999年6月に厚生省から看護婦国家試験出題基準(以下,出題基準)が出されてから初めてのものであった。出題基準は,「看護教育のあり方を拘束するものではない」とされながらも,「看護教育課程の卒業生のほぼ全員が看護婦国家試験を受験するという事実を踏まえると,看護教育の方向性に大きく影響を与えるものであることに疑いの余地はなかろう」という真部の主張1)には同感である。
その意味でも,本年度の国家試験問題が具体的にどのように出題基準が反映されていたのかは,特に看護教育に携わる者にとっては強い関心の的である。しかし,今回1回の出題傾向をみるだけで,結論めいたことまで言及することは避けたい。ただ出題の中味についての吟味は,公正にかつクリティカルに行なっていきたいものである。そこで本稿では,試験の順を追って具体的に問題を検討することから全体を振り返ってみたい。国家試験が持つ問題の本質をともにお考えいただければ幸いである。なお,設問は別表を参考にされたい。
看護を反映するような問題
午前の問題の中には,「看護がみえる」ようなおもしろい出題の試みがいくつかあった。それらを,午後の「状況設定問題」の中に取り入れるように工夫したら,国家試験はもっとおもしろくなっただろう(例えば問題8)。具体的には,基礎医学の知識を日常場面と結びつけることができるかを問う良問や,まさに看護に期待されている知識を問う良問がみられた。さらに科学的なものの考え方を確かめるような出題は,看護の学問性を浸透させていく意味からもよい試みと言えるだろう。一方で,生活指導と疾病の予防という観点を結びつけて考えさせるよい出題形式もあったが,回答するにあたっては「予防効果を示さない」と断定させるにはやや無理があった(問題17)。さらに,看護という言葉に囚われすぎて,なぜあえて「看護」という枕詞がつく必要があるのか,という疑問が残る問題もあった(問題40)。
曖昧な言葉使いパターン化への危惧
曖昧な設問や現実離れした設定は,受験生にパターンとして,いわば反射的に回答をする癖をつけかねない。そのことは,人をみる見方を狭めていくように,受験生を誘導し「考える」という最も基本となる行為の育成を阻害しかねないとも危惧する。問題23では,実際の場面では慢性硬膜下血腫の可能性を念頭に置きながらも,重篤度や緊急性,あるいは急変する可能性の高いものなどをきっちりと鑑別していかなければならないことは言うまでもない。
問題44では,身体的アセスメントだけでは全体像は把握しきれないが,観察項目が看護婦の目的意識で決まってしまったら困りものである。さらに「系統的観察」という言葉が意味するものが曖昧であり,それについては正誤は問えない。
問題46では,2は明らかに誤りだが,状況によっては1や4もマイナスに作用する可能性もある。また問題81では,出題者が障害を受容する人を「壮年期の就業している者」と想定しているならば3かもしれないが,就業前の学生と考えると,わずかこの1行の設問文で限定的な回答を求めることには無理がある。
問題49にある「気湿」という言葉は一般常識化しているものなのであろうか疑問である。他の3つが「気○」であるから無理に揃えたのではとさえ疑いたくなるような単語である。
問題51にあるような,与薬時に姓名を言ってもらうという行動自体は誤りでないとしても,痴呆の程度や悪戯盛りの小児に対しては必ずしも「確認」ということにはならない場合もあり,これについてはどう考えたらよいのであろう。疑問が残る。
問題91では「指導で適切なものは」と問うているが,選択肢の内容は指導ではない。日和見感染の1つにカリニ肺炎があるというのは事実であって,それについてどうしたらよいのかについて伝えることこそが指導ではなかろうか。問題92は91と同様で,ステロイド薬投与量調整の適否についての理由を患者が理解することを援助することこそが指導の一部であろう。
状況設定問題
午後の状況設定問題では,せっかくの状況説明文が生かされておらず,もったいないと思われる設問や,状況説明文と連携していない問題がいくつかみられた。実際には,設問が状況説明にあまり関与しておらず,むしろ午前の問題ではないかと思われる問題や,状況説明文の条件だけから答を1つに絞り込むには無理があるものも散見された。
問題31では,一見すると4が優先度が低そうである。しかし,例えば尿崩症があれば回数とともに尿量も同程度に重要な観察項目となる。特に高齢者にとっては脱水は生命予後に直結する。この状況でのすべての原因は「痴呆」のためであると無言の大前提がなされてはいないだろうか。
問題55ではdを直接示唆する状況説明は見当たらないもののaとの関連からdを不適切とは言い切れまい。cもbと間接的に関係ありそうだとすれば,これ以上何を根拠に絞り込んだらよいのであろうか。
問題58は可能性の高さを状況説明文からだけでは決められない。受験テクニックとしては「同室者」という言葉が頻回に登場することから2に誘導されるかもしれないが,この患者の精神分裂病が妄想型であるかもしれず,何とも答えようがない。問題59,60も,この状況説明文の曖昧さが受験生の回答困難を導くものと言える。
全体を振り返って
今国家試験で全般的に言えることは,疾患そのものを問う問題はかなり少なくなっている。しかしながら,特に母性看護に関連する問題では従来に近いものも比較的認められている。また,人間を多面的に広く捉えることが看護の醍醐味と言われているにもかかわらず,特に精神看護に関連する問題では,ペーパー試験という制限からどうしても限定的な回答を期待せざるを得ない,という現実とのすり合わせに苦労した面も見受けられた。また,時代を反映して在宅場面を想定した問題の増加も目立った。しかし一方の現場では,ホームヘルパー,介護福祉士といった保健医療に関わる職種が,病院等の医療施設外で急激に増えている。すなわち,在宅という場面はプレーヤーが増えたアリーナとなっているわけであり,「看護職は改めて『看護業務とは何か』について真剣に見つめ直さなければならなくなっている」2),という考えに同感である。
そもそも看護婦国家試験とは免許試験であり,臨床場面で看護活動を行なうことを許可してよいかを判断するものである。午前の問題26のような基本中の基本とも言うべき問題ができなかった場合には,たとえ他の問題の正答数が多くとも合格にはできない,とするべきではなかろうか。医師国家試験では通称「禁忌問題」といい,そのような仕かけをしていると聞いている。たとえて言うならば,自動車運転免許試験で縦列駐車の出来映えと交通信号解釈の出来映えが同じではいけないということである。縦列駐車は多少下手くそであっても,赤信号と青信号を間違うようなことは決して許されないのである。
しかしながらただ通ればよいといったものであっては困る。試験で問われる形式はいわゆる○×式であっても,その回答に至る根拠と過程を身につけていなければ,ちょっとした応用すら効かないことになる。
例えば,自動車の運転免許を考えてみよう。特に,「左折の時にはミラーをよく見て歩行者や自転車を巻き込まないように気をつけなければならない」ということは知っていて当然である。しかし,それだけではなく運転者から死角が大きいことや,内輪差によって思った以上に車が内側によってしまうことなどを理解していることこそが重要なのである。何を見るとはなしに,機械的にミラーを眺めるだけならばせっかくの行動にも意味がない。そればかりか,かえって見たという行為に慢心してしまうおそれもあるのである。「人間を多面的に広く捉えることが看護である」と言われているにもかかわらず,受験生の思考をパターン化してしまう危険性についてはもっと危機感を持つべきではなかろうか。
出題基準は,従来の「疾患モデル」でない独自の「看護モデル」に基づくものであり,「病気ではなく健康を軸とした内容である」とされている。しかし現実の活動場面にあっては,果たしてこの出題基準は十分に生かされ得るものなのであろうかという批判1)にもうなずけるものがある。現実として,「看護が臨床場面で作用するためには,病態や疾患の知識は欠かせないもの」1),という真部の見解には現実味を強く感じさせられる。本来国家試験は,臨床場面での活動を許可してよいかどうかを判断する免許のための試験であり,学問体系としての看護学についての知識を問うことを本務としたものではないはずである。看護モデルの一例として,提示された出題基準を今後も育んでいくとともに,自らの枠組みに自らを縛り込んでしまうことのないよう,互いが注意を喚起していきたいと考えている。
〔文献〕
1)真部昌子:「国家試験出題基準」はどのような看護婦を求めているのか,看護教育,41(3),202-207,2000.
2)南裕子:21世紀における社会環境の変化と看護教育の課題,日本看護学教育学会誌,9(3),53-61,1999.
