バーチャルリアリティ技術による新しい医療技術の幕開け
小山 博史(国立がんセンター中央病院医長 脳神経外科)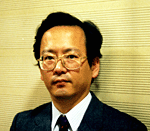 バーチャルリアリティ(以下VR)といえば,テレビゲームを中心としたゲームの推進技術と考えられる傾向にある。しかし,近年VR技術を用いた訓練システムや治療システムが登場し,医療医学への応用が欧米を中心に盛んになっている。
バーチャルリアリティ(以下VR)といえば,テレビゲームを中心としたゲームの推進技術と考えられる傾向にある。しかし,近年VR技術を用いた訓練システムや治療システムが登場し,医療医学への応用が欧米を中心に盛んになっている。
本稿では,今後期待されるVR技術による新しい医療技術応用開発の可能性について,国立がんセンターでの研究成果を中心に概説し,昨年開かれた日本学術会議分野7呼吸器学研究連絡会・内視鏡研究連絡会主催のシンポジウム「新しい医療技術の展開;バーチャルリアリティ技術の医療応用」について報告する。
VR技術とは?
VR技術とは,「人間に対して人工的擬似知覚刺激を与え,現実とは異なる空間を認知させる技術」である。ノースカロライナ大のフックス教授は「経験を増幅させる技術」と称し,東大の舘教授は「人工現実感」と唱えている。VRシステムの基本的構成要素を図1に示す。
医学とVR技術の関連
VR技術は,基礎医学の分野では人間に対して工学技術により擬似的な知覚刺激を与える技術であるために知覚生理学や認知科学,精神心理学との関連が深い(図2)。また,臨床応用分野では,人工的な空間を再構成することにより体験型医学教育,手術訓練(特に管腔手術),手術ナビゲーション,遠隔手術,リハビリテーション,ストレス緩和,PTSD(Post Traumatic Stress Disorder;心的外傷後ストレス障害)やPhobia(恐怖症)に対する行動療法に応用されている。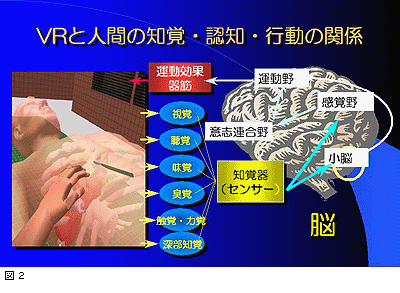
国立がんセンターでのVR研究の成果
■医学教材解剖学教育への利用に関する研究では,VR技術を用いて人体解剖の基礎医学教育を学生と教師が同じ仮想空間の中で仮想臓器を用いながら,様々な討議ができる環境構築に関する研究を進めている(図3)。
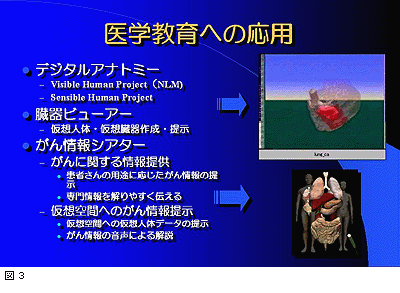
■医学教育(手技訓練)
医学教育への応用に関する研究への利用は,今まで不可能であった注射や縫合等の手技や操作の教育訓練方法と,その達成評価方法を可能にしつつある。国立がんセンターでは平成6(1994)年度に脳腫瘍の開頭手術の手順を体験学習するための研修医向けのシミュレーションシステムについて産官で共同研究を行ない実現した。さらに,平成10(1998)年にはリアルタイムにボリュームレンダリングで任意の範囲のボリューム削除が,触覚を体感しながらできるシステムを構築した。これにより臓器の詳細な表現と触感の表現によるリアリティの向上を図ることが可能となった(図4)。
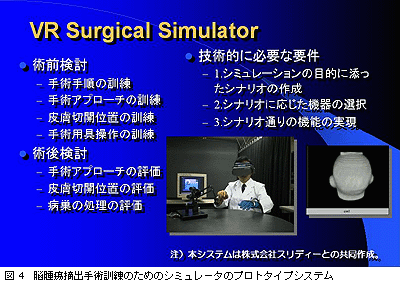
■次世代の画像再構成
3次元画像処理は今まで2次元画像診断の陰に隠れてきた。その理由は,CTやMRから再構成する処理過程が煩雑であることや,リアルタイムボリュームレンダリング法で画像表示させるためにはスーパーコンピュータなみの画像処理速度が必要であり,そのために高価なコンピュータが必須であったことによる。
しかし,コンピュータテクノロジーの急速な進歩と低価格化により,パーソナルコンピュータでも画像再構成が容易となり,脳動脈瘤発見のための脳ドック等への臨床応用が盛んになりつつある。ここ数年で,新しい放射線診断法としての地位を確立するに十分な基礎技術が成熟してきている(図5)。
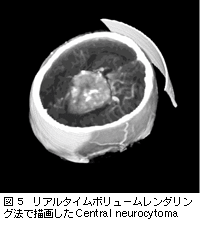
■精神心理療法への応用
VR技術が人間の多様な知覚(視覚・聴覚・触覚・嗅覚等)に刺激を与え仮想体験させる技術であるため,医療分野と関わりが深く,特に閉所恐怖症や高所恐怖症等の神経症への脱感作療法として利用されつつある。
リハビリテーションへの応用は,米国および欧州での技術開発が進んでおり,頭部外傷や血管障害や手術後遺症による認知障害患者へのリハビリテーション法の開発や,運動障害に応用研究が行なわれている(表1)。
一方,VR体験自体が体験者にストレスをきたすことが知られているが,逆に快適な仮想空間を提供することでストレス緩和を行なうがん緩和療法としての研究を開始し,主観評価では精神的な状態の緩和効果を認めている(表2)。
■ロボット技術との融合による
新しい低侵襲手術の術式の開発
人口の高齢化と社会的なニーズにより,外科の分野での低侵襲手術の開発がここ数年で急速に進んでいる。この実現のためには,技術要素レベルをクリアしていくことが必要となる。国立がんセンターでの低侵襲手術支援システムの開発用に作成した技術達成レベルを図6に示す。
国立がんセンター中央病院でもがん克服新10か年戦略事業の中で官民共同研究を行ないVR-Guided Neruosurgeryを実現するためのシステムを構築した(図7)。このシステムの特徴は,術野・再構成臓器・穿刺針の3座標が各々変化してもリアルタイムに合わせることが可能で,フリーハンドに穿刺生検操作ができるところにある。本装置は,レベル4の段階までの機能を可能とした。
現在,機能を向上させるためには医療用仮想空間を操作するマニュピュレータに関する研究,特にRobotics技術をVR技術と融合させ利用する新しい外科手術手技の開発に関する研究を進めている。
日本が得意とする世界に誇るロボット技術がやっと医療応用開発研究へ眼を向け始め,Telesurgery,Remote Surgery,Humanoid Robotic Surgeryが可能な医療機器の実現に向けた研究開発が21世紀の新しい医学の展開として必要な時代になってきている。
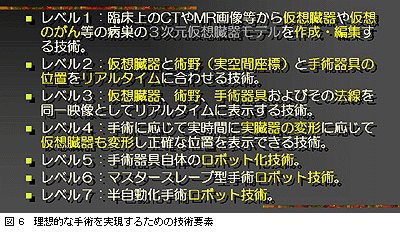
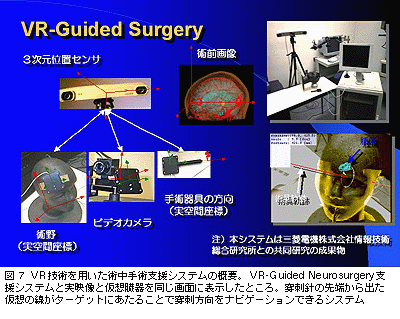
VRと生命倫理との関連
VR技術が医療医学へ応用されるにつれ,遺伝子工学などの先端技術と同様に倫理的な問題を考慮する必要性が指摘されている。VR技術を医療医学へ利用する場合に生じる倫理的な問題には大きく3つの場合が考えられる。1つ目は,被験者を必要とするVR技術研究の場合,2つ目は,VR技術を用いた新しい医療機器の有効性について検討を行なう場合,3つ目はVR技術自体が持つヒトに与える影響に関する問題である。このような場合は,「ヘルシンキ宣言」が大原則となり,VR技術を用いて人間の生理学的機能を解明したりする場合の被験者の同意は必須の要件となる。
VR技術を用いた医療機器の有効性に関する検討では,医師に対してVR技術を利用した新しい治療を施行する場合には詳細な研究計画書(プロトコール)の作成と独立した施設内評価委員会(IRB)によるその治療計画のAuditが必要としている。患者側保護の立場からは,医師は被験者の自由意志によるインフォームドコンセントを,できれば文章で入手すべきである。
第3の問題として,VR技術が持つ技術要素そのものが人間に与える影響を考える必要がある。VR技術の最大の特徴は人間の知覚器に刺激を与えて,あたかも現実と異なる空間に存在するような感覚(没入感)を得る技術ということである。それゆえに,「人間の精神や心理的状態や認知等の高次機能に影響を与える可能性があり慎重な対応が必要である」と,1991年の「Lancet」で指摘されている。このような場合の医師の役割として,「ヒトにおけるバイオメディカル研究は,医学的資格を持つ人の監督の下に,臨床的に有能な人によってのみ行なわなければならない……(中略)……被験者のプライバシーを尊重し,彼の身体的,精神的全体性およびその性格や個性に対して与える影響を最小限度に留めるためには,あらゆる予防手段を講じなければならない」としている。社会学的影響については,長期の疫学的あるいは社会学的研究も必要となるであろう。このように,この問題は俯瞰型研究として総合的かつ先駆的な研究計画を作成する時期にきている。
日本学術会議シンポジウム
VR技術は,人間の生理学的機能と深く関連のある,今までにない医学と工学を融合させた新しい技術であり人間の神経生理学的研究にも応用できる可能性が高い。新しい技術が世の中に登場した際は,電話やテレビが世の中に出現したようにいろいろな憶測が生まれる。時代とともに技術が社会に浸透していくまでは幾多の課題を克服していく必要がある。昨(1999)年11月19日に,日本学術会議分野7の中の呼吸器病学研究連絡会と内視鏡学研究連絡会(代表=国立がんセンター名誉総長,現済生会中央病院長 末舛惠一先生)で,学術会議シンポジウム「新しい医療技術の展開:バーチャルリアリティ技術の医療応用」が開催された。特別講演に東大工学部教授の舘章先生をお招きし,また東女医大長の高倉公朋先生をはじめ医学界の著名な方々のVR技術に関する講演が行なわれた。小生もお世話をする機会をいただき大変勉強になり,VR技術の応用が医療に多くの恩恵をもたらすことを再認した。また,本シンポジウムは,国内での医療医学分野主催のVRに関するシンポジウムとしての価値は高く,また,VR技術を21世紀の医療医学の基盤技術として捉えたことの意義は大きい。
まとめ
VRは今後医学分野に多大の貢献をもたらす技術であることは疑いない。表3に今後VR技術を用いて効果が期待される医療分野の一覧を示す。本稿によりゲームとは別のVR技術の医療への有用性についてご理解いただければ幸いである。
〔補記〕
この記事でも紹介されている,VRの医療応用の最先端が議論された日本学術会議シンポジウム「新しい医療技術の展開:バーチャルリアリティ技術の医療応用」の模様をおさめたビデオが1部5500円(送料込み)にて販売中。
ご希望の際には,下記まで申込むこと。
〒108-0073 東京都港区三田1-4-17
済生会中央病院 院長室内(黒田)
| 表1 リハビリテーションへの応用 | |
|
| 表2 バーチャル空間を用いた行動療法 VRT(Virtual Reality Treatment) | |
|
| 表3 将来のVR技術の医療医学適応分野 | |
|
