特別寄稿
移植免疫学再考
免疫学と臓器移植の過去と現状より
小林英司 自治医大臨床薬理学教室・同大大宮医療センター外科助教授
 最近,医学生に対する免疫学の講義の一端で移植免疫学を教えているが,この学問は今後,基礎系と臨床系のどちらに属するべきなのかを考えることがある。もちろん移植免疫の基礎はPeter Medawarという偉大な基礎免疫学者により築かれたのである。彼が移植片拒絶という現象が免疫反応に他ならないと証明したのは1950年代半ばのことである。その後,拒絶反応というダイナミックな現象を用いて多くの免疫反応が研究された。近年,分子生物学の応用で免疫学は子細に研究され,その分野も多岐に細分化された。現在の移植免疫学は免疫学のごく一部になりつつあるような気がする。
最近,医学生に対する免疫学の講義の一端で移植免疫学を教えているが,この学問は今後,基礎系と臨床系のどちらに属するべきなのかを考えることがある。もちろん移植免疫の基礎はPeter Medawarという偉大な基礎免疫学者により築かれたのである。彼が移植片拒絶という現象が免疫反応に他ならないと証明したのは1950年代半ばのことである。その後,拒絶反応というダイナミックな現象を用いて多くの免疫反応が研究された。近年,分子生物学の応用で免疫学は子細に研究され,その分野も多岐に細分化された。現在の移植免疫学は免疫学のごく一部になりつつあるような気がする。
一方,臓器移植治療は,移植に有利な免疫抑制剤の応用で,臨床医学の中できわめて重要な位置を確立した。京大移植免疫医学講座(主任:田中絋一教授)は1996年に開設され,現在,1か月に6症例の生体肝移植を行なう,日本における肝移植のメッカであり臨床の講座である。本稿では,免疫学の歴史的流れの中で移植免疫学が,また移植治療がどのように発展してきたかを概説する。そして今後の移植免疫学のありかたに対する私的意見を述べたい。
特異性(specificity)に基盤を 持つ免疫学
1996年12月10日,Rolf M.ZinkernagelとPeter C.Dohertyにノーベル医学・生理学賞が授与された。T細胞の特異抗原の認識の仕方を解明した業績に対するものである。特異抗原と自分の持つMHC(主要組織適合抗原複合体)の両方を認識する(genetic restruction)仕方をダイナミックに説明した仕事であった。この仕事でキーになるのが特異性である。過去の歴史をみても,この特異性を研究することがすなわち免疫学の流れであるような感がある。Edoward Jenner(1749~1823)が,牛痘を人為的に接種することで痘瘡の予防に成功したのが18世紀末である。しかし,免疫学がただ単に「疾患から免れる」という漠然とした意味から,“non-recidiv(2度なし現象)”という再感染に対する防御反応と定義されたのは,Louis Pastear(1822~95)による。彼は,病原微生物の存在を明らかにし,ワクチンの実用化を行なった。免疫学の特異性に対する歴史はここからはじまると言っても過言ではなく,彼が免疫学の祖とされる由縁である。
Karl Landsteiner(1868~1943)は,血液型の発見者として有名であるが,化学構造の異なった人工抗原を用いて抗原特異性を明確にした。これは,これまでの病原微生物に対する血清学(serology)の流れから,抗原を化学の立場から解析しようとする免疫化学(immunochemistry)へと発展したかたちとなった。
1950年代に入ると,これまでの蛋白科学的なアプローチだけでなく,生物学的な理論が数多く出てくる。その中で,Macfarlane Burnetの唱えたクローン選択説(clonal selection theory,1957)は,外来抗原に対し特異性を持つ細胞がどのように拡大するかを示した。そして後の世の抗体産生理論の発展をうながした。その後しばらく免疫学は,現象を合理的に説明しようとする理論と,それを実験的に証明しようとする努力に多くの情熱が傾けられた。
1980年代に入ると,急速な進歩を遂げてきた細胞工学や遺伝子工学の技術が免疫学に導入されてくる。1987年度のノーベル賞受賞者となった利根川進博士は,天文学的な数の抗原に抗体可変部がどのように対応するかを証明した。すなわち,免疫グロブリン可変部の遺伝子は,V領域,D領域,J領域各々に複数個あり,胚細胞期のリンパ球が各領域からそれぞれ1個ずつ連結して再合成が生じることを証明した。これにより抗原特異的に作られる抗体の多様性が説明できるようになった。これも免疫現象の特異性の探求であった。このように,免疫学の流れは,特異性の解明と追求であるように思える。
非特異的免疫抑制剤の導入で 現実化した移植治療
近年,日本は宗教的な問題などから移植後進国となったが,世界的には臓器移植は末期臓器不全の唯一の治療法として確立されている。世界的に移植治療が認められた歴史はノーベル賞受賞者の歴史としてみることができる(表1)。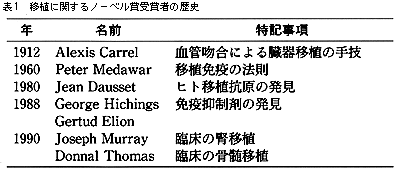
20世紀初頭,血管吻合法にその名を残すAlexis Carrelは,いったん切離した臓器を血管吻合することで臓器を移せることを示した。その後,異系間で臓器を移すことが試みられたが,移された臓器は一時的には機能したが早々に廃絶した。当時は,炎症や栄養不良によると考えられていたが,その反応が免疫による拒絶反応であることを証明したのは,Sirの称号を持つPeter Medawarであった。
Medawarの5つの実験
1956年,Medawarによって移植免疫の基本とも言える5つの実験が示された。第1の実験は,自己物質と異物(非自己)との識別能をみたものである。当時確立された近交系マウスを用いて,同系間の皮膚移植はacceptされ,異系間のそれは拒絶されるという実験である。第2の実験は,応答の記憶をみたものである。第1の実験で異系の皮膚移植を行ない第1の移植片を拒絶した宿主に再度同じ異系の皮膚移植を行なうと,一次拒絶の場合は約10日で移植片が失われるが,2度目の移植片はより早く拒絶されることをみたものである。第3の実験は応答の特異性をみたものである。第2の実験の宿主に他の異なる異系のマウスの皮膚を移植した場合は,一次拒絶反応を示すことから,応答の記憶には特異性を持っていることを示した。第4,第5の実験はそれぞれ異系皮膚を拒絶した宿主の細胞性免疫応答および液性免疫応答をみたものである。前者は,皮膚を拒絶した宿主の脾細胞を宿主と同系の正常マウスに注射(adoptive cell transfer)した際,その宿主が同一ドナー皮膚移植片を二次反応で拒絶することを示すものであった。体液性応答の実験は,皮膚移植片を拒絶した宿主の体内にドナーに対する抗体ができていることを示した実験であった。免疫抑制剤の臨床応用
しかし,この法則で血管吻合法を利用することで臓器移植ができるという夢の治療は,通常の状態ではこの免疫学的拒絶反応という壁を乗り越えることができないことが明らかになった。その後約20年間は,臨床の臓器移植は遺伝子背景が同一である一卵性双生児間でしか成立しなかった。その間,Jean Daussetはヒトの移植抗原を明らかにした。現在も使用されているアザチオプリンは,1952年に発見され,1960年代に臨床応用され始めた。1988年のノーベル賞はHichingsとElionのアザチオプリンの発見を称えるものであった。これはただ単に新しい薬物を発見したという業績ではなかったことが,この名誉ある賞の受賞でも十分理解できる。しかし,臨床の臓器移植が格段に進んだのは,1970年にBorelにより発見されたサイクロスポリンが臨床応用された1980年代に入ってからである。その後の1世紀の間に移植治療が社会的にも確立したことは,1990年のノーベル賞受賞者の顔ぶれでわかる。Joseph Munreyは臨床の腎移植で,Donnall Thomasは骨髄移植でその功績が認められた。さらに1990年代は相次いで新しい免疫抑制剤の臨床応用がはかられ,移植治療は特別なものでなくなった(表2)。この歴史から見てもわかるように,非特異的免疫抑制剤の臨床応用で移植治療が現実のものとなった。
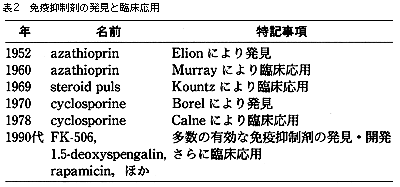
狭間をさまよう現在の移植免疫学
外科医で移植治療に興味がない人はむしろ少ないであろう。なぜなら,本治療が現在の末期臓器不全に対する唯一の方法であるからである。患者さんを思う外科医なら賛否は別として興味はあるであろう。多くの先輩外科医がそうであったように,われわれと同世代の外科医は,移植免疫を志し,また移植治療をマスターすべく欧米へ留学している。しかし,たとえ留学から帰ったとしても,時には各大学間の壁が問題となり,われわれ若い世代が協力し移植治療を行なうには,まだまだ時間がかかりそうである。また免疫学を志す者で移植免疫に興味のない人はいないであろう。しかし,前述したが,移植治療は現在の非特異的免疫抑制剤の使用で一般化されている。一方で,移植免疫学はあくまでも免疫学の流れの中で特異性を求めることにこだわりがある。もっと現実的な話にすると,消化器癌の臨床をやりながら外科医が移植免疫学を志してもアカデミックさに乏しくなる(一部で非常に高いレベルで仕事を続けておられる方もいらっしゃるが)。また基礎の免疫屋と呼ばれる免疫学者にとってみれば,移植免疫学は免疫学の一部にすぎないこと,臨床的状況を理解することが難しいなどの問題点がある。現在の日本においては,移植免疫学はそのような狭間にあるように感じられる。
今後は臨床と基礎の併合が必要
それでは,移植免疫学は今後どのようにあるべきなのであろうか。日本という小さな島国において,移植治療を各大学が競ってやる必要はないし,またいくら有効な免疫抑制剤が導入されたからといって,移植免疫学を勉強しないでいるわけにはいかないであろう。結局は,臨床と基礎を併合したような講座あるいはセンターが必要であることは明白である。大学で臨床をやりながら移植免疫学を携わる者にとっては,まさに夢のような話だが,前述したように,特異性の追求と非特異的免疫抑制剤の使用の現実を総括するようなことができれば,日本の移植治療も移植免疫学も世界に声を大にできるのではないかと考えている。〈追記〉
本文中の免疫学の特異性についての歴史は,藤原道夫先生(現東大実験動物センター)の新潟大学医学部における免疫学の講義内容を参考にをまとめた。
