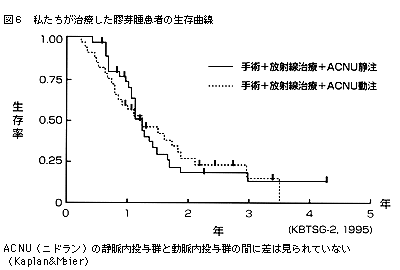連載
脳腫瘍
発生要因から遺伝子治療まで(7)
抗がん化学療法の現状と問題点
生塩之敬(熊本大学教授・脳神経外科)はじめに
この連載も回を重ね7回目となった。今回は悪性脳腫瘍の治療の現況を化学療法に焦点を当てて述べたい。悪性脳腫瘍の多くは脳の中に浸潤性に発育するが,場所が場所だけに手術や放射線治療は強い制約を受ける。化学療法にも薬剤耐性,血液脳関門の存在,副作用などの問題があり,使用が可能な薬剤は限られている。したがって悪性脳腫瘍の治療に際しては,すべての治療法が総動員され,しかもそれぞれの治療法が最大限の効果を発揮した集学的なものでない限り,患者の延命や治癒は望めない。このような集学的治療の対象となる原発性悪性脳腫瘍のうち,主なものは悪性グリオーマ(膠芽腫と退形成膠腫),髄芽腫,頭蓋内原発胚細胞腫,および頭蓋内原発悪性リンパ腫などである。これに転移性脳腫瘍が加わる。これらの腫瘍に対して,化学療法が有用であることはすでに証明されているが,腫瘍によっては,なお化学療法に強い抵抗性を示すものから,最近の化学療法の進歩により劇的に治療成績が向上しているものまでさまざまである。
化学療法が救った脳腫瘍患者たち
悪性脳腫瘍の化学療法が新しい時代を迎えたのは1960年代の後半,血液脳関門を通過し,しかもグリオーマに感受性のあるニトロソウレア系抗がん剤(BCNU,CCNU,ACNU〔ニドラン〕)が開発された時に遡るが,1970年代後半にはシスプラチンを主剤とした多剤併用化学療法が原発性頭蓋内胚細胞腫瘍に対して著効を呈することが証明され,化学療法が再び脚光を浴びるに至っている。小児の松果体部やトルコ鞍上に好発する原発性頭蓋内胚細胞腫のうち,胎児がんや卵黄嚢腫瘍は極めて悪性度が高く治療に抵抗し,患児の生存日数は1年前後という悲惨な腫瘍であった。ところが,Einhornらが性腺の胚細胞腫に対してPVB療法(シスプラチン+ビンブラスチン+ブレオマイシンの3剤併用)を開発して以来,様相が全く異なってきた。すなわち,このPVB療法さらにはPE療法(シスプラチン+エトポシドの併用)を治療に組み入れることにより,これらの腫瘍がよく治療されるようになってきた。図1に私たちが治療した胎児がんと卵黄嚢腫瘍患者の治療成績を示すが,PE療法を加えた集学的治療を開始して以来1人の患児も失っていない。
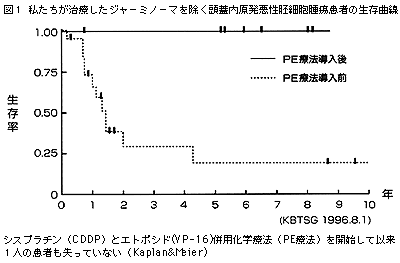
図2は腫瘍の髄液腔内転移と意識障害で発症した当時9歳の女児の経過を示すが,今年は見事に高校入試に合格している。まさに化学療法の勝利と言ってよい。
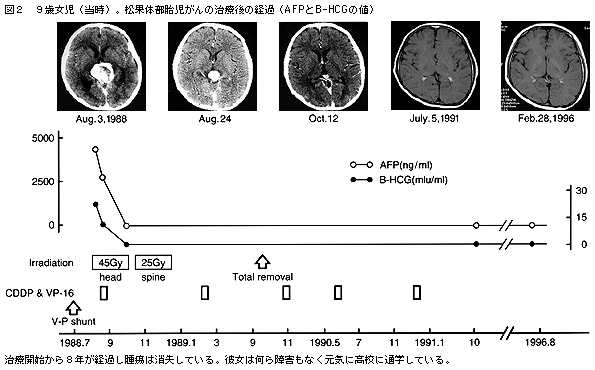
このような成功を踏まえて,もう1つの頭蓋内胚細胞腫瘍であるジャーミノーマに対しても治療法の改善が検討されている。すなわち,このジャーミノーマは悪性腫瘍でありながら放射線に対して感受性が高いことから放射線治療により高率に治癒していたわけだが,放射線の副作用として患児に現れる身体的および知能的障害が問題であった。そこで,化学療法を主体として治療することにより放射線治療を縮小する方法が試みられている。今までのところこの試みは成功する可能性が高いと考えられている。胚細胞腫瘍におけるほど劇的な改善はもたらしていないが,化学療法の有用性が証明されたことから,従来の治療法に変革が現れているもう1つの腫瘍に,髄芽腫がある。髄芽腫はやはり小児に好発する極めて未分化な腫瘍であるが,放射線に感受性が高いことから,従来から治療成績は比較的良好であり5年生存率はおよそ60%前後である。化学療法に対しても感受性が高いことが知られており,浸潤や髄液腔内への転移の存在など病期の進行した患児では,化学療法に統計学的にも有意な延命効果が認められている(図3)。
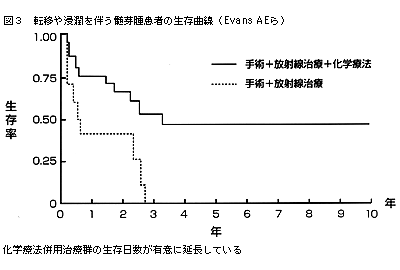
化学療法としては,放射線治療中は副作用(骨髄機能障害)の重ならないビンクリスチンを使用し,照射終了後からニトロソウレア剤とビンクリスチンの2剤併用を行なうのが一般的である。この腫瘍は髄液腔内に播腫転移しやすいため,放射線治療としては予防的に全脳全脊髄照射が行なわれてきたわけであるが,比較的良好な延命効果が得られる一方,治療を受けた患者,とくに幼小児では放射線治療の副作用である精神的および肉体的発育障害が大きな問題となってきた。そこで,特に放射線の障害を受けやすい,髄鞘形成が完成していない3歳未満の乳幼児に対しては,放射線照射を控え化学療法のみで治療し,患児が3歳になった時点で腫瘍の残存があれば放射線治療を加える方法が試みられている。
Aterらは,2歳以下の髄芽腫患児12名を術後まずMOPP療法(ナイトロゲンマスタード+ビンクリスチン+プロカルバジン+プレドニゾロンの4剤併用)により治療し,以後放射線治療を必要としなくなった患児6名を含め,全体で65%の5年生存率を得ている。放射線治療が行なわれなかった患児には精神および発育の障害はみられていない。このような結果は乳幼児髄芽腫に対する新しい治療方針の正当性を示しているが,この腫瘍は治療が無効な場合直ちに致命的なものだけに,この方法を一般的に採用するまでにはさらに十分な検討が必要である。
化学療法が有効な成人脳腫瘍
悪性グリオーマ(膠芽腫と退形成膠腫)は悪性度と頻度から悪性脳腫瘍を代表し,しかも難攻不落であったが,最近その一角が崩れてきた。すなわち化学療法を加えた集学的治療の進歩により,退形成膠腫患者の生存日数が徐々に延びはじめ,兄貴分の膠芽腫との間に水が開き始めている(図4)。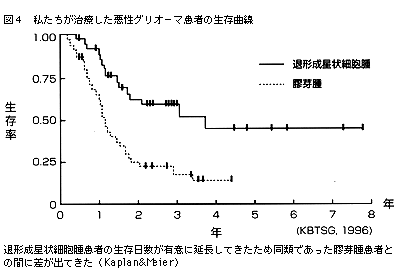
この腫瘍には悪性の星細胞腫,乏突起膠腫,および上衣腫が含まれる。これらの腫瘍は脳内で浸潤性に広がるが,しばしば肉眼的に境界を判断することができるため,これを探り可能な限りまず肉眼的な全摘出を図る。化学療法は,その後原則として2週間以内に,放射線治療と同時に開始し並列して使用する。ACNU単独か,これに副作用が重複しない薬剤を併用した全身投与が一般的である。
種々試みられた多剤併用のうち,CCNU(ロムスチン),プロカルバジンおよびビンクリスチンの3剤併用療法(PCV療法)はニトロソウレア剤単独と比較して統計学的にも有意な延命効果が認められている(図5)。私たちは,ACNUとインターフェロンを併用することによりACNU単独と比較して有意な延命効果を認めている。患者の生存期間中央値は4年を越えようとしている。
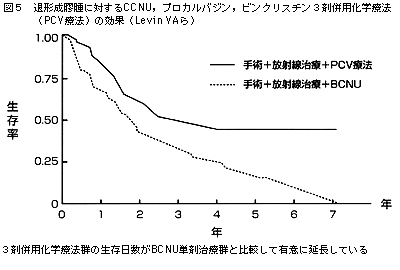
悪性リンパ腫は高齢者に好発する腫瘍であるが,放射線と化学療法に感受性があり一時的には腫瘍の消失をみることができる。化学療法としてはPE療法,CHOP療法(サイクロフォスファマイド+アドリアマイシン+ビンクリスチン+プレドニゾン4剤併用)やメソトレキセートの大量療法などに有効性が見られている。しかしながら,未だいずれも延命効果に関しての検定結果は出ていない。
転移性脳腫瘍に対して集学的治療が有効であり,肺がんの脳転移を例にとると2/3の確率で完全寛解を得ることができる。したがって,原発がんがよく治療されている限り積極的な治療の適応になる。化学療法としては,転移性脳腫瘍と言えども,部分的には血脳関門は保たれていることから,感受性がありしかも関門を通過する薬剤を使用する必要がある。一般にはニトロソウレア剤を加えた多剤併用療法が行なわれている。
私たちは肺がんの脳転移患者100名を対象としてphaseIII studyを行なったが,放射線治療単独の有効率が36%に対して,放射線とACNU+テガフール併用治療群の有効率は72%であり化学療法に有意な腫瘍縮小効果を認めている。
手強い膠芽腫
先に述べた悪性グリオーマのうち,退形成膠腫に水を開けられ取り残されたのが膠芽腫である。取り残されたとはいえ,最近では多くの患者が化学療法を含めた集学的治療により有意義な社会または家庭生活に復帰しているわけであるが,ただ平均生存日数が1年半を越えるに至っていない。2年以上の延命をめざして,化学療法も多剤併用,大量投与または局所投与法など数多くの研究が躍起になされているが,残念ながら従来のニトロソウレア剤単独治療と比較して統計学的に有意な延命に結びつく化学療法は開発されていない。図6は私たちのACNU動注療法の試みを示すが,静注群と比較して生存曲線に差を認めていない。この腫瘍に対する抗がん化学療法の改善には何らかの発想の転換が必要と思われる。