診療に関わる病理医の存在意義をアピール
一般公開シンポ「国民が求める病理医のあり方」
 認定病理医など診療に関わる病理医の組織である日本病理医協会(会員数約1000人)主催の一般公開
シンポジウム「国民が求める病理医のあり方」(司会=新潟市民病院 岡崎悦夫氏,東海大教授 長村義
之氏)が,さる4月26日,東京・千代田区の東海大学校友会館にて開かれた。
認定病理医など診療に関わる病理医の組織である日本病理医協会(会員数約1000人)主催の一般公開
シンポジウム「国民が求める病理医のあり方」(司会=新潟市民病院 岡崎悦夫氏,東海大教授 長村義
之氏)が,さる4月26日,東京・千代田区の東海大学校友会館にて開かれた。
病理医に関しては日本病理学会が厚生省に「病理科」の標榜新設を要望してきたが,今年3月見送ら れた経緯がある。今回のシンポジウムは,病理医に対する市民の認知度の低さを改善するにはどうすべき か,医療をよくするために病理医はどのような役割を果たすべきかなどを考える目的で企画されたもの。 病理医のみならず多数の市民の参加を得て開催された。
患者から見えない存在
シンポジウムでは6人の演者が発言。まず患者の立場から,辻本好子氏(ささえあい医療人権センター COML代表)とワット隆子氏(あけぼの会会長)が病理医に対する考えを述べた。辻本氏が代表を務めるCOMLは,患者の主体的な医療参加を求める団体。辻本氏は,患者にとって認 知度の低い病理医の存在と役割を理解するためのセミナーを開いた経験を報告した他,電話相談に寄せら れた病理医の診断に関わる事例も紹介。「主治医による診断の説明の際に,冷静な第三者としての病理医 の立ち合いがあれば患者の受け入れ方が違ったのに」と痛感するトラブルがあることを示す一方,病理医 の誠実な説明によって患者・家族が納得できた例も提示した。さらに,病理医と臨床医がよい関係でない 場合には医療不信につながりかねないとして,内部の努力を求めた。
乳癌手術体験者の会の会長であるワット隆子氏も,患者にとっての病理医のなじみの薄さを指摘しな がら,「現在乳癌にはいろいろな手術法があり,患者がそれを選択する時代。だからこそ病理医の重要性 がある」と発言。「病理診断は画像診断と同じく目で見ることができ,患者が自分の状態を納得するのに 最適な材料ではないか」と述べ,病理科の標榜にも期待を示した。
続いて,読売新聞で連載「医療ルネサンス」を担当してきた丸木一成氏が登壇。「患者には今“自分 のことは自分で知ろう”という大きな意識変革が起きている」と述べ,病理診断の正確さの評価に関して 「専門家同士のかばい合いをなくしてこそ国民に信頼される医療が可能」との考えを提示。また病理医の ネットワークや医学教育の充実など,解決すべき課題もあげた。

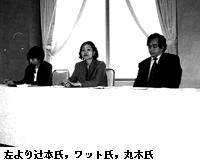
臨床医からの期待 - 病理診断の質管理
次に,外科医の立場から病理医に求めることについて,竹中文良氏(前日赤医療センター外科部長, 日赤看護大教授)が提言。癌診療では病理診断のウエイトが大きいだけにミスが重大な結果を生むとして, 病理診断にからむ医療過誤の原因を分析した。また外科医の側の術後合併症の診断ミスについても触れ, 制度的なチェック体制が必要であると強調。病理医が前面に出ることでチェック機能が働くのではないか と述べた。また,抗癌剤による癌治療に携わる福島雅典氏(愛知県がんセンター)は,病理診断の「質の管理」 に関して病理医の役割への期待を述べた。福島氏は,臨床医にとって病理医の診断は絶対的な価値を持つ と述べたのち,解決すべき課題として病理医間の診断の不一致を指摘。各地域でのレビューシステムの構 築を求めた。また今後は病理医も遺伝子診断をめぐる社会的な議論に参加する義務があると付け加えた。
最後に,病理学出身で,日本医療機能評価機構評議員の河北博文氏(河北総合病院理事長)が,医療 機能の評価の面から考えを述べた。河北氏は,日本の医療は量的な公平から質を重視するようになってき たと解説。しかし現在は,本来まず質として評価すべき診療の質の評価基準がないとして,今後の「医療 の学術性と客観性」における病理医の役割の重要性に期待を寄せた。また病理医の教育のあり方にも意見 を述べ,(1)十分な数の病理医の養成,(2)「臨床病理」教育の充実などを訴えた。
病理医をいかに医療に組み込むか
その後,シンポジストの意見を受けて,参加者との意見交換が行なわれた。この中で一般の参加者か らは,家族や友人が病気になった時の経験を中心に,「主治医でなく病理医からの直接の説明が聞きたい」 や「確定診断ができない場合には率直に言ってほしい」,「存在意義のアピールを」など,病理医への期 待や注文があった。このうち病理医と直接話したいという意見に対しては,病理医から「最終的な責任者 は主治医にあり,現在のシステムでは病理医が独立して診療の場に介入するのは不可能であることを患者 側に知ってもらう必要がある」との立場が示された。また病理医の側からの「どこまで診療に立ち入るか」という問題については,「患者の全体像を知ら ない,主治医でない者(病理医)が病理診断だけを患者にぶつけるのは危険。現状ではシステム上制約も あり,慎重でありたい」との意見が現時点での代表的な考え方と言えよう。他に「現状でも病理医が患者 との調整役をすべき」との積極的な意見や「説明等は主治医の問題。また病理医には説明に費やす時間が ない」などの声も出された。 この他多くの発言があり,時間を延長しての熱気ある討論が交わされた。 全体を通して,「病理のプロフェッショナルとしての病理医をどのように医療に組み込むか」という課題 をめぐり,様々な立場からの意見の交換を可能にした貴重な試みとなった。(司会の岡崎氏のコメントを 別掲)
公開シンポジウムを終えて - これからの展望
岡崎悦夫 前・日本病理医協会長,新潟市民病院臨床病理部長
 市民向けの公開講座を学会の会期中に催すところが多くなったが,啓蒙講演とは逆に,今回は市民,
内科・外科の専門家,医療機能評価推進のそれぞれの立場から意見を聞く公開シンポジウム「国民が求め
る病理医のあり方」を開催した。日本病理医協会の歴史38年間で初めての企画である。
市民向けの公開講座を学会の会期中に催すところが多くなったが,啓蒙講演とは逆に,今回は市民,
内科・外科の専門家,医療機能評価推進のそれぞれの立場から意見を聞く公開シンポジウム「国民が求め
る病理医のあり方」を開催した。日本病理医協会の歴史38年間で初めての企画である。
地味なテーマにもかかわらず広い範囲から関心が寄せられ,東京近郊だけでなく宮崎,名古屋,富山,
新潟,前橋,小山からも一般参加があった。出席者は約200名。平素気づかない問題が提起され,医療全
体に対する新しい感覚と責任感を持った病理医を求める声が強いことを感じた。
これまで病理医は正確な病理診断や意見を臨床医に報告することだけが役割だとされ,臨床医からそ
れ以外を求められることはなかった。その結果,客観性を持つ確かな医療に病理医という専門的な医師の
仕事は欠かせないにもかかわらず,国民には知られない存在で,法的にも認知されず諸外国にも例のない
制度になっている。
今,医療の特徴は「チーム医療」であり,説明し納得と同意のある医療,医療情報の開示など,患者
中心の医療に移行している。病理医は臨床と一体になって「病気中心の医療」に関わってきたが,これか
らの医療で病理医はどんな役割を果たすべきか,シンポジウムでは一般市民の病理に対する要望が,体験
をもとに語られたのである。
一般参加者の声
◆米国の小説によく出てくる病理医のイメージがよくわかってきた。日本にも(病理医が)いることを
ようやく知ることができた◆病理診断は100%正しいわけではないことを知った。では誤りの危険を防ぐ
ため医師の間でどういう手段をとっているか知りたい◆病理医自らの質をどう確保するか,病理医の立場
から病院医療の質をどうモニターするか,これらが問われている◆医療界の問題点を率直に提起し改善し
ようという姿勢がうかがわれた◆医療情報には直接主治医に聞きにくい面があり,病理医のような存在に
は関心を持っている◆希望すれば病理の先生に会って話ができるようにしてほしい◆このように話し合う
機会を全国でつくってほしい◆率直な意見が多く,少しはよい方向に行くと思う。でも結局は患者個人の
考え方・意思が重要で,医師と一緒になって初めて医療・福祉を変えていくことができるのだと実感した。
今後の展望
専門の守備範囲や仕事内容が変化し,病理医のあり方や役割は時代,地域,施設によって異なる。米
国の病院では病理医が外来に呼ばれて患者の甲状腺,乳房から穿刺した細胞を即刻診断したり,リンパ節
を生検手術する姿を見るほどである。
日本では医療評価の推進にあたり,客観的学術的な評価の基本資料となる病理診断の意義は大きいと,
病理医の意識改革を促す意見が,演者や参加者からあった。そのためには適切で迅速な病理診断と表記方
法の標準化,医療全般にわたる見識,患者と接触し得る臨床能力の養成が必要であり,臨床研修は現在の
選択制より義務づけが望ましい。
インフォームド・コンセントの充実にはビジュアルに提示できる病理の特性を生かし,納得のいく説
明に病理医の参加も考えられてよい。市民との対話は,病理医,市民とも医療の実態を理解し両者の立場
で改善策を考えるのに役立つことがわかったので,今後もシンポジウムを続けることを予定している。
