Study & Try
医学生 研修医のための
日常診療に役立つ
臨床疫学
Clinical Epidemiology
第11回(最終回)最新の医学レベルを維持する法
山本和利 京都大学附属病院総合診療部
はじめに
本シリーズは,日常診療に密着した臨床疫学の有用性を示すことを基本方針にして連載してきた。こ れまでに,診断に関しては感度,特異度,陽性尤度比,陰性尤度比,ROCカーブ,治療に関しては検査閾 値,治療閾値,検査・治療閾値,NNTを応用する方法などを述べた。今回は,最終回に当たり,時代に遅れることなく最新の医学レベルを維持するために医師はどのよう にしたらよいかについて述べる。
事例
48歳の男性。腹部が腫れ,腹部全体の痛みを訴え受診した。1年以上前から足背部腫脹に気づいてい た。横臥位にて肝臓は右季肋部中央で14cm触知した。肝臓の辺縁を触れると圧痛があるが,結節は触知 しなかった。手掌紅斑,10数個の蜘状血管腫,女性化乳房,臍周囲の静脈の怒張(bruitはない)を認める。病歴・身体所見から,肝硬変を最も疑った。加えて,腹部全体に鈍い痛みが続くため,腹膜炎も疑わ れ腹水穿刺が行なわれた。その細菌培養結果から大腸菌による腹膜炎と診断され,アンピシリンとゲンタ シンによる治療が開始され,腹痛は軽減した。 腹部は緊満したままであったが,患者は退院を希望した。どうすべきか?
医学レベルを維持する
医学は急激に進歩しており,患者にその技術や知識を用いて貢献するためには多大な努力が必要であ る。2年間の初期研修が終了し,学んだ知識や技能を用いて目の前の患者を診断し,治療を行なおうとす ると,すでに時代遅れとなっていることさえまれではない。その時,医学の流れに乗り遅れ,過去の知識 だけで患者に対応していると,患者に害を与えることにもなりかねない。臨床能力とその実践
学生・研修医時代に学ばなければならないのは,医師として必要な知識と技能,態度を身につけるこ とである。この3つを合わせたものを臨床能力(clinical competence)と 呼ぶ1)(これに情報収集能力,判断力を加えることもある)。 それはバッテリーに蓄えられたエネルギーに似て,それだけでは不十分である。 医師として患者に貢献するためには,患者の抱える問題にその知識や技術を適用しなければならない。 そこで初めて臨床実践となる。この臨床能力が必ずしも実践に結びつくわけではない。なぜなら,同じ臨床能力を持つものが同じ環 境に置かれても同様の実践をするとは限らないからである。
動機と障害
臨床能力を実践に結びつけるのに大切なのは,患者の苦悩をなんとかしてあげたいという動機を持つ ことである。その動機を作り出すもとは最良の方法を発見したいという気持ちや与えられた現状に満足し ない意欲,専門家として質の高い医療をしたいという内的な欲求,などである。逆に,医療システムや経済的な面で障害があると,臨床能力があっても実践に結びつけられない。診 療現場の状況が変われば,自ずと克服すべき障害も異なる。大学病院で優秀な医師であっても地域の診療 所で必ずしもそうならないのは,このためである。
評価されるべきは,臨床現場での実践であって,単なる臨床能力ではない。すなわち,実践の場で最 大の成果を発揮するためには,眼の前にした患者の健康問題をなんとか解決したいと動機づけされた医師 が,立ちふさがる障害を乗り越えながら,解決するために必要な知識や技術を使って共感を持った態度で 臨むことである(臨床実践=臨床能力+動機-障害)1)。
診断・治療に関する実践の評価
実践の評価をする際に,結果に焦点を当てる場合とその過程に焦点を当てる場合とがある。臨床上の 結果は,病気そのもの,診断検査,治療行為,臨床実践,患者のコンプライアンスの5つが影響する。そ れゆえ,結果だけで評価したときにはいくつかの問題が起こる。例えば,副作用がまれな場合には間違っ た実践をしていても同定できないし,間違った実践をして悪い結果が引き起こされても,遅れて起こった ときには同定されない。また意図しない悪い結果になったときに,医師のやり方のまずさよりも患者の状 態のまずさのせいにしやすいなどである。それゆえ,結果のみならずその過程も評価すべきである。では,過程を評価するには,どうしたらよいであろうか。それには用いた方法論を検討することが必 要となる。臨床上の結果は,病気それ自体の重症度や受け持った患者のコンプライアンスが影響するので, それ以外の要素となる診断検査や治療行為が適切であったか検討することに重点が置かれることになる。 診断検査や治療行為が適切であったかはいかに最新の文献を批判的に読んで臨床に応用したかどうかにか かってくる。
文献から実践力をつけるための方法
しかしながら,最新の文献をたくさん読むことが臨床実践力をつけることには必ずしもつながらない。 なぜなら,多くの臨床雑誌に掲載される論文は目新しい考えを述べたものであり,今後,追試が必要とな るものが大部分であるからである。そこで,最新の文献を読むときにはいくつかの点について心すべきで ある。まず,自分の関心のあることについて,一定の評価がされている一般医学雑誌だけを読む。そして, タイトルや要約から医師が実際にやっていることに注目する。次に,患者に利益をもたらすか,自分の状 況に似ているか,包括的で常識に照らしておかしくないか,対照群があるか,バイアスがないか,統計的 のみならず臨床的にも有意差があるか,などを検討することである(詳細はこれまでの診断・治療編を参 照)。
事例への対応例
そこで,主治医は治療に関してコンピュータ検索を行なった。key wordsはAscitesand Random Allocationを用いた。その結果スペインの多施設で行なわれたGinesら2)の研究論文を 見つけた(表1)。表1を読むには,number needed to treat(NNT)についての理解が 必要になる(連載第8回参照)。NNTは治療効果がどの程度大きいかをみる指標である。合併症発生率 に関して,絶対リスク減少率:absolute risk reduction(ARR)は, 単純に引き算をして0.61-0.17=0.44と計算でき,44%であると表現される。 ARRを一歩進めて,臨床の現場で患者に説明し医師自身も具体的なイメ-ジを把握できるように,NNTが 考え出された。それは単に1をARRで割った値で示される。このようにすると,1例の効果を観察するため には,その治療を何人の患者に用いなければならないかという指標に置き換えられたことになる。
表1を言い換えると,「利尿剤治療が無効な場合でも,腹水穿刺とアルブ ミン補給を3人の患者に行なうと少なくとも1人の割合で合併症発生を予防できる」となる。 事例ではもちろん腹水穿刺とアルブミン補給を行なった。
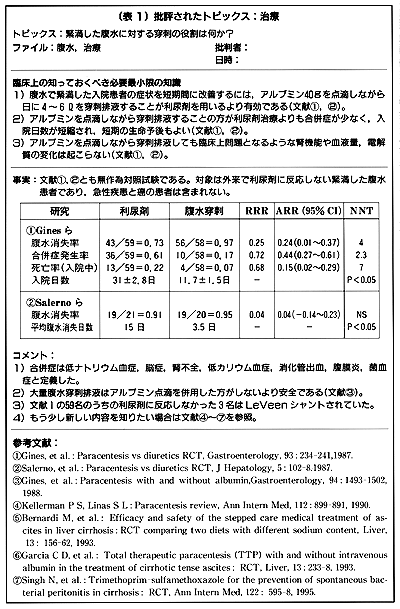
教える側に求められること
学ぼうとする医師自身が興味を持っていることに関しては,教材やプログラムにかかわらず能力を高 めることができる。しかし,必要ではあるがあまり興味がないことについては教える側に工夫が必要であ る。臨床を学ぶために必要なことを,臨床問題,事実(clinical evidence), 批判力(critical appraisal)の3つの事象で考えるとよい。よく教授が行なっている患者回診において, 教授が知っていることを述べて,それを無批判に医局員が聞くだけであるのならば,根拠のある事実は 蓄積されず,健全な批判能力も身につかない。
最新の医学レベルを維持するためには,「実際の患者」について,「自分1人の力で必要な事実を検 索」し,それを「健全に批判」できることが必要である。学生や研修医に一度に最終レベルに到達するこ とを期待しても無理である。そのためには,教える側が資料を準備し,段階的にレベル・アップを図る必 要がある。
具体的には,ベッドサイドで患者の抱える問題を研修医に尋ねるのがよい。そして順次,患者の身体 所見のとり方,臨床上の決断のしかたを教える。はじめは適切な文献を手渡し,最後には自分で探せるよ うにする。どのように患者を評価し,治療するかという疑問を投げかけること(「なぜそう決断したのか」 と問いつづけること)が重要である。
教える側は,単に文献を手渡すのではなく,その前の段階として,簡単に参照できる資料を準備すべ きである(表1を参照)。その資料は,原則として以下の点を最低限満たす必要がある。 (1)実際の患者を基にする,(2)診断,予後,治療,病因について問題をしぼる,(3)すぐに見つかる最良 の事実を示す,(4)その内容について,a)患者の簡単な記載をする,b)事実を見つけるのに用いた 方略を示す,c)何をすべきかの必要最小限を記載する,d)重要な点を表を使ってまとめる,e)臨床上 の問題をコメントする,f)最新の文献を引用する,などである。
このような努力をしようとしても,理想と現実にはもちろんギャップがある。役に立つ事実を検索し ても現状では見つからないことも多い。しかしながら,最も不足している点は,よい臨床医を育成しよう とする情熱が教える側に具体的な行動として現れていないことではなかろうか。
最新の医学レベルを維持する必要性は研修医に限らない。教えることは学ぶ最良の近道である。教え る側が意識を変革し,教える側自身が時代に遅れないよう努力し,そこで培ったことを後輩に伝えること が今一番求められていることではないだろうか。
まとめ
1)実践の評価をする際には,結果のみならず,その過程も評価すべきである。2)文献から実践力をつけるための方法を身につける必要がある。
3)最新の医学レベルを維持する必要性は研修医に限らない。教える側が意識を変革し,教える側自身 が時代に遅れない努力をする必要がある。
参考文献
1)Sackett D L, et.al: Clinical Epidemiology. A Basic Science for Clinical Medicine, Boston, Little Brown, 1991.2)Gines, et al.: Paracentesis vs diuretics RCT, Gastroenterology, 93: 234-241, 1987.
山本和利氏の連載「臨床疫学」は今回で終了です。ご愛読ありがとうございました。編集室では連載 へのご意見,ご感想をお待ちしております。
