新連載
脳 腫 瘍
なぜ,いま脳腫瘍なのか-脳腫瘍の現在
発生原因から遺伝子治療まで(1)
野村和弘(国立がんセンター中央病院病棟部長)
はじめに
医学の進歩は日進月歩,とどまるところを知らない。ほっとしていると,すぐに間を空けられてしま う。真にめまぐるしく進歩する世界である。脳腫瘍も恐ろしいがんとして考えられてきたが,医学の領域 全体から見た場合にはマイノリティ(少数派)であり,片や手術で95%以上治癒の期待できる髄膜腫や下 垂体腺腫ががんの仲間入りをしてるかと思うと,脳の実質内をアメーバのように浸潤していく膠芽腫の遺 伝子治療が,がん治療の最先端を走っていたりする(図1,2,表)。脳腫瘍の治療に専念しているものからみると,何と混乱した世界であろうか。したがって,基礎 医学においては最先端の話題が提供されていても,研究者自身は,臨床面における治療の進歩について無 案内のようであるし,自ら遺伝子関連の最先端の研究をしていると考えている臨床家は,その真髄を理解 していないのではないかと危惧される。中でも,転移性脳腫瘍(図3)に至っては,が ん死亡が24万人を超えた今日,その2割から2割5分が脳転移を持っているということだから,1年に約5万 人の人が脳腫瘍の治療を必要としていたことになる。しかし,その実態はほとんど知られていないのでは ないだろうか?
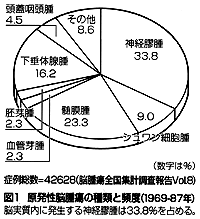
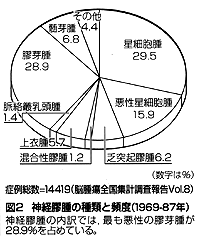
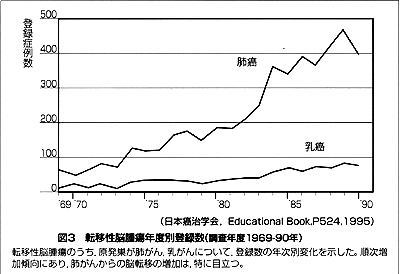
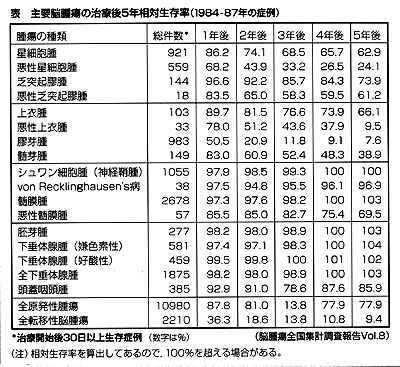
脳腫瘍における診断・治療技術の進歩
この20年間の脳腫瘍における診断技術,治療技術の進歩,はたまた生物学的特性解明の成果は著しい ものがある。小生が大学を卒業した当時は,脳腫瘍の診断には血管の走行の変化をみる血管撮影,空気あ るいは酸素を髄腔内に注入してその変位をみる気脳撮影が最新の診断法であった。これらは腫瘍が大きくなって脳を圧迫して生ずる脳の歪みをみて,腫瘍があるか否かを診断する 方法であった。したがって腫瘍そのものを画像でみるなどということは考えも及ばなかった。現在では, それらがいとも簡単にCT,MRIなどで抽出され,コンピュータによって立体視のみならず,バーチャル リアリティ(仮想空間)として,画像の中に術者が入っていって観察が可能とまでなっている。まさに革 命的な進歩である。さらに,画像診断の領域では進歩の早さは緩を許さず,現在では脳の機能分野の特定 も生体で可能である。
昔の図譜は,多くの解剖データの集積として脳の機能分野が同定され,それが外科の基本となり, メスを入れてはならない聖域が決められていた。これは,たくさんのデータの集積であるから,個々の人 間ではもちろん,個人差が大いにあるはずである。したがって,個々の患者さんの脳の機能分野がしっか り同定され,腫瘍との関係が明白になれば,治療,特に外科療法の進歩の可能性は万人が認めることであ る。
手術の技術面においては,手術顕微鏡の導入によって安全な手術が可能となり,レーザーや超音 波吸引器の導入は出血を抑え,かつ正常な血管,神経を温存することを可能とした。定位脳手術は,脳の 深部の組織を1mmも狂うことなく確実に採取することを可能とした。
放射線医学の進歩は,ガンマナイフと称せられる201個のコバルト線源をヘルメット周囲に張り 巡らせ,これを用いて頭の全方位から,すなわち360度から集光して病巣に焦点を作り,がんだけを殲滅 する照射法が導入されている。放射線治療における最近のホットニュースは,がんの治療への陽子線や重 粒子線の応用である。現在,臨床応用は綿密な計画の下に進められており,その結果が出るのもそう遠く ない。
基礎と臨床の融合
基礎研究では,分子生物学の進歩がめざましい。腫瘍の多くを占める星細胞腫の起源とされる細胞の 増殖の特性が,形態学はもとより分子生物学的に増殖因子との関連において究明された。その結果,分化 した星細胞腫がいかにして膠芽腫に変化するかの多段階的悪性化について解明されてきている。ここまで進むと,基礎研究と臨床医学とが結合することにより,直接治療への貢献が期待される ようになる。すなわち,最も悪性の脳腫瘍,膠芽腫に2種類あることである。星細胞腫から段階的に悪性 化して膠芽腫に至った腫瘍と,一方,最初から膠芽腫としての性格を得て出発したものとがあり,EGFR の増幅の度合で両者が判定可能であることがわかってきた。すなわち星細胞腫の悪性化による膠芽腫では, p53遺伝子異常が重要な因子となって,時にEGFRの異常もみられるが,その割合はすこぶる少ない(P. Kleihues)こと,一方de novoの膠芽腫では,EGFRの増幅異常が主体であり,p53遺伝子異常の認められる 症例は少ないことなどである。
従来から,膠芽腫全体の予後はすこぶる悪いのだが,その中で抗がん剤や放射線の治療である程 度の効果を期待できるものと,ほとんど効果の期待できない症例とが存在することが,経験的にわかって いた。それが遺伝子関連因子を検索することで区別できる可能性が示唆されたわけである。脳腫瘍の生物 学的特性が徐々にではあるが,しかも確実に一歩一歩解明されてきていることがわかる。
一方の流れとして,遺伝子治療は脳腫瘍で着実に前進している領域である。脳腫瘍が,脳以外の 臓器にほとんど転移しないことや,正常の脳は分裂しないで脳腫瘍細胞だけが分裂増大する組織であると いう特性が役立っているようである。ガンシクロビルを中心に欧米では遺伝子治療が臨床で実施され,日 本では,さらに効果的治療を求めてリポゾーム等を用いた遺伝子の効果的運搬法が考えられている。
疫学の面においては,高齢者の脳腫瘍が増加傾向にあることや,その原因について従来は化学発 がんの研究が中心であったが,現在では遺伝子を人工的に導入して脳腫瘍を作成することが可能となり, 遺伝子操作によって脳腫瘍を作成可能としている。逆に考えれば遺伝子の変化を正常に戻すことによって, 脳腫瘍を正常化,あるいは良性化させる治療が可能となることを示唆している。
抗がん剤と手術の有効な併用法
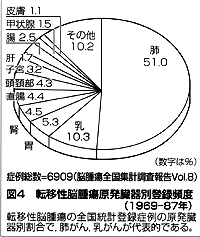 転移性脳腫瘍に目を向けて
みよう(図4)。脳転移の治療は,すべてのがんでStage 4として分類され,がんの最終
段階と判断されている。しかしながら,これからがんの治療が進歩し,長期生存を得られた場合,脳への
転移は最後の陥落させなければならない要塞である。この脳転移の治療が現在どのように行なわれている
かは,多くのがん治療医の注目するところである。
転移性脳腫瘍に目を向けて
みよう(図4)。脳転移の治療は,すべてのがんでStage 4として分類され,がんの最終
段階と判断されている。しかしながら,これからがんの治療が進歩し,長期生存を得られた場合,脳への
転移は最後の陥落させなければならない要塞である。この脳転移の治療が現在どのように行なわれている
かは,多くのがん治療医の注目するところである。
ご存じのように,脳に転移したがんの多くは球形に増殖し,周囲脳を圧排性に増殖する。したがっ て,このような脳転移に関しては,前述のガンマナイフによる照射が大変効果的である。しかしながら, 外科的手術におけるその有用性が決してなくなったわけではない。特に3cm以上の大きさを持った腫瘍で は,やはり摘出を第一にし,その後に照射を考えるべきである。
ガンマナイフによる1回のみの照射で治療が終了できることは,終末期を迎えた患者さんにとっ て朗報なのは言うまでもない。しかし,将来の長期生存可能な治療の出現を考えた場合に,いわゆる緩和 ケアを目的とした治療に目標を据えていたのでは,将来像を見失っていることにならないだろうか。この 点において,さらなる脳転移を治癒させる手段を求めて努力を進めておく必要もある。放射線を強調する あまり,抗がん剤による化学療法の進歩も忘れてはならない。シスプラチンの出現はやはり,髄芽腫にとっ ては朗報である。
ニトロソウレア系薬剤のわが国での開発は,神経膠腫の治療の1つの標準を示すことができた。 インターフェロンも,わが国において悪性脳腫瘍に対する有用性を認められた抗がん剤である。
まとめ(連載にあたり)
これらの全体像を眺めてくると,脳腫瘍を取り巻く環境,診断,治療,それに分子生物学的な分野に おける,進歩,発展は目をみはるものがある今回の連載は,これらの分野について,それぞれの専門家に 解説していただくことにしているが,脳腫瘍,特に神経膠腫および,脳転移の臨床と基礎研究の有機的な 結合によって,お互いの理解がさらに深まり,患者さんへの福音となれば,私にとって至上の喜びである。なお,この連載は10回のシリーズとして毎月2回程度の掲載となるが,構成は以下の通りである。
【脳腫瘍-発生要因から遺伝子治療まで】
〔第2回〕脳腫瘍のリスク因子(国立がんセンター研究所がん情報疫学部長 山口直人)
〔第3回〕脳腫瘍の性格を規定する因子,悪性化を促す遺伝子変化(佐賀医大教授 田渕
和雄)
〔第4回〕最新の診断・診療機器の現状と展望(1)-CT, MRIなどの機器の改良と臨床応用に
ついて(東女医大教授 小林直紀)
〔第5回〕最新の診断・診療機器の現状と展望(2)-三次元画像,バーチャルリアリティの
臨床応用について(国立がんセンター中央病院 小山博史)
〔第6回〕脳の機能分野の確定とその手術への応用(東北大 中里信和)
〔第7回〕新しい放射線治療の臨床応用(東女医大教授 高倉公朋)
〔第8回〕抗がん化学療法の現状と問題点(熊本大教授 生塩之敬)
〔第9回〕遺伝子治療の現状と将来性(名大教授 吉田純)
〔第10回〕増加傾向にある転移性脳腫瘍の治療(国立がんセンター中央病院 渋井壮一郎)
