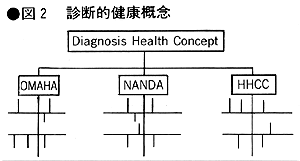第12回NANDAのカンファレンスに参加して
その役割の変化を肌で感じる 江川隆子 大阪大学教授・保健学
テーマにNANDAの意気ごみが
 第12回NANDA(北米看護診断協会)のカンファレンスが開催されたここピッツバーグは,19世紀後半から鉄鋼産業の町として栄え,世界的な億万長者である,カーネギー,フリック氏らを輩出しただけでなく,労働組合(Union)運動の結成,崩壊といった労働組合の中心であった歴史を持つペンシルバニア州第1の都市である。そのペンシルバニア州は,米国独立の礎であった歴史を,Keystone Stateと州名に残している。そして現在のピッツバーグは,最大の産業公害都市からハイテク産業の町へと変貌を遂げ,今や米国でも最も住みやすい町の1つとして蘇っている。
第12回NANDA(北米看護診断協会)のカンファレンスが開催されたここピッツバーグは,19世紀後半から鉄鋼産業の町として栄え,世界的な億万長者である,カーネギー,フリック氏らを輩出しただけでなく,労働組合(Union)運動の結成,崩壊といった労働組合の中心であった歴史を持つペンシルバニア州第1の都市である。そのペンシルバニア州は,米国独立の礎であった歴史を,Keystone Stateと州名に残している。そして現在のピッツバーグは,最大の産業公害都市からハイテク産業の町へと変貌を遂げ,今や米国でも最も住みやすい町の1つとして蘇っている。
そこで,NANDAはこのカンファレンスを,この地名にあやかって,「The Keystone to a Unified Nursing Language」と題して,4月11-15日の5日間,「統一看護用語のためのかなめ石」としてのNANDAの新しい役割を内外に明示した。
そして,この大会の基調講演に「Painting the Glue Red」と題したJoane Disch博士の講演内容は,まさにNANDAのメインテーマを包括するものであった。博士は,効果的な看護をするための統一看護用語の概念(Nursing Effectiveness Initiative)を1つの関連図に示して統一看護用語の看護効果を明らかにした。そして,統一看護用語を開発するためには,まず現在行なわれている看護診断分類を統合するマップ作り(mapping)が必要であることを強調していた。そしてそのマップ(地図)の概念は診断的健康概念であろうと結んでいた。
統一看護用語が看護の発展のために不可欠だと信じていた私にとっては,最初から感動させられた講演であった。
NANDAのターニングポンイト
1998年,NANDAは25周年を迎える。NANDAはこの25年間に看護をより専門的な学問とするために,看護診断分類の開発や普及,教育や妥当性研究等によって世界をリードしてきた。そのNANDAの業績は,国内外にさまざまな影響を与えている。ヨーロッパのNDECや日本のJSNDの結成をはじめ,アメリカ国内での看護診断に関する研究グループ,OMAHA,NDEC,あるいはNIC,NOCといった看護専門家の研究プロジェクトチームの結成と発展はその影響であるといえる。
そして,今度はこの25年の輝かしい歴史を持って,広がりつつある看護専門グループの業績を,看護の利益のために1つに結束する役割をNANDAが担うことの決意がそれ以降のプログラムから受け止められた。それは,参加した誰もが感じたことであり,特にそれぞれのグループのリーダーが感じたことではなかろうか。
観察-看護診断-期待される結果-看護援助-評価の系統的な知識体系と,各々の段階で用いられる看護用語の統一化は,提供する看護の質を高めるために私たち看護専門家が切望することであり,それはNANDAの発足の理念であったはずである。それがここにて来て,それぞれの団体や個人が頭角を現したからといって,1団体,あるいは個人の利益のためだけの後戻りは許されないだろう。
このNANDAのカンファレンスは,あらためて看護専門家としての自覚と利益,結束を統一看護用語として訴えているようであった。
NANDA,NDEC,NIC,NOC参加のパネル討論
このパネル討論はメインホールで行なわれたせいもあって,参加者のほとんどが集合していた。日本からの8人の参加者も全員出席していた。このパネルでは,日本でも知られているOMAHA(Omaha System)やHHCC(Home Health Care Classification)以外の看護診断研究プロジェクトであるNIC(Nursing Intervention Classification)やNOC(Nursing-Sensitive Outcome Classification),それからNDEC(Nursing Diagnosis Extension Classification)が参加して行なわれた。ご存じのように,NICは看護介入分類を,NOCは看護成果の分類を,そしてNDECはNANDA分類の改善を目的にした研究プロジェクトチームである。
これらはNANDAのような会員形式を取っている団体でなく,公的研究資金を取って研究するグループである。このグループの特徴は当然のこととしてNANDAのメンバーが参加していることと,アイオワ大学中心であることである。
このパネルでは,それぞれの代表が自分たちの研究方法と成果を披露していた。それぞれ非常に興味深く,その手法は今後の日本に必要であることから非常に勉強になった。しかし一方ではバラバラな感じが否めなかった。そして,ここでもNANDAが看護用語開発プロジェクト間の統一をめざしていることが感じとれた。
NANDAとNDECからの提案
パネルに続いて,NANDAとNDECからは図1のような各プロジェクトで開発された看護診断用語の統一の概念(Concept)が示された。この概念はまた図2のように診断的健康概念を介して,OMAHAとNANDA,HHCCをコードによって結びつけるというものである。この具体例は,例えば「活動耐性」について言うなら表1のような関係になると説明した。ちなみにここで用いている「診断的健康概念」は,前日の基調講演でDisch博士が述べたmappingの概念のことである。
このような整合性は,看護援助や期待される結果などにも適用されるだろう。
この提案を聞きながらNANDAも含めて,どのグループも診断分類や援助方法,あるいは期待される結果を構築したけれど,それぞれの検証が十分にされていない状況であるということを感じた。そして,またこの統合には,多くの人材や能力,時間などの協力が不可欠であることをあらためて確認できた。
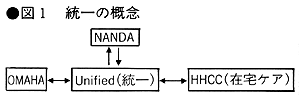
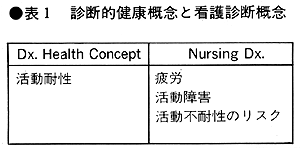
一般演題とポスターセッション
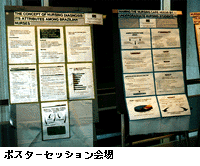 看護診断に関する研究グループとの協働,各専門団体との協働というNANDAのキャッチフレーズが目立った一般演題発表であった。
看護診断に関する研究グループとの協働,各専門団体との協働というNANDAのキャッチフレーズが目立った一般演題発表であった。
中でも在宅ケア,リハビリ,クリティカルケア,国際障害-糖尿病ハンデキャップ(ICIDH)などが積極的にNANDAの看護診断分類を各々の分野で活用していること,またその看護診断の妥当性についても検討されていることが発表されていた。
また,その他の一般演題も看護診断の妥当性研究の発表が目立った。ポスターでも妥当性研究,特に文化的な影響を受ける看護診断について発表されていた。
NANDAからの報告
この5日間で最も参加者を引きつけたのは,NANDAの分類委員会と診断診査委員会(DRC)からの報告であった。分類委員会からは,9つの看護診断分類の改正について報告があった。この報告の中では,従来の9つの反応パターンが教育や臨床の場でも理解しにくいとの指摘を受けて,分類用語を動詞系から名詞に直すだけでなく,現実的な11の分類名を提案した。
この提案された分類名を見て感じたことは,ゴードンの機能的健康パターンや松木氏の生活行動様式に似ているという印象であった。しかしながら,臨床的でわかりやすい点では両者よりいいものを持っていると私は感じた。同時に従来の9つの反応パターンをもっと具体的なレベルで概念を分類したという感じを持った。
一方,診断診査委員会(DRC)からは,それぞれの分類法とその定義上の特徴が文献と専門家によるレビューが行なわれていること,そしてその概念分析方法が事例を用いて詳しく説明された。
以上のような画期的な提案や作業の内容を今回の参加で一足先に知る機会が得られ,自分たちがやろうとしている研究の技法に影響を与えてくれたことを感謝している。
その他のメリット
日本の看護診断学会に比べて,このカンファレンスへの参加人数は約300人足らずと少ない。その理由は,参加者が地区ごとの代表者だけのせいであることを知った。そのために,ゴードン,アルファロ,カルペニートなど,日本でも知られている看護診断に関する研究家,教育家,実践家の面々と学会中,身近に接することができるというメリットが参加者にある。また,場合によっては,その方たちとの研究や人事の協力や交流が交渉できる機会が得られると思った。その他,国際交流の場が今回からポスト・カンファレンスとして設けられたことで,アメリカ以外の国での看護診断に関する動向,特にその国の代表者レベルの意見が聞けたことはすばらしい経験であった。
この学会参加を通して
この学会参加を通して感じたことは,NANDAの役割はこの25年間でほぼ達成したことである。同時に,それぞれの国において,NANDAの傘の中で,その国の独自性を反映した看護診断名の開発,定義上の特徴の検証,そしてそれぞれの看護診断に対する援助方法の研究と検証を早急に行なわなくてはならないということも感じた。日本では,そのNANDAの意図を実践,リードできる立場にあるのは「日本看護診断学会」であると信じている。今後,日本看護診断学会はNANDAと公式的な関係を保ちながら,日本の文化や習慣を網羅した看護の専門用語の開発と統一化に一層努力して欲しいと痛感した。
もっと積極的な参加を
ヨーロッパからは,日本とほぼ時を同じくして発足した15か国からなるACENDIO(Association for Common Eurpean Nursing Diagnosis Intervention and Outcomes)の積極的な活動が報告されていた。今回の学会にしても,デンマークなどは看護士を含めて27名も参加させ,自国での看護診断の動向や研究を発表していた。次回,第13回目の学会は,1998年にNANDAの発祥の地セントルイスで行なわれる。そこには,ぜひ日本看護診断学会として,また個人的にももっと積極的に参加して研究を発表して欲しいと思う。特に日本看護診断学会の理事,評議員の方々たち,学会委員の方々は,ぜひ参加し世界の動向を肌で感じて,私たちの行く道を明確にして欲しいと考える。
(第12回NANDAカンファレンスについては本紙第2191号にも関連記事を掲載)