眼科学臨床-最近の話題
第100回日本眼科学会記念特集


白内障手術
馬嶋慶直(藤田保健衛生大学・眼科学)
近年における白内障手術および眼内レンズ挿入術の進歩には目をみはるものがある。超音波水晶体乳
化吸引術(PEA)の本邦における導入期の1976年頃には種々な問題点があるとする批判的意見が多く,今日の現状を誰が想像できたであろうか?すでに本邦においても1970年,故桑原安治教授は,将来は白内障手術の約95%が超音波法で可能であろうと予見されたごとく,いまではPEAが本手術の主流になったと言っても過言ではあるまい。さらには眼内レンズ挿入術の進歩により術後の視機能は著しく向上した。
一方,PEAにおける周辺機器の改善・改良や眼薬理学の進歩,粘弾性物質の臨床への導入により, 本手術のさらなる安全性が確立され,これに伴う小切開対応眼内レンズの開発へと発展し現在に至っている。しかしなお,将来に向かっては流動的であり,さまざまな新知見が報告されている。本稿では日常臨床に直結した白内障手術周辺のトピックスの2~3について述べたい。
より効果的で安全な乳化吸引
まずPEAを中心とした白内障手術では前嚢切開が従来に代わってCCC(Circular curvilinear capsulorhexis) が推奨され,その手技として用手法,高周波法,レーザー法(Er-YAG,YLF-YAG等)で確実に施行した後,核破砕は前嚢切除された水晶体嚢内で行なう乳化吸引法が主流となった。なお,超音波発信時間の短縮による角膜内皮細胞への侵襲の軽減を目的として,リニアモードによる超音波発信は術者によって制御ができ,より安全に核の乳化吸引が施行されている。一方,最近ではMMP(multi modulation phaco)すなわち術中核の乳化吸引時の超音波発信と吸引 圧を種々設定することによって,一層効果的で安全な乳化吸引が可能となり,その有用性が注目されている。また,これらの吸引では,従来の蠕動ポンプの改良,ダイヤフラムポンプ,ベンチュリーポンプが利用され術中吸引圧の変動をコントロールし,その確実性と安定性を確保し手術の安全性を高めるとともに,USチップのデザインもより効果的に改良されている。
さらに新しい試みとしてはEr-YAG Laserの白内障手術への応用がある。これまでにも,レーザー によるphoto phaco distruptionとして核破砕が試みられていたが,臨床的な有効性に乏しかった。 ところが, 水の最大吸引波長とほとんど同一波長のEr-YAG Laserの利用による前嚢切開,核破壊が臨床応用 されるようになり,今後さらなる改良によって本法への期待が持たれている。
一方,術後視力に影響をおよぼす乱視についても,創の作成部位の方法や縫合糸の種頻, 縫合方法について,これまで数多くの報告はあるが,PEAの切開創が小さいことは,手術による 角膜乱視の程度が少ないことでもあり,さらに現在,侵襲の少ない手術として普及した自己閉鎖 創無縫合手術とfoldable IOL挿入は,角膜乱視の軽減に一層有効であった。そしてこの乱視をコントロールするため,PEA においては最近,Refractive Cataract Surgeryとして,Astigmatic Keratotomyを併用する方法 もとられ,手術による乱視発生の軽減をめざし細心の注意が払われている。
また近年,術後角膜乱視を中心とした角膜形状を詳細に診断するために,角膜トポグラフを 撮影して,これを角膜形状解析装置で解析し,その状態を一層明確に把握し術後角膜乱視の程度, 治癒過程,そしてRefractive surgeryの要,不要について診断している。
foldable IOLの進歩
このような小切開手術の長所を生かし,切開を拡大することなく挿入可能なfoldable IOLが開発され, 従来の短所とされていた点を解決した。すなわちHomo polymerである軟材質のシリコン, HEMA IOLは,本邦では1984年頃より臨床治験され,前者はすでに日常診療においてそれなりの成績 をあげている。一方,後者は2~3の問題点があるとして許認可はされなかったが,現在含水率の低い HEMA IOLとして臨床治験が行なわれている。しかしこれらの材質は屈折率が1.41~1.46で, 従来からの屈折率1.49のPMMAに比べ必ずしも満足するものではないので最近Co‐polymesからなる foldable IOLが開発された。1つは熱硬化性樹脂からなるIOL(Acry sof(R))で屈折率は1.55,他は熱可塑性樹脂からなるIOL (Memory(R))で屈折率は1.47と,いずれもPMMAに近似もしくはそれ以上の屈折率を持つと同時に, foldable IOLで小切開対応のIOLである前者はすでに市販され,その有用性は多くの術者が知るところであ る。1995年に,本IOL光学部内に細い白点が見られ,これをグリスニング(輝点)として問題視されたこ とがあったが,臨床上には特に問題もなく,むしろ後発白内障発症が少ないと報告している。
また後者は現在本邦では臨床治験中のIOLであるが,形状記憶性を持つ材質で光学部がつくられ, 低温で二つ折にして保管し,そのままの状態で挿入し眼内でゆっくりと原型に戻るIOLであるため,挿入 時に鑷子で二つ折にする必要がなく光学部に傷をつけないことから,将来その有用性は高いと考えられる。
多焦点IOLには賛否両論
ついで,IOLに機能性を持たせた多焦点IOLには,現在なお賛否両論がある。上記したようにIOLの有 用性は今さら言うまでもないが,よりよい術後視機能の向上を望むためには,一般的に挿入されている単 焦点IOLの欠点(調節力を伴わない)を補うために多焦点IOLが開発され,すでに市販されている。しか し,JSCRSのアンケート調査(1994年)では必ずしも十分な賛同は得られず,疑義として問題点が残され ている。このIOLはデザインの構造上から回折型と屈折型に大別され,前者では1つの焦点には入射光はそ れぞれ41%が集光され,残り18%は高次回折波および散乱によって損失されるため,単焦点IOLに比べて 暗く見え,色収差が出やすくコントラスト感度が低下すると言われている。しかしデザイン上,瞳孔径の 大きさには影響がないことが長所とされており,これまでの臨床成績では患者からの訴えもなく,厳格な 適応の選択と適切な術式で行なえば有用性があると考えられている。屈折型では2,3,5ゾーンのレンズ デザインがあるが,現在5ゾーンの屈折型IOLが許認可されている。これにはPMMAとシリコン材質の2種 類があるが,特に後者はfoldable IOLであり,小切開創からの挿入が可能で術後乱視が少ないこともあって 有用性が期待されるところである。
一方,手術に関連した術後併発症の1つである後発白内障や前嚢混濁の発症については,水晶体 上皮細胞がIOLとの接触により産出されるといわれるサイトカインの挙動を細胞生物学的に検討し,その 形成メカニズムを解明するとともに予防ならびに治療法の確立へと研究が進められている。
現在確立されたかに見える白内障手術,IOL挿入術においても,尚問題点が皆無ではないことを 銘記したい。


緑内障-薬物治療
新家 眞(東京大学医学部附属病院分院・眼科)
緑内障は,従来は「正常範囲を越える高眼圧と,それによる視神経障害および対応する視野障害をき
たした状態」と理解されてきた。もちろん高眼圧をきたす病態としては,先天性異常,原因が現時点では
特定できないもの(原発性),他の病気によるもの(二次性)等多くあるわけであるが,以上のような理
解から,緑内障の薬物療法は,すなわちいかに効率よく,また副作用なく眼圧を下降させるかということ
に目的があったわけである。しかし近年における幾多の研究成果は,高眼圧以外にも,緑内障性視神経障
害形成に関与する因子が存在することを示唆してきた。現時点でこの因子は,高眼圧により間接的に惹起
される何らかの病態なのか,または全く眼圧とは関係のない因子なのかは同定されてはいない。しかし,
何らかの局所組織循環に関連する因子であると推定する研究者が多い。
プロスタグランジン関連物質
さて緑内障薬物治療をめぐる最近のトピックスを語るにあたっては,便宜上,上記高眼圧とそれ以外 の因子に対する薬物的アプローチに分けて話してみたい。まず眼圧下降剤であるが,従来広く使用されていたβ-遮断剤,縮瞳剤,エピネフリン製剤の3 種類では,原発開放隅角緑内障(primary open angle glaucoma: PO‐AG)を成功裏に管理できる確率は10年 間のfollow‐upで約2~3割に過ぎないことが分かっていた。この割合を上昇させるには,従来の3種類と違 う眼圧下降作用機序の薬剤が最もふさわしいことは想像にかたくない。その観点より近年大きな話題となっ ているのはプロスタグランジン(PG)関連物質である。PG関連物質,特にPGF2α関連物質は,従来の薬 物ではほとんど作用がなかった強膜ブドウ膜流(uveoscleral flow)を増加させることにより眼圧を低下さ せることが明らかとなっており,従来の眼圧下降剤無効例に臨床上特に有用と考えられる。この系統の薬 物としては本邦で開発されたunoprostoneが既に市販されており,スウェーデンで開発されたlatanoprostも 臨床治験を既に終了し,近年市販される予定である。特にlatanoprostは,代表的β-遮断剤チモロール以 上の眼圧下降効果を有すること,およびチモロール等β-遮断剤の全身的β-遮断作用に起因する呼吸系, 循環系の副作用がないこと等より,将来的に期待される薬剤である。
炭酸脱水酵素阻害剤の点眼薬化の成功
もう1つの重要な近年の進歩として炭酸脱水酵素阻害剤(carbonic anhydrase inhibitor,CAI)の点眼薬化 の成功がある。CAIは長期内服可能な唯一の眼圧下降剤としてすでに約35年の歴史を持つ薬剤である。そ の効果は現在最も広く使用されているβ-遮断剤点眼に匹敵しまた両剤とも房水産生抑制により眼圧を下 げるが,房水産生抑制メカニズムが異なっているため,CA Iとβ-遮断剤では,眼圧下降に対する併用効 果がある。ただし,内服投与しか従来は投与法がなく,種々の全身的副作用が存在することが大きな問題 であった。CAIの化学構造式を修飾し,それを眼圧下降用点眼剤として使用可能としたもの,dorzolamide が発表されたのは数年前であるが,本剤もすでに臨床治験を終了し近年市場に姿を現す予定である。 dorzolamideも,β-遮断剤にその眼圧下降作用ではほぼ匹敵し,かつ,β-遮断剤点眼でみられるような 全身的β-遮断による副作用およびCAI内服でみられる全身的CAI作用による副作用がないため,安全性 に優れ将来期待されている薬剤である。以上2剤に代表されるように,最近の眼圧下降剤の開発は,β -遮断剤と違う作用機序により,それに優れる,またはほぼ等しい眼圧下降作用を持ち,かつ,β-遮断 剤の持つ全身的副作用がないものを目標としており,従来よく行なわれたような,チモロールより副作用 の少ないβ-遮断剤を点眼用に開発するという行ないかたは,完全に過去のものとなった感がある。眼圧以外の因子への薬物治療- 遮断剤
遮断剤
次に眼圧以外の因子に対する薬物治療のトピックスについて述べてみたい。従来より,血管拡張剤と
しての 遮断剤投与が,眼圧が正常範囲にあるにもかかわらず緑内障性障害が進行する病型,正常眼
圧緑内障の一部症例に治療的効果があるという指摘がなされていた。正常眼圧緑内障は,本邦では全緑内
障の6割近くも占めるため,
遮断剤投与が,眼圧が正常範囲にあるにもかかわらず緑内障性障害が進行する病型,正常眼
圧緑内障の一部症例に治療的効果があるという指摘がなされていた。正常眼圧緑内障は,本邦では全緑内
障の6割近くも占めるため, 遮断剤に関するこれらの報告は重要である。このような経過および,
laser doppler, laser speckle,またはカラー超音波ドップラー法等を使用して,生体眼でも非浸襲的に眼また
は眼動脈の血流を測定できる機器が開発されてきたことにより,従来の眼圧下降剤や
遮断剤に関するこれらの報告は重要である。このような経過および,
laser doppler, laser speckle,またはカラー超音波ドップラー法等を使用して,生体眼でも非浸襲的に眼また
は眼動脈の血流を測定できる機器が開発されてきたことにより,従来の眼圧下降剤や 遮断剤の眼組
織血流に対する研究が盛んに行なわれるようになってきた。現在までのところ,内因性交感神経刺激作用
をもつβ-遮断剤や他の一部のβ-遮断剤,ある種の
遮断剤の眼組
織血流に対する研究が盛んに行なわれるようになってきた。現在までのところ,内因性交感神経刺激作用
をもつβ-遮断剤や他の一部のβ-遮断剤,ある種の 遮断剤等は視神経循環に好影響を及ぼすこと
が示唆されている。また眼血流に好影響を及ぼす薬剤は,視野保存にもより有効に働く可能性も示唆され
ている。さらに新たな点眼薬の開発に関しても,眼血流に好影響を及ぼし,かつ充分な眼圧下降効果を示
すものが望ましいと考えられるようになってきている。以上緑内障の薬物治療をめぐる最近のトピックス
の一端につき紹介した。
遮断剤等は視神経循環に好影響を及ぼすこと
が示唆されている。また眼血流に好影響を及ぼす薬剤は,視野保存にもより有効に働く可能性も示唆され
ている。さらに新たな点眼薬の開発に関しても,眼血流に好影響を及ぼし,かつ充分な眼圧下降効果を示
すものが望ましいと考えられるようになってきている。以上緑内障の薬物治療をめぐる最近のトピックス
の一端につき紹介した。


緑内障手術療法
北澤克明,山本哲也(岐阜大学・眼科学)
緑内障の管理はここ10数年ほどで急速な変貌を遂げた。緑内障は古くは青そこひと呼ばれ,この名称
は緑内障発作(急性原発閉塞隅角緑内障)後の目の外観に由来するとされるが,このタイプの緑内障は眼
科的ケアの浸透とレーザー虹彩切開術の開発普及により大幅に減少し,また急性原発閉塞隅角緑内障と同
一の眼圧上昇機序でありながら,急性症状を欠く慢性の原発閉塞隅角緑内障も早期に発見治療され,視機
能障害をきたす症例はわずかになっている。
線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)
そこで改めて注目を浴びているのが原発開放隅角緑内障と,日本において2.0%(40歳以上)と最も 有病率の高い緑内障病型であることが近年明らかにされた正常眼圧緑内障(低眼圧緑内障)である。原発開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障は眼圧上昇の有無で鑑別され,原発開放隅角緑内障には眼 圧下降治療が行なわれる。また,正常眼圧緑内障はその名の示す如く眼圧が常に正常範囲内(21 mmHg以 下)にあるため,病因論に議論が多いが,当該の視神経にとっては相対的に高眼圧であるとの考えから, やはり眼圧下降治療が行なわれることが多い。
原発開放隅角緑内障,正常眼圧緑内障などの慢性緑内障および一部の急性緑内障に対しては,薬 物による降圧が第一選択である。薬物治療,レーザー治療を施行した後にも,十分に眼圧下降が得られな いと判断されたとき,言いかえれば,そのままでは視機能の重大な障害が生じると判断されたときに,眼 内に存在する液体(房水)の新たな流出路を形成し,眼圧下降をはかる手術が適応とされる。この手術は 緑内障濾過手術と総称され,今世紀初頭から本格的に行なわれはじめたが,1960年代後半に英国で創始さ れた線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)と呼ばれる術式が最も優れているとされ,現在に至るまで第 一選択の術式とされている。
創傷治癒機転の研究が進展
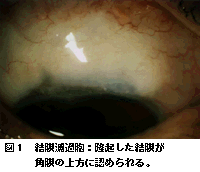 線維柱帯切除術では,眼球の強膜と角膜の境
界に小さな孔を開け,その孔を通じて,前房と結膜下の間に房水流出路を形成する。このため,線維柱帯
切除術が成功すると結膜に濾過胞(図1)と呼ばれる房水の貯留した
部分が形成される。しかしながら,手術部位に生じる生理的な創傷治癒機転により手術部位に瘢痕化が起
こり,手術効果のなくなることが10年ほど前まではしばしば認められた。手術の奏功しにくい眼の条件と
して,ぶどう膜炎,若年者,白内障緑内障などの手術既往,などが知られていた。また,民族差も存在し,
日本人は白人に比較して濾過手術が成功しにくいとされてきた。
線維柱帯切除術では,眼球の強膜と角膜の境
界に小さな孔を開け,その孔を通じて,前房と結膜下の間に房水流出路を形成する。このため,線維柱帯
切除術が成功すると結膜に濾過胞(図1)と呼ばれる房水の貯留した
部分が形成される。しかしながら,手術部位に生じる生理的な創傷治癒機転により手術部位に瘢痕化が起
こり,手術効果のなくなることが10年ほど前まではしばしば認められた。手術の奏功しにくい眼の条件と
して,ぶどう膜炎,若年者,白内障緑内障などの手術既往,などが知られていた。また,民族差も存在し,
日本人は白人に比較して濾過手術が成功しにくいとされてきた。
その後,手術部位における創傷治癒機転の研究が進み,線維芽細胞の増殖抑制により,濾過胞の 形成を促進させる(手術効果を持続させる)試みが,1980年代半ばにより活発になり,マイトマイシンC や5-フルオロウラシルなどの核酸代謝阻害薬をごく少量手術部位に投与することで手術成績の大幅な改 善が得られるようになった。
マイトマイシン:線維芽細胞増殖阻害薬
例えば,著者らの教室で研究を続けているマイトマイシンCは日本で発見され各種の悪性腫瘍に用い られている核酸代謝阻害薬であるが,現在,線維柱帯切除術に併用する線維芽細胞増殖阻害薬の標準とさ れている。マイトマイシンCを緑内障手術に用いる際にはこの薬物0.04%溶液をしみ込ませた小スポンジ を手術部位に術中3-5分間程度当てることで投与し,この操作のみで瘢痕形成が抑制され,濾過手術の成 績向上がもたらされる。この投与法で,眼球表面に投与されるマイトマイシンC量は10μg程度と推定されており,投与 量が少量であることもあり,全身的な副作用は報告されていない。また,5-フルオロウラシルの場合, 5mg(0.1 ml)を1日1回7日間程度結膜下注射で投与する方法が基本であるが,マイトマイシンCに準じた 投与法も時に行なわれる。
線維柱帯切除術の眼圧コントロール成績が格段に向上
著者らのマイトマイシンCを併用する線維柱帯切除術の眼圧コントロール成績は,生命表を用いた計 算では,原発開放隅角緑内障を対象とした5年の経過観察で,無投薬で眼圧が常に15mmHg以下にコント ロールされる確率は76%,無投薬で眼圧が常に20mmHg以下にコントロールされる確率は86%,点眼治療 を入れて88%であった。また,濾過手術の予後不良とされてきた症例でも眼圧コントロールは原発開放隅 角緑内障とほぼ同等で,無投薬で眼圧が常に15mmHg以下にコントロールされる確率は60%,無投薬で眼 圧が常に20mmHg以下にコントロールされる確率は80%,点眼治療を入れて94%であった。この成績をマイトマイシンC非使用例で以前に報告された原発開放隅角緑内障の成績61%(経過 観察4年,内服治療を含めて20 mmHg以下),予後不良例の成績31%(経過観察3年,内服治療を含めて) と比較すると,マイトマイシンCの使用により眼圧コントロール成績の格段に向上したことが一目瞭然で ある。正常眼圧緑内障に対する手術成績も改善し,眼圧が適切な値になる可能性は約90%であり,一部の 症例で視野進行の停止が認められており,手術療法の効果は明らかである。
緑内障手術治療の問題点として,手術合併症とそれに伴なう視機能の低下をあげることができる。 白内障,低眼圧黄斑症などの発症により,約10%の症例では視力が2段階以上低下する可能性があること に注意すべきである。
多くの緑内障患者が失明の恐怖から解放される
緑内障濾過手術は本特集でも取り上げられている白内障や網膜硝子体などの手術と異なり直接的に視 機能向上に結び付くものではないため華やかさに欠けるが,治療対象となる緑内障の慢性の経過を考える 時,その有用性が認識される。手術治療が最後の手段であるという緑内障治療体系の基本的な骨格は現在 も変わっていないが,この手術により,一生の間有用な視機能を保持できると思われる症例が大幅に増加 し,多くの緑内障患者が失明の恐怖から解放されていることは紛れもない事実である。

PRK手術の適応
所 敬(東京医科歯科大学・眼科学)
近年,わが国において近視矯正手術に対する関心が極めて高くなってきている。しかし,わが国では
角膜前後面放射状切開術(PK手術)による水疱性角膜症の苦い経験から,これまで正常の角膜に侵襲を
加える屈折矯正手術(PRK手術)には批判的であった。しかし,諸外国の趨勢からみても,わが国でもこ
れらの手術を正しく評価する必要が生じてきたため,日本眼科学会では屈折矯正手術適応検討委員会を設
け,1993年6月18日に屈折矯正手術の適応に関する答申を出した。
眼鏡・コンタクトレンズ装用困難者が対象
この答申が,欧米諸国のPRK患者選択基準と異なる点は,まず基本的に眼鏡およびコンタクトレンズ 装用困難者を対象としたことである。これは屈折矯正法としては,角膜に障害を起こすことのない眼鏡矯 正が第一選択であり,ついでコンタクトレンズが安全性,確実性の上から優れているという見地からであ る。また矯正量は,それ以前の欧米諸国の臨床報告を参考にして,比較的良好なPredictabilityが得られる 6Dを上限とした。さらに目標屈折値は,将来を含め遠視にならないように軽い近視を残すこととし,両 眼を手術する際には,他眼の手術は片目手術後6か月以上あけることとした。この第一次答申が出された 当時,欧米諸国がPRKについて多くの知識および臨床経験を得ていたのに比べ,わが国はかなり遅れをとっ ていた。しかしその後,わが国でも15余りの多施設で5機種のエキシマーレーザーを使用したPRKの治験 が行なわれ,現在までに手術眼数も600眼余に及んだ。昨年10月に第二次答申
わが国のPRK臨床治験経過の報告によると,術後裸眼視力はほぼ全例で上昇し,矯正視力は強い角膜 上皮下混濁やレーザー照射時の大きな中心ずれがなければ,術前と比較して不変または上昇した。そして, 矯正量が6D以下の症例では目標屈折値の±1.0D以内に入る確率は70~90%で,良好なPredictabilityが得ら れており,これらの結果は従来欧米諸国で報告されてきたものと比べ大差はなかった。PRKの治験が順調 に進行し,第一次答申から2年が経過したため,日本眼科学会は新たに屈折矯正手術適応検討委員会を設 けてその適応について再検討を委嘱した。そこで本委員会は,それまでの臨床治験の成績,および日本眼 内レンズ屈折手術学会会員へのアンケート調査をもとに,内外の文献も参考にして,主にエキシマレーザー による屈折矯正手術の適応の指針として,1995年10月1日に第二次答申を出した(表 1,2)。| 20歳以上の眼鏡またはコンタクトレンズの装用困難者で説明を十分に受け納得し,
かつ以下の各項目のいずれかに該当する者 (1) 2D以上の不同視 (2) 2D以上の角膜乱視 (3) 3D以上の屈折度の安定した近視 但し屈折矯正量は10Dを限度とし,術後の屈折度は,将来を含めて遠視にならない ことを目標とする。なお,両眼に手術を行なう場合には,片眼手術後3か月以上経 過観察し,経過が良好なことを確認した上で,他眼の手術を行なうべきである。 特に,屈折矯正量が6Dを超える場合にはさらに慎重な経過観察が必要である。 |
| 1) 外眼部の炎症
2) 円錐角膜 3) 緑内障 4) 白内障(核性近視を含む) 5) ぶどう膜炎 6) 術後角膜創傷治癒過程に問題のある疾患 7) 重篤な乾性角結膜炎 基礎分泌量が,Schirmerテスト第1法変法で5mm以下,かつローズベンガル 染色試験で++以上のもの 8) 角膜ヘルペスの既往のあるもの 9) 他の屈折矯正手術の既往のあるもの 10) 角膜疾患をきたすおそれのある薬剤を服用中のもの ※手術当日問診にて体調の不良を訴えるものには注意を要する |
この第二次答申でも適応選択における前提条件は,第一次答申と同様に眼鏡およびコンタクトレ ンズ装用困難者とした。屈折矯正手術が拡がりつつある今もなお,安全性と確実性において眼鏡やコンタ クトレンズに優る屈折矯正法がないことから,この条件は妥当であると思われる。一方,第一次答申に比 べ広く許容されることになったのは,最大屈折矯正量と他眼の手術時期である。最大矯正量は,第一次答 申では6Dまでとしたが,第二次答申では10Dを限度とした。臨床治験の結果では,矯正量が6D以下の場合 には予測屈折値と術後の屈折値とがおおむね一致していた。しかし,矯正量が増加するにつれてその差が 大きくなり,角膜の混濁も増強する傾向があった。そこで,強度近視や強い不同視のため,やむを得ない 症例に限り,10Dを限度とした矯正も許容されると考えられる。
片眼術後経過観察期間を短縮
また両眼に手術を行なう場合は,片眼手術後,他眼を手術するまでの期間を第一次答申では6か月と したが,第二次答申では片眼術後3か月以上観察し,経過が良好なことを確認した上で他眼の手術を行な うこととした。これは,術後2~3か月で屈折値がほぼ安定すること,片眼を手術することによって人為的 に強い不同視になるため両眼視が困難になる症例が多いことなどからで,術後3か月の経過が良好なもの では他眼の手術を施行してもよいと考えられる。ただし,6Dを超える矯正を行なう場合には,角膜の混 濁や術後屈折値の変化などの面から慎重に経過を観察し,他眼の手術は6か月以上あけることが望ましい。 この他,涙液の反射性分泌は低下しているものの基礎分泌はある程度保たれているような軽度のドライア イは,PRKを行なうことにより角膜上皮障害を改善できるという報告もあり,第二次答申では涙液の分泌 量についても,基礎分泌量がSchirmerテスト第1法変法で5mm以下,かつローズベンガル染色試験で+ +以上の症例は禁忌とすることを明記した。臨床上の問題点
PRKの臨床治験において,屈折および視力に関してはほぼ良好な結果が得られたが,臨床上いくつか の問題点もみられた。それは,(1)術後疼痛,(2)上皮下混濁と近視への戻り,(3)レーザーの照射ずれ,(4) 感染症,(5)角膜内皮障害,(6)セントラルアイランド,(7)視力の質などであった。術後疼痛に対しては, 近年disposable soft contact lens装用や冷却,ジクロフェナクナトリウムの内服,点眼が有効であるといわれ ている。しかし,ジクロフェナクトナトリウムの点眼は上皮再生の遅延と感染症の危険があり,disposable soft contact lens装用は低酸素状態と易感染性の危険もある。さらにdisposable soft contact lens装用とジクロ フェナクナトリウム点眼の併用により術後早期の上皮下混濁を生じたという報告もあり,これらの使用に は慎重を要する。角膜上皮下混濁とそれに伴う近視への戻りは,副腎皮質ステロイド薬の点眼や冷却によ り軽減できるといわれているが,副腎皮質ステロイド薬の長期使用は眼圧上昇,易感染性の点で問題があ る。しかしこの混濁は幸いにも一過性のものが多く,一般に術後6か月から1年で消失し視力に影響を与え ることは少ないが,ごく一部の症例で強い混濁のために矯正視力が低下したという報告もある。症例の選択には厳格さが必要
 また,レーザー照射の中心ずれが起こると不
正乱視による矯正視力の低下を招く。レーザーの照射中心は,欧米諸国では角膜頂点に合わせることが多
いのに対して,わが国では入射瞳中心に合わせることが多い。幸い角膜頂点と入射瞳中心のずれはほとん
どの症例で0.5mm以下であり,どちらに中心を決めてもまず問題は生じない。術後感染については,現在
までのところ報告は少ないが,わが国において1例重篤な角膜潰瘍を経験しており,角膜組織の切除によ
り常に感染を起こす危険があるという認識も必要である。角膜内皮は,スペキュラーマイクロコープによ
る観察では,術前後で変化がないと報告されているが,わが国で抗精神病薬の長期内服患者1例に術後内
皮障害が報告されている。しかし,これがPRKによるものか常用薬による影響かは不明である。セントラ
ルアイランドは,VISX社製のエキシマレーザーを使用した施設でよく報告されたが,中心部分に追加照
射を行なうプログラムの改良によりほとんど消失した。しかし,この追加照射により過矯正になり大きな
遠視化を起こしたという報告もあり,まだ改良が必要のようである。その他,裸眼視力や矯正視力が良好
であるにもかかわらず,近方視不良,夜間の見にくさやハローを訴える症例もあり,視力の質(Quality of
vision)という点では必ずしも良好とは言えないようである。
また,レーザー照射の中心ずれが起こると不
正乱視による矯正視力の低下を招く。レーザーの照射中心は,欧米諸国では角膜頂点に合わせることが多
いのに対して,わが国では入射瞳中心に合わせることが多い。幸い角膜頂点と入射瞳中心のずれはほとん
どの症例で0.5mm以下であり,どちらに中心を決めてもまず問題は生じない。術後感染については,現在
までのところ報告は少ないが,わが国において1例重篤な角膜潰瘍を経験しており,角膜組織の切除によ
り常に感染を起こす危険があるという認識も必要である。角膜内皮は,スペキュラーマイクロコープによ
る観察では,術前後で変化がないと報告されているが,わが国で抗精神病薬の長期内服患者1例に術後内
皮障害が報告されている。しかし,これがPRKによるものか常用薬による影響かは不明である。セントラ
ルアイランドは,VISX社製のエキシマレーザーを使用した施設でよく報告されたが,中心部分に追加照
射を行なうプログラムの改良によりほとんど消失した。しかし,この追加照射により過矯正になり大きな
遠視化を起こしたという報告もあり,まだ改良が必要のようである。その他,裸眼視力や矯正視力が良好
であるにもかかわらず,近方視不良,夜間の見にくさやハローを訴える症例もあり,視力の質(Quality of
vision)という点では必ずしも良好とは言えないようである。
手術を希望する患者は,テレビや雑誌などのマスメディアを介して屈折矯正手術を知ることが多 く,とかくその利点にのみ気をとられ,手術に大きな期待を持つ傾向がある。実際外来へ手術を希望して くる患者の中には,単に眼鏡やコンタクトレンズが煩わしいだけや美容上の動機で受診する者も多く,症 例の選択においては厳格さが必要である。さらに手術を行なう術者は,患者に対して過剰の期待を持たせ ないように注意することも大切である。
再び注目されはじめたRK手術
これらの問題点の他に,今後の屈折矯正手術の普及という観点で考えると,PRKはレーザー装置を含 めその維持費が高価であるという問題がある。そこで安価で手懸けやすいRKが近年再び注目されるよう になり,さらに切開方法を改良したmini RKにより従来指摘されていた角膜の脆弱性を改善できるという ことで,再びRKを施行する術者が増えてきている。また,新しい屈折矯正手術法として登場したlaser in situ keratomileusis(LASIK)とは,角膜上皮と実質浅層とをフラップ状に切除しておき,エキシマレーザー を照射後このフラップを戻す方法で,近い将来PRKにとって代わるといわれている。LASIKは,PRKの術 後疼痛を軽減し,より早期の視力回復が得られるが,戻したフラップの脱落やPredictabilityも含め長期予 後が不明であるという問題がある。眼科専門領域で取り扱うべき
いずれにせよ屈折矯正手術は眼科専門領域で取り扱うべき外科的・光学的治療法であり,術者は日本 眼科学会認定の専門医であることはもちろん,角膜の生理や疾患ならびに眼屈折に精通していることが必 須条件である。わが国の臨床治験の結果をふまえ1995年に第二次の答申が出されたが,屈折矯正手術の長 期予後は不明であるので,長年月にわたる観察がぜひとも必要である。このためには,屈折矯正手術のす べてのデータをセンターに登録して長期観察を行ない,これらに基づき,この手術法の正しい評価をすべ きである。また眼科医は,屈折矯正手術について,一般の国民への正確な情報提供を積極的に計らなけれ ばならない。そして屈折矯正手術はその社会的影響に鑑み,早急に公的医療に組み込まれる必要がある。 (執筆協力者:北澤世志博)

糖尿病網膜症
堀 貞夫(東京女子医科大学糖尿病センター・糖尿病眼科)
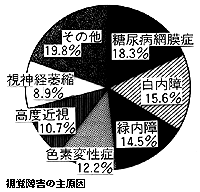 わが国での糖尿病患者数が500―600万人と推
定されている今日,糖尿病眼合併症である糖尿病網膜症が原因で視覚障害者に認定される患者は,全視覚
障害者の約20%にあたり,原因疾患の第1位にあげられている。欧米では既に1970年代に,失明者を生み
出す最も危険な疾患として糖尿病網膜症が取りあげられ,患者自身の不幸とともに治療や保護にかかる費
用も含めて社会的な問題となっていた。
わが国での糖尿病患者数が500―600万人と推
定されている今日,糖尿病眼合併症である糖尿病網膜症が原因で視覚障害者に認定される患者は,全視覚
障害者の約20%にあたり,原因疾患の第1位にあげられている。欧米では既に1970年代に,失明者を生み
出す最も危険な疾患として糖尿病網膜症が取りあげられ,患者自身の不幸とともに治療や保護にかかる費
用も含めて社会的な問題となっていた。
文化や生活の質が欧米化をたどっていた日本にいつかは訪れるであろうと予測された状況は,欧 米と同じように糖尿病患者が増えて,合併症である糖尿病網膜症による失明が深刻な事態となることであっ た。欧米から遅れて10数年,今や日本はまさにその事態に陥ってしまった。
一方で糖尿病網膜症の治療は,この20数年の間に大きな進歩を遂げた。ことに最近10年間での治 療機器や技術の発達により,失明予防の成果は確実に向上している。最も大きな治療の進歩は,レーザー 光凝固と硝子体手術にみられる。
何万人もの失明を予防したレーザー光凝固術
糖尿病網膜症に対するレーザー光凝固術の目的は,新生血管の発生防止または消滅と,網膜浮腫,こ とに黄斑浮腫の改善である。この技術が確立してから何千いや何万人の患者の失明を予防したことであろ うか。レーザー治療法の発達には様々な試行錯誤があり,いまだに方法として確立していない部分もある。 ことにレーザー治療中に黄斑浮腫が進行して,治療中に視力が低下する現象は,どんなに注意していても 完全には解消できず,治療する眼科医の頭痛の種である。さらにレーザーは治療機器のみならず診断用機器にも広く導入され,網膜血管の血流量,局所網 膜電位,走査型眼底撮影,網膜の部位別厚測定などの専門分野でも実用されている。光・工学の粋を集め て新しいレーザーの応用がさらに広げられ,もっと安全で有効な診断・治療法が開発されることが期待さ れる。
「早期硝子体手術」が普及へ
硝子体手術は約25年前に考案された手術法であるが,この手術名が眼科医の耳になじむようになった のはこの10数年内のことである。それ以前は手術的には立ち入ることができない聖域に例えられていた硝 子体にメスを入れたのは米国のR.Machemer教授で,その25年を省みた記述には,当初ほかの手段ではどう にもならない症例に立ち向かうため,周到な準備に知恵を絞り満を持して執刀した様子が窺える。ここに も光・工学の粋が集められ,機器と技術がともに急速な勢いで発展した。成功率が向上するとともに,ど うにもならなくなってするのではなく,神経の機能が糖尿病によって侵される以前に手術を施行する「早 期硝子体手術」が提唱され,最近普及する傾向にある。もう1つ注目に値するのは糖尿病黄斑浮腫に対する硝子体手術である。レーザーは黄斑浮腫に対 する治療手段として有効であるが,浮腫が重篤であると全く役に立たない。黄斑浮腫の原因が様々取り上 げられているが,硝子体が大きく関与することが多く,硝子体手術を施行すると浮腫が緩解することがわ かった。最近では初期の黄斑浮腫にも有効であることが提唱され,ひとつ間違えば即失明につながりかね ない硝子体手術の適応を,どこまで広げるかが論点になってきている。
やはり血糖コントロールが基本
このように2つの大きな治療方法があるとはいえ,糖尿病網膜症において最も基本になるのは血糖コ ントロールである。「血糖を低く保っていれば糖尿病網膜症は絶対に発症しないのか。糖尿病なのだから ちょっとくらい血糖が高くてもしょうがないのではないか」。糖尿病患者がよく口にする,逃げ口上とも とれる質問や言い訳である。米国のDiabetes Control and Complications Trial Research Group(DCCT)の平均 6年間の経過観察結果は,血糖を正常近く厳格にコントロールしていれば,糖尿病網膜症の発症は76%減 らすことができ,初期の網膜症の進行を54%抑制できることを証明した。これはインスリン依存型糖尿病 患者での結果であるが,日本に多いインスリン非依存型糖尿病患者にも当てはまるであろう。糖尿病網膜症による失明の脅威は,欧米に10数年遅れて日本に襲いかかっている。この10数年の 間に進歩した失明予防の研究成果を有効に利用して,現在の日本での失明を最小限に抑え,次の10年間の 目標を失明の撲滅に置くことを提唱したい。
