| 【対談】
外科手術のアートとサイエンス |
|
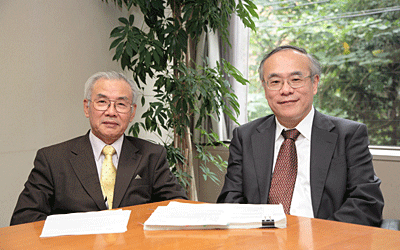 |
|
|
外科手術には,単なる知識ではない,経験に裏付けられたアート(art)が求められると言われる。しかし,「天才」「達人」にしか不可能な手術では,多くの患者を救うことはできない。手術には,暗黙知と同時に,誰もが学び,身につけることができるサイエンス(Science)が求められる。
小社から10月に刊行された『トップナイフ――外傷手術の技・腕・巧み』を「外科の風姿花伝(花伝書)」と評した訳者・行岡哲男氏と,外傷外科手術の分野において文字通り「トップナイフ」の評価を受けてきた山本修三氏が,手術のアートとサイエンスについて語った。
■「手術は頭でやれ」
達人の「巧み」をかいま見た瞬間
行岡 私が山本先生とお会いしたのは,外科の勉強のために済生会神奈川病院(以下,済生会)に行かせていただいた時のことです。済生会の外科チームで過ごした体験は,その後の医師人生において,すごく大きなものになりました。実は今回,『トップナイフ』という本の翻訳を引き受けたのも,読んでいて済生会時代がまざまざと蘇ったからなんです。実体験としての「ああ,あの時と同じだ」といった感慨とともに,本質的な考え方の部分で,済生会で教えてもらったことと同じことが書かれていると感じたんです。
山本 本書を読ませていただいて,私も「そういえばこんな症例もあったな」と思い起こされましたね。外科医である自分の「仲間」が書いている,そのことによる臨場感を感じました。
行岡 病院会会長としてのご活躍が有名で,若い読者の中には山本先生のご経歴をご存じない方もおられるかもしれません。あえてご紹介すると,先生はまさに「トップナイフ」というにふさわしい,外科手術の達人です。私が済生会に行く時にも「山本先生という,めっぽう手術のうまい人がいる」という評判をお聞きしていました。
今でもよく覚えているのですが,済生会に行ってすぐに,山本先生の前立ちをしていたところ,先生が腸間膜をスッとクーパーで外されたんです。「ずいぶん乱暴なことをするなあ」と思ったのですが,私がそのように感じたことがおそらく,言葉に出さなくても伝わったんでしょうね。術後に先生が「なぜ,こっちから取ったと思う? あれは……」と説明されたんです。正直,僕には発作的にされたようにしか見えなかったので(笑),「そんなことまで考えながらやってるのか!」と衝撃を受けました。
『トップナイフ』には,口酸っぱく「手術は頭でやれ」と書かれています。「何を考え,どういう状況判断をして,どう対処したのか」ということを頭でわかっていなければいけないということなのですが,これは,済生会で山本先生や,他の先輩方に言われたこととまったく同じでした。
はたから見ていただけではわからない,さまざまな因子が絡み合った状況判断や,言葉にならないような微妙な手技が手術現場にはある。済生会でかいま見た,そういう「巧み」の世界を感じたことが,この本を翻訳しようという大きな動機づけになりました。
単純を旨とせよ――「手術のサイエンス」への志向
山本 『トップナイフ』の原題のサブタイトルは“Art and Craft of the Trauma Surgery”となっています。先生の「外傷手術の技・腕・巧み」という訳はすごくいい訳だと思いますが,読者がこの「巧み」について,浅い捉え方をされてしまうと困るなと感じました。単なる「名人芸」という話で片づけてほしくない,ということです。現著者であるマトックス氏は,再三「単純を旨とせよ」と書いています。これはいろいろな捉え方ができる表現だと思いますが,私は「わかりやすく,再現性のある手術をしなさい」ということだと解釈しました。これは,私が長年テーマとしてきた,「手術をいかにして,誰にでもできるようなものにするか」という問題意識につながっているように思います。
このように捉えた場合,「単純を旨とせよ」というメッセージは,ArtやCraftといった言葉が指し示す世界よりもむしろ,究極的な意味でのサイエンス(Science)の世界に近いのではないかと思いました。そのうえで,手術をサイエンスとして,わかりやすくするということは,実は簡単ではないのだ,ということを言っている。「単純というのはいいものなんだ。でも,そこに到達するのは難しいよ」ということを,彼は書きたかったのではないかと思います。
行岡 私もそうだと思います。いま先生がおっしゃった「サイエンス」という言葉は,「普遍性」と置き換えられますよね。
大名人がいて,その人にしかできない手術というのは,結局のところ廃れてしまう。そうではなく,きちんと修練をしたら誰でもできるようになる,そういう普遍性を獲得できない手術はダメだ,という考え方のベースにあるのはサイエンスへの志向なのだと思います。
外科手術だけでなく,あらゆる臨床において今,そうしたクリニカルサイエンス(Clinical Science)が求められているのではないでしょうか。
■手術を「書く」ことの意義
研修医にも手術記事を
行岡 手術記事の書き方についても,山本先生とマトックス氏は同じことを言っています。端的にいえば「わかりやすく書く」ということなのですが,それは単に表現力・文章力ということを意味しない。自分がかかわった手術について,頭の中が整理できていないとわかりやすい手術記事は書けないからです。このあたりにも,サイエンス・普遍性への志向が感じられますね。山本 人間を手術するということは,大変なことですよね。人に傷をつけるわけですから,やるほうにはそれだけの覚悟と,きちんとした知識を持たなければいけない。そういう意味で,私がいまちょっと疑問に感じているのは,新しい臨床研修制度の中で,研修医に手術記事を書かせていない,ということなんです。実際に多くの病院で聞いてみたのですが,書かせていない。
もちろん,公式には手術記事は術者が書くものですから,研修医が書かなくても問題はありません。しかし,研修,教育という観点から見るなら,手術に参加した研修医が,手術記事を書かずにどうやってその手術を考え,指導を受け,自分のものにするのか。その部分が研修の中で欠けているように思い,危惧しています。
自分の見たことを,自分なりにまとめて書き,上級医から「こうじゃないよ。こういう意味があるから,こうやったんだよ」と修正してもらってはじめて知識が共有され,学びとなるのだと思うのです。その機会が失われているということは,研修医の皆さんにとって不幸ですよ。
行岡 そうですね。私も,済生会時代に,手術記事の書き方について受けた指導ははっきり覚えています。「ここをこう剥離したでしょ? それを書かなきゃ意味ないよ」と。他の先生から「よかったな。もう1回手術したな」と言われました。
高い目標としての「単純」
山本 私は,そういうふうに手術を普遍化し,言葉にする経験を持っていない人が,術式だけを覚えていくということの危険性を強く感じています。この本も,読む人によって,書かれていることの意味が大きく変わってきますよね。「こういう時はこうすればいい」といったマニュアル感覚で捉えると,この本の価値はまったくなくなってしまいます。例えば,ダメージコントロールという概念1つとっても,紹介されている手技や判断基準をマニュアル的に適応するということでは,この本の意図するものから大きく外れてしまうでしょう。
行岡 そうですね。手術では,患者が受けた侵襲に,手術侵襲が加わるわけですが,2つの侵襲の和が対応限界を超えたら患者は死んでしまう。そこで,いかに手術侵襲を下げるかという,ダメージコントロールの考え方がでてきます。ですから,極端な話,手術以外の選択肢を考えることも,広い意味でのダメージコントロールなんですが,そこを理解せずに一時的止血=ダメージコントロール,と考えてしまってはいけない。
山本 その場で何を選択するかには非常に多くのファクターが絡み合っており,適切な判断をするには乗り越えなくてはいけない壁がたくさん存在します。それを1つひとつ乗り越えることによって初めて,マトックス氏がいうところの「単純」に到達できる。「単純」に至る道は,なかなか険しいわけです。
彼はもちろん,そのあたりの難しさは重々承知のうえで,あえて「単純を旨とせよ」と書いているのでしょう。「誰にでもわかりやすい手術を行う」というのは,実はものすごく高い目標ということを理解したうえで,そこをめざしてほしいということですね。
血管を扱える外科医に
行岡 ダメージコントロールのお話が出たので少し触れておきますと,マトックスは心臓血管外科出身なんですね。ダメージコントロールの解説を含めて,本全体からそれを感じることができます。山本 普通の外科医とは視点が違いますよね。やはり,血管損傷のことがかなりきっちり書いてある。一方で,この人は尿道損傷とか,膀胱破裂があったらうろたえそうだな,と思ったりしました(笑)。ただ,どのような手術であっても,いかに血を止めるのか,という課題は避けられないはずで,すべての外科医にとって,血管損傷についての知識は大切だと思います。
もともと外傷手術をやってきた人は別にして,普段,待機的な手術で胃癌や胆嚢,肝臓切除をやっている先生は,あまり「もしこの血管から血が出たらどうしよう」という発想をしていないと思います。外傷外科医は常にそれを頭において手術をしていますから,基本的にドライフィールドで行える手術であっても,何かの具合で出血があった時,落ち着いて処置ができる。そういうスキルは,すべての外科医が最低限持っていなくてはいけない部分ではないかと思います。
行岡 この本が血管損傷への対応を強調しているのも,心臓血管外科出身だからというよりも,「手術では血を止めることが重要だ」というしっかりとした思想があるのだと思います。
山本 外傷をたくさん扱っている人でも,この本のレベルからすると,血管の扱い方について抜け落ちている知識も少なくないかもしれませんね。
行岡 まったく同感です。血管外科の方と話すと,やはり発想が違います。言われてみれば別にどうということもない,基本的な血管外科の手技なのですが,それを適切な場面で「ぱっ」と使える。血管外科的にはすごく基本的な知識・手技が,外傷手術の場面であまり活用されていない,ということがあるように思います。それはやはり,単に個別の手技・技術の問題ではなくて,発想や考え方の部分が違うんですよね。
■「手術のサイエンス」確立に向けて
いかに自分たちの医療を表現するか
行岡 先の手術記事の話題とも関係しますが,こうした実践書には,どうしても「本を読んで手術ができるか」という批判があります。マトックス氏はこれに対し,「自分たち自身が印刷された文字を介して,会ったこともない先人の知恵・経験に導かれてきた」としたうえで,「自分たちの本が同じように読者にとって役に立つものであることを願っている」と書いています。また,『トップナイフ』とは別の論文ですが,肝損傷の7例の手術を紹介した,ダメージコントロールについてのもので,たった7例の手術経過を淡々とつづったものがありました。統計もなければ,平均値も書いてない。でも,“Annals of Surgery”に掲載され,読んだ私たちにもその意味するところがしっかりと伝わってくる,よい論文でした。メタアナリシスでなくても,現場の真実がきちんと表現されている論文は,そうした権威ある学術誌でも採用されるわけです。
つまり,現場で起こっていることを,「アート」「度胸」「経験」で終わらせず,どう表現し,伝えていくかということが大切なのだと思うのです。医療が持つ不確実さも含めて,「われわれがやっていることはこうなんです」という,本当のギリギリのところで,医療の姿を伝えたいし,そういう責任が医療者にはある,と私は考えています。
そういう意味で『トップナイフ』は真の意味で臨床家が臨床家に向けて書いた本だといえるでしょう。アメリカはやはり,臨床に対して骨太いと実感しましたね。
手術の「幽玄」に到達するために必要なこと
山本 序文の中で行岡先生はこの本を『花伝書』になぞらえていますね。世阿弥が『花伝書』で書いた能の世界は,マトックスらが描く手術の理想と近い,邪魔なものを取り除いたシンプルな世界といえると思います。もちろん,能と医療では,最終的な目的は違うわけですが,そこにいたるまでの道のり,考え方のシンプルさ,というところがよく似ています。行岡 まさに,先生がおっしゃった意味で,私は『花伝書』を引用しました。能の世界では「幽玄」という,わかったようなわからないようなものが,1つの理想として提起されています。しかし,『花伝書』を読むと,その幽玄に向き合うためにどう考えるべきかということが,ものすごく論理的に,伝達可能なものとして書かれています。読むことによって「向こう側」に広がるグレートな世界をかいま見ることができる。
もちろん,山本先生がおっしゃったように,能と医学では最終的な目的は違います。しかし,私はサイエンスでもアートでも,つまるところは社会にどう受け入れられるかというところに行き着くのではないかと思っています。世阿弥は「芸術というのは人を喜ばせるためにあるのだ」ということを言っていますが,それにならえば,医療は「人の命を救うためにある」といえるでしょう。
『花伝書』は,社会の中で能が能として認められることに貢献してきました。それと同じように,社会の中で医療が医療として認められることに,この本は貢献できるのではないか,と感じています。
マトックスに会って話をしたとき,「『風姿花伝(=花伝書)』は600年間読まれている。きっとあなたの本も,今後600年間読まれるだろう」と伝えたところ,えらく喜んでいました(笑)。
山本 『花伝書』にならうなら,私たちの舞台は手術場であり,何を表現するかといえば救命ということになるでしょう。そういう文脈をしっかり頭に入れて,何が必要かを考えて舞台に立ってはじめて,満足な表現,つまりは手術ができるということですね。
今,若い人たちの外科離れが問題視されていますが,私はやはり救急や外科を志すならば,あえて「手術が好きだ」という人でなければいけないと思っています。そうでなければ壁を越えて,魅力的な世界が広がっているところまでたどり着くことはできません。
この本は,技術的には外傷手術を専門としない外科の先生には非常に参考になる内容だと思いますし,これから外科を志す人には,外科手術というのがどれほどの広がりを持っているものなのかを感じさせる手引き書として読まれるのではないかと思いました。
世の中に,医学書の名著というのはいくつかあるけれども,これはそういう可能性を持った本ですよね。
行岡 山本先生にそういっていただけると本当にうれしいです。本日はありがとうございました。
 |
山本修三氏
日本病院会会長,アジア病院連盟会長。1959年慶大医学部卒。同大外科学教室,芳賀赤十字病院,米国シンテックスリサーチセンター研究員を経て,73年済生会神奈川県病院外科医長に就任。その後,同院外科部長,副院長・救急センター部長,院長,名誉院長を務める。 |
| 行岡哲男氏
東京医大主任教授・救急医学。1976年東京医大卒。済生会神奈川県病院勤務などを経て2000年より現職。重症救急,特に重症外傷・広範囲熱傷を専門とする。日本救急医学会,日本熱傷学会役員,米国外科学会・外傷学会・熱傷学会正会員。救急医療現場の社会学・現象学的研究にも従事。 |
 |
