MEDICAL LIBRARY 書評特集


山雄 健次,須山 正文,真口 宏介 編
《評 者》竹原靖明(相和会 横浜総合健診センター長)
画像と病理の対比を中心に疾患の理解を深める名著
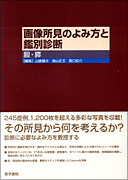 「作品はどんなに高邁な思想や理論に基づくものであっても,それが対者に何らかの感動を与えるものでなければ名作とはいえない。名著とはその内容が充実していると同時に読者に納得と感動を与える『何か』がなければならない。その『何か』とは卓越した知識,経験のうえに,読者にその内容を理解させようとする誠意と情熱ではなかろうか」。本書を手にし,類書にない新しい企画を目にしたとき,編・著者らの熱意が伝わり,老躯も疲労も忘れて,深更の空が白むまで読み耽った。そしてこれは正に「名著」であり,この領域を志す新進の若き臨床医への力強いメッセージとも思えた。
「作品はどんなに高邁な思想や理論に基づくものであっても,それが対者に何らかの感動を与えるものでなければ名作とはいえない。名著とはその内容が充実していると同時に読者に納得と感動を与える『何か』がなければならない。その『何か』とは卓越した知識,経験のうえに,読者にその内容を理解させようとする誠意と情熱ではなかろうか」。本書を手にし,類書にない新しい企画を目にしたとき,編・著者らの熱意が伝わり,老躯も疲労も忘れて,深更の空が白むまで読み耽った。そしてこれは正に「名著」であり,この領域を志す新進の若き臨床医への力強いメッセージとも思えた。
本書の最大の特徴は,画像と病理(マクロ)の対比を中心に,その疾患の把握と診断に関わる要点を「コラム」として簡潔にまとめ,それを適所に配して,種々の疑問や難解な事柄を氷解させている点にある。
その内容を具体的に列挙すると,
1)250例に及ぶ多数の貴重な症例が開陳されている。
1985年に発足し45回を数える消化器画像診断研究会で熱い討論を経て練り上げられた症例が中心であり,一例一例に高い教育的価値がある。
2)常に画像とマクロが並列で対比され,画像が何を反映しているか,画像に描出された所見とマクロ所見との関係が明示されている。
画像はすべて病変をマクロ的に表現したものであり,マクロ所見と画像所見の関係を正確に把握することは形態診断の真髄であり,外科的治療にとってもきわめて重要な情報である。これだけ多数の症例を蒐集し対比させることは至難の業であり,四星霜にわたる編・著者たちの並々ならぬ労苦と熱意が感じられる。
3)新しい診断論理が展開され,簡潔にして理論的に各種検査の個々の症例に対する有用性が示されている。
疾患単位に各所見をまとめ診断に導く従来の診断論理に捉われず,各所見単位に検査順位や診断経路を考える新しい方式が提示されている。この方式は論理的にはごく自然であり,簡明で理解しやすい。また,これは無駄を排除するクリニカルパスの理念にも通じるものである。
4)各疾患の理解と診療に欠くことのできない要点を「コラム」として簡潔にまとめ,適所に配置している。
この「コラム」には疾患概念(分類やその変遷の経緯も含む),臨床像,病理(マクロ所見),診断(鑑別診断も含む),治療,予後など疾患ごとに必要なもののみを取り上げ,きわめて簡潔かつ明快にまとめており,理解するうえで大変有用である。
等々である。
本書を通読して改めて感じたことは,編・著者たちの画像診断に寄せる執念にも似た情熱と,次世代に伝承しようとする熱意が全編に漲っている点である。新進の若者を視野の中心に据え,多くの障害を克服して,信念を貫き,あるべき姿と歩むべき道を示した本書は,初心者にはもちろんベテランにも有為の「名作」であり,「労作」である。
願わくは,本書が起爆剤となり,本邦の消化器画像診断がさらに飛躍されることを期待して止まない。


目黒 泰一郎 編
《評 者》光藤 和明(倉敷中央病院副院長・循環器内科)
TRIのメリットを活かしデメリットを除く方法を提示
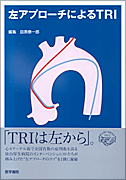 右上肢からCAG(Coronary Angiography;冠動脈血管造影)あるいはPCI(Percutaneous Coronary Intervention;経皮的冠動脈形成術)を行ったことのある術者は,右上肢からの冠動脈造影ではカテーテルのエンゲージの困難な例を少なからず経験しているはずである。腕頭動脈が蛇行しカテーテルが上行大動脈に折り返すように進んでいくときなどはその極みである。それらは左上肢からのアプローチが解決してくれることも,また多くの術者が感じていると思われる。なぜなら,大腿からのアプローチと左上肢からのアプローチは,大動脈弓を超えた後の走行が類似しているからである。さらに橈骨動脈アプローチでは,上腕動脈アプローチに比較して穿刺点は術者からそれほど遠いわけではなく,比較的左大腿動脈アプローチに近くすることが可能である。にもかかわらず,多くの術者は右橈骨動脈アプローチを好んで用いている。理由はいくつかあるであろう。(1)慣れていないのでコツがあるとしてもそれがわからない,(2)不測の不都合が起こり得ることが心配である,(3)いくつかの予測し得るデメリットが考えられる,(4)現状で満足して“食わず嫌い”になっている――などである。
右上肢からCAG(Coronary Angiography;冠動脈血管造影)あるいはPCI(Percutaneous Coronary Intervention;経皮的冠動脈形成術)を行ったことのある術者は,右上肢からの冠動脈造影ではカテーテルのエンゲージの困難な例を少なからず経験しているはずである。腕頭動脈が蛇行しカテーテルが上行大動脈に折り返すように進んでいくときなどはその極みである。それらは左上肢からのアプローチが解決してくれることも,また多くの術者が感じていると思われる。なぜなら,大腿からのアプローチと左上肢からのアプローチは,大動脈弓を超えた後の走行が類似しているからである。さらに橈骨動脈アプローチでは,上腕動脈アプローチに比較して穿刺点は術者からそれほど遠いわけではなく,比較的左大腿動脈アプローチに近くすることが可能である。にもかかわらず,多くの術者は右橈骨動脈アプローチを好んで用いている。理由はいくつかあるであろう。(1)慣れていないのでコツがあるとしてもそれがわからない,(2)不測の不都合が起こり得ることが心配である,(3)いくつかの予測し得るデメリットが考えられる,(4)現状で満足して“食わず嫌い”になっている――などである。
PCIの術者は他者が行っている方法を取り入れるべきかどうかを考慮するとき,しばしば自らが長年行ってきた方法を擁護するような論理を展開して,新しい方法を排除しようとする。時としてその手技の理念にかかわることなので,新しい方法がそれまでの自分の行ってきた方法の価値をおとしめることになってしまうのが大きな理由であるように思われる。しかし実際に新しい方法を取り入れてみるとそのメリットが初めて理解できるし,新たな展開の手段にも考え至ることが多いのである。また取り入れてみないとそのよさが永遠に理解できない部分がある。
本書は左橈骨動脈アプローチのメリットとデメリットとを論理的に明らかにして,メリットを活かす方法とデメリットをキャンセルする方法とを具体的に示している。そしてそれらは独自の工夫に満ちたものである。著者らの施設における左橈骨動脈アプローチのシステムは一朝一夕ででき上がったものではなく,現在の完成された形に成長するために多くの努力が傾注されたものである。論理的背景と手技の実際の記述はその手技を知らない術者にもそのメリットがきわめてよく理解でき,左橈骨動脈アプローチを取り入れることを躊躇させないであろう。
また本書は,左橈骨動脈アプローチをすでに行っている術者にとってもその質を高めるための具体的な方法が数多く記述されているし,橈骨動脈アプローチ一般に関して有益な情報もあわせて記載されている。さらに本書は,実際に日々左橈骨動脈アプローチを数多く行っている比較的若い術者が執筆しており,現場からの生の情報という新鮮さがあると同時に,マスターといわれる目黒泰一郎先生のような人でなくても質の高いTRI(Trans-Radial Coronary Intervention;経橈骨動脈冠動脈形成術)ができるという勇気を与えてくれるものである。多くのカテ室で座右の書物となる価値がある。


高橋 三郎,染矢 俊幸,塩入 俊樹 訳
《評 者》井上 新平(高知大学理事(研究担当))
臨場感あふれる症例で治療手法の適応を学ぶ
 本書は1981年にはじまったDSMケースブック・シリーズの最新版である。このシリーズには診断・診療計画を扱ったものと治療を扱ったものがあり,DSM-IV-TRによる前者の症例集は,同じ訳者によりすでに邦訳されている(『DSM-IV-TRケースブック』医学書院,2003)。今回出版された【治療編】では,この症例集にある235例から29例が選ばれ,さらに新たに5例を加えた34例についての治療が紹介されている。疾患的にはほぼ網羅されているが,気分障害圏,神経症やパーソナリティ障害,児童青年期の障害が多く,逆に器質性精神障害が少ない。米国の一般の精神科医が遭遇するケースを中心にしているのだろう。構成としては,症例要約とDSM-IV-TR診断のあとに治療方針が書かれているが,その著者は当該分野の第一人者で,統合失調症の症例のホガティ,境界性パーソナリティ障害の症例のガンダーソンらである。オーソドックスな治療法の解説とともに,この症例ではどうするかということが,時にかなり具体的に提示され,また同一症例で複数の専門家がまったく異なった立場から論じているのもあり(境界性パーソナリティ障害,パニック障害など),その記載には臨場感がある。
本書は1981年にはじまったDSMケースブック・シリーズの最新版である。このシリーズには診断・診療計画を扱ったものと治療を扱ったものがあり,DSM-IV-TRによる前者の症例集は,同じ訳者によりすでに邦訳されている(『DSM-IV-TRケースブック』医学書院,2003)。今回出版された【治療編】では,この症例集にある235例から29例が選ばれ,さらに新たに5例を加えた34例についての治療が紹介されている。疾患的にはほぼ網羅されているが,気分障害圏,神経症やパーソナリティ障害,児童青年期の障害が多く,逆に器質性精神障害が少ない。米国の一般の精神科医が遭遇するケースを中心にしているのだろう。構成としては,症例要約とDSM-IV-TR診断のあとに治療方針が書かれているが,その著者は当該分野の第一人者で,統合失調症の症例のホガティ,境界性パーソナリティ障害の症例のガンダーソンらである。オーソドックスな治療法の解説とともに,この症例ではどうするかということが,時にかなり具体的に提示され,また同一症例で複数の専門家がまったく異なった立場から論じているのもあり(境界性パーソナリティ障害,パニック障害など),その記載には臨場感がある。
中味を通して,生物心理社会的モデルに基づく評価と治療計画の重要性が随所に強調されているのが目に付く。その一つとして,Engelが1977年にScienceに寄せた論文が紹介されている。わが国では,このモデルは統合失調症などで主に扱われているが,ここでは「生物学的治療の成否は心理社会的要因とそれに対する共同的アプローチ次第」(パニック障害の治療)という見解が随所に出てくる。精神医学が他の医学分野に貢献できるモデルであるという米国精神医学の主張が底流にあるのだろう。
併存症としてのうつ病の多さとSSRIの適用の広さも目を惹く。中には,うつ病治療でfluoxetineを服用し寛解状態になったが,副作用と思われる性機能不全が起こった,さてどうするか,(1)fluoxetineを減らすか耐性ができるのを待つ,(2)性的副作用のより少ない薬剤に変える,(3)バイアグラのような薬剤を追加するという問いかけがあり,思わず主治医となった気分で読まされる。
米国の保険診療の実態も折々に触れられている。「重症の過食行動と下剤乱用がある摂食障害の患者の入院には著しい電解質異常か著明な心電図異常が必要」(第三者支払い機関)という実情や,統合失調症のリハビリテーションに対するmanaged careの無理解などが生々しく紹介されている。
本書で紹介されている治療手法については,訳者も言われるようにわが国でも広く行われているものがほとんどである。しかし,その適応や実際の手法については大変参考になることが多い。また前述したような精神医療の基本姿勢や医療状況なども含めて参考になる事柄が要所要所に書かれている。今日の米国精神科医療を知るうえでも大変役立つ書であろう。


国際膵臓学会ワーキンググループ 著
田中 雅夫 訳・解説
《評 者》松野 正紀(東北厚生年金病院長)
消化器病の診療に携わるすべての医師に
 粘液産生膵腫瘍
粘液産生膵腫瘍
癌研究会附属病院の大橋計彦らが,十二指腸乳頭の特異な所見を伴った粘液産生膵腫瘍を,世界に先駆けて報告してからはや四半世紀が経過した。この間,数多くの報告がわが国および諸外国からなされ,この疾患が膵臓病の中で重要な位置を占めるようになった。何故重要なのかというと,発生頻度はそれほど高くはないが,経過とともにがん化する傾向が強いからである。
わが国の高齢者の剖検膵では,半数以上に微小なものも含めて嚢胞性病変が認められる。このような状況の中で,嚢胞性疾患の鑑別診断が治療上重要になってきた。世界保健機関(WHO)が,粘液を産生する嚢胞性膵腫瘍を膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)と粘液性嚢胞腫瘍(MCN)の2群に分類したのが10年前であった。それ以後,本疾患に対する理解が急速に深まった。
診療ガイドラインに関する国際シンポジウム
2004年に第11回国際膵臓学会が仙台で開催された際,「IPMN/MCNの診療ガイドライン」のシンポジウムが持たれた。最初にわが国から発信され,その病態解明についてはわが国が世界をリードしている本疾患のガイドライン作成の討議が日本で行われたのはきわめて当然のことであった。
シンポジウムの司会と意見の取りまとめ役を担当したのが本書の訳・解説者の田中雅夫教授であった。それは世界各国の第一人者を集めてのコンセンサスミーティングとなった。その時の国際膵臓学会の成功はひとえに「国際診療ガイドライン」のシンポジウムの充実によるところが大きく,田中雅夫教授の事前の意見調整のすばらしい手腕と見事な司会振りは今でも語り草になっている。その後,広く国際的合意を得て英文で学会誌『Pancreatology』に掲載されたものが「International Consensus Guidelines for Management of Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms and Mucinous Cystic Neoplasms of the Pancreas」である。本書はその日本語版解説書である。
診断と外科治療のキーポイントを示す
消化器病の診療でしばしば遭遇する嚢胞性膵疾患では,鑑別診断と切除が必要かどうか,切除範囲はどこまでかの判断に多くの医師が悩まされる。英文のガイドラインを読みやすく翻訳するとともに,ガイドラインで使用できなかった画像を随所に挿入しながら,診療のポイントをわかりやすく解説しているのが本書の特徴である。新たに挿入された病理組織像や画像は,多数の中から厳選された典型的なもので,それだけでも一見の価値がある。本邦で最も多くのIPMN/MCN症例を経験している著者の解説だけに説得力がある。
膵疾患を専門とする医師だけでなく,広く消化器病の診療に携わる方々に本書の一読をお薦めしたい。


日本頭痛学会 編
《評 者》片山 宗一(総合南東北病院神経疾患研究所長/獨協医大名誉教授)
慢性頭痛のすべてを網羅した診療に必須のガイドライン
 器質的脳障害のない,いわゆる慢性頭痛は日常臨床の場でもっとも多くみられる症状の一つであり,数多くの論文(PubMedではheadache約38,000編,migraineに限ると約18,000編)が発表されている。また頭痛に関する教科書も毎年多数出版されている割には診療指針となる情報は多くない。2004年,15年ぶりに改訂された「国際頭痛分類 第2版」は系統的,合理的な分類と同時に詳細な解説を加えた188頁(日本語版)の大著であり,それ自体がガイドラインを構成しているが,厳密さを求めるあまり,説明が煩瑣,冗長であり,専門医は別として,一般医には読みにくいと批判されている。
器質的脳障害のない,いわゆる慢性頭痛は日常臨床の場でもっとも多くみられる症状の一つであり,数多くの論文(PubMedではheadache約38,000編,migraineに限ると約18,000編)が発表されている。また頭痛に関する教科書も毎年多数出版されている割には診療指針となる情報は多くない。2004年,15年ぶりに改訂された「国際頭痛分類 第2版」は系統的,合理的な分類と同時に詳細な解説を加えた188頁(日本語版)の大著であり,それ自体がガイドラインを構成しているが,厳密さを求めるあまり,説明が煩瑣,冗長であり,専門医は別として,一般医には読みにくいと批判されている。
『慢性頭痛の診療ガイドライン』は他疾患のそれとは異なり,『国際頭痛分類第2版』に準拠し,日常の臨床で取り上げるべきテーマについて,専門医のほか一般医をも対象として慢性頭痛の問題点をすべて抽出し,また患者団体の協力をも得て,臨床的課題を明確にした。すなわち,91の設問に分けてエビデンスをもとに解説が加えられている。まず,頭痛の一般的解説として,診断,治療のほか,病診連携,職場・学校での頭痛対策,OTCや漢方薬による対応法,その他,医療経済の記載もみられる。さらに,一次性頭痛(片頭痛,緊張性頭痛,群発頭痛),小児の片頭痛,薬物乱用頭痛,遺伝などのほか,「その他の一次性頭痛」についても多くの頁をさいている。この分類はいわばwaste basketの様相を呈しており,思いつくまま咳嗽,労作,性行為,睡眠時などに伴う雑多な頭痛が取り入れられており,その他,雷鳴頭痛(thunderclap headache),持続性片側頭痛(hemicrania continua),いわゆる慢性連日性頭痛(chronic daily headache)の分類上の問題など,第一版刊行後,厳しい検証を受けたがまだ議論の余地のある疾患もいくつか含まれている。
本ガイドラインではエビデンスとして選りすぐりの文献が多数引用されている。そのうち国内文献は国際分類の翻訳,その他を除いても約10%を占めており,1973年に発足し,3分の1世紀の歴史を有するわが国の頭痛学研究の実績が反映されているといってよい。しかし,トリプタンなど,画期的な治療薬に関する重要な論文は皆無に近い。この事実は他の神経治療薬と同様,新薬導入が海外より10年遅れた事情によるもので,「トリプタンの失われた10年」によりわが国の優れた臨床神経学者が海外の学者と互角に競い合える機会を奪われたものと考えられ,大変残念でならない。
慢性頭痛は十人十色で,“There are no diseases,only patients”といわれるように,各症例にはおのおの特徴があり,それぞれにsubdiagnosisを必要とすることも少なくない。本書は日本頭痛学会の総力をあげて編集され,慢性頭痛のすべてを網羅した,大変読みやすい画期的なガイドラインであり,日常の臨床で国際頭痛分類に基づいて正しく診療する際に欠かすことのできない座右の書である。
B5・頁240 定価4,200円(税5%)医学書院
