| 連載 臨床医学航海術 第10回 医学教育(2) 田中和豊(済生会福岡総合病院臨床教育部部長) |
(前回よりつづく)
臨床医学は大きな海に例えることができる。その海を航海することは至難の業である。吹きすさぶ嵐,荒れ狂う波,轟く雷……その航路は決して穏やかではない。そしてさらに現在この大海原には大きな変革が起こっている。この連載では,現在この大海原に起こっている変革を解説し,それに対して医学生や研修医はどのような準備をすれば,より安全に臨床医学の大海を航海できるのかを示したい。
前回は,医学教育について,基礎学力の低下の問題について述べた。今回は,医学教育におけるギャップの存在という問題について述べたい。
ギャップの存在
前回述べたように現在の医学教育は,小学校・中学校・高等学校・大学というように教育の各課程の積み重ねを前提としている。小学校・中学校・高等学校で,国語・数学・英語・理科・社会を学び基礎学力を養成する。そして,大学医学部では,さらに自然科学・基礎医学そして臨床医学を順に履修していき,その集大成として医師国家試験を受験することになっている。この医師国家試験合格後,医学生は研修医として臨床研修を受けることになる。しかし,実際はほとんどの研修医は医療の現場で滞りなく働くことができていない。この理由は医師国家試験合格と研修医の間に大きなギャップが存在しているためである。そして,このギャップの最大の原因は,医学部の実習が単なる病院見学であって,アメリカの医学生が行うクリニカル・クラークシップのようなフィールド・ワークがほとんど行われていないことにある。言い換えると,このギャップとは机上の勉強と実際のフィールド・ワークとの間のギャップとも言える。このため,研修医はこの大きなギャップを自分で埋めることを強いられているのである。採血・点滴などの手技,問診・診察方法,カルテの記載方法,主訴から問診・診察・検査を通して診断に至る診断プロセス,各種検査値の読み方,さまざまな薬物の使用方法などなど。これらすべてのことについて体系的な教育システムなど存在しない。これらのことを研修医は五里霧中の医療環境の中で自分自身の力で手探りで学んでいかなければならないのである。
アメリカの医学教育システム
ところが,アメリカでは日本のように医学校と研修医との間に大きなギャップは存在せずに,普通に勉強していれば自然に優れた医師になるようなシステムが存在するのである。私はアメリカで内科レジデント教育を受けたが,その中で私が最も感銘を受けたのがこのアメリカの体系だった臨床医学教育システムである。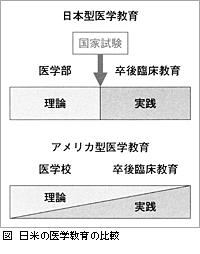 日本の医学教育システムでは,図のように医学部卒業以前は机上の勉強という「理論」が中心で実地の臨床研修という「実践」がほとんどない。しかし,医師国家試験合格を境に臨床研修では逆に肉体労働という「実践」で忙殺され,ほとんど机上の勉強という「理論」がなくなる。このような状態では,研修医は雑務に忙殺されて,臨床研修中に肝心の医師の職務である問診・診察・検査・診断・治療・マネジメント能力が十分に育成されない。
日本の医学教育システムでは,図のように医学部卒業以前は机上の勉強という「理論」が中心で実地の臨床研修という「実践」がほとんどない。しかし,医師国家試験合格を境に臨床研修では逆に肉体労働という「実践」で忙殺され,ほとんど机上の勉強という「理論」がなくなる。このような状態では,研修医は雑務に忙殺されて,臨床研修中に肝心の医師の職務である問診・診察・検査・診断・治療・マネジメント能力が十分に育成されない。
ところが,アメリカの臨床医学教育ではこのようなことがないように,医学校から卒後臨床教育まで連続的にかつ段階的に発展できるように,「理論」と「実践」が理想的に配分されているのである。このように確立された臨床医学教育制度があるアメリカでは,どんな医学生でも普通に努力していれば自然に優れた医師になることができるようになっているのである。
日本で研修医として働いていた私はいつまで経っても無駄な雑務,カラオケや宴会芸の練習にばかりに追われて,一向に臨床能力が向上しないことに自己嫌悪に陥っていた。日本で臨床研修を受けた後アメリカでこのような優れた医学教育を見た私は,極端に言えば,アメリカの大リーグに入団してショックを受けた日本の田舎の草野球選手のように悔しかったのを今でも覚えている。
ギャップを埋める
このように大学医学部と臨床研修制度の間にある大きなギャップを埋めるために,大学教育も改革されているのは確かである。大学医学部教育は戦前には,一般教養2年,基礎医学2年,臨床医学2年という古典的なドイツ医学の医学教育であった。しかし,現在ではこの枠組を取り払って低学年から臨床医学教育を行うように変化している。また,教育方法も過去には一方的な講義中心であったものが,少人数チュートリアルなどの双方向の教育形式が取り入れられつつある。このようにさまざまな努力が行われているにも関わらず,日本の医学教育がアメリカの医学教育に近づくのは近い将来には考えにくい。つまり,大学医学部と臨床研修制度の間の大きなギャップは開き続けているのである。それならば医学生はいったいどうしたらよいのであろうか? 答えは,現在の状況ではこの大きなギャップを埋めることを教育に期待できないので,医学生はそのギャップを自分自身で埋めるしかないということである。単刀直入に言うと,医学生のときに単に医学部卒業および医師国家試験合格という目標だけでなく,卒業後の大学医学部と臨床研修制度の間にある大きなギャップを自分で埋めるために,あらかじめ学生のうちから勉強しておけということである。
医師として働くならばこの大きなギャップを埋める苦労はいずれしなければならないものである。どうせしなければならない苦労は後回しにすればいいと考えて,「学生時代=遊び」,「研修医時代=勉強」と割り切るのも一つの手である。しかし,いずれ埋めなければならないギャップならば,いっそのこと学生時代から埋める努力をしようという生き方もあってもいいように思う。
参考文献
田中和豊:米国の医師養成に学ぶ〈第2回〉体系的医学教育の必要性(Attending Eye Vol.2, No.1, p82-83, 2006)
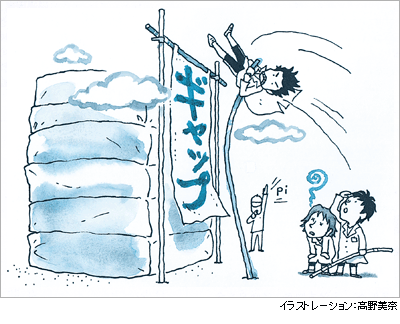
|
・基礎医学から臨床医学の時代へ
・疾患志向型から問題解決型の時代へ ・専門医から総合医の時代へ ・単純系から複雑系の時代へ ・確実性から不確実性の時代へ ・各国主義からGlobalizationの時代へ ・画一化からtailor-madeの時代へ ・医師中心から患者中心の時代へ ・教育者中心から学習者中心の時代へ |
|
・プロ精神を持つ
・フィールド・ワークを行う ・真理の追究目的から患者の幸福目的へ ・知識を知恵にする |
|
・基礎学力の低下
・ギャップの存在 ・教育・学習方法 ・評価方法 ・人間関係 |
(次回につづく)
