【interview】
「臨床研修に関する調査」が伝える研修医の声
篠崎英夫氏(国立保健医療科学院長/「卒前教育から生涯教育を通じた医師教育の在り方に関する研究」主任研究者)厚労省は8月31日,厚生労働科学研究費補助金研究「卒前教育から生涯教育を通じた医師教育の在り方に関する研究」班において,平成17年度「臨床研修に関する調査」報告を発表した。同調査は,新医師臨床研修制度による修了1期生が今春誕生したなか,その成果と今後の行方を占う大規模調査として注目される。
本紙では,同研究班主任研究者の篠崎英夫氏(国立保健医療科学院)に,研修医の満足度や臨床研修修了後の進路について聞いた。
――篠崎先生は,「卒前教育から生涯教育を通じた医師教育の在り方に関する研究」の主任研究者をされております。最初にこの研究班のねらいからお聞きかせください。
篠崎 新医師臨床研修制度は平成16年4月に施行されて,今年3月に1期生が研修を修了しました。ただ,2年間の臨床研修における到達目標が示され,処遇も改善するなど整備がなされたことで,逆にその前後の課題が浮き彫りとなりました。「卒前教育はこのままでいいのか」という指摘がなされ,2年間の臨床研修が終わったあとの,いわゆる後期研修や専門医制度,生涯教育はどうするのかという問題もあります。
私は13年度から2年間,厚労省医政局長として制度設計に関わってきました。その当事者のひとりとして,卒前教育から生涯教育を通じた医師教育の在り方を提言したいということで,3年プロジェクトの研究班を立ち上げました。
医師不足と研修医の動向
――3年プロジェクトの1年目にあたる昨年度は,「臨床研修に関する調査」をされました。中でも今回注目されたのが,臨床研修修了1期生の進路,後期研修に関する調査項目です(表)。アンケート結果を見ると,「研修後に専門としたい診療科」では,小児科,産婦人科,麻酔科が比較的多かったですね。| 表 研修後に専門としたい診療科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「専門とする診療科が決まっている」と答えた2年次研修医3298人に対する調査。旧制度の同世代である「20代医療施設従事医師診療科別割合」(n=26206,平成14年)では,小児科6.8%,麻酔科4.6%,産婦人科4.2%となっており,今回の調査のほうがいずれも割合が高い。 (解説=本紙編集室) |
篠崎 そうですね。実際にその診療科に定着するかという別の問題もありますが,医師不足が問題とされている診療科で希望者が多かったのは光明だと思っています。
――「最近の研修医は,収入優先やトラブル忌避で,負担の少ない診療科を選ぶ」というイメージが巷ではよく語られます。
篠崎 この結果をみると,そうではないですね。やはり良医になりたいと思って医学部に入る人が大半だろうし,「小児科や産婦人科が少ない」となると,志が高い人はそちらへ行こうという気持ちになるのですね。
「臨床研修修了後に専門とする診療科を選んだ理由」(図1)をみても,「学問的に興味がある」(63.0%),「やりがいがある」(60.2%)といった回答が上位で,「収入がよい」(3.6%),「訴訟が少ない」(2.9%)は少ない。収入だけが目安ではないということで,ホッとしてもいます。
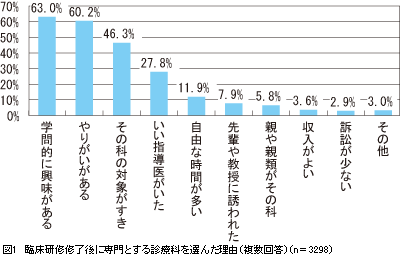 |
| 表と同じく「専門とする診療科が決まっている」と答えた研修2年次生3298人に対する調査。また,希望診療科別の分析も行われており,「その科の対象がすき」の項目では小児科,「やりがいがある」で産婦人科,「いい指導医がいた」で麻酔科が,12診療科のうちでいちばん高い割合となっている。なお,臨床研修の前後で将来専門とする診療科を変えた研修医は1156人(35.1%)。診療科を変更した理由は「研修してみて興味がわいたから」71.3%に対して,「研修して興味がそれた」25.0%,「研修してみて大変だと思った」17.6%。 (解説=本紙編集室) |
――現在は医師不足,特に地域・専門分野別の偏在が問題となっています。
篠崎 新しい臨床研修制度が医師不足の元凶であるとは思っていません。いろいろな要素が重なったのです。ひとつは,国立大学・国立病院の独立行政法人化が平成16年4月にスタートしたこと。そしてもうひとつの大きな背景は,診療報酬改定の影響で,病院経営が苦しくなってくると,大学病院を中心にして人の集約が始まります。そういった様々な問題が一気に顕在化したために,地方の中小病院からの引き上げにつながっていったのではないかと思います。
――旧制度と比べると,これまで医師の少なかった地域や中小病院で研修医が増えているようです(本紙2649号表「2次医療圏医療規模別研修医在籍状況」参照)。
篠崎 そうですね。数の上では地方に研修医が行っています。ただ,研修医は教育を受ける立場でもあるわけで,一人前になるには時間がかかります。だから,病院での貢献度が昔とは違ってきているのは確かで,研修医が成長するまで現場がどう対処するかというのは課題だと思います。
それと,いままでは外の施設で研修しようと思うと,自分の大学病院の医局の誘いを断ったり,市中病院を探すにも情報収集が大変だったりしたのが,マッチングによってひとりで考えて選べるようになりました。それが研修医の大学離れを招き,大学での医師不足の間接的な要因になった面はあると思っています。
中小病院の熱意が研修医に伝わった
――研修体制・プログラムについても,それぞれ満足度やその理由を調査されています。どういった点が注目されるでしょうか。篠崎 研修体制についての満足度は,病床規模が小さい病院ほど高いという結果が出ました(図2)。これはむしろ当然かなと思います。大病院となれば,指導医をはじめ,周囲の医療人との関係が薄くなります。それから,小さい病院ほどプライマリケアが担う患者さんも多いだろうし,研修の中味も濃くなるでしょう。
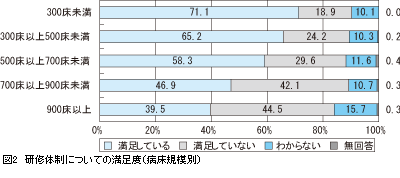 |
| 2年次研修医への調査。病床規模が小さい病院ほど,研修体制に対する満足度は高い。なお,臨床研修病院・大学病院別では,「満足している」が前者65.5%に対して,後者39.2%である。研修プログラムに対する満足度でも,大学病院より臨床研修病院において高く,また病床規模が小さい病院ほど高い結果となった。 (解説=本紙編集室) |
――研修体制に満足している理由をみても,「職場の雰囲気がよい」とか,「指導医の指導が熱心」といった回答が多かったようです。
篠崎 旧制度下の指定要件では,原則として300床以上の病院しか臨床研修病院になれず,大病院が研修の中心でした。新制度ではその要件を外して,研修医を受け入れたい,やる気のある病院ならば一定条件下で認めています。いまは中小規模の病院でもかなりの数の研修医を受けて入れるようになって,そういうところでは意欲が研修医にも伝わるのだと思います。
――理念と熱意があれば,「地方の小さい病院だから,来てくれない」と悲観する必要はないと。
篠崎 いまはマッチングがあって,インターネットなどを用いてしっかり情報収集していますしね。今回の調査をみても,研修医は研修体制・プログラムをしっかり調べて選んでいるということがよくわかります。今後は研修を終えた1期生,2期生の意見が医学生のあいだに浸透していくでしょうから,ますますそういう傾向は強まると思います。
――受け入れ側の大学病院や臨床研修病院は,今後どういう研修体制を築くべきでしょうか。
篠崎 この話は後期研修とも関係しますが,まずはプライマリケアの徹底を図るべきです。それはいま国民が望んでいることで,今後の大きな課題だろうと思います。
ただ,基本手技に関して言えば,例えば臨床研修の到達目標に気管挿管や採血法があります。これらは医学生のうちに実習できますから,在学中にある程度習得しておけば臨床研修ではより深い部分ができるわけです。そうやって,卒前から生涯教育まで通して2年間の臨床研修を考えれば,いま以上に中味の濃いプライマリケア研修ができるようになります。
■臨床研修制度と医学教育の将来像
悲願だった研修医の処遇改善
――臨床研修制度は,今後見直しが控えています(厚生労働省令第158号附則「厚生労働大臣は,この省令の施行後5年以内に,この省令の規定について所要の検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」)。篠崎 平成14年12月21日に大臣告示を発しましたから,その5年後だと19年。今年末から来年にかけてが山場でしょう。新制度のスタート時は,実現可能性も考えて理想と現実のぎりぎりのラインをめざしたわけです。いろいろな立場の方の意見を聞いて,よいところはそのまま残し,逆に直したほうがいいところは「改むるには憚ることなかれ」で直す。今回の調査報告は,そうした議論の土台となるものだと思っています。
――新制度創設に尽力してこられたご経験から,制度見直しのなかでも特に残したい点はなんでしょうか。
篠崎 まず,処遇は絶対に後退してほしくない。個人的な話になりますが,私の原点はインターン闘争なのです。
――それが厚労省で新制度の準備に関わられて,運命のめぐり合わせですね。
篠崎 そうなんです。インターン闘争は,処遇の改善要望から始まりました。それで昭和43年にインターン制度が廃止され,医師免許証は大学卒業後に取得できることになりましたが,処遇の改善はあまりなかったのです。その状態がずっと続いて,結局アルバイトをやりながらでないと臨床研修ができない状況になり,研修もストレート研修に近いものになってしまった。患者を全人的に診る能力もないままに,卒業したらすぐに専門家をめざして大学病院に残るようになってしまったわけです。
こうした点を新制度でなんとか改めたいと思っていた私にとって,最大のポイントは研修医の処遇でした。そして間接的にではありますが,研修医の処遇に補助金が出るようになり,研修に専念できる環境が整ったわけです。
長期的視点で考える医学教育
篠崎 「卒前教育から生涯教育を通じた医師教育の在り方に関する研究」は3年プロジェクトで,昨年は外国をいくつか視察しました。例えばシステムについては,日本は医学部6年+臨床研修2年で,義務化年限が8年となります。これをアメリカのように4+4にしたらどうかという意見もあります。EU統一の医学教育制度をスタートさせようとしているヨーロッパも含めて,医師教育の体制を調査しました。来年はこの3年間のまとめとして提言をする予定です。2年間の臨床研修が終わったあと,どういうかたちで専門医制度に結びつけていくかが大事だと思います。――「専門医志向が強いのだから,研修制度は1年でいい」という意見もあります。
篠崎 諸外国のどこを見ても,プライマリケア能力の習得に2-3年はかけていて,その上に4-5年の専門医研修で一区切り,というのがほとんどです。もちろん,卒前教育でどこまでできるかにもよりますけれども,1年ではさらに細切れ研修になってしまいます。制度本来の趣旨から鑑みても,やはり2年は必要じゃないでしょうか。
医学教育の在り方を考える際,少子高齢化,国民のニーズ,医学の進歩といった様々なファクターがあります。日本もこうした点を考慮しながら,長期的な視点で考えていかなければいけないでしょうね。
(了)
| 平成17年度「臨床研修に関する調査」の概要
新医師臨床研修制度の効果等を検証・分析するため,臨床研修病院・大学病院849施設,および1-2年次研修医1万4870人に対して今年3月に実施された。有効回答数は,2年次生3809人(51.9%),1年次生4315人(57.3%)。詳細は厚労省「新たな医師臨床研修制度のホームページ」で閲覧可。 |
| 篠崎英夫氏
1973年慶大医学部大学院卒。英国マンチェスター大・大学院修士(Community Medicine)。広島県公衆衛生課長,静岡県衛生部長,厚生省精神保健課長,厚生科学課長,健康局長などを経て,2001年より医政局長。新医師臨床研修制度の創設に尽力する。2003年より現職。WHO執行理事。 |
 |
