MEDICAL LIBRARY 書評特集


荒木 重雄,福田 貴美子 編
体外受精コーディネーターワーキンググループ 協力
《評 者》玉田 太朗(日本女性心身医学会理事長/日本不妊学会名誉会員/自治医大名誉教授)
新知見を盛り込み本邦ARTの方向を示す
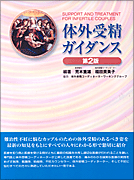 本書の生い立ち
本書の生い立ち
編著者のひとり,荒木重雄博士は,1966年札幌医科大学卒業後,同大学,群馬大学,コロンビア大学,自治医科大学を通じて,20年余,生殖内分泌学の基礎的な研究に没頭してこられた。特に,ヒト卵巣内の卵胞発育・排卵の形態学的および内分泌学的研究に長年携わり,ヒトの単一排卵機序,ヒト排卵前後におけるGnRHの動態・意義などについて,国際的にも注目される多数の論文を発表された。
博士が体外受精に着手されたのは,1990年頃からかと記憶するが,ARTに必要な知識・技術はまさにそれまでの研究の延長線上のものであったので,それをたちまち自家薬籠中のものとされたのである。
1996年,当時自治医科大学病院の生殖内分泌不妊センター長であり,また自治医科大学看護短期大学教授を併任されていた博士は,医学書院から初版『不妊治療ガイダンス』を出版された。これが好評を博し3年足らずで3刷を重ねた。この間,ARTの普及により,わが国で不妊治療を受け妊娠した方の4分の1がARTによるまでに至った。そこで同書の第3版の改訂に当たって,第2版までの書名を継承した『不妊治療ガイダンス』とは別に,2002年,新たな『体外受精ガイダンス』を発表された。これも好評を博し,2005年夏には医学書院から増刷を勧められたが,この領域の進歩は特に急速であり,新知見を加えた改訂版が必要と考えられ,2003年以後の新しい文献を加えて今回の改訂版が上梓された次第である。
新しいエビデンスが網羅されている
このような意図で企画された本書に,2003年以後の新知見が加えられているのは当然であるが,それが各章の終わりに2頁から数頁というコンパクトな形の「最新情報Q&A」としてまとめられている。概観したところ,2003年以後2006年までの文献はほぼ100編に達する。ARTの経験を積んでいる臨床家は11ある章の章末に付加されたこのセクションを覗くだけで,毎日のプラクティスの改良に役立つ情報を得ることができるだろう。最後の12番目のQ&Aは,「ARTにおける法規制とガイドラインに関する最新情報Q&A」として,諸外国の規制と,国外の学会のガイドラインが解説されている。ARTは,それ自体が「最新技術と倫理の相克」の問題をはらんでおり,今後のわが国の方向を考えるうえで参考になる。
一方,初心者は,従来の記載から卵・精子の成熟,排卵・受精・着床の生理および病理を基礎から理解できるようになっている。
ARTにナラティブ(人生の物語)は欠かせない
不妊自体は,ある女性にとっては病的な状態でもなければ,心の負担でもない。一方,正常な妊娠,出産,育児でも母性と家族にとっては,身体的,心理的,社会的に大きな喜びであるとともに,不安や負担となる。まして,身体的,心理的,経済的,時間的に負担が大きいARTには,悩み出すと際限がないほどの多くの問題がある。
本書では,教育を受けた熟練したコーディネーターとクライエントとの会話や本音がちりばめられている。このような立派なコーディネーターに会えるクライエントは幸せである。このような人たちがARTの現場で広く活躍できるようなシステムがわが国で1日でも早く整備されることを切望するものである。
最新の科学的なエビデンスとクライエントに対する具体的な接し方について,高いレベルで,しかもわかりやすく解説されている本書が,わが国のARTのレベルアップにつながることを信じ推薦するものである。


聖路加国際病院呼吸療法チーム 執筆
蝶名林 直彦 編集
《評 者》宮城 征四郎(群星沖縄研修センター長)
NPPVに携わるすべての医療従事者の必読書
 聖路加国際病院呼吸療法チームによるNPPV(非侵襲的人工呼吸管理)ハンドブックがついに日の目を見た。本書の編集は,私が日ごろから親しくお付き合いをさせていただいている蝶名林先生である。その内容が内容だけに,彼によれば企画から本の完成までに3年もの年月を要したという。しかし,この本をくまなく読んでみると,それは当然だということがよくわかる。
聖路加国際病院呼吸療法チームによるNPPV(非侵襲的人工呼吸管理)ハンドブックがついに日の目を見た。本書の編集は,私が日ごろから親しくお付き合いをさせていただいている蝶名林先生である。その内容が内容だけに,彼によれば企画から本の完成までに3年もの年月を要したという。しかし,この本をくまなく読んでみると,それは当然だということがよくわかる。
この方法が日本に導入されたのは,ほんの15年ほど前のことであり,従来の侵襲的人工呼吸管理そのものを根本的に見直す機会を与えた人工呼吸管理法だからである。
鉄の肺に始まり,閉鎖回路による陽圧人工呼吸管理に終始していた1980年代後半までの人工呼吸管理法に,決定的な改革をもたらしたのはこの方法によるものであった。それだけに,この療法に関する教則本の数は日本の医療界を席巻するほどあまたある。
しかし,この本の特徴はまずすべてが箇条書きに統一されているので,読者にとって大変に読みやすいことである。NPPVを導入しているこの聖路加国際病院独特の図がいたるところにちりばめられていて,きわめてその内容も具体的である。
従来の人工呼吸管理法と違って,本法は一部の医療者によって独占される類のものでは決してない。その証拠に,呼吸不全を起こしている病態に導入されている場所が救急室,集中治療室,一般病棟,小児病棟,外来,自宅など多岐である。それだけに,本法に携わっている医療者は麻酔医,呼吸器科医,小児科医,臨床工学技士,看護師,看護ステーションケアマネジャーその他であり,これらの人々によるバランスのとれたチーム医療である。それぞれの立場から,これだけの人々に意見を募るだけでも容易ではない。編集者が最も苦労されたであろう理由はここにある。
本法を導入するにあたっては,これらの医療人それぞれがこの方法に習熟していなければならない。決して一部の人々の特権的医療行為ではないのである。NPPVは現在,急性や慢性を問わず,呼吸不全のあらゆる分野で導入が試みられている。そして大事なことは,従来の閉鎖式人工呼吸管理法の適応条件その他が根本的に修正を余儀なくされたことである。
従来の方法に比して,何よりも廉価である。呼吸不全を伴うあらゆる病態に,禁忌条項さえなければ,まず本法を導入し,どうしてもそれが駄目なら従来の人工呼吸管理法を導入するというのが一般的である。循環器を専門としてきた医療人も,この方法を通じて呼吸器,麻酔との接点を求めているし,従来にはなかった早目の導入,すなわち「予防的導入」や「早期抜管」,術後管理などが容易となった。
本書は10章から構成されているが,どの章を読んでも余すところなく,それぞれの専門的立場から書かれており,有意義である。スタッフの時間的・物理的制約の多さ,導入の困難さ,知識や技術の必要性,適応病態,合併症その他が惜しみなく書かれているが,なお,各病院でこぞって導入すべき方法であり,また,本書はその点でも圧巻である。この分野に携わるすべての医療人に一読をお願いしたい良書である。


夏目 長門 編
《評 者》加藤 正子(愛知淑徳大教授・言語聴覚学)
豊富な図とわかりやすい解説 臨床現場の言語聴覚士にも
 言語聴覚士は,正常なコミュニケーション過程を基にして,コミュニケーションの障害に関連する問題を明らかにするために検査や評価を行い,必要な場合は訓練,指導,助言によってコミュニケーションに困難を示している人とその家族の言語生活を支援することを専門に行う臨床家である。人間の高次機能である言語の性質から,対象は,言語発達に問題があり教育的配慮も必要な子どもから,高次脳機能障害をもつ成人まで多岐にわたっている。したがって,言語聴覚士に必要とされる知識は言語学・音声学・音韻論・音響学などの言語学領域のほかに,心理学や教育学,社会学の領域が医学領域と同様に大きな部分を占めていることが他の医療分野にはみられない特徴である。
言語聴覚士は,正常なコミュニケーション過程を基にして,コミュニケーションの障害に関連する問題を明らかにするために検査や評価を行い,必要な場合は訓練,指導,助言によってコミュニケーションに困難を示している人とその家族の言語生活を支援することを専門に行う臨床家である。人間の高次機能である言語の性質から,対象は,言語発達に問題があり教育的配慮も必要な子どもから,高次脳機能障害をもつ成人まで多岐にわたっている。したがって,言語聴覚士に必要とされる知識は言語学・音声学・音韻論・音響学などの言語学領域のほかに,心理学や教育学,社会学の領域が医学領域と同様に大きな部分を占めていることが他の医療分野にはみられない特徴である。
言語聴覚士の国家試験は今年で8回目を迎えたが,評者は現任者のために最も易しい問題が出題された第1回目の国家試験を受験した。言語聴覚士としての資格や専門の養成課程がなかった時代は,評者を含め,心理学や教育学,言語学などを大学で学んだ者(いわゆる文系出身者)が医療現場で言語治療士として多数働いていた。したがって,国家試験の受験勉強でいちばん苦労したのは基礎医学,臨床歯科学,臨床医科学などの膨大な医学・歯学系の科目であった。本書のようなテキストがあの当時にあったら,どんなに受験が楽であったかと考えると感慨深いものがある。
本書の特徴は,「言語聴覚士のための基礎知識」と銘打ってあるとおり,本の構成が細目に至るまで言語聴覚士の国家試験出題基準に完全に対応した構成となっている点である。すなわち,I章の臨床歯科医学には,歯・歯周組織,口腔ケアについて,II章の口腔外科学には,口腔・顎・顔面,顎関節,唾液腺,言語障害と関係ある疾患,言語・咀嚼・摂食障害に対しての歯科医学的治療法,歯・口腔・顎・顔面の炎症,腫瘍,囊胞,外傷と治療後の欠損,中枢疾患における口腔機能障害,加齢による口腔機能障害という言語聴覚士にとって必要な項目が,発生,構造,機能(咀嚼・構音),疾患・治療に分類され,豊富な図とともにコンパクトにわかりやすくまとめられている。特筆すべきは,歯科医学に関連する400語以上の専門用語を解説した章が独立して設けられていることである。この章は,学生のみならず臨床現場にいる言語聴覚士にとっても非常に有益なものである。
本書は,言語聴覚士の国家試験委員や出題基準検討委員を当初から担当しており,言語聴覚士に必要な歯科医学・口腔外科学の知識を熟知している夏目氏により編集され,口腔外科学領域で著名な専門家たちによって現在知っておくべき標準的な基礎的内容が書かれている。今後,改訂の際には,言語聴覚士と最も関係のある口蓋裂と類似疾患の言語症状についてのより深い記載と,いくつかの項にわたっている類似疾患を参照できるインデックスを付けるといったことを検討していただけると,さらにありがたいテキストとなるのではないか。


齋藤 滋 監修
村上 敬,原田 和美 編集
《評 者》一色 高明(帝京大教授・内科学)
コメディカルスタッフ PCIに携わる医師の傍らに
 コメディカルスタッフの活動は近年非常に活発である。この潮流は経皮的冠インターベンション(PCI)の分野が引っ張ってきたものであり,PCI関連の学会やライブデモンストレーションではコメディカル関連のセッションが大きな会場を満杯にして運営され,PCIに関するさまざまな問題点に焦点を当てて,主として実務的な側面から積極的な討論がなされている。PCIは看護師,放射線技師,臨床工学士と医師の手によるチーム医療であることを考慮すると,この流れは非常に重要かつ有意義なことである。
コメディカルスタッフの活動は近年非常に活発である。この潮流は経皮的冠インターベンション(PCI)の分野が引っ張ってきたものであり,PCI関連の学会やライブデモンストレーションではコメディカル関連のセッションが大きな会場を満杯にして運営され,PCIに関するさまざまな問題点に焦点を当てて,主として実務的な側面から積極的な討論がなされている。PCIは看護師,放射線技師,臨床工学士と医師の手によるチーム医療であることを考慮すると,この流れは非常に重要かつ有意義なことである。
PCIを行ううえでの患者管理の注意点は多岐にわたる。PCIの周術期すなわち術前,術中,術後のそれぞれにおいて,(1)患者の状態,(2)PCIの内容やアプローチ部位,(3)合併症の有無,などのすべてを把握しておくことが必須であり,これらについてそれぞれの立場での役割分担が十分になされていることが重要である。これらのことはまさに「言うは易く行うは難し」であり,その重要性を頭では理解していても,個人レベルでの過去の経験や,その施設で引き継がれてきた慣習に引きずられやすい。施設によっては異なった職種間での意思の疎通が十分に行われていない(行えない?)こともあるように思われる。
さて,市井にはPCIに関連する書物が少なからず存在しているが,その大半は医師向けのものであり,コメディカルスタッフを対象にしたレベルの高い専門書は非常に少ない。今般,医学書院より出版された『PCIスタッフマニュアル 第2版』は湘南鎌倉総合病院循環器科の齋藤滋部長の監修によるもので,コメディカルスタッフを対象にした実践的なマニュアルである。本書は初版本が出てから5年が経過したため新しいデバイスや技術の進歩を考慮してこの度大きく改訂された。本書を拝見して,齋藤滋部長の先見の明のすばらしさにあらためて感服した。5年前にすでに今日のコメディカルスタッフの熱意の高まりを予想していたかのような企画である。内容は充実しており,実践経験豊かな看護師,放射線技師,臨床工学士が,それぞれの立場からPCIに関わる部署別の重要なポイントを記述している。また,それぞれの分野が縦糸と横糸で結ばれるように構成が工夫されており,PCIの時系列での注意点から,全体を俯瞰したクリティカルパスに至るまで抜かりなく収められている。
本書はこれからPCIに関わるコメディカルスタッフの初心者にとっては勿論のこと,各部門で後輩の教育に当たる立場の職員にとって,そしてまた,コメディカルスタッフとともにPCIにあたる医師にとって,ぜひとも身の回りに置いておきたい1冊である。


インフォームド・コンセント
その理論と書式実例[ハイブリッドCD-ROM付]
前田 正一 編
《評 者》高原 亮治(上智大教授・総合人間科学部)
良好な医療者・患者関係の構築に役立つ本
 医療は目覚ましく発展し,以前では当然死亡したような患者さえも救命できるようになりました。しかしながら,同じ技術を同じ医師が適用する場合であっても,治療成績は必ずしも一定せず,個体や病態の差または偶然の変動としかいいようのない事態もみられます。
医療は目覚ましく発展し,以前では当然死亡したような患者さえも救命できるようになりました。しかしながら,同じ技術を同じ医師が適用する場合であっても,治療成績は必ずしも一定せず,個体や病態の差または偶然の変動としかいいようのない事態もみられます。
これらの要素により,時には死亡事故も発生することがあります。医療については,患者と提供者のと間に“情報の非対称性”が存在するという状況や,“不確実性”といった特質があることが指摘されており,本書のテーマであるインフォームド・コンセントは,医療倫理で通念となっている患者の自己決定権を保障するツールとして,不可欠の存在となりつつあります。また悲しいことに医療の高度化・複雑化についてまわる有害事象への対処としても,重要性が高まっていると言えます。
インフォームド・コンセントは,近年,医療事故裁判のなかでもしばしば問題にされているようです。有害事象が生じた場合,患者あるいは家族は,そのリスクについてあらかじめ説明を受けていなければ,その結果に納得できないかもしれません。
本書によると,説明すべき事項として,裁判所は一般に,(1)患者の病名・病態,(2)実施予定の医療の内容・性格,(3)その医療の目的・必要性・有効性,(4)その医療に伴う危険性とその発生率,(5)代替可能な医療とそれに伴う危険性およびその発生率,(6)何も医療を施さなかった場合に考えられる結果――を挙げるということです。
こうした裁判所の判断は個別の具体的状況のもとで下されたものであり,医学的にも必ずしも明確に答えられるものばかりではないでしょう。その判示内容を,どの程度,医療を行う際に考慮すべきか,またそもそも考慮する余裕があるか難しいところです。また,行う説明をどのように文書にするべきかという問題も難しいものがあります。本書で示されているように,患者が意思決定するうえで重要な事項については,文書によりわかりやすく説明がなされると,患者は受ける医療について理解を深めることができ,医療により主体的に協力できます。必ずしも期待どおりの結果が得られない場合でも,説明をめぐって「言った」「言っていない」といった不毛な紛争を回避することができ,仮に説明をめぐって紛争が発生した場合でも,医療従事者は説明した内容を本文書により証明することができます。このように,説明文書は,患者にとっても医療従事者にとっても重要な意味があることがわかります。
しかし,説明やその文書のあり方については,これまで十分な議論がなされませんでした。このため,一方では粗雑な説明および説明文書が維持され,またその一方では,編者がいみじくも問題にするような生命保険の約款のような文書までが作成される可能性がでてきました。このような状況の中で,本書は,インフォームド・コンセントに関する基礎理念の解説を行い,説明とその文書のあり方について指針を示したうえで,第一線の実務家が作成した説明文書の具体的事例を提供しています。つまり,本書は,まさにわが国の医療界が待ち望んでいた一冊と言えます。
現在の医療現場の状況を考えれば,本書で示されている文書を,今すぐにすべての医療機関で実践するのは難しいかもしれません。国際的にみてもこの説明レベルはきわめて高いものだと思います。しかし,仮に難しいとしても,本書を読み解き,参考にすることは可能です。インフォームド・コンセントの問題の本質を理解するうえでも本書は貴重な一冊といえます。この意味で,特に研修医・中堅医師にはぜひ本書を手にとっていただき,より良好な医療従事者・患者関係の構築に役立てていただきたいと考えています。
B5・頁292 定価4,830円(税5%込)医学書院
