「脳の中の身体」にアプローチ
第7回日本認知運動療法研究会開催
さる7月15-16日,森岡周会長(畿央大)のもと,福岡国際会議場(福岡県)において,第7回日本認知運動療法研究会が開催された。「脳は空より広い――認知神経リハビリテーションの彼方へ」をテーマに開催された今学会には600人を超える参加者が集まった。一般演題76題,分科会における12の症例発表など,認知運動療法の基礎となる神経科学領域から臨床実践に至る幅広い発表が行われたほか,芸術によってセラピストの「感性」を喚起することを意図した映像と音楽による「認知の樹」プロジェクトなど,多彩なプログラムが組まれた。
リハビリテーションの新たな動き
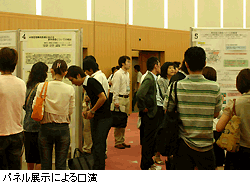 認知運動療法はイタリアのリハビリテーション医,カルロ・ペルフェッティによって提唱された治療体系であり,「運動機能回復は筋力増強や反射の促通や抑制といった治療的介入ではなく,学習の基盤である認知過程への治療的介入によって達成される」と定義づけられている。従来のリハビリテーションの枠組みに改編を迫る理論として,若手理学療法士を中心に近年,急速に注目が高まっている。
認知運動療法はイタリアのリハビリテーション医,カルロ・ペルフェッティによって提唱された治療体系であり,「運動機能回復は筋力増強や反射の促通や抑制といった治療的介入ではなく,学習の基盤である認知過程への治療的介入によって達成される」と定義づけられている。従来のリハビリテーションの枠組みに改編を迫る理論として,若手理学療法士を中心に近年,急速に注目が高まっている。
行為のシミュレーションが重要
分科会では,3つの会場でそれぞれ4人の演者が,自施設でのリハビリテーションにおける認知運動療法の実践を報告した。片岡保憲氏(愛宕病院)は,「行為のシミュレーション」をキーワードに,70歳代男性の立ち上がりリハビリテーションのもようを,ビデオを用いながら解説した。左上下肢の随意性は比較的保たれていたものの,感覚・注意障害が重く,立ち上がり・歩行の随意性が回復していなかった患者に対し,片岡氏は,「立ち上がり」行為にまつわる認知を言語化させるよう促す。これは,自己の行為についての内部観察,さらにはこれから行う行為をイマジネーションすることを重視する,認知運動療法の考え方にのっとったアプローチである。
片岡氏はリハビリテーション開始当初,「手に力を入れれば立ち上がれる」と述べていた患者が,数か月後の訓練では,「(麻痺足の)左足の裏に,ちょっと多めに体重をかけるようにして,次にふとももの裏に力を入れる」といった,行為の再構築を伺わせる発言を口にした様子を紹介。「単なる行為達成ではなく,患者本人の中に,行為のシミュレーションが再構築されてきた様子に注目してほしい」と述べた。
これに対して,フロアからは「このレベルの麻痺で,立ち上がり・歩行の回復に4か月もかかるのは非効率的ではないか」という疑問も投げかけられたが,片岡氏は「“回復”とは何か,ということを今一度問い直す必要がある。行為のイメージが回復しないまま,結果として歩行ができている,という従来型の“回復”では,患者は満足していない」と反論。患者が自己の行為を的確にシミュレーションできるようになることの重要性を強調した。
脳科学の最新知見を紹介
 認知運動療法では,身体動作の認知,つまりは「脳の中の身体」を治療対象としている。いまだその端緒についたばかりといってよい脳科学の知見はもちろん,心,身体にまつわるあらゆる知見が,この領域には関係しているといえる。こういった観点から,ミラーニューロン研究の日本における第一人者である村田哲氏(近畿大)が教育講演に,脳科学研究者の茂木健一郎氏(ソニーコンピュータサイエンス研究所)が特別講演に登壇するなど,最新の「脳と心」にまつわる研究成果が披露された。
認知運動療法では,身体動作の認知,つまりは「脳の中の身体」を治療対象としている。いまだその端緒についたばかりといってよい脳科学の知見はもちろん,心,身体にまつわるあらゆる知見が,この領域には関係しているといえる。こういった観点から,ミラーニューロン研究の日本における第一人者である村田哲氏(近畿大)が教育講演に,脳科学研究者の茂木健一郎氏(ソニーコンピュータサイエンス研究所)が特別講演に登壇するなど,最新の「脳と心」にまつわる研究成果が披露された。
村田氏は,近年話題となったミラーニューロンシステム(以下,MNS)について概観を紹介したうえで,MNSと運動制御システムとのかかわりについて自説を述べた。MNSの考え方では,自己の運動と,他者の運動とが同じニューロン上に表現され,マッチングされているとされる。マカクザルで最初に発見され,同様のシステムが人間にも存在するとして,コミュニケーションや共感,言語などに結びつく脳機能の1つとして注目を集めている。
村田氏は,このMNSが,他者との関係だけではなく,自己の運動制御においても大きな役割を担っているのではないかと考えていると述べ,視覚と体性感覚の一致・不一致に関する最新の研究成果を紹介した。
偶有性がカギ?
茂木氏は自身の研究分野である「脳とクオリア」研究の現状について,中世ヨーロッパにおける「錬金術」になぞらえて解説。「錬金術では,“金ができるかもしれない”という仮定に基づいて,ありとあらゆることをやりました。結局,その仮定は誤っていたのですが,その過程では多くの発見がありました」と述べ,脳科学の現状がいかに手探り状態であるかということを強調した。 そのうえで茂木氏は,「だから今,僕らにできることは“この方向に沿って調べていけばいいんじゃないか”という大きな枠組みを作ることだと思っています。それが仮に正しかったとしても,その研究が完成するにはおそらく100年単位の時間がかかる。それくらいの構えで取り組まなくてはいけない」と述べ,同じく,脳の神秘性へのチャレンジである認知運動療法に取り組む参加者に向け,エールを送った。
そのうえで茂木氏は,「だから今,僕らにできることは“この方向に沿って調べていけばいいんじゃないか”という大きな枠組みを作ることだと思っています。それが仮に正しかったとしても,その研究が完成するにはおそらく100年単位の時間がかかる。それくらいの構えで取り組まなくてはいけない」と述べ,同じく,脳の神秘性へのチャレンジである認知運動療法に取り組む参加者に向け,エールを送った。
茂木氏の講演の話題は多岐にわたったが,特に「半ば規則的に,半ば不規則に生じる」偶有性(contingency)が人間の認知機能において大きな役割を果たしているという話題に関心を寄せる参加者が多く,終了後も多くの質問が投げかけられた。
人間の認知機能には,多くの場面で偶有性が見られる。例えば近年,人間の記憶は,ずっと変わらない形でストックされているのではなく,常に編集が加えられているということが明らかになってきたが,その編集方針には一貫したガイドラインは存在しない。茂木氏は「記憶編集の際に偶有性を受け入れられるということが,人間の脳が持つ大きな可能性を構成している」と指摘。また,ドーパミン分泌の条件にも強い偶有性が見られたという実験結果を紹介したうえで,「人間のシステムには,世界の不確定性に対応できるように偶有性が組み込まれている」と述べ,偶有性を取り入れたリハビリテーションの可能性にも言及した。
