MEDICAL LIBRARY 書評特集


佐々木 克典 著
《評 者》岡村 均(神戸大教授・分子脳科学)
新しい時代の医学生・医師・教師のための解剖学書
 本書は,日本で初めての,臨床の役に立つ本格的な「局所解剖学」の書である。臨床外科医の経験を持たれる解剖学者の著者が,臨床に役に立つ解剖学実習とは何かという疑問に正面から取り組まれた,実にオリジナルな書であり,目から鱗が落ちる記述が満載され,解剖学を学ぶ学生や教師にとっても,外科臨床に携わる医師にとっても非常に有用な本であると言える。私は,解剖学教育に長らく携わってきた者として,これから医師になるために人体解剖学実習を行っている多くの医学生に,特にこの本を推薦したい。
本書は,日本で初めての,臨床の役に立つ本格的な「局所解剖学」の書である。臨床外科医の経験を持たれる解剖学者の著者が,臨床に役に立つ解剖学実習とは何かという疑問に正面から取り組まれた,実にオリジナルな書であり,目から鱗が落ちる記述が満載され,解剖学を学ぶ学生や教師にとっても,外科臨床に携わる医師にとっても非常に有用な本であると言える。私は,解剖学教育に長らく携わってきた者として,これから医師になるために人体解剖学実習を行っている多くの医学生に,特にこの本を推薦したい。
いったい解剖学とはどんな学問であり,解剖学実習とは何を目的にするのであろうか? 解剖学は体の形態と構造から生体の秘密を探ろうとする学問である。その手法は,見えるものすべてに名前をつけ,形を認知することから始まる。構造を明らかにするために,解剖学〔anatomia(anaすっかり,tomia切る)〕の名のごとく,外部のみではなく,内部を切り分けて研究し,名前をつける。医学部で行われる人体解剖学実習の目的は,言うまでもなく医学の基礎知識としての解剖学の習得であるが,実は,日本においては,先に述べた解剖学の本来の学問の意味の追体験として行われている。これは,何が医学的に重要かの知識を持ち合わせていない学生に対し,最初に行われる体系的な専門教育としてやむを得ない措置であるが,医学生にすれば,名前を覚えることはむやみに漢字や英単語を覚えることのように無味乾燥なものとなり,その学習意欲が削がれることが往々にある。
解剖学は名前をつけるだけの,死んだ時代遅れの学問なのであろうか?歴史を紐解くと,人体解剖学は,近代の人間精神の確立に最も貢献があった輝かしい学問であることがわかる。「ヒトが筋肉,骨,内臓,神経からできている」という解剖学の発見は,ルネサンスにおける最大の成果の1つであり,中世の信仰から人間を解放するという社会や人間精神に及ぼしたインパクトは,現在の分子生物学の比ではなく,はるかに大きい。しかし,16世紀に人体解剖学が確立してからすでに400年以上にもなり,人体理解のための基礎学問としての重要性は失われてはいないものの,如何せん時代の流れは大きい。19世紀以降,相次いで,生理学,微生物学,病理学,生化学が勃興し,20世紀後半には,生物を分子レベルで記載する分子生物学が爆発的に進展し,医学・生物学を塗り替えた。ここに至り,科学的思考は他の学問でも代替可能なものとなり,解剖学の存在意義を,より実用的なものに求めるようになったのは当然の推移であった。
これに対応し,米国では,臨床医学にとって必要な,「実用的な解剖学」が比較的早く要求されるようになった。すなわち「臨床解剖学」の成立であり,臨床的に重要なことを理解するための基礎知識を得るために解剖学があるという認識である。この動きは数十年前からあったが,不思議なことに,日本では「臨床解剖学」として,本格的に解剖学を再構築する試みは一般化されず,解剖学教育に「臨床的に重要なもの」を取り入れ,その分,従来の教育を削るといういささか場当たり的とも言える対応で対処されてきた。
この解剖学書は,臨床医学を見据えた本邦初の本格的な局所解剖学書であり,このような日本の現状には大変有用な書である。本書では,臨床的(特に外科学)に重要な点は,非常に詳しく,細かい所見も載っている。多数の収録された図はほとんど著者のオリジナルで,的確に描出されており,読んでいるうちに読者をあたかも心臓の構造を手にとって見ているような気にさせる。また,著者は,「タイムクリップ」の欄を設け,ここで,解剖学の臓器に関する歴史や,その臓器に対する疾病の術式を考案した医師のエピソードを実に魅力的に記載している。その博覧強記には驚くべきものがあり,書物で名前を聞くだけの歴史的な人物に親近感を抱かせるもので,医学生にとっても興味深い。
著者の佐々木克典氏は,外科医としての豊富な臨床経験の後,解剖学に向かわれ,主体的に解剖学の授業・実習に取り組まれている。出来上がったものは,米国の臨床解剖学書とは一味違った,型破りの日本の解剖学書である。本書は人体解剖学を臨床の目から再構築しようとする意思に貫かれた解剖学書であり,人体解剖学実習の臨床的意義を知るには必読の書であるといえる。難解な内容がわかりやすく解説され,興味深い話題が豊富に盛り込まれているので,人体解剖学実習を行っている医学部生だけでなく,解剖学教官が医学部その他の教育の場で人体解剖学の講義をする際に,学生に何が重要なのかを知らせるためにも,大いに役立つと思われる。もちろん,解剖学を再び学習したい外科医の要求に応える内容であることは言うまでもない。


抗精神病薬の「身体副作用」がわかる
The Third Disease
長嶺 敬彦 著
《評 者》中村 純(産業医大教授・精神医学)
精神科は「身体」に着目する時代に
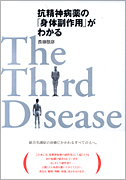 第2世代抗精神病薬のインパクト
第2世代抗精神病薬のインパクト
統合失調症に対する薬物療法が始まって50年余り経ったが,その発展は副作用克服の戦いの歴史ともいえる。
1996年にわが国にも第2世代抗精神病薬(非定型抗精神病薬)の導入がなされて,現在までに5剤(リスペリドン,オランザピン,クエチアピン,ペロスピロン,アリピプラゾール)の新しい抗精神病薬の使用が可能となった。
これらは錐体外路症状の出現が比較的少なく,陽性症状のみならず陰性症状にも効果を示す薬剤として注目を浴びている。しかも統合失調症の治療戦略として,治療初期からリハビリテーション期を見据えた生活指導と薬物療法の併用によって良好な予後を期待できるようになった。これらの新しい抗精神病薬は「患者中心の精神医療」へと医師や家族の意識を向けたのである。
新しい副作用=内科疾患への着目
従来からの抗精神病薬は,パーキンソン症候群,水中毒など抗ドーパミン作用と関連した副作用や,抗ヒスタミン作用による過鎮静,抗α作用による起立性低血圧などを起こしていたが,第2世代抗精神病薬の導入によってこれらの副作用発症は激減し,患者のQOLは改善され,服薬のコンプライアンスは上がり,再燃が減少するなどのよい循環もみられるようになった。
とはいえ,新しい抗精神病薬も万能ではない。人によっては,循環器系,呼吸器系,消化器系,特に内分泌系の副作用である肥満,糖尿病,メタボリック症候群など,最悪の場合には死に至る可能性を有する重症の内科疾患が発症することが指摘されている。精神科医は精神症状の変化だけでなく,以前に増して身体合併症へも関心を向けなければならなくなったのである。
精神科病棟をいちばん歩いている内科医
このような統合失調症に対する薬物療法の変革のなかで,精神科病院の患者と向き合い,精神科医,看護師などとの連携ができる内科医がいたらどんなにすばらしいことだろうか。
精神科病院に勤務されている内科医も多いが,私が知っている内科医のなかで最も統合失調症の患者さんを診て,精神科薬物療法に精通している内科医は本書の著者である長嶺敬彦先生ではないだろうか。
自称,「精神科病棟をいちばん歩いている内科医」である長嶺先生が実際に発見し,治療した抗精神病薬による副作用を呈した患者さんからの経験が,本書には豊富にまとめられている。したがって,第2世代抗精神病薬に関連した副作用だけでなく,従来からの抗精神病薬による副作用も含めて,実践的な対応が随所に書かれている。
医局に一冊あれば多くの副作用に対応できる
本書は,非常にわかりやすい。さらに内科医が書いた抗精神病薬を理解する本としてユニークである。糖尿病との比較など,内科医としての統合失調症に対する理解は,精神科医にとっても新鮮な意識を与えてくれ,興味深いものがある。
これからの精神科医は薬物療法の変化に加えて,内科や外科など精神科以外の場所でも統合失調症を診る機会も増えることが予想されるため,身体合併症に対する理解も必要である。
精神科病院の医局に本書があれば,抗精神病薬による副作用の多くは対処できるのではないかと思われ,ぜひご一読を薦める。


Neurological CPC
順天堂大学脳神経内科 臨床・病理カンファレンス[ハイブリッドCD-ROM付]
水野 美邦,森 秀生 編
《評 者》廣瀬 源二郎(浅ノ川総合病院脳神経センター常勤顧問)
最終診断に至るまでの科学的プロセスを学ぶ
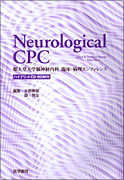 神経内科領域におけるすばらしい臨床・病理カンファレンス(CPC)の記録業績が,わが国で初めて出版された。CPCで長く続けて公に出版されているのは,New England Journal of Medicineに毎週掲載されるMGHでの症例記録(Case Records of the Massachusetts General Hospital)である。きわめてtimelyでレベルの高いディスカッションがされることから,最新情報を把握したい内科系臨床医にとり最も魅力的なCPC記録として知られるものである。30数年前ハーバード大留学中の私も最も楽しませてもらったカンファレンスである。要望が強いため,その中から神経疾患についてのCPCだけをまとめて過去に欧米で発刊されたこともある。この方式に倣い,順天堂大学脳神経内科の剖検症例で,過去100回以上開催された神経疾患患者CPCの内,97症例をCD-ROMのPDFファイルにまとめ,そのうち教室の伝統的業績を反映した症例で,編者が重要であると思われたパーキンソン病およびその類縁疾患を中心に30症例が選択されCD-ROM付き冊子体として発刊されたわけである。このCPCは『脳と神経』誌に1990年以来掲載されているとはいえ,冊子体として発刊されたものを通読すると,その臨床神経学の内容,材料に改めて感心するばかりである。教室員によるしっかりとした病歴聴取,詳細な神経学的所見把握をもとに,教室のteaching staffが主に討論者となり,論理的に考えを推し進め診断にいたるプロセスを呈示している。さらに森助教授が中心となり,その神経病理診断がなされており,HE染色のみでなくKB染色,Bodian染色,さらには種々の免疫染色を駆使して詳細に検討し,それらの所見を正確に記載し,どちらかといえばアメリカ流というよりはドイツ学派の考えを交えて解説している。
神経内科領域におけるすばらしい臨床・病理カンファレンス(CPC)の記録業績が,わが国で初めて出版された。CPCで長く続けて公に出版されているのは,New England Journal of Medicineに毎週掲載されるMGHでの症例記録(Case Records of the Massachusetts General Hospital)である。きわめてtimelyでレベルの高いディスカッションがされることから,最新情報を把握したい内科系臨床医にとり最も魅力的なCPC記録として知られるものである。30数年前ハーバード大留学中の私も最も楽しませてもらったカンファレンスである。要望が強いため,その中から神経疾患についてのCPCだけをまとめて過去に欧米で発刊されたこともある。この方式に倣い,順天堂大学脳神経内科の剖検症例で,過去100回以上開催された神経疾患患者CPCの内,97症例をCD-ROMのPDFファイルにまとめ,そのうち教室の伝統的業績を反映した症例で,編者が重要であると思われたパーキンソン病およびその類縁疾患を中心に30症例が選択されCD-ROM付き冊子体として発刊されたわけである。このCPCは『脳と神経』誌に1990年以来掲載されているとはいえ,冊子体として発刊されたものを通読すると,その臨床神経学の内容,材料に改めて感心するばかりである。教室員によるしっかりとした病歴聴取,詳細な神経学的所見把握をもとに,教室のteaching staffが主に討論者となり,論理的に考えを推し進め診断にいたるプロセスを呈示している。さらに森助教授が中心となり,その神経病理診断がなされており,HE染色のみでなくKB染色,Bodian染色,さらには種々の免疫染色を駆使して詳細に検討し,それらの所見を正確に記載し,どちらかといえばアメリカ流というよりはドイツ学派の考えを交えて解説している。
臨床神経学とは,患者の病歴にはじまり,診察で神経学的所見をとり,この両者をまとめて病変が神経系のどこにあり,如何なる病因・疾患かの鑑別をあげて最終診断を下す科学的プロセスの遂行である。最近の神経科学領域の進歩は実にめざましく,とくに分子生物学的・遺伝学的なアプローチおよび進歩した画像診断を駆使した病因・病態の把握,診断には目をみはるものがある。最先端の新しい事実を求めて進んでいくことは神経学研究のさらなる進展には不可欠であろう。しかしながら得られた新知識が何のために患者に用いられるかを考えなかったら臨床医学は発展しない。臨床をないがしろにした最先端の神経学的業績のみでは,神経疾患・神経難病を患う人は決して救われない。神経学の行く先こそは,最新の分子生物学的手法を利用して得た知識を,患者の神経症候学を基盤に昔ながらの正しい臨床神経学にのっとり診断,治療する際に用いていくことにある。この流れに沿った本書の発刊は時宜を得ており,「神経学よ!何処へ?」との多くの神経内科医の懸念を吹き飛ばし,今後の神経学の進むべき道として改めて臨床神経学の基本・本流に戻ることを教えてくれるものである。臨床に携わる神経内科医,これから神経内科専門医をめざす若い医師にはぜひ本書を読んでいただき,このレベルをわが国の臨床神経学のスタンダードとしていただくことを期待するものである。


岡﨑 勲,豊嶋 英明,小林 廉毅 編
《評 者》能勢 隆之(鳥取大学長)
医療従事者の必須知識を明瞭簡潔に解説
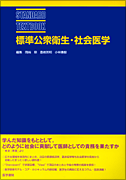 今度,医学書院より『標準公衆衛生・社会医学』(編集:岡﨑勲,豊嶋英明,小林廉毅)が発行されました。
今度,医学書院より『標準公衆衛生・社会医学』(編集:岡﨑勲,豊嶋英明,小林廉毅)が発行されました。
今日ほど,保健・医療・福祉等の分野の内容が医学教育とくに,医学教育モデル・コア・カリキュラムのなかで多くとり入れられ,重要視されたことはありません。そのため,医学生や医療従事者にわかりやすく,かつ適切に教授するための教科書が必要となっています。
公衆衛生の分野は,大変幅広く奥が深いので,テキストにすると項目が多岐にわたり,大変厚い本となってしまいます。
しかし,本書はまず,公衆衛生分野の今日的な課題について,国家試験などの資格試験に最近よく出題される部分に集約されて編集されています。また,序章をもうけて,公衆衛生・社会医学のかかえる新しい課題を解説することによって,あらかじめ本テキストの総論的なコンセプトを理解できるようにしているので,教授する側にも都合がよい編集になっています。また,各章の解説内容もそれぞれの専門分野の先生が担当されていますが,テキストとしては専門的な詳しい内容よりも一般の学生が医療従事者として知っておくべき必要最小限の内容について明瞭簡潔に解説されています。また,公衆衛生・社会医学の分野も最近では健康増進に関することのみならず,生活習慣病の具体的予防方法や臨床的な内容を含んだ地域医療,介護保険等の内容も関連するようになりましたが,本書ではわかりやすく説明されています。
あらゆる医療従事者等の教育に十分適しており,また,医学生諸君が参考書として活用するのに適していると思いますので,本書を推薦いたします。


医療現場におけるパーソナリティ障害
患者と医療スタッフのよりよい関係をめざして
林 直樹,西村 隆夫 編
《評 者》有賀 徹(昭和大病院救命救急センター長)
パーソナリティー障害を知る最良の書
 この度,『医療現場におけるパーソナリティ障害 患者と医療スタッフのよりよい関係をめざして』が上梓された。救急医療に携わったことのある読者であれば,よく理解されていることと思うが,救急医療において精神医学的な支援を要する局面は多々あって,身体的な治療が一段落するや,しばしば精神科医にコンサルテーションをあおぐ。そのような中で,“パーソナリティ障害”を指摘される事例もまた少なからず経験される。そこでは,“パーソナリティ障害は病気なのか,病気でないのか”について質疑をしたり,一般的な精神病に比して“パーソナリティ障害は10倍も苦労が多い”などと聞いたりするものの,結局のところ,精神医学に疎いわれわれ一般医にとって“パーソナリティ障害”を理解することはやさしいものでは到底なかった。これがわれわれ一般医の本音である。
この度,『医療現場におけるパーソナリティ障害 患者と医療スタッフのよりよい関係をめざして』が上梓された。救急医療に携わったことのある読者であれば,よく理解されていることと思うが,救急医療において精神医学的な支援を要する局面は多々あって,身体的な治療が一段落するや,しばしば精神科医にコンサルテーションをあおぐ。そのような中で,“パーソナリティ障害”を指摘される事例もまた少なからず経験される。そこでは,“パーソナリティ障害は病気なのか,病気でないのか”について質疑をしたり,一般的な精神病に比して“パーソナリティ障害は10倍も苦労が多い”などと聞いたりするものの,結局のところ,精神医学に疎いわれわれ一般医にとって“パーソナリティ障害”を理解することはやさしいものでは到底なかった。これがわれわれ一般医の本音である。
本書の副題には「患者と医療スタッフのよりよい関係」が謳われているが,まずはわれわれが一定水準まで“パーソナリティ障害”を知ることがこのための大前提であろう。本書はその意味でわれわれ一般医にそれを叶えてくれる,言わば“傑出した”良書である。もちろん,本書は実際の精神科診療に関するカンファランスを契機にまとめられたもので,精神科医にとってもこの分野で十分に役立つ内容が含まれている。それらは,著者らが大変よく噛み砕いて,親切に説明していることで一見してよくわかる。精神医学の奥の深さや社会との繋がり等々,きわめて含蓄の豊かなことに驚く。
以上に加えて,本書においては,精神科医師,看護師,医療相談員,ケースワーカー等々,医療の最前線で苦闘する職員が困った問題に立ち至った際に,組織的な病院医療をいかに実践して彼らを守っていくかという医療安全の側面についても周到な言及がなされている。このようにして,本書が幅広い読者に高い満足度を与えることは間違いない。
A5・頁228 定価2,940円(税5%込)医学書院
