MEDICAL LIBRARY 書評特集


新井 達太 編
《評 者》幕内 晴朗(聖マリアンナ医大教授・心臓血管外科)
読者の考える力を涵養する教科書
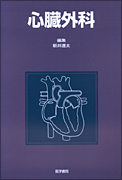 わが国でも心臓外科の教科書はいくつかあるが,手術手技に力点を置いた本格的な手術教科書は意外と少ない。この『心臓外科』には,各心疾患の診断,局所解剖,手術適応とタイミング,手術成績なども記載されているが,その中心をなすのは手術手技であり,これが本書を特徴づけている。編集は埼玉県立循環器・呼吸器病センター名誉総長の新井達太先生によるものである。現役時代に数多くの心臓手術を手掛けられた先生は,学会のシンポジウムの司会で外科医が聴きたい「手術のコツ」などについて演者に鋭く質問されていたことを,今でもよく憶えている。新井先生は以前に『心臓弁膜症の外科』という書を編集されているが,今回は先天性心疾患から冠動脈疾患を含めた後天性心疾患まですべて網羅しており,実際に読んでみると先生の本書にかけるこだわりが随所に認められる。
わが国でも心臓外科の教科書はいくつかあるが,手術手技に力点を置いた本格的な手術教科書は意外と少ない。この『心臓外科』には,各心疾患の診断,局所解剖,手術適応とタイミング,手術成績なども記載されているが,その中心をなすのは手術手技であり,これが本書を特徴づけている。編集は埼玉県立循環器・呼吸器病センター名誉総長の新井達太先生によるものである。現役時代に数多くの心臓手術を手掛けられた先生は,学会のシンポジウムの司会で外科医が聴きたい「手術のコツ」などについて演者に鋭く質問されていたことを,今でもよく憶えている。新井先生は以前に『心臓弁膜症の外科』という書を編集されているが,今回は先天性心疾患から冠動脈疾患を含めた後天性心疾患まですべて網羅しており,実際に読んでみると先生の本書にかけるこだわりが随所に認められる。
まず特筆すべきは,きわめてup-to-dateな内容が満載されている点である。このような大部の教科書では執筆開始から出版までに時間がかかり,市販された時点ですでに陳腐になっている場合が少なくないが,それを見事に克服している。
項目立ても通常と異なり,連合弁膜症などの合併手術,および同一疾患でも病態や使用材料に応じた術式について,さまざまな角度から取り上げている。またMy Techniqueという,2人の著者に同一疾患の手術法を執筆させるユニークな方法は,「手術のコツ」の微妙な違いを浮き彫りにし,最新の手術法に関する理解を深めるのにきわめて有用で,本書をマニュアル的な押し付けでない,読者の考える力を涵養する教科書にしている。このほか,Pitfall & One Point Adviceと称した囲み記事にも工夫のあとが感じられる。さらに最後の25章と26章では,遺伝子工学や細胞工学の心臓外科への応用という最先端の研究を掲載し,明日の心臓外科の指針となる重要な課題を教示している。
本書の執筆陣は新進気鋭からベテランまで幅広く構成されており,わが国を代表する心臓外科医がほとんど網羅されている。これだけ執筆者が多数にわたると,ともすれば内容がばらばらになりがちだが,非常によくまとまっているところに編者の多大な努力のあとがしのばれる。手術書の生命といえる図については,執筆者が精魂込めて作成したものが多数掲載されており,必要に応じてカラーとなっていて大変わかりやすい。術中写真も実に鮮明で,術式の理解に役立っている。ただあえて難を言えば,図のタッチに多少統一性を欠くことであるが,多数にわたる執筆者を考慮すれば致し方ないであろう。
心臓外科医は仕事に追われて常に忙しいが,本書は手術の概念がよく解説されているので,手術に入る前にぜひ一読することを推奨したい。そして手術法を十分に理解した上で,さらに自分がどのように工夫するか考えて手術に臨めば,必ずよい結果が得られるはずである。いずれにせよ,この手術書は将来心臓外科医を目指す修練医はもちろんのこと,ベテランの心臓血管外科専門医にとっても大変有用であり,常に手元に置いておくべき価値の高い書といえる。


相馬 孝博 監訳
《評 者》高久 史麿(自治医大学長)
医療事故の原因はシステムにある
 相馬孝博氏の監訳,池田真理,上條優子,斉藤安希3氏の訳による『患者安全のシステムを創る-米国JCAHO推奨のノウハウ』が医学書院から刊行された。JCAHO(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization)は,病院をはじめとするすべての医療関連施設を評価する米国の権威ある第三者機関である。そのJCAHOは最近,医療事故に特に注目し,医療事故を警鐘事象(essential event)として紹介,医療界に医療事故に関する警鐘を鳴らし続けてきた。これらの警鐘事象を丹念に調査分析し,その結果をまとめたのが本書である。
相馬孝博氏の監訳,池田真理,上條優子,斉藤安希3氏の訳による『患者安全のシステムを創る-米国JCAHO推奨のノウハウ』が医学書院から刊行された。JCAHO(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization)は,病院をはじめとするすべての医療関連施設を評価する米国の権威ある第三者機関である。そのJCAHOは最近,医療事故に特に注目し,医療事故を警鐘事象(essential event)として紹介,医療界に医療事故に関する警鐘を鳴らし続けてきた。これらの警鐘事象を丹念に調査分析し,その結果をまとめたのが本書である。
本書の内容は,医療事故の現状を述べた「Introduction」から始まり,引き続いて(1)今日の医療安全において求められる医師の役割,(2)手術や術後のエラーと合併症から患者を守る,(3)部位間違い/患者間違い/手技間違い手術から患者を守る,(4)誤薬事故から患者を守る,(5)治療の遅れによる悪い結果から患者を守る,(6)身体拘束による重篤な傷害や死亡から患者を守る,(7)自殺から患者を守る,の7つの章によって構成され,さらに付録として,「安全と医療:エラー削減のための基準」の項目が付け加えられている。各章では数多くのニアミス例,警鐘事象の例が具体的な症例提示の形で簡潔かつわかりやすく紹介されており,筆者はそれらの症例を読んでいるとその事故現場に居合わせているような感じさえ持った。本書の中で一貫して主張されていることは,「医療事故は個人の過失というよりも,システムのミスである」という点で,各警鐘事象の例を参照しながら,そのような事故がどのようなシステムのミスによって起こったか,そのようなミスを起こさないようにするためにはどのような具体的な戦略が必要かについて詳しく述べられている。また随時補足資料の形でそのまとめが行われていることも本書の特徴であるといえよう。
本書の中で強調されているもう1つのことは,医療安全への対策としての,病院管理者・医師のリーダーシップ,医療従事者の間のチームワーク・コミュニケーションの重要さである。また,管理者の責務として医療の現場に必要な数の医療従事者を配置することの重要さが繰り返し述べられている。わが国で医療安全の問題が取り上げられる場合,医療従事者の数や過労の問題が論じられることがほとんどない状況に対して筆者は以前から強い不満を持っていたが,本書ではその点が折に触れて述べられており,本書を通読してわが意を得たりという感じがしたことを付け加えたい。
本書を通読して,この本は医療従事者は言うにおよばず,患者さんや家族,医療の安全に関心のあるマスコミの方々,さらには医療に関心のある一般のすべての方々にぜひ読んでいただきたい本であるということを痛感している。


新井 信隆 著
《評 者》中野 今治(自治医大教授・神経内科学)
神経病理学を学ぶための道標となる好著
 見知らぬ街,新しい地を行く時に必要なのは地図である。ただし,この地図は闇雲にすべてを書き込み,詳しくさえあればよいというものではない。案内の地図には何を載せるかよりも何を載せないかが重要である。神経疾患症例の脳あるいはその標本を前にしたときに必要なのは指南書――いたずらに網羅的でなく,地図と同じく簡にして要を得た指南書である。
見知らぬ街,新しい地を行く時に必要なのは地図である。ただし,この地図は闇雲にすべてを書き込み,詳しくさえあればよいというものではない。案内の地図には何を載せるかよりも何を載せないかが重要である。神経疾患症例の脳あるいはその標本を前にしたときに必要なのは指南書――いたずらに網羅的でなく,地図と同じく簡にして要を得た指南書である。
書評子はかつて本書の著者と同じ研究所に在籍した関係で,著者の研究室の膨大な症例コレクションを承知している。本書の執筆に際し,その中からどれを捨てるかということが最も頭の痛い点であったとの著者のつぶやきを耳にしている。何を捨て何を載せるかが考え抜かれたのが本書と言える。
このフィロソフィーは,随所にちりばめられたシェーマにも貫かれている。ここでは,事象の複雑さを知り抜いた者のみがなし得る簡明さを読みとることができる。その例として図8-20「アストロサイト内の主な蓄積物」(79頁)を取り上げてみる。この図には,アストロサイトの蓄積物が6種類示されているが,特にわかりやすいのがともにリン酸化タウ蛋白が蓄積して形成される房状アストロサイト(tuft-shaped astrocytes)とアストロサイト斑(astrocytic plaques)の描写である。前者はリン酸化タウ蛋白が突起の基部に蓄積するために凝集して見え,後者はアストロサイトの胞体から離れた部位に蓄積するため粗に見えるということが,的確にされている。書評子はこのように考えたことはなく,この図と説明で蒙を啓かれた思いがする。本書は,神経病理学における知見を整理し,考え方を正しい方向に導く好著である。
それのみではない。本書は分子遺伝学,分子生物学の最新の知見を取り入れた新しい疾患分類を取る。その代表例はタウオパチー,α-シヌクレイノパチー,トリプレットリピート病の章である。疾患分類は,その時点での疾患の理解の深さを反映している。神経疾患を本書のような切り口でとらえてみると,複雑な疾患群の輪郭が鮮明に見えてくる。ただし,このような斬新な分類も現時点での知見という制約を受けていることは否めない。例えば,アルツハイマー病はタウオパチーでありながら,蓄積物質から言えばβアミロイドパチー(?)でもある。ただし,このことは著者もつとに承知済み(136頁メモ:神経変性疾患はオーバーラップ症候群)であり,本書の価値を些かも下げるものではない。
著者の研究室の染色技術は高度であり,本書の写真もすばらしい出来映えである。欲を言えば,もう少し大きな写真であってほしかった。そうすれば,書評子のような眼の悪くなった者にもより見やすかったと思われる。本書は,厚さも重さも手頃であり,タイトルの如くインデックスとして鞄に潜ませるのに適している。われわれの世代を含めて神経病理学を学ぶ者,さらには神経病理学的知識の習得を望む臨床家にとって必携の書と思われる。


今村 知明,康永 秀生,井出 博生 著
《評 者》開原 成允(国際医療福祉大教授/国際医療福祉大大学院長)
これまでの医療経営本と一線を画すユニークな本
 私はこの本を一読して興奮を禁じえなかった。医療の世界では,学問は現実の問題に対処できなければならないと考え続けてきたが,ここには生きた学問がある。
私はこの本を一読して興奮を禁じえなかった。医療の世界では,学問は現実の問題に対処できなければならないと考え続けてきたが,ここには生きた学問がある。
これまで多くの医療経営に関する本が書かれてきたが,この本はどの本とも違っている。共著ではあるが,章ごとに著者が分かれているようなものではなく1つの理論的体系を持ったまとまった本であり,医療機関の経営は,「営利が目的ではないが質を確保する財政基盤も確立する必要があるから従来の経営学とは異なった視点が必要である」という考え方がその基本にある。まだ名著というには早いかもしれないが,版を重ねれば歴史に残る名著の1つになるかもしれない。
本の構成も大変ユニークである。第一部「現代の医療システム」で日本と諸外国の医療を比較しつつ概観しているが,欧米諸国の医療システムを簡潔にまとめてあって役に立つ。第二部「病院管理」が,通常の意味での病院経営の部分であるが,ここの記述も独自の工夫があり,「基本戦略」,「財務・会計」,「運営」,「マーケティング」,「組織・人事」の5章を設け,最初に理論を記述して後に,今の病院の現実の問題を例として述べている。そもそも「戦略」が述べられていること自体がユニークであるが,戦略の部分には,土曜に開業をすべきか,自由診療をすべきかなどが戦略の問題として論じられているし,財務・会計の部分では,院外処方率などを論じ,病院運営では,クレジットカード決済の導入などを論じるなど,常に視点は現実の問題を離れていない。
第三部「医療安全と医療経営」では,病院にとって重要な医療安全が経営の立場からよく論議されている。訴訟の実態や医療事故の費用などが論じられているのも他にない特徴である。
第四部「日本の医療の論点」は,医薬品の価格,医療機器・材料の内外価格差,混合診療,株式会社による医療機関経営という最近議論のあった問題が公平な立場で解説してあり,これらの問題を理解するのにこれほど便利な本はない。
もちろん,もっと論じてほしかった問題も多く残されている。いくつか例を記せば,第一に,日本の公的病院と民間病院の置かれている経営状況の差を取りあげてほしかった。経営の立場から見れば,公的病院も民間病院も本来差はないはずであるが,初期投資と税負担の点で日本の現状には大きな不公平が存在し,それが双方の病院経営に大きな影を落としている。特に,この本には税制の問題がどこにも触れられていないが,税負担のあり方は経営の根幹にもかかわる重要な問題である。第二は,医師・看護師のリクルートや給与のあり方の問題にも触れてほしかった。極論すれば,医療機関の経営はよい医師や看護師の確保の問題であるといっても過言ではない。いかに立派な経営理念を持っていても,医師や看護師が確保できないために経営が破綻した病院は数限りなくある。その背景には,医局による医師支配という日本独特の制度があることも事実であり,この点もぜひ取り扱ってほしかった。
この本は現実の問題を扱っているだけに,今後の改訂が頻繁に必要になるとも考えられる。ぜひ出版社もこの点を理解して,著者に頻繁な改訂ができる環境を与えてほしい。
最後に多少私事を書かせていただくと,著者の一人である今村知明氏は,私が東大にいた頃,世界を放浪することの好きな誰にも好かれる活気のある大学院生であった。大学院修了後,厚生省(当時)に入り,医療行政の修羅場も経験した。最近東大病院の経営に携わる立場になったことは,まさに天が適材を適所に与えた感がある。また,この本もこうした経験を持つ今村氏だったから書くことができたのだと思う。私としては,今村氏が,このようなすばらしい本を仲間と共に書くようになったことを心から嬉しく思っている。


ラングマン人体発生学 第9版
安田 峯生 訳
《評 者》大谷 浩(島根大教授・発生生物学)
古典-最先端まで収載
スタンダード人体発生学書
 前第8版において,人体発生学,医科発生学の教科書として,既に世界的なスタンダードとしての評価を確立していた本書に,初めて分子発生生物学的な知見の紹介が加わった。多くの章に,発生の分子制御についての説明が意欲的に取り入れられた。これらの知見の多くは,ヒト以外の動物から得られたものであり,必ずしもただちにヒトに外挿できないが,純記載的で,発生現象の機構についてはほとんど触れないか,あっても推論の域を出ない記載に終始していたそれまでの人体発生学の古典的教科書に,時代に対応して分子レベルでの説明が加えられた。第9版においては,その後の分子発生生物学の進展に対応して,これらの分子制御に関する記載が新しくなり,かつより広範に取り入れられている。日進月歩のこの分野の最先端に教科書が即応するのはほとんど不可能であるが,前版に比べて医科発生学の教科書として,古典的記載と分子制御の解説がよりバランスよく配置され,より「なじんで」きた印象を受ける。そこには,訳者序文にあるように,現著者サドラー博士の意図をより正確に読者に伝えようと訳出された,安田先生のご努力が大きく働いている。ラングマンの優れた古典的な著述に加えて,現著者と訳者という医科発生学・先天異常学の世界的権威のお二人の合作として,本書および訳書があるという強みは,本版においても健在である。
前第8版において,人体発生学,医科発生学の教科書として,既に世界的なスタンダードとしての評価を確立していた本書に,初めて分子発生生物学的な知見の紹介が加わった。多くの章に,発生の分子制御についての説明が意欲的に取り入れられた。これらの知見の多くは,ヒト以外の動物から得られたものであり,必ずしもただちにヒトに外挿できないが,純記載的で,発生現象の機構についてはほとんど触れないか,あっても推論の域を出ない記載に終始していたそれまでの人体発生学の古典的教科書に,時代に対応して分子レベルでの説明が加えられた。第9版においては,その後の分子発生生物学の進展に対応して,これらの分子制御に関する記載が新しくなり,かつより広範に取り入れられている。日進月歩のこの分野の最先端に教科書が即応するのはほとんど不可能であるが,前版に比べて医科発生学の教科書として,古典的記載と分子制御の解説がよりバランスよく配置され,より「なじんで」きた印象を受ける。そこには,訳者序文にあるように,現著者サドラー博士の意図をより正確に読者に伝えようと訳出された,安田先生のご努力が大きく働いている。ラングマンの優れた古典的な著述に加えて,現著者と訳者という医科発生学・先天異常学の世界的権威のお二人の合作として,本書および訳書があるという強みは,本版においても健在である。
分子制御の記載の充実に加えて,CD-ROM“Simbryo アニメーションで見る人体の発生”の巻末付録が新たにつけられた。模式図的ではあるが,元来動的な変化である初期発生と主な器官系の形態形成の様子を,より容易に把握できるよう工夫されている。さらに,臨床に関連する改善点として,進展著しい出生前診断や胎児治療に関する記載を充実させて,先天異常に関する解説と合わせて別に章立てしている。この他にも,新知見に基づいて古典的な記載が適宜修正されている。これらの改善は,それぞれ基礎および臨床面において,読者の人体・医科発生学への理解を助けるであろう。今回の改訂においても本書は,著者と訳者の相補的な共同作業によって,世界的な教科書として確立された地位に甘んずることなく,さらに着実な進化を遂げている。
B5・頁496 定価8,820円(税5%込)MEDSi
URL=http://www.medsi.co.jp/
