【インタビュー】
臨床では聞こえない患者の声 |
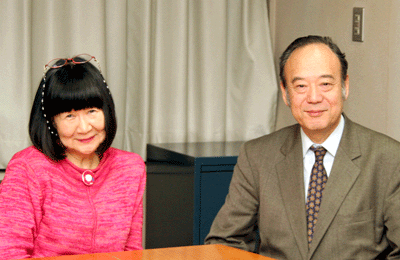 |
|
大熊由紀子氏(国際医療福祉大大学院教授)
開原成允氏(国際医療福祉大大学院長) |
2006年2月に刊行された『患者の声を医療に生かす』(医学書院)が反響を呼んでいる。同書は,国際医療福祉大大学院で行われた同名の公開講座のもようを収録・再編したもの。患者会はもちろん,医療訴訟の当事者をも講師として招いた同講座は,2005年4月から13回にわたって行われ,毎回多くの医療スタッフや学生,医療ジャーナリストらを聴講生として集めた。
「患者の声を聞く」というコンセプトそのものは珍しくない。しかし,医療者・患者の立場の違いを超えて,ストレートに「患者の声」を聞くことは,言葉ほどたやすくはない。患者が壇上に立ち,医療者が生徒になる「でんぐりがえし」によって初めて立ち現れた「患者の声」とはどのようなものだったのか。同講座を企画した開原成允氏,大熊由紀子氏に話を聞いた。
「利用者側の論理」が明らかにすること
――はじめに,公開講座「患者の声を医療に生かす」を企画された経緯をお聞かせください。開原 私はこれまで,2つの病院設立のプランニングをやらせていただき,どちらの時も,医師,看護師,技師など,その病院で働くことになるさまざまな人たちの意見を聞き,それを取り入れたプランニングを心がけました。
しかし,後になってから,「病院を利用するのは患者さんなのに,彼らの意見を聞いてこなかった」ことに気がついたのです。病院に限らず,日本では供給者側の論理で決めることが一般的です。利用者側の論理を取り入れたらどのような病院ができるのだろう?と考えるようになりました。
数年前ですが,大学入試の試験問題のミスを受験生が指摘したというニュースがありました。プロである大学教員のミスをいわば素人である受験生が発見する。これと同じようなことは,医療でも起こりうるのではないかと考えました。
大熊 私は医学記者だった1960年代から,病を持つ当事者だから気がつくこと,あるいは社会や医療者に訴えたいことがある,と感じて,紙面でご紹介したり,シンポジウムを開いたりしてきました。当事者による運動が長い時間をかけて,バリアフリー法などに結実する様子を目にする中で,患者・当事者から,医療従事者が学ぶ機会を何とか作れないかと考えていたところに,開原先生から「患者の声を医療に生かす」という公開講座への協力を相談されたのです。
単なる「体験談」ではない,患者による講義
――全13回の講座をコーディネイトしていくうえで,いちばん工夫されたのはどういった点だったのでしょうか。開原 医療従事者が生徒,患者さんが講師という形でやろうと決めてから,実際に授業を開始するまで1年近くかかりました。各患者会などから,講師候補の方に来ていただきディスカッションを重ね,グループメールで意見を交換してもらい,お互いへの理解を深め,テーマを絞り込むという作業を行っていただきました。
患者会の代表者の方は,どうしてもご自分の患者会が扱う疾患に関心が集中してしまいがちです。医療者にとっては,そういった話も参考にならないわけではないですが,やはり講義として開く以上,その活動の持つ意味について話をしていただくことが重要だと考えました。最終的には「ピアサポート」「医学教育」「臨床試験とガイドライン」など,活動のテーマごとに3名程度の講師にお話しいただきました。このテーマ設定の作業がいちばん重要だったところで,ここに多くの時間と労力がかかりましたね。
大熊 デンマークに「でんぐり返しプロジェクト」と呼ばれる,病を体験した人を教師に,医療・福祉の専門家が学ぶという研修があるのですが,そこでは教師となる人は単に自分の患者体験を話すのではなく,教師として知識と表現力に磨きをかけることを求められ,またプロとしてきちんと報酬を受け取るシステムとなっています。
私たちのプロジェクトでも,実に水準の高いお話をしていただき,聞いている専門家がすっかり感心してしまわれました。最初のうち警戒心を持っていた方が,ご自分の病院で患者会のリストを配るように変身なさいました。同じ日に講義していただく方には,事前にそのグループごとに顔合わせをし,グループメールでやりとりをしていただくことによって,お互いの講義の内容を確認していただきました。そのこともあって,毎回,複数の講師がテーマ性を共有しながら講義をしていただけたと考えています。
「臨床では聞こえない声」を聞く
――公開講座には多くの医療従事者が参加したとお聞きしています。医療者には,その模様を収録した本書『患者の声を医療に生かす』を通して,どのようなことを学んでほしいとお考えでしょうか?開原 看護師の方はおそらく,共感し,また納得して読んでいただける内容となっているのではないかと思います。私が少し心配しているのは,医師がこの本をどう読むか,ということですね。
例えば多くの患者さんがおっしゃることに「一番大変な時に,先生がそばにいてくれなかった」というものがあります。こういった訴えについては,多くの医師が「気持ちはわかるけれども,実際にはそんなことは不可能だ」と感じるでしょう。こういった印象から「患者の声を医療に生かす」なんて不可能だ,と考えておられる医師は多いと思うのです。
しかし,講義をされた患者さんのお話をうかがうと,「患者の声を医療に生かす」というのは,何もすべてを患者の言うとおりにやれということではないということがわかります。脳腫瘍・くも膜下出血体験者の内田スミスあゆみさんという方は,ご自分の講義の冒頭で「今日のテーマは“患者の声に関心を持ってください”です。“患者の声に従いましょう”ではないんです」とおっしゃっています。
大熊 日本がん患者団体協議会の山崎文昭さんも「患者さんの喜ぶことっていうのが,お医者さんたちの不幸の上に成り立っているならおかしい」とおっしゃっていました。医療者と患者の願いは究極のところでは同じだということが,参加していただいた皆さんの話からうかがわれます。
開原 それからもうひとつ。「患者の声なんて,いつもベッドサイドで聞いているよ」という方もいらっしゃると思います。しかし,臨床での医師と患者の立場の違いを考えれば,それはやはり,本当の患者の声とは言えないと私は思います。今回の講座のように,対等の立場に立つことによって初めて,「患者の声」が医療者まで届くのではないでしょうか。
本書の帯に「新しい“患者の声”は,対立型でもお客様型でもない。医療者とともに良き医療をめざす≪パートナーシップ型≫だった」とあるんですが,正にその通りだと私は思います。患者の声がすべて正しい,ということではなく,まず「反対側の声」が存在する,ということを知っていただけたらと思っています。
※本インタビューは,2006年3月9日に行われた対談を元に構成したものです。対談の詳しい内容は,弊社刊行『看護教育』6月号に収録される予定です。
大熊由紀子氏
国際医療福祉大大学院教授。朝日新聞科学部次長を経て2001年までの17年間,論説委員。阪大教授を経て04年より現職。『寝たきり老人のいる国いない国』『福祉が変わる医療が変わる』(ぶどう社)など著書多数。http://www.yuki-enishi.com/でも発信中。
開原成允氏
国際医療福祉大大学院長。内科医。1961年東大卒業後,東大教授,東大図書館長,大蔵病院長などを経て現職。『医療の個人情報保護とセキュリティ』(共著,2005年,有斐閣)など,著書多数。
