【寄稿】
患者さんのために病理に強い医師になる!
福嶋 敬宜
東京大学助教授(人体病理学・病理診断学)
同医学部附属病院病理部・副部長
今年も風も香るようなさわやかな季節になった。病棟や各部門には新たなスタッフ,新研修医やローテーターなどが配属され,何となく新鮮な雰囲気に包まれる。
そんな一方で,季節の変わり目にはちょっとしたサプライズや混乱も起こりがちである。
病理部からも担当者の嘆き声が聞こえてくる。
・検体と依頼書内容の不一致
・生食に入れられた病理検体
・脂肪とリンパ節でギューギューの容器
・その日に提出した検体についての診断結果の問い合わせ
・「染色希望」として論文に書いてある免疫染色が羅列された検査申込書
それぞれは不注意や申し送りミスなど,その場限りの問題として済まされてしまうことが多い。しかし,このような問題の原因は,病理診断結果に興味を持つ人は多くても,病理検体の扱いやその診断過程にまで関心を持つ人がとても少ない,ということにあるのではないかと考えられる。
病理診断は治療方針に直接的に影響を及ぼす。このため本稿では,指導者的立場の方も含め,なるべく多くの方々(特に臨床担当医)が病理情報を正しく理解し,診療に役立てていただきたいとの思いから,それを実現する行動指針を示すことを主眼とした。また,図として示した「病理検査・診断の流れ」も参考にしていただけたらと思う。
デキる医師は病理に強い
私は,これまでの臨床医との付き合いから,デキる臨床医は病理にも強い,という確信を持っている。「病理に強い医師」。
こういうと,「そりゃあ,病理に詳しいに越したことはないけど……」,「臨床医にそんな暇はない」,「病理医の仕事を押し付けるつもり?」など,ネガティブな声も聞こえてきそうだ。
しかし,ここでいう「病理に強い」は,必ずしも病理学に精通しているということを意味していない。もちろん詳しいに越したことはないが,まずは治療方針決定の根拠にもなる検査・診断方法やその過程について,少しばかりの知識や関心があるだけでずいぶん違うと思うのだ。
病理に強い医師は,自分が予測していた結果が生検で得られなかった時にも,次にどうすればよいかの方針を立てられる。検体採取の部位を変えればよいのか,採取法を変えてみるか,または再検査自体に意味がないと判断するかなど。そして病理所見を十分に理解しているので,患者さんにはわかりやすく診断と治療の根拠を説明することができるのだ。このような臨床担当医の適切な方針決定や対応が,患者さんにとって大きな利益になるのはいうまでもない。
病理研修と臨床病理カンファレンス
私が「病理に強い医師」の存在を認識し,その意義を感じたのは,以前がん専門病院に勤務していた頃である。そこには病理に強い医師がとても多く,カンファレンスなどで病理所見に関しての光るコメントや質問に感心させられることもまれではなかった。このような医師が多かった理由として二つが挙げられる。一つはレジデントに病理研修が義務付けられていたこと,二つ目は,レベルの高い臨床病理カンファレンス(CPC)が頻回に行われていたことである。数か月でも病理診断の現場を経験すれば,病理の検体がどのように処理されて顕微鏡標本になり,どのような過程を経て,またどのような思考過程を経て診断が下されるのかを学ぶことができる。また,それまで臨床担当医の立場で画像や内視鏡像として捉えていた病変の実像を繰り返し見ることによって,臨床能力を高めることにもつながるはずだ。
CPCの役割や有用性はここで書くまでもないが,現在私が勤務している東京大学病院でも10種類以上のCPCが定期的に開催されており,そこでは当該臨床科の医師だけでなく,病理医,放射線科医も参加して,活発な討論が行われている。
病理に強くなるための5か条
病理に強い医師を生み出す方法として病理研修とCPCを挙げたが,もちろん工夫次第で“自主トレ”も可能である。今日から実行可能な次の5項目で,「病理に強い医師」をめざしてほしい。1)提出する病理検体に気を配る
2)病理検体~標本作製,診断の流れを知る
3)病理診断レポートに関心を持ち,上手に読む
4)必要に応じて病理医と一緒に顕微鏡をのぞく
5)自分の施設の病理医と仲良くなる
1)何でも病理に出せば答えが出るというものではない。検体の扱いはその種類や検査目的によってもポイントが異なるので注意が必要である。わからない場合は病理医に尋ねてほしい。
2)大雑把にでもこれらを理解しておくと,診療のマネジメントの中に病理検査もうまく取り込めるようになる(図)。いつごろ診断結果が得られそうか,質的診断はどこまで可能か。病理診断の守備範囲や限界を知っておくことも重要である。個々の症例について事情は異なるため,細かいニュアンスは担当技師や病理医から得るのが効率的だろう。
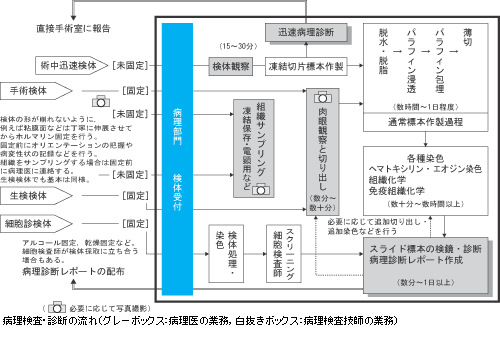
3)通常,病理診断結果は文書で伝えられる。所見文が長い時は診断欄しか目を通さない人も多いようだが,コメントがあればそれは読むべきである。そして,いつもとは違う表現があった場合には気をつけて本文まで読むようにしたい。
4)5)病理診断レポートの内容に少しでも疑問や確認したいことがあれば病理医に連絡してほしい。そのうえで,可能であれば顕微鏡をのぞきに病理部に押しかけよう。これが「病理に強い」医師へのもっとも近道である。
病理診断とコミュニケーション
病理に強くなるための行動指針を示したが,これらすべてに関わってくるのがコミュニケーション能力である。ぜひ,5か条の指針とともに「コミュニケーション」というキーワードを意識して,さらに「病理に強い医師」をめざしていただけたらと思う。ここまでは一方向的に,臨床医に対して「~すべき」と述べてきたが,病理医(またはそれをめざす人)に向けても少し書いておきたい。
なぜなら,コミュニケーションとは双方向で成り立つものであり,診療の現場で病理診断が十分に活かされるためには,病理医にもその能力が求められるからである。
まず,病理医は,検体や病像に素直であろう。そして,その病像を臨床的にもっともよく把握している臨床担当医の言葉には十分に耳を傾けるべきである。病理診断レポートに病理所見のすべてを書くことができない(または書かない)のと同様,申込書にも十分に書かれていない場合があるからだ。したがって不十分な情報は,電話などでその詳細を聞こう。病理標本だけを見ていたのでは気づかなかった,新たな視点や事実を知ることができることも少なくない。
そして,病理医も,臨床医の「いつもと違う」言葉を敏感にキャッチするように努めよう。それを説明できる“何か”が病理標本中にもきっとあるはずだと考えて,もう一度標本をレビューするのだ。重要な所見を見落としているかもしれないし,そこから新たな知見が導き出されるかもしれない。
病理検査申込書と病理診断レポートという文書の交換であっても,それも一つのコミュニケーションであると認識しよう。どうしたら病変や病像のニュアンスを正確に第三者に伝えられるか,イメージ力を駆使しながら文章にも注意を払いたい。
病理診断とコミュニケーションは切っても切れない関係であり,またそこが病理診断学の面白さや醍醐味にもつながるものだと信じている。
すべては患者さんのために
臨床担当医も病理医もめざすところは同じである。つまり患者さんがなるべく効率よく適切な医療を受けられることである。そのためには,われわれ医師同士がコミュニケーションすることをポジティブに捉え,共有できる部分を増やし,それぞれがレベルアップしていくという良循環を作っていくことができたらと思う。◆東京大学 人体病理学・病理診断学分野HP
URL= http://pathol.umin.ac.jp/
| 福嶋敬宜氏
1990年宮崎医大卒。関東逓信病院(臨床・病理),国立がんセンター(研究)のレジデント課程を修了。97年国立がんセンター中央病院医員,2001年米国ジョンズ・ホプキンス大研究員,04年東医大講師,05年東大講師を経て,06年4月より現職。医学博士,認定病理専門医,細胞診専門医。編著に『診療・研究に活かす病理診断学―消化管・肝胆膵編』(医学書院刊)。チームワークとネットワークで患者さんのための病理診断学を実践していくことを目標としている。 |
 |
