MEDICAL LIBRARY 書評特集


新井 達太 編
《評 者》小柳 仁(聖路加国際病院ハートセンター・顧問)
心臓外科におけるランドマークとなる書
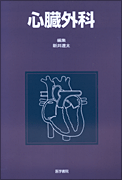 ダヴィンチの詳細な解剖学から500年,ウィリアム・ハーベイの血液循環説から350年,アレキシス・カレルの血管吻合法から100年,カレル・リンドバーグポンプ(人工心肺の原型)から60年ほどの時間が経過した。現在の心臓外科の医療は,これらの歴史的な業績の上に成り立っており,エジプト以来の5000年の歴史を持つ脳外科,整形外科と比べて格段に短い60年の時間を刻んできた。
ダヴィンチの詳細な解剖学から500年,ウィリアム・ハーベイの血液循環説から350年,アレキシス・カレルの血管吻合法から100年,カレル・リンドバーグポンプ(人工心肺の原型)から60年ほどの時間が経過した。現在の心臓外科の医療は,これらの歴史的な業績の上に成り立っており,エジプト以来の5000年の歴史を持つ脳外科,整形外科と比べて格段に短い60年の時間を刻んできた。
ここで1人の心臓外科医の個体発生を,学習,習熟,練達のキャリア形成として考えてみよう。せいぜい40年の職業生活の前半に心臓手術に習熟し,後半はリーダーとして当該分野に貢献しなければならない。人生は決して長くなく,直接の指導者以外に,ここに手術書の存在理由がある。
心臓外科の手術書は評価に足るものだけでも本邦と世界をあわせ十指を越えるが,すべて20世紀までの「形状認識を助けるための解剖書」である。そして美しい手術のシェーマについてのきわめて良心的な警告が語られている。それは,“Diagrams do not bleed.(手術の絵は決して出血までは描いていない)”という言葉である。
この秋,驚くべき教科書が世に出た。ここにご紹介する『心臓外科』(新井達太編)である。新井先生は東京女子医科大学,東京慈恵会医科大学で心臓外科の教授を20数年務められ,小生は先生の講師時代から,人工心肺係,つまり外回りの奴隷として,常に肩越しに先生の緻密な手術を拝見してきた。人工心肺も心筋保護も不安定な時代であり,決して時間が豊富にあるわけではない。その環境で,決して後悔しない美しくも確実な手術を心がけておられた。そして,その先駆的な時代に記録性を追求され,病院の写真技師は術野の真ん中で宙吊りのような姿勢で狭い術野を記録することを厳しく要求されていた。本書を拝見し,まず感銘したのは術中や写真の迫力であり,surgeon's viewで,一針一針に術者の苦心と息づかいが感じられる。もちろん現代であるから術野に血液は見られないが,この優れた写真とシェーマの臨場感は,出血をも描いているといえよう。各著者も編者の期待に見事に応えたといえる。
全体の構成こそ特筆すべきものである。確立された手技については第一人者が,そして考え方,手技の改良,材料の進歩が今なお続いている手技では対論を語れる複数の著者により記述が行われている。手技の成熟度によって軽重の差が巧まずしてつけられており,異論のあるところに手厚い。記述として特に,左室形成(Dor,David-Komeda),大動脈基部置換(Ross,ホモグラフト),Tissue engineering,不整脈の外科などに斬新さがある。
類書にないこのような構成は,外科医に思考の機会を与え,また自らの手技を完成させていくための恰好の道標となろう。
ダヴィンチの解剖図は見事であるが,死体置場でのスケッチから生まれている。ルネッサンスの実証科学が解剖図を生んだ。50年前,暗黒大陸のような心臓外科に分け入った編者の透徹した視線を各所に感ずることができる。21世紀初頭,われわれはランドマークのような手術書に出会うことができた。世界に類のない臨場感溢れる本書について唯一の不満は,本書がもし英文で書かれていれば,全世界の若い心臓外科医の自己研鑽に貢献できる可能性があったということであろう。
本書は,成熟して完成期に入った心臓外科のバイブルであり,1人の心臓外科医にとって自らのキャリアデザインを図るための最適の書である。ぜひ座右に置き,日々紐解かれることを勧め,また期待している。


板倉 徹 編
《評 者》田中 達也(旭川医大教授・脳神経外科学/日本てんかん学会理事長)
脳神経外科医必携の定位脳手術の入門書
 1973年に,パリの国立科学研究所でマントヒヒを用いた定位脳手術の研究を始めた時,年代物の実験用定位脳手術装置が,Horsley-Clarke Apparatusであると聞き,感激したことを覚えている。パーキンソン病に対する定位脳手術は,この実験用定位脳手術装置を人間用に改良したSpiegel and Wycisにより1947年に開始された。しかし1967年にL-DOPAが臨床応用されると,その劇的な効果の前に手術を受ける患者は激減したが,L-DOPAの長期使用による,wearing-off現象や不随意運動などの副作用が問題となってきた。
1973年に,パリの国立科学研究所でマントヒヒを用いた定位脳手術の研究を始めた時,年代物の実験用定位脳手術装置が,Horsley-Clarke Apparatusであると聞き,感激したことを覚えている。パーキンソン病に対する定位脳手術は,この実験用定位脳手術装置を人間用に改良したSpiegel and Wycisにより1947年に開始された。しかし1967年にL-DOPAが臨床応用されると,その劇的な効果の前に手術を受ける患者は激減したが,L-DOPAの長期使用による,wearing-off現象や不随意運動などの副作用が問題となってきた。
1980年代に後腹側淡蒼球破壊術が,1990年代にDBSが開発され,2000年4月より本邦でもDBSの保険適用が認められた。わが国でも,多くの施設で,定位脳手術がおこなわれるようになってきた。このたび,板倉徹先生編集による定位脳手術の入門書『定位脳手術入門 DVD付』が刊行されたのは,実に時の要求に応えたものと言える。
本書は,これから定位脳手術を始めようとする脳神経外科医にとっては,必携の入門書である。初めに定位脳手術のために必要でしかも基本的な解剖学と生理学をマイクロレコーディングの手技も含めて,詳細に説明されている。
疾患各論では,各分野の第一線で最も活躍されている研究者が,初心者によくわかるように,詳細かつ丁寧に構成を心がけている。しかも,付録のDVDには,手術手技の実際はもとより,手術前後の変化も含めて詳細に解説されている。このため,初心者はもちろんのことであるが,実際に定位脳手術を行っている脳神経外科医にとっても,自分の手術手技や手術のターゲットについて,リフレッシュするための座右の書の1つになるものと思われる。
近年,難治性てんかんの症例でも,視床下核,視床前核,てんかん焦点部の電気刺激が,less invasiveな治療法として,国際的にも注目されている。本書が,定位脳手術を必要とする多くの患者さんを救うために,多くの研究者の愛読書となるものと期待している。


栗林 幸夫,佐久間 肇 編
《評 者》山科 章(東医大教授・第二内科)
循環器科・放射線科の架け橋
臨床重視の実践書
 循環器の診療も大きく変化してきた。私が研修医になった1970年代には,循環器疾患は病歴,身体所見,心電図と胸部X線写真で8割は診断がつくといわれていた。その当時の治療法の主体は薬物治療であり,それで十分であったかもしれない。ところが,80年代になって断層エコー,心筋シンチが普及し,さらに心臓カテーテル検査が多くの病院でルーチンに行われるようになった。一方で,冠動脈カテーテルインターベンションが普及し,従来の機能的情報だけでなく,詳細な解剖的情報が要求されるようになった。
循環器の診療も大きく変化してきた。私が研修医になった1970年代には,循環器疾患は病歴,身体所見,心電図と胸部X線写真で8割は診断がつくといわれていた。その当時の治療法の主体は薬物治療であり,それで十分であったかもしれない。ところが,80年代になって断層エコー,心筋シンチが普及し,さらに心臓カテーテル検査が多くの病院でルーチンに行われるようになった。一方で,冠動脈カテーテルインターベンションが普及し,従来の機能的情報だけでなく,詳細な解剖的情報が要求されるようになった。
そういった要求に応えるように,90年代後半からは機器のディジタル化,画像処理の進歩などに伴い循環器画像診断が大きく進歩した。特にMR,CTは日進月歩であり,循環器病診断を大きく変化させつつある。MR,CTによってわかる心血管系の解剖,心機能,冠動脈病変,心筋灌流,心筋性状などは循環器科医にとってきわめて重要な指標であり,大きな注目を集めている。
ところが,心臓CT,心臓MRは普及してきているとはいえ,機器の進歩が先行しており,正直なところ,われわれ臨床医がこれらを使いこなせるという状況でない。循環器科医にはCTやMRの理論や画像処理がよくわからない。MRを例にあげると,傾斜磁場,スピンエコー法,インバージョンリカバリー,T1強調画像,ブラックブラッド,フローボイド,MIP,などと続くとつい敬遠してしまう。そこで,放射線科医や放射線技師を巻き込んで一緒にやりたいと思うが,検査が混んでいて,心臓の検査まではできない。一方,放射線科としても,なじみの少ない心臓でありとっつきにくい。そういったことで,お互いに二の足を踏んでいるのではないだろうか。
そういった循環器科・放射線科の“はざま”を埋めるために,いろいろな機会が持たれてはいるが,わかりやすく勉強できる教科書がない。そういったタイミングで今回,医学書院から『心臓血管疾患のMDCTとMRI』が上梓された。本書を編集された栗林,佐久間両先生は心臓放射線研究会,ハートイメージング研究会,心臓MRハンズオンセミナー,心血管画像動態学会などで中心的に活躍され,心臓CTと心臓MRの普及に努めてこられている。お二人とも放射線科が出身であるが,われわれ循環器科医が理解しにくい領域,あるいは放射線科医や放射線技師が苦手な点を熟知されている。そういったノウハウを凝集し編集されたのが本書である。お二人の長年の啓蒙・教育活動に基づいた,臨床を重視した実践的な企画になっている。
筆者もこれまで幾度となく心臓MRやCTの講演を聞き,あるいはセミナーを企画したりしてきたが,なかなか理解できないことが多かった。しかし,本書を通読する機会を得て,「目からウロコ」の連続であった。たとえば,CTではガントリーを回転しながら拍動している心臓を撮像して,どうやって画像を再合成するかという基礎的な疑問も解けたし,VRやMPRなどの画像表示法も理解できた。心臓のcross-sectional anatomyもよく勉強できた。上述したMRの基本的事項や,遅延造影などMRでしかわからない臨床的意義も理解できた。などなど,あげはじめたらきりがない。
疾患の項目も非常に多くとってありCT・MRの特徴を理解するうえで勉強になる。それぞれの疾患・病態について“知っておくべきこと”をまず紹介したあとで,その疾患における検査の意義,手順,診断・評価の仕方が解説されており,非常に理解しやすくしかも実践的である。また,CT・MRの現状と限界・ピットフォール,さらに,将来への展望までup to dateが網羅されており興味深く読むことができた。本書は読み手として循環器科と放射線科の両者を意識して書かれているため,いずれが専門でも読みやすくなっている。
心血管系の詳細な解剖,心機能,冠動脈病変,心筋灌流,心筋性状などの非侵襲的評価が望まれている。こういった時代のニーズにマッチしているのが心臓CT・心臓MRである。まだまだ,発展途上で日々進化し続けている検査法であり,今からでも遅くない。始めなければ始まらない。これから心臓MR,心臓CTを学ぼうとする方,始めようとする方,始めたけどうまくいかない方に,ぜひとも本書を薦めたい。


クリニカルパスがかなえる!
医療の標準化・質の向上
記録のあり方から経営改善まで
立川 幸治,阿部 俊子 編
《評 者》村山 典久(滋賀医大理事)
クリニカルパス導入・運営の解決策を具体的に示す
 クリニカルパスについては,医療現場における多くの課題(医療の標準化と個々の疾患に対応できる医療,情報開示,医療の質・安全性の維持,業務の効率化,経営改善等)を解決するツールの1つとして注目されて久しい。
クリニカルパスについては,医療現場における多くの課題(医療の標準化と個々の疾患に対応できる医療,情報開示,医療の質・安全性の維持,業務の効率化,経営改善等)を解決するツールの1つとして注目されて久しい。
現在,多くの医療機関でその導入レベルに差はあるもののクリニカルパスが導入・運用されている。本院(滋賀医大病院)においても,業務の効率化をめざし,ようやく「クリニカルパスを(正式な)医療記録にしよう!」(本書IV章)と改革を進めている段階にある。
クリニカルパスに関するイメージが先行し,誰もが導入すべきと考えているにもかかわらず,いざ具体的な改革に入るとさまざまな反論を受けて前に進まない,あるいは当初予定していたほどの効果が現れていないというのが,本院を含む多くの医療機関の実状であろう。
本書は導入から運用,普及,発展まで段階的に,どこに問題点があるのか,注目すべき点などをわかりやすく解説し,医療機関の抱える課題の解決策について,さまざまな職種の医療従事者から事例を交え,きわめて具体的に示している。 (1)組織としてクリニカルパスを推進していくことの重要性
クリニカルパスを作成するうえで最も重要なことは,医師・看護師だけでなく,多職種の参加である。多方面からアプローチしていくことがよりよいパスに仕上げていく近道であるといえる。
本書では,病院全体のコンセンサスを得ることは必須であり,クリニカルパス委員会やプロジェクトチームといった小単位でのがんばりだけではパスを推進していく力は弱く,組織としてのサポートが最も大きな力となることを示唆している。そして,このことこそが,「パスで病院が元気になる!」(本書III章)所以なのであろう。 (2)地域医療機関を含む連携パスの活用
医療に対する期待がこれまで以上に求められる昨今,チーム医療の実現は医療機関にとって必須の課題となっている。本院でも,NST(栄養サポートチーム)や褥瘡チームなどさまざまな専門職種から形成されたチームによるアプローチを行い,効果的な結果を導いている。しかしながら本院では後方支援病院を含めた急性期治療から慢性期治療への移行についての連携パスまでは実現していない。
連携パスは,チーム医療を1つの医療機関だけで捉えるのではなく,他施設,地域との密接な連携により情報の共有と治療の継続を可能にし,患者にとって最も望ましい適切な医療を,適切な場所で提供することを可能にする。
今後,院内のクリニカルパスのみを推進するのではなく,関連病院を含む広範囲にわたるパス活用に一歩でも二歩でも踏み出していきたい。 (3)DPCを踏まえたクリニカルパス活用による医療の効率化
医療機関,特にDPCを導入している医療機関にとってはDPCを踏まえた適切な在院日数による有効な病床利用など医療の効率化が可能になり,今後,連携パスを発展させていくことがその解決策となる。
本院の今後の取り組みにおいても,特に以上の3点を中心にぜひ参考にさせていただきたいと考えている。


画像診断ポケットガイド
胸部Top100診断
南 学 訳
《評 者》杉本 英治(自治医大教授・放射線医学)
胸部全体を俯瞰する単純X線写真も収載
AMIRSYS社刊行の画像診断ポケットガイドシリーズ“Chest”の日本語版が刊行された。主著者はGurney教授,訳は筑波大学の南教授である。訳者序文で述べられているように,Gurney教授はChest Radiologyを病態生理に基づいてどう解釈すべきかを深く考え続けている希有な放射線科医である。また,ポータブル撮影の合理的解釈についての経験も豊富で,いかなる条件のX線写真であっても可能な限り系統的に所見を拾い上げる方法論とその意義を理解している放射線科医でもある。Gurney教授の胸部画像診断に対する姿勢を知っていたからこそ,南教授は本書の翻訳を引き受けられたのである。この本にはこれまで刊行されたこのシリーズの他の本と際だった違いが2つある。ひとつは章立てである。章立ては臓器別でも疾患別でもない。解剖学的領域,画像所見,外傷,ICUポータブル撮影など,いろいろなカテゴリーの14章から構成されている。これは胸部画像診断学の他のどのテキストとも違っている。他ではあまり扱われない心臓やポータブル撮影が含まれていることは特筆に値する。「ペースメーカー・除細動器のリード線」「チューブ・カテーテル」の画像診断にいたっては,日本のテキストで解説されることはまずない。この章立ては胸部画像診断学の全体像を説明するためにはきわめて合理的なものと思われる。
もうひとつの特徴は図の配分で,本書では,単純X線77,CT92,MRI1,アンギオ1,シェーマ29と,乳腺を除く他のシリーズと比べて単純X線の割合が多い。そのため,本文でも単純X線所見の記述に大きなスペースが割かれている。HRCTの登場によりルーペ像を分析するような読影に重きが置かれる傾向があるが,胸部画像診断では胸部・胸郭の全体像を俯瞰することがなによりも重要であり,それには胸部X線写真が最適な手段である。だからこそ著者らが図の4割を単純X線に割り当てたのである。
本書はただのポケット本ではない。レジデントや医学生だけではなく,胸部診断学=CTという時代から勉強を始めた世代の放射線科医にとっても大いに価値のある本と思われる。ぜひ,Gurney教授の胸部画像診断の考え方とそれに対する南教授の熱い思いを共有していただきたい。定価5,460円は大バーゲンである。
A5変・頁378 定価5,460円(税5%込)MEDSi
