【寄稿】
何が医療現場を疲弊させるのか
濃沼 信夫(東北大学大学院教授・医療管理学)
人手不足の処方箋
4月に予定されている診療報酬改定は,マイナス3.16%という史上最大の引き下げとなり,医病院は一層厳しい運営を余儀なくされる。多くの医療関係者が辛く険しい現実に向き合わざるをえない中にあって,安心と安全の医療を実現するには手厚い人員配置が欠かせない,という考え方が盛り込まれた点は高く評価できる。例えば,急性期医療では,これまで最高の評価であった2:1看護(実質配置10:1)の上位に,1.4:1看護(同7:1)がより高い点数で新設される。慢性期医療では,医療の必要度が高い患者が多い(8割以上)病棟における看護職員の配置基準は,5:1(実質配置25:1)から4:1(同20:1)に引き上げられる。また,在宅医療(在宅療養支援診療所)においても,手厚い看護配置が要請されることになる。
これに関連して,特定機能病院の人員配置標準は,現行の2.5:1から2:1に引き上げられる(省令改正)予定である。これらは,医療のあるべき姿を実現するステップ・ストンであり,急性期医療でいえば,次期改定には急性期医療の世界標準である1:1看護が設定されることが強く望まれる。
手厚い看護は,医療の質を高め,医療事故のリスクを下げ,患者満足を促すと考えられる。これが,医療に対する国民の信頼を回復する限られた道であることを実証するには,選択肢として,手厚く高い点数の看護体制が診療報酬に存在することが不可欠だからである。手厚い医療を実践する施設が患者に選ばれるようになることで,わが国の医療の底上げが進むことが期待される。
1.4:1看護の新設,産科や小児医療の重点評価が画期的である理由は,これが医療における質と量との適正なバランスが志向された結果と考えられるからである。医療事故の多発傾向や深刻化する医師不足は,行き過ぎた量的拡大(病床数,受診数)によって,質の確保が困難になっていることの警告として捉えることが重要である。市場原理による調整が困難なわが国の医療において,質と量との至適バランスを保つには強い政策力が欠かせない。
国際比較にみる日本
現在,医療・福祉関連のヒトは就業人口の約8%を占め,医療・福祉分野はわが国の産業で最大規模の人員を擁する。人減らしが進む分野が少なくない中で,この分野は就業者数が年々増加し,少子高齢化等に伴って,これからも確実な成長が見込まれる。医療分野は人集約型産業の典型であるから,ヒトなしには何も始まらない。したがって,この分野のヒト(専門職)は計画的に養成されてきた。人口当たり養成数を世界標準(グローバルスタンダード:主要30か国の平均)と比べてみると,医師は世界標準の下限にあり,看護師はちょうど世界標準,薬剤師は世界標準を上回る。
わが国の医療従事者の人口当たり養成数がほぼ世界標準にあるにもかかわらず,世界に類を見ないほど人手不足が深刻化している最大の理由は,病床数,受診数が世界標準の数倍も多い(応需可能な限界を超える)ことと考えられる(表1)。医師不足でいえば,この状況に,卒後臨床研修の必修化,地域による偏在や診療科のアンバランス,女性医師の増加,医師とチームワークを行うべき専門職の資格化の遅れなどの様々の要素が加わって,社会問題化しているようにみえる。
| 表1 医療提供体制の各国比較(2003年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔出典〕「OECD Health Data2005」(厚生労働省資料) |
世界標準の数倍の病床数,受診数に対応するには,現行の数倍の人員配置が必要となる(図1)。世界標準の数分の1の人員配置でも,世界に遜色のない医療を提供してこられたのは,医療者の強い意志と献身的な努力に依るところが大きい。しかし,これにも限界があり,非常事態が恒常化することで,医療者は疲弊し,ミスや事故が起こりやすくなる。中堅の医師が開業したあとに残された医師は,一層の過重労働を強いられる。若手の医師は,きつい診療科を敬遠する。不十分なサービスには患者の不満が募る。これらは,個々の医療人や個々の医療施設の,人道主義と職能意識に基づく懸命の努力をもってしても,もはや対応しきれない構造的な課題である。
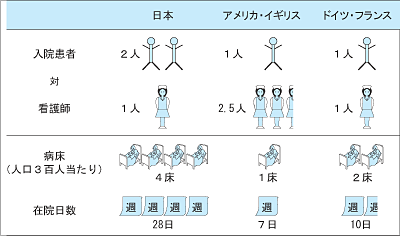 |
| 図1 わが国の深刻な人手不足(イメージ図) 人口当たりの看護師数は世界標準でも,病床数(入院患者数)が多いため,世界標準の数分の1の人員配置となる。 |
医療制度改革の背景
わが国の医療は,WHOの「ヘルスシステム達成度」(2000年報告)で世界第1位にランクされているが,一方,OECDの「健康自己評価」(2005年報告)では最下位を低迷している。健康自己評価は,国民の健康意識という文化的な交絡要因が影響するとしても,わが国はいかにも低すぎる。この「なぜ?」を考えるヒントは,各種の世論調査に隠されているように思われる。多くの世論調査で上位にあげられる,医療に対する国民の不満・不安は,(1)親切さ,(2)素早さ,(3)安全さの3つであり,医療ではサービス業の基本が満たされていないことがわかる。医療に対する評価のベースラインが低いことから,健康調査でも高い評価は得られ難く,事故やニアミスが起これば,これが大きなトラブルとなる可能性も大きい。
国民の3大不満・不安の原因を考えると,これらに共通するのは人手不足であることがわかる。労働集約型産業の典型である医療において,人手不足は致命的な課題であり,医療制度改革の核心はこの人手不足の軽減ないし解消にあるといえる。この主たる原因は過度の量的拡大(病床数,受診数)にあり,医師の不足と職員の疲弊という深刻な社会的な課題が生じる。そして,上述のごとく,応需の限界を超える業務は,事故の多発傾向とサービス低下につながり,医療に対する国民の信頼は急速に低下してきているように思われる。
集約化と連携のトレンド
今回の診療報酬改定で,急性期入院医療の実態に即した看護配置(入院基本料)として,新たに設定された1.4:1看護(実質配置7:1)の取得は,より良い入院医療を実現するうえでの重要な病院戦略となる。これまでの最高水準であった2:1看護(実質配置10:1)を算定していた病院にとっては,高い機能をめざす観点からも,また,病院経営の観点からも1.4:1看護の取得は急務となる。後者でいえば,在院日数の短縮化による病床利用率の低下や,紹介率を要件とする加算点数の廃止などで,無視できない減収が見込まれるからである。手厚い看護配置と短い在院日数を実現するには,看護職員の集約化が必要となり,病床のスリム化(病院のダウンサイジング)が検討されなければならない。病院の一般病床107万床に63万人の看護師が勤務しているとして試算すると,現在2:1(病床数の65%)から4:1まで存在する人員配置を,全病床での1.4:1看護を実現するには病床数は3分の2に,同じく1:1を実現するには病床数は半減する必要がある(図2,3)。その実現には,5ヵ年計画,10ヵ年計画がデザインされる必要があろう。
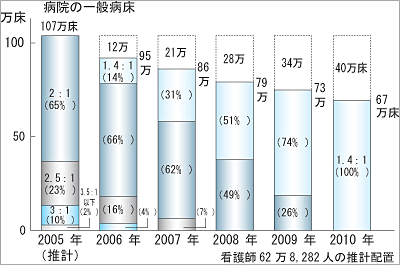 |
| 図2 看護体制の充実に向けて(1)(私案) → 5ヵ年で全病床1.4:1看護を実現するには |
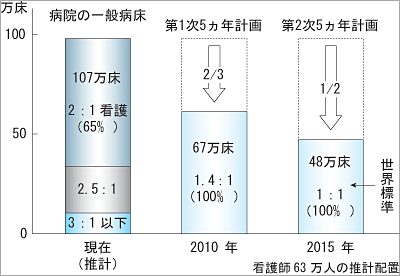 |
| 図3 看護体制の充実に向けて(2)(私案) → 10ヵ年で全病床1:1看護を実現するには |
過度に進んだ量的拡大を総括し,質的充実に転換する医療制度改革は,国家レベルの待ったなしの政策課題である。入院医療における人手不足を解消するための限られた選択肢は,病床数の適正化である。これには,スウェーデンのように,政策発動がもっとも迅速かつ効果的である(エーデル改革等で約3分の1に削減)が,民間病院が多いわが国でこれを行うことは難しい。
病床数の適正化を間接的に進めるには,(1)医療費や在院日数の削減という政策目標の設定,(2)供給過剰と,EBMに依らない入院適用によって生じる社会的入院の排除,(3)医療施設間の連携と資源の集約化,(4)地域における受け皿の整備(入院医療の代替ないし補完機能としての在宅医療の充実等)が重要である(表2)。これらを進めるには,病床の抱え込みに通じる法令上の病床数の規定をすべて職員数の規定に置き換える,などの現実的な法令の整備が欠かせない。
| 1)目標設定と計画策定(国・県/改革大綱) 2)社会的入院の排除(療養病床の再編) 3)連携と集約化の推進(医療計画) 4)在宅等の受け皿の確保(在宅療養支援診療所) |
人手不足の解消は,医療者の疲弊という国民にとって最悪の事態を改善し,患者満足とともに職員満足に通じる重要な病院戦略といえる。人手で成り立つ医療分野では,職員の満足なくして真の患者満足は得られないであろう。この意味から,人的資源の充実は医療の生命線といえる。
 |
濃沼信夫氏
1975年東北大医学部卒。武蔵野赤十字病院で研修後,フランス政府給費留学,秋田大医学部助手。81年厚生省入省。その後,WHO本部事務局(ジュネーブ),国立がんセンターを経て,90年より現職。 |
