【対談】胃癌を知る――『胃癌の構造』第3版発刊によせて |
|
 |
|
| 中村恭一氏 (横浜市立みなと赤十字病院・病理/東京医科歯科大学名誉教授/筑波大学名誉教授) |
馬場保昌氏 ((財)早期胃癌検診協会中央診療所・所長/同協会常務理事) |
かつては「死に至る病」として恐れられた胃癌も,早期に発見されれば内視鏡による低侵襲治療が可能になった。しかし,その適応を誤れば追加手術や癌の再発にもつながり,術前の深達度や浸潤範囲の診断の正確さが改めて問われている。
そこで本紙では,わが国の消化管病理学の泰斗である中村恭一氏が『胃癌の構造』第3版を上梓されたのを機に,中村氏と,ともに胃癌の診断学の進歩に臨床面で多大な貢献をされてきた馬場保昌氏のお二人に,改めて「胃癌」をめぐってご対談いただいた。
馬場 中村先生,このたび先生のライフワークともいうべき『胃癌の構造』第3版が刊行されました。大変おめでとうございます。本書は,先生の最初のご著書『胃癌の病理』(1972年,金芳堂)から30年余の先生のご研究を集約するかたちで版を重ねてこられたもので,本書では先生の基本的な考え方,論理の展開,そして臨床診断への応用まで,その研究成果が系統的にまとめられています。本日は『胃癌の構造』の根幹である,胃癌組織発生の理論がどのようにして誕生したかを含めて,第3版発行までの道程を伺いたいと思います。
また,先生の長年にわたる系統的な研究によって,「胃癌の構造」という大きな木(図1)が育ったわけですが,その枝葉にあたる個々の研究のエピソードについても,お話をお聞きしたいと思っております。
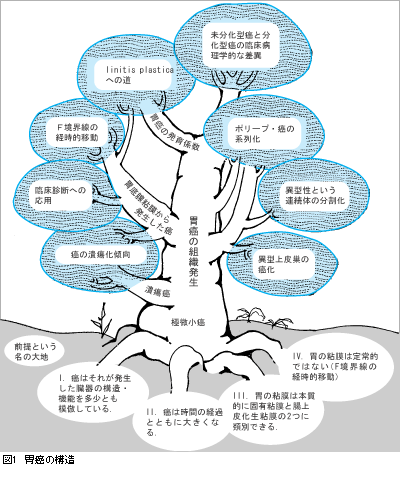
では,まず「胃癌の構造」という本書のタイトルはどのようなことからおつけになったのか,ということからお話しください。
中村 昔読んだ『論理』という本(中谷太郎著,共立出版,1972年)に「複雑な事物を簡単な要素に分析し,見とおしの困難な事象を単純な過程に分割し,それらの要素や過程のあいだの関係を明らかにし,総合することによって,全体の構造や関連を正しく認識していこうとするとき……」という文言がありまして,これを引用して,胃癌にまつわる,諸々の事象をコマ切れに記述するのではなく,4つの前提を礎とした胃癌の組織発生,それを中心としていろいろなことを互いに関連づけ,胃癌というものの体系化,胃癌の姿を浮き彫りにするという意味で『胃癌の構造』と題しました。少し難しくなってしまいましたが(笑)。
■「潰瘍癌化説」を否定
馬場 先生は1959年に東京医科歯科大学医学部をご卒業になられて病理学に進まれ,癌研究会癌研究所(癌研)病理部で消化管癌の病理を研究されるようになられました。病理の道に進まれて,胃癌の組織発生を研究された動機は何だったのですか。中村 まず私が胃癌の病理を研究し始めた頃の時代背景ですが,胃癌というのは,潰瘍,ポリープ,慢性胃炎を母地として発生するという学説が一般的でした。そしてそれぞれ,潰瘍癌,ポリープ癌,胃炎癌と呼ばれていました。
私が太田邦夫先生(当時,東京医科歯科大学病理学教授)の病理学会の宿題報告のお手伝いをしていた時に,太田先生から潰瘍癌症例の組織学的な写真を撮るようにいわれました。つまり,潰瘍癌の組織診断基準を満たしている症例を集めて,写真をたくさん撮っていました。そのような時,粘膜内癌で潰瘍癌に分類される症例の潰瘍は,ほとんどの症例が癌の中にありました。Hauser typeの潰瘍癌といわれる,潰瘍の辺縁における小さな癌というのはほとんどなかったのです。
癌の中に潰瘍があるという病変は,潰瘍癌化説からすれば,癌は潰瘍辺縁で多中心性に発生しているか,または1か所から発生して潰瘍の周りを広がっていくかのどちらかになるわけです。潰瘍癌の発生は潰瘍辺縁の1か所から発生する単中心性か,多中心性発生かということについて,潰瘍癌の写真を太田先生に見ていただいていた時に質問をしたところ,太田先生が「その問題で困ってるんだよ」とおっしゃったのが非常に印象的でした。
馬場 そこで,「どうもおかしいぞ」と思われたんですね。
中村 そうです。この問題はしばらく,そのままになり忘れていましたが,ある時,ふとこの問題を思い出したのです。潰瘍の後に癌ができるのであればそれは因果関係である。しかし潰瘍癌の組織診断基準といわれているHauserの基準,村上忠重先生そして太田先生による基準にしても,その因果関係を物語る所見が何もない。因果関係があるなら,組織診断基準に時間の前後関係を示す所見がなければなりません。
馬場 それで時間の要素を取り入れられたのですね。
中村 時間を物語るものは何かと言えば,場を同じにして発育している粘膜内癌の大きさです。場というのは粘膜内のことですが,癌発生からの連続的な経過時間の指標となる所見は,粘膜内癌の大きさしかないと考えたわけです。
そこで,粘膜内癌の大きさ別に潰瘍を伴っている癌の頻度を調べたところ,見事に癌が大きくなるほど潰瘍を伴っている率が高くなっていました。「大きい癌ほど潰瘍癌の率が高い」ということは,潰瘍の癌化によって癌ができるのではなく,「癌の潰瘍化」であると言うことができます。
馬場 「癌の潰瘍化」と「潰瘍癌」の基準がまったく一緒であるということがわかったわけですね(笑)。
中村 本当に潰瘍に癌化が起こるかどうかは,微小癌が潰瘍の辺縁ではなく潰瘍の瘢痕内に限局して存在している頻度を調べればよい。つまり,微小癌を探して,それを調べるより他に方法がありません。
当時,微小癌は臨床ではほとんど見つけられない状態でした。そこで,切除胃を全部切り出して微小癌を見つける以外に方法はないということで始まったのが,微小癌発見のための全割標本作製です。馬場先生にも手伝っていただいてずいぶん悩ませた,あれです(笑)。
馬場 でもあのおかげで,微小癌の特徴がわかるようになりました。不整形で,辺縁がポコッと隆起しているような。今でも臨床の役に立っています。
中村 微小癌が病理検査で見つかるようになり,そのような時に「微小癌が内視鏡,レントゲンに写っているのではないか」ということで,熊倉賢二先生,高木国夫先生と話をして,病理で発見された微小癌症例のレントゲンと内視鏡のretrospectiveな検討を箱根の姥子にあるホテルで,徹夜でしました。そこで初めてレントゲン,内視鏡ともに写っている症例を2,3例見つけることができました。
馬場 すると,微小癌の診断というのは,臨床よりも病理のほうが早かったということですか。
中村 微小癌はそうですが,粘膜内癌は臨床のほうが早かったです。
馬場 でも当時は,粘膜内癌を認めない病理の先生がいらっしゃいましたよね。教授の先生は「これは癌とは言わないんだ」,でも助教授の先生のところへ行くと「これは癌でいいだろう」とおっしゃる(笑)。
ポリープ癌説への異議
馬場 ポリープ癌も,潰瘍癌と同じように先生が否定されたわけですが,それは高木国夫先生のバイオプシー,内視鏡的な診断と同時期ですか。中村 1964年頃から,高木先生がファイバースコープの横に鉗子をビニールテープでくくりつけて,それを使って病変部からマッチ棒の頭ぐらいの組織を採取し,私はそれの診断をしていました。初めのうちはよくわからなかったですね。手術材料では大きな粘膜内癌や進行癌しか見ていないでしょう。小さな生検組織について,異型上皮が採取されると,それが癌なのか癌でないのかがよくわからなかった。
馬場 私が癌研の先生のもとで研修することになり,上京した折がちょうど生検組織の診断基準の案づくりの時期でした。
中村 その頃は1-2cmの扁平隆起などが生検でかなり見つかっていましたが「癌の疑い」ということで,すべて手術をしていたわけです。そこから異型上皮の良性,悪性はどうやって鑑別したらよいのだろうかという研究が始まったんです。潰瘍癌の研究とだいたい並行してやっていました。
馬場 ポリープ癌か異型上皮の癌の中に微小癌のようなものが見つかれば,ポリープから癌が発生すると確実に言えるということになったんですよね。
中村 ところが,実際に調べてみると,それはあまりないのです。つまり,ポリープの中における微小癌の存在をもってポリープ癌とみなすことができますが,そのような症例はきわめてまれです。
馬場 実際にはそうですよね。
中村 ただ当時は潰瘍癌にしろ,ポリープ癌にしろ,その学説の全盛期でしたから,はっきり「少ない」と言うのはきついんですよ。周りから「この若造,何を言うか」と袋叩きにあいますからね(笑)。そのような時代に,村上先生はずっと耳を傾けてくださいました。1976年9月に,村上先生とチリへ行った時に,飛行機の中で長時間もろもろのこと,私的なことをも含めてお話しくださったこと,今でも鮮明に思い出すことができます。
馬場 村上先生はその頃,「癌は潰瘍を起こしやすい」として悪性サイクルということを提唱されましたね。
■臨床診断に必要な胃癌の知識とは
馬場 この本のプロローグにある「胃癌の構造」の図(図1)によると,「大地の木の根」が腫瘍病理学の前提で,「木の幹」が微小癌をもとにした組織発生ですよね。次の「枝葉」のところに多くのテーマがありますが,中村先生はそれらの研究を系統的になさってきました。その中で,私たち臨床診断をする医師にとって大事なことがいくつかあると思います。例えばlinitis plastica型癌の発生,発育をまとめられて,「linitis plasticaへの小径」という名前をつけておられますよね。
その他にも,先生から見て「これは知っておいたほうがいいよ」というものは何でしょうか。
中村 やはり胃底腺粘膜領域を限界づけるF境界線内部領域から発生した癌,つまり胃底腺粘膜から発生した癌でしょうね。
なぜかと言うと,微小癌の研究において,胃固有粘膜からは腺管形成傾向のきわめて弱い未分化型癌が発生するという結論が出たのです。そうすると,胃底腺粘膜も固有粘膜の1つですから,そこから「発生する癌は未分化型癌でなければならない」という命題が出てきます。
胃癌の好発部位はというと,幽門前庭部ですよね。胃体部から発生する癌は,幽門前庭部に比べると少ない。実際,微小癌のほとんどは幽門前庭部から見つかっていました。これを胃全体に一般化するためには,やはり,胃底腺粘膜から発生した癌の組織型は未分化型癌であるということを証明する必要があったわけです。
そこで胃底腺粘膜から発生した癌を調べるために,胃底腺粘膜に囲まれている癌の組織型を調べてみたところ,やはり未分化型癌が多いということがわかりました。次にはそれらの癌は,胃底腺粘膜から発生したと言えるかどうかということが,問題になってくるのです。
馬場 癌が発生した時,そこが確かに胃底腺粘膜だったという証明ですね。
中村 それを証明するためには,腸上皮化生のない胃底腺粘膜領域を限界づける線の経時的な動きを知っておかなければいけません。なぜなら,ある程度の大きさの癌は,ある程度時間が経過しているわけです。その癌が発生した時点,すなわち微小癌であった時も,そこは胃底腺粘膜であったことを証明するためには,そこには腸上皮化生がなかったことが条件ですから,腸上皮化生のない境界線,つまりF線の動きを知っておく必要があるのです。
そして調べてみた結果,F線は不可逆的に変化していました。
馬場 いったん萎縮してF線が上がったら元に戻らないということですね。
中村 そうです。
馬場 先生は,F線をある大きさの粘膜面をもって定義されたのですが,これにも反論があったのではないかと思います。当時は細胞単位で,壁細胞があるところが胃底腺だとか,点のレベルの定義が多かったですよね。
中村 そうです。そのように点で定義する,つまり壁細胞の出現部をもってF線の定義をすると十二指腸粘膜に壁細胞が出現する頻度はかなり高いので,そのように定義すると変なことになります。比較的スムーズに受け入れられましたね。おそらくそこに着目している人があまりいなかったからですかね(笑)。F境界線を調べるのは大変ですから。そのうちに内視鏡での染色法であるコンゴレッド法が出て,F線の動きが立証されました。
その後,癌の大きさにかかわらず胃底腺粘膜領域の組織型は,99%が未分化型癌であることがわかりました。『胃と腸』(29巻10号:1994年)で特集を組んで,統計を出しましたね。
馬場 私も確かその号に論文を書いたと思います。分化型癌は全部合わせても1-2%だったと思います。
中村 95%以上が未分化型癌であるということは,「確率事象」ではなく「確実事象」です。
馬場 当時は未分化型癌から分化型癌になるという人,一度分化型癌になってから未分化型癌になるのだという人がいて,組織の多様性を見て推論しているようなところがありましたね。
中村 腫瘍病理学の前提である「癌はそれが発生した臓器・組織の構造・機能を模倣する」ということからすれば,固有粘膜から発生する癌も腺管をつくらないはずはありません。ただ,その頻度は少ない。これが胃固有粘膜から発生した癌,胃底腺粘膜から発生した癌の特徴なのです。
馬場 それが胃底腺領域の癌を調べたことで証明されたわけですよね。
中村 そうです。癌は正常粘膜を模倣するから,腺管をつくらないわけはない。胃底腺粘膜から発生した癌でも,5%はちゃんと腺管をつくっているということです。
馬場 胃癌は腺癌ですから,当たり前と言えば当たり前ですよね。ただ,その頻度が非常に少ないというだけで。先生はこのことを組織発生の大前提,腫瘍病理学の大前提としてあげられていますね。
中村 そうです。そして胃底腺粘膜内の癌を調べている間に,その中にlinitis plastica型癌が出てきたわけです。
馬場 スキルス型,LP型ともいいますね。
中村 linitis plastica型癌の原発巣が幽門前庭部に発生した癌であれば,自覚的・他覚的にもっと早期に必ず見つけることができるでしょう? それなのに,非常に手遅れの状態で見つかることが多い。ということは,症状が出にくく,しかも原発巣の発見が難しい部位であるはずだ,となるわけです。そして,そこはどこかということになるでしょう?
馬場 自由に伸び縮みをするような胃上部または体部ですね。幽門部であれば症状が出やすいということですね。
中村 そこでまた,linitis plastica型の癌を全割標本にし始めたわけです。それによって,原発巣が胃底腺粘膜に囲まれている癌がどのくらいあるかということを調べたわけです。その結果たくさん存在することがわかり,やはりlinitis plastica型癌は胃底腺粘膜から発生した未分化型癌だというところに行き着いたのです。
馬場 その臨床的な証明になったのが,胃底腺領域の小さい癌を一生懸命見つける努力を続けていたら,結果的にスキルス型癌,LP型癌が減ったという東京都がん検診センター(当時)の西沢護先生一派の研究です。臨床での証明というのは,時間もかかりますし大変なことですよね。立派な研究です。
中村 本当にそうだと思います。
馬場 先生も早期胃癌の発育曲線を調べられた際には,数多くの経過症例を対象にしておられましたが,これを集めるのも苦労されたのではないかと思います。
中村 あれは芦沢真六先生と高田洋先生が,日本消化器内視鏡学会で癌の発育経過についてのシンポジウムを企画された時に,私が「内視鏡的にretrospectiveに微小癌にまでたどれた症例で,手術時点での面積とフォローアップ時間がわかれば,最小二乗法により癌の発育速度がだいたい計算できる」と,芦沢先生に提案したのです。そうしたら,「うん,やってみよう」ということになり,各施設からそういった症例が80例ほど集まり,それで計算してみました。
そして導きだされた関数は「S=0.3t2-1.1t+3.5」(S=癌表面積,t=時間)となり,発育係数はどうも0.3であるということがわかりました。一方,大雑把な方法ですが,胃癌組織発生の観点から,胃癌の発育速度を理論的に計算することができ,その発育係数は0.1,0.2,0.3が得られていました。実際症例から導かれた結果0.3と一致したわけです。
■臨床に有用な「胃癌の三角」
馬場 中村先生は「胃癌の三角」(図2)という臨床診断の概念を提唱されていますよね。聞きなれない言葉ですが,命名されたいきさつについてお聞きしたいのですが。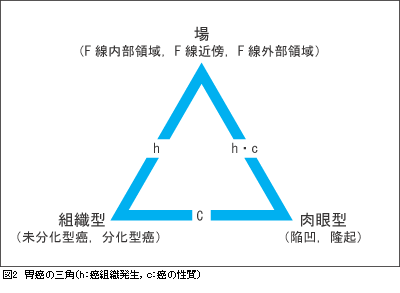
中村 胃癌というものは,組織発生から分化型癌,未分化型癌の大きく2つに分けられます。また癌の存在は場があってはじめて存在しうるわけで,場なくして癌はあり得ません。したがって,場と強い関係があるということになります。
それともう1つ,組織型を大きく2つに分けると……。
馬場 X線・内視鏡所見,ないしは肉眼的に所見の違いがあるということですね?
中村 そう。所見の違いがあります。その間,つまり場と組織型との間を結びつけているのが癌の組織発生で,組織型と肉眼型の間を結びつけているのは,癌のそのものの性質ということになります。そうすると肉眼型と場との関係というのは2つの合成関数ということになりますから,「これは三角関係じゃないか」と気がついたわけです。
このように関連づけて覚えるのが,非常に単純化されていて臨床的に使いやすいのではないかと思ったわけです。
馬場 普通ですと,ここに時間の要素を入れたりして複雑になるので,3つに分けることができませんよね。これを見て,大きさが違うじゃないかとか,発生の時間的なファクターが必要じゃないかと言う人がいると思いますが。今までの先生の理論には,経過時間や動きといった要素が入っていましたよね。
中村 時間,つまり癌の大きさを入れて,「子どもの胃癌の三角」と,「大人の胃癌の三角」というのをつくればいいんですよ(笑)。この図は主に「早期胃癌の三角」ですね。
馬場 これが臨床の診断にどのように役立つかということが問題になりますが,大事なことは,この考え方,全体の関係を生かすということですよね。
例えば生検で分化型IIcと思ったら未分化型癌が出たといった場合,なぜそこで矛盾が出たかということを,もう一度この図に当てはめて考えていく。そして,分化型癌だとみなしたところに,どこか論理的な間違いがあるはずだと,自分で診断の過ちを修正できる。それがこの「胃癌の三角」のよいところだと思います。
中村 飛行機のバックアップシステムと同じですね。要するにフェイルセイフシステム(fail-safe system)。1つのシステムが故障しても他にもう1つのシステムがあって,それによって飛んでいくことができるというものです。
馬場 実際の臨床診断では,早期癌の大部分は肉眼だけで診断できますから,「場」が大事にされないんですよ。とはいえ,小さい癌や境界があまりはっきりしない癌の診断ということになれば,とたんに場が重要になります。
ですから,内視鏡の先生たちがもっと場を大切にしてくれるといいなと思っています。発育進展様式まで違ってきますからね。今の臨床診断では分化型癌・未分化型癌というのは用語として確立していますから,これと関係のある場の考え方が臨床の場にもっと応用されるとよいと思います。
中村 胃癌というものを全体的に眺めて,枝葉を落として集約していくと,この「胃癌の三角形」になるのだと思います。
フィルターとしての知識
馬場 中村先生は,2000年3月に東京医科歯科大学の病理学講座を退官される際,「胃癌・大腸癌の構造」について最終講義をされましたが,その中で「強い問題意識と深い思索と」そして「新しいうねりは既存の知識の破壊から始まる」と話されました。まさに先生の研究がそうだったわけですが,「強い問題意識と深い思索と=素朴な問題意識と単純な思索と」というのは,私も大好きな言葉です。中村 そう,単純な思索です(笑)。また,なんでも破壊すればよいというものではなく,そこには論理的な矛盾を明らかにして初めて破壊があるのであって,理由なき反抗であってはならない。ジェームス・ディーンの映画『理由なき反抗』というのがありましたね(笑)。
馬場 何にでも「おかしい」「なぜだろう」と感じることも大事だということですね。問題には誰でも気づいても,先生のように論理を展開していくのはなかなか難しいことだと思います。
最後に若い研究者や,臨床医に向けたメッセージをお願いしたいと思います。中村先生は「おかしな所見があった,生検した,病理診断をした,癌だった,癌ではなかった」では駄目だとおっしゃっていますよね。
中村 胃癌の術前診断において「生検組織を採取すればわかる」という短絡的発想は,極端に言うなら,医師たることを放棄していることにも通じるのではないかと思います。やはり病変が呈する所見の意味を知らないで,診断能力の向上はありえません。たとえ手技に熟練していても,「病変の知識」という名のフィルターがないと,在れども見えずの状態のままにとどまるのではないかと思います。長い間,胃と大腸の生検組織診断をしてきましたが,内視鏡診断と生検組織診断の食い違い例の検討からそのように感じています。
馬場 この『胃癌の構造』というフィルターを通すことで,癌の性質とか,発育とか,癌によって生じる変化までがわかるということですね。胃癌の内視鏡治療が盛んに行われるようになりましたが,その適応を決めるうえでも胃癌の診断学がいっそう重要になってきています。その意味で本書を臨床の先生方の必携の書としていただきたいと思っております。本日はありがとうございました。
(終了)
 |
中村恭一氏
1959年東医歯大卒。病理学・太田邦夫教授に師事。65年に(財)癌研究会癌研究所を経て,75年に筑波大教授,91年には東医歯大教授。2000年より現職。71年に第20回総合医学賞,81年に第6回『胃と腸』賞を受賞した他,90年にはチリ共和国政府より『Bernardo O'Higgins勲章』を受ける。91年国際協力事業団総裁感謝状,95年に日本国外務大臣表彰を受ける。 |
| 馬場保昌氏
1969年久留米大卒。71年より(財)癌研究会癌研究所にて中村恭一氏のもとで研修。73年からは同附属病院内科にて,熊倉賢二氏のもとで研修。77年同附属病院内科医長,内科副部長,総合健診センター所長を経て,2001年より現職。96年には「X線的胃小区像からみた背景粘膜の質的診断」の論文(95年『胃と腸』掲載)で白壁賞を受賞。 |
 |
