寄稿
病理診療外来の奨め
田村浩一(日本医科大学付属病院病理助教授)「組織検査の結果,悪性の疑いがあります。他にもいろいろ検査をしますが,手術を前提に入院してください」
外来での説明としては珍しい光景ではないだろう。患者は頭の中が真っ白になったまま,「よろしくお願いします」と答えるしかなく,その後はベルトコンベアのような治療のレールに乗せられる。
最終診断の根拠となった病理診断は,病理医のレポートを見た臨床医から伝えられる。患者にショックを与えないように,レポートにはない「疑い」などという言葉を付けて説明されることもあるだろう。
「十分な説明に基づく納得の医療を」と言われる中で,病理診断については,「詳しく説明しても(自分にだってよくわからないのだから)患者にわかるはずはないし,短時間でわからせるのは無理である」という臨床医の気持ちと,「説明に必要なことは診断レポートにすべて書いてある」という病理医の独りよがりな言い分が見え隠れする。患者が実際にどこまで説明を受け,納得しているのかは疑問と言わざるをえない。
病理診療外来のメリット
病理診断の所見を病理医が直接患者に説明する機会を設けたい,と当院では2003年から病理診療外来を開設している。院内患者への診断結果説明の場だけでなく,院外からのセカンドオピニオン外来の1つとしての機能もある。(詳細はhttp://jsp.umin.ac.jp/opinion/tamura_050107.pdf参照)。患者にとっての意義はまず,自分の病気を眼で見られるという点にある。いきなり「がんだから手術する」と言われても,(理論ではなく気持ちとして)受け入れきれない患者が,実際の標本を見ながら病理所見の説明を受けることで納得し,その後の治療へと気持ちを切り替える。あるいは手術後に,自分の身体から取られた腫瘍組織の顕微鏡像を見て,結果を納得する。このような例を経験すると,データではなく現物を見せられる形態学の強みを感ずる。臨床医にとっても,患者や家族の理解度を増し,治療への協力を得るために役に立っている。もちろん病理診断をした医師に直接会って話をすることも納得につながるし,病理診断名だけではわからない病気への理解が深まるという点でも大切な意味を持つ。
臨床診断に対するセカンドオピニオンとして,第三者である病理医の意見を求められる場合もある。外科医とは別に内科医の意見も聞いてみたい,というものと同じであり,診断のプロとして,また病理解剖の経験を含めて「病気の本態の解明」を生業とする病理医の意見を求める意義は大きい。結果として多くの場合,臨床医にとっても自分の診断や治療の裏付けが得られることになる。
患者の正確な疾病理解のために
院外から病理診断を含めたセカンドオピニオンが求められた場合,多くの病院では臨床科の医師が対応し,標本だけが病理診断部にまわされる。しかし担当の臨床医が「病理診断レポート」を渡して説明するだけでは,「あっちの病院ではがんと言われ,こっちではがんではないと言われ」という事態も生じうる。「その道の大家」の診断と,病理専門医になりたての病理医がつけた診断の重みの違いが,正しく患者に伝わるとは限らず,自分の望む診断名を求めて病院めぐりをする患者や家族を生むことにもなる。診断名を伝えるだけでなく,病理診断はどのようにくだされているのかを含めて説明し,なぜ診断名に違いが生じたのかを理解してもらい,さらに実際にこれからどうすればよいのか,という相談に乗るのが患者のためではないだろうか。それには,臨床医とともに病理医が直接患者や家族に会って,標本を一緒に見ながら説明するのがいちばんよいと考えられる。
外来開設に必要なこと
病理診療外来は,病院にとって直接の収益には繋がらない。しかし医療サービスとして,さらに医療の質の改善を図るための病院側の努力として患者の満足度につながり,結果として病院の評価があがるはずである。病理は標榜科になっていないが,病理外来の設置は院内に専門の病理医がいることを明瞭に示すことにもなる。これまでも,患者に直接病理診断結果を説明したり,セカンドオピニオンを受け付ける病理医はいたが,多くは個人のボランティアの形であった。その場合,診療としての記録をどう残すのかが,責任の所在とともに問題が残る。日医大の病理診療外来では,事務を医療連携室が担当し,予約の受付,部屋・担当医・相談者の時間調整,費用の請求,診療記録の管理,紹介元病院と相談者への報告書(外来終了後に担当医が作成)の送付などを行う。特別外来に必要なのは,シャーカステン,病理標本を提示するための顕微鏡と画像投影装置(コンピュータ・モニタ・プリンタ)程度であり,これらをプライバシーが保てる部屋に設置し,遺伝外来,糖尿病看護外来,IVR外来と共用で利用している。なお日医大病理診療外来では,剖検結果の説明は行っていない。
臨床医との協力体制が鍵
病理診療外来の開設がスムーズに進むためには,まず患者や一般市民の方々の理解が第一である。病院の採算性を理由に外来開設に至らない病院の病理医たちは,一般の方々からこのような外来を要求する声があがることを期待している。もちろん,臨床医の理解がなければ成り立たない。多くの臨床医が,「病理診断は大切である」と言いながら,どこかで「数値で結果の出る検査」と同じ感覚で扱ってはいないだろうか。病理診断の内容や,判定の難しさをよく理解している臨床医ほど,始めから病理外来に好意的に対応してくれる。病理側からは必ず,臨床と説明が異なったら患者が混乱するのではないか,あるいは,臨床側とトラブルになるのは困るという声があがる。患者がそれを聞けば,自分の書いたレポートは何なのか,臨床医が勝手に解釈して説明しても構わないと思っているのか,と言われかねない。病理の診断はそれだけ重い,というならばなおさら,そのような理由で外来開設を躊躇すべきではないだろう。
臨床医にとって,正確なインフォームドコンセントに努めることが患者との関係を悪くするはずはない。むしろ病理外来をきっかけとして,臨床と病理の連絡を密にし,お互いにより深い信頼関係を築くように努力すべきではないだろうか。要するに,患者のためにどのような協力体制が取れるかが問題であると思う。
病理医の役割に理解を求めたい
日本病理学会でも,一般の方々に病理診断のことを知ってもらおう,患者から顔の見える病理医を目指そう,と広報活動を続けている(http://jsp.umin.ac.jp/public.html)。病理専門医は広告できる専門医の1つであり,実技試験や面接試験を含む厳しい試験で認定されている。その数は全国で1924人(2005年現在)しかいない。中規模の病院で常勤病理医のいないところは少なくない。いても1人だけ(1人病理医と呼ばれる)で細胞診,組織診から剖検,臨床研修医の指導まですべてを担当している。その仕事量を考えると,病理医すべてに病理外来を担当しろと言っても無理である。また,通常の外来と異なって1回30分以上を要するので,多くの患者を対象にはできない。したがって,大学附属病院など複数の病理医がいる病院,がんセンターなど専門病院,患者と話すことに慣れている臨床からリクルートした病理医がいる病院,などに開設を求めるべきであろう。担当日を決めた特殊外来を開かずとも,患者が相談できる「体制」のある病院を増やすことが大切だと思う。できれば各都道府県に1か所あるのが望ましいが,これは病理医の数およびその適正配置の問題とも関連してくる。そのような体制のある病院が増えれば,病理のセカンドオピニオンを求めて病理医が(担当臨床医と相談して)患者を紹介できるようになり,患者にとっての意義も大きい。
病理診療外来は一般の診療と異なり,患者および臨床各科の理解と要望がなければ成り立たない。一方で,不足している病理医を増やすことも急務と言える。病理医に対するご理解とご支援をいただければ幸いである。
◆日本医科大学付属病院病理部HP
http://www.nms.ac.jp/nms/h/byouribu/
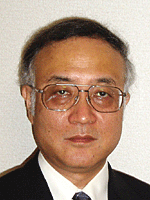 |
田村浩一氏
|
