(前回よりつづく)
前回は「重心移動の原理」によって筋力に頼らない上体起こしをご紹介しました。今回は「バランスの活用」という原理を用いて,長座状態からの立ち上がり介助を行います。前回と同じく重心移動を活用しますが,バランスのコントロールを更に精密にすることによって,通常では考えられないチカラを発揮する方法をご紹介します。
長座位からの立ち上がりを1人で介護!
 車椅子やベッドから被介護者の方がずり落ちてしまい,持ち上げなければいけない。その他の場面においても,長座状態からの立ち上がり介護は,施設でも家庭でも頻繁に直面する問題かと思います。そして,1人で力任せに行うと介護者の腰に相当な負担がかかります。
車椅子やベッドから被介護者の方がずり落ちてしまい,持ち上げなければいけない。その他の場面においても,長座状態からの立ち上がり介護は,施設でも家庭でも頻繁に直面する問題かと思います。そして,1人で力任せに行うと介護者の腰に相当な負担がかかります。
図1では,被介護者の後ろから手を回し,胴をしっかり持ち,両足を踏ん張って土台を安定させ,足腰に力をいれて持ち上げています。これは一般的な力の使い方だと思いますが,これではよほど筋力があるか,相手が軽くない限り,なかなか持ち上がりません。実際,現場でもこの方法で無理して持ち上げようとして,腰を痛める方がいらっしゃいます。
バランス感覚が鍵!添え立ちのポイント
こうしたケースでは,以下にご紹介する「添え立ち」(図2)を活用することで,介護者・被介護者双方に負担をかけずに介護できます。「添え立ち」には,さまざまな「チカラ」が複合的に使われていますので,図の解説をよく参照してください。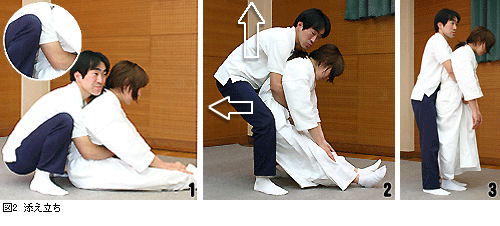 |
|
-1 両足を肩幅に広げてしゃがみ,腕を自分の膝と相手の胴の間に挟み,相手の胴に手を回す。足を置く場所は「足裏感覚」で決定。
-2 後方へ倒れつつ,お尻を上に突き上げていく。後ろに倒れる力と,上方向に立ち上がる2つの力が合成されて,斜め後ろ方向の力が生じる。 -3 うまくいくと,ほとんど腕の力をつかわなくても相手が立ち上がってくる。 |
1つ目のポイントは「自分の腕を自分の膝で挟む」ということです。普通に相手の胴に腕をまわすと「相手の胴を挟み,固定する」ために腕の力を使ってしまうことになります。腕を膝の内側に挟みこむことで,腕の力を使わずに,両腕で相手の胴をロックすることができるのです(図2-1)。
また,胴に手を回した時には,第2回(本紙2643号)でご紹介した「キツネさんの手」を利用するとさらに強力です。中指と薬指を曲げ,その2本の指だけをもう一方の手の手首に引っ掛けるようにします。これも,腕をロックするために余計な力を使わないための工夫です。
2つ目のポイントは足の位置。これが「添え立ち」の要となりますが,重要なのはこれを「足裏感覚」で決めることです。図2-1の体勢から少しだけ後方に倒れてみてください。自分と相手との間にバランスが保たれるような「足裏感覚」が生じたら,そこがベストポジションです。
体勢ができたら一度,後方へ倒れこんでみましょう。すると,自分と相手が尻餅をつくような状態でずるずるっと後方へ引っ張ることができると思います(図3)。その時,自分の力はほとんど使ってないのに相手を引っ張れたということに注目してください。筋力をつかわずに後ろに引っ張る。これだけでもベッド上での移動などに活用可能な技術ですが,「添え立ち」ではさらに,上方向の「立ち上がる」動きを加えなければいけません。
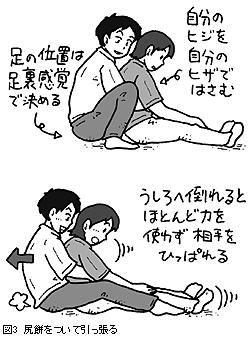 図2-2を見てください。立ち上がりの瞬間です。ちょうどエビが泳ぐような姿勢です。相手との間に常にバランスを保ちながら(綱引きの綱がピーンと張ったような状態で),斜め後方に倒れていくことによって,立ち上がらせるのです。つまり,後ろに倒れていく力と,上に行く力の合成によって,斜め後方の力を生じさせるわけです。
図2-2を見てください。立ち上がりの瞬間です。ちょうどエビが泳ぐような姿勢です。相手との間に常にバランスを保ちながら(綱引きの綱がピーンと張ったような状態で),斜め後方に倒れていくことによって,立ち上がらせるのです。つまり,後ろに倒れていく力と,上に行く力の合成によって,斜め後方の力を生じさせるわけです。
この時,ついつい日常のクセが出てしまい,腕の筋力で相手を引き上げようとしてしまう方がよくおられます。しかし,筋力を出すためには足場を安定させなければならないため,その瞬間,後ろへ倒れる動きが止まってしまうことになります。その結果,筋力のみで持ち上げるような形になってしまい,失敗してしまいます。また,後ろに倒れてしまう恐怖感から,立ち上がり始めた時に足を踏ん張ってしまう方も多いようです。これも同様に,失敗の原因になります。
このバランス感覚は,前回の重心移動よりもさらに難しい感覚だと思いますが,うまくいくと相手はまるで浮き上がるように,すっと立ち上がってきます。通常の方法との差は歴然ですので,同僚と練習する場合は交代で被介護者役も体験してみてください。私自身(体重56kg),最近の講習会で105kgの方を楽に立ち上がらせることができました(私も周囲もかなり驚きました)。
介護する人が介護される!?
もちろん「添え立ち」は万能ではありません。介護現場にはいろんな方がいらっしゃいますから,使えない場面も多いでしょう。そもそも介護者を2人確保できるなら,そのほうが絶対楽で安全です(笑)。しかし,たとえ実際に使うことがなかったとしても,「添え立ち」を練習する意味はあると私は思います。それは,「添え立ち」を練習することを通じて,新たな身体の使い方,ひいては発想の転換を体験できるからです。
通常の介護では,介護者の力で被介護者を動かします。しかし「添え立ち」では,介護者が倒れるのを被介護者に支えてもらい,両者のバランスの中で生じた力を活用しています。「立たせた」のでなく「結果として立ち上がった」のです。これは,介護する人が,介護される人に助けられている関係とも言えるでしょう。「添え立ち」は,こうした古武術独特の「発想の転換」を積み重ねてできています。ぜひ,ご自身の身体で発想の転換の楽しさを実感していただきたいと思います。
難易度は「自転車」程度
とはいえ,今回の「添え立ち」には,かなり苦戦する方が多いと思います。また,後ろに倒れるということについて,「危険で実用的ではない」という感想もあるだろうと思います。確かに,練習せずにいきなり行うと危険です。無理をして失敗すると腰を痛めることもあります。しかし,極端に危険で難しいわけでもありません。私がこの技術を覚える時に感じた個人的な実感としては「自転車の乗り方を覚える」くらいの難易度です。
自転車というのは,冷静に考えると不安定で危険な乗り物です。しかし,多くの人が練習によってバランス感覚を養い,乗りこなしています。もし,安全第一だからと補助輪をつけることを義務づけられていたら,ずいぶん乗りにくくなるでしょうし,ここまで普及することもなかったでしょう。自転車は不安定だからこそ動きやすいのであり,それをコントロールしているのは,訓練されたバランス感覚なのです。
「添え立ち」も,自転車と同じくバランス感覚がポイントです。自転車の練習って,小さな頃は転んだりしながら,ずいぶんやりましたが,気がつけば乗れていましたよね。ちょっと昔に戻ったつもりで楽しみながら練習すれば大丈夫。みなさんの中にあるバランス感覚が目覚め,実践でも使いこなせる技術になると思います。
次回は,今回のバランス活用の感覚を踏まえた実践的練習法とともに,表面からは見えない,気がつきにくい「体幹内処理」の原理を通して「添え立ち」の技術をさらに深めてゆきましょう。
イラスト:海谷 和秀
(次回につづく)
●岡田慎一郎氏講習会情報
◆新宿教室(tel:03-3344-1945)
|
岡田慎一郎氏プロフィール
介護福祉士,介護支援専門員。古武術の身体操法を応用した介護術を研究。岡田慎一郎氏への質問・講演依頼等は岡田慎一郎氏公式サイト(http://shinichiro-okada.com/)まで。
|
|||||||||||||||||
【関連情報】
●岡田慎一郎氏の最新刊 『DVD+BOOK 古武術介護実践編』 (動画配信中!)
●岡田慎一郎氏が最新技術を紹介する「こんな方法もあるかもしれない――介護発,武術経由の身体論」は,『看護学雑誌』で2008年1月号(Vol.72 No.1)より2010年3月号(Vol.74 No.3)まで連載。電子ジャーナル「MedicalFinder」からも検索・閲覧・購入できます。
●岡田慎一郎氏の公式サイトは こちら です。


