MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


野村 総一郎,樋口 輝彦 編集
《評 者》神庭 重信(九大大学院教授・精神病態医学)
時代に即応し,精神医学の ロマンを伝える上質な教科書
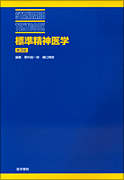 編者と執筆者とが一体となって教科書作りを楽しんだ,そんな印象を与えるのが本書である。章による出来不出来や体裁の不統一が少なく,分担執筆の強みが生きている。つまり,その領域を知り尽くしている専門家の手による,正確でしかも漏れのないテクストが端正な姿を見せ,しかも“厳選された”という執筆者の個性的主張がそこかしこに滲み出ているところがとてもよい。
編者と執筆者とが一体となって教科書作りを楽しんだ,そんな印象を与えるのが本書である。章による出来不出来や体裁の不統一が少なく,分担執筆の強みが生きている。つまり,その領域を知り尽くしている専門家の手による,正確でしかも漏れのないテクストが端正な姿を見せ,しかも“厳選された”という執筆者の個性的主張がそこかしこに滲み出ているところがとてもよい。
本書には編者の工夫の跡が随所に見てとれる。例えば各章は,頭に“学習目標”と“キーワード”が配置されている。これはちょうど地図を手渡されて,登ろうとしている山々の特徴を頭にいれておくようなもの,とでも言えようか。そして,それぞれの章は箇条書きからなる“重要事項のまとめ”をもって終わる。全体を理解しながら,細部を記憶しなければならない学生には嬉しい配慮である。
某大学で内科学の教授をしている同級生は,学生時代にハリソンの内科学を原文で読み,周囲の尊敬を集めていた。近年取りざたされるのは国試合格率の数パーセントの優劣であり,国試のガイドラインは年々そのボリュームを増している。ハリソンにのめり込んでいては国試に落ちるかも知れない。対策マニュアルが氾濫するのも仕方のないご時世ではあるが,本物の医学を学ぼうとする志の高い学生は少なくないはずだ。彼らには,本書が伝えようとしている精神医学のロマンや奥深さに触れてほしいと願う。
昨今,精神医学への要請が社会のさまざまな場面で高まっている。医療が最先端になるほど,患者や家族の心のケアが重要となってくる。これらの現場には,人がこれまで経験したことのない不安,葛藤,懊悩が満ちているからである。一方プライマリケアでは,今年始まったニューヨーク市医師会の取り組みのように,うつ病の早期発見とそれによる自殺予防が喫緊の課題となっている。家庭・学校・職場におけるメンタルヘルスの重要性は今さら言うに及ばない。本書は,卒前教育の枠を超えて,こうした時代の要請にも十分応えられる上質な教科書に仕上がっている。


小口 芳久,澤 充,大月 洋,湯澤 美都子 編集
《評 者》所 敬(東医歯大名誉教授・眼科学)
基本的手技から最新機器まで 眼科の検査法を網羅
 外界の情報の約80%は眼から入ると言われている。最近は高齢化が進み,これに関連して,QOLが問題になっている。視覚はQOLに最も関連が深く,視機能に関する検査法に精通することは大切である。
外界の情報の約80%は眼から入ると言われている。最近は高齢化が進み,これに関連して,QOLが問題になっている。視覚はQOLに最も関連が深く,視機能に関する検査法に精通することは大切である。
この眼科検査の大部分は眼科医あるいは視能訓練士が行うもので,内科の検査と違って中央検査部に依頼する検査はほとんどないという特徴がある。
しかも,眼科検査法は日進月歩であり,うっかりすると取り残されてしまう。また,新しい検査法の話題や記載があっても,調べる書がほとんどない。
本書は1985年7月に第1版が発刊され,1995年1月に第2版,1999年8月には第3版,2005年6月には第4版が改訂出版されている。これをみても第2版までは10年の月日が経っているが,2版から3版,また,3版から今回刊行された4版までは5-6年の間隔で改訂されている。これは眼科検査機器の進歩が著しいことを物語っていて,5年経過したハンドブックは検査法によっては使いものにならない可能性も秘めている。
特に目立つのは電子工学とコンピュータの発達,進歩である。これらの技術が眼科検査機器に応用され,今までは考えられなかったことが,可能になってきている。例えば,光干渉断層法(OCT)は網膜の断層像を光学組織切片に近い精度で画像化する方法である。これにより,網膜疾患の病態と診断に寄与する点は大きい。しかもこの装置は7-8年の間に第1世代から第3世代と改良され,画像精度も高まっている。このような装置を的確に使用できることは必要であるが,報告書に添付されてきた画像を読影できることも大切である。
この他,角膜トポグラフィー,波面センサー,FDT視野計,涙液油層観察装置(DR-1),SLOマイクロペリメトリ,ハイデルベルグ網膜断層計(HRT),走査レーザーポラリメトリ装置(GDxVCC)など,ほとんどの新しい機器について,本書には記載されている。
一方,眼科の基礎となる検査法についても,現状に即して小改訂が各所に見られる。例えば,logMARチャートによる測定法,涙液検査のメニスコメトリ法,涙道内視鏡検査などである。視力検査,屈折検査,細隙灯顕微鏡検査,眼底検査,眼圧検査は眼科においては最も基本である。研修医の方々は,これらの章をぜひ一読してほしい。
本書では,基本的手技から最近の新しい機器の手技と解釈に至るまで眼科の検査法を網羅しており,この種の本は類を見ない。第4版では編集者も執筆者も大幅な交代がなされて,次々と開発,発売されてくる新しい機器に即応している。基本的検査法は詳読し,特殊検査については本書を座右において,適時参照するようにするとよい。
診療室に本書を1冊常備することを薦めたい。


富野 康日己 編集
《評 者》堀田 知光(東海大医学部長/教授・血液・腫瘍内科学)
日常診療で陥りやすい禁忌を 厳選して解説
 まれに起きる,原因がよくわからない薬の有害事象に対して,かつて「特異体質」という用語がよく用いられた。今日では薬剤の代謝や体内動態の解明が進み,薬物の相互作用のメカニズムや効果と副作用における個人差の理由が遺伝子多型によることなどが明らかにされた薬剤も少なくない。薬物療法に関するさまざまな理解が進む中で,副作用(期待しない効果・毒性)に対して,「飲み合わせ」や「特異体質」などという経験的で非科学的な説明に頼るべきではない。
まれに起きる,原因がよくわからない薬の有害事象に対して,かつて「特異体質」という用語がよく用いられた。今日では薬剤の代謝や体内動態の解明が進み,薬物の相互作用のメカニズムや効果と副作用における個人差の理由が遺伝子多型によることなどが明らかにされた薬剤も少なくない。薬物療法に関するさまざまな理解が進む中で,副作用(期待しない効果・毒性)に対して,「飲み合わせ」や「特異体質」などという経験的で非科学的な説明に頼るべきではない。
本書は,日常診療において内科領域で「禁忌」とされる薬物療法について重要なもの100件を選んで,禁忌の種類(絶対的か,相対的か),重要度(1,2,3),内科で関連する領域,基本薬剤データ(一般名,商品名,適応,副作用,類似薬),禁忌の理由と起こりうる病態,禁忌処方をしてしまいやすい状況,同様の作用機序で発症する禁忌,禁忌処方の予防策,代替治療などについて,簡潔にまとめられている。
中には,「えっ,こんなものが禁忌なの?」と意外に思うものが含まれている。よく読むと「なるほど,そうか」と納得できる。また,自分の専門以外の領域の薬物療法が「こんなに変わったのか」と驚かされるものもある。
近年,医師国家試験において禁忌肢問題が出題され,2問を誤答するとそれだけで不合格となることから受験生には「地雷」と呼ばれて恐れられている。もっとも,国家試験レベルの禁忌は,間違うと死に至る,もしくは重篤な機能障害を残すもので,医師として基本的な能力が欠如したとんでもない医療行為が対象となる。日常の内科診療においてはこのようなとんでもない禁忌は誰でも知っており,わざわざ取り上げて解説するまでもない。むしろ,それとは知らずにやってしまいそうな禁忌や,かつては一般的に行われていたが,今日では正しくない薬物療法が問題であり,これが意外に多い。
本書は,内科のそれぞれの領域の臨床の第一線で活躍するエキスパートによる日常診療で陥りやすい禁忌を厳選して解説する従来にはないタイプの本である。内容は,当たり前とされてきた処方の最近の知見に基づく見直し,わかってきた薬物相互作用,新規分子標的薬の使い方など,「禁忌」集のスタイルをとった薬物療法の最新知見集でもある。本書は禁忌のいわばアドバンスド・コースであり,内科医,臨床研修医のみでなく,看護師や薬剤師にも役立つように配慮されている。
本書は医療現場において,薬物療法の安全性の確保と質の向上に役立つものと期待される。


月城 慶一,山本 澄子,江原 義弘,盆子原 秀三 訳
《評 者》石井 美和子(フィジオセンター・理学療法士)
歩行分析の 思考過程を学べる書
 本書の著者であるNeumann氏は,これまでに日本で計7回,「観察による歩行分析」をテーマにセミナーを開催している。私はそのうち2回ほど参加したが,セミナーは系統立ててまとめられ,非常にわかりやすく,興味深い内容であった。それと同時に,受講者側が終始講師であるNeumann氏の気迫に少々押され気味になるほど情熱的にセミナーが進められたことも印象的であった。本書は,同氏がセミナーで熱く語った「観察による歩行分析」への思いが丸々詰まっている。
本書の著者であるNeumann氏は,これまでに日本で計7回,「観察による歩行分析」をテーマにセミナーを開催している。私はそのうち2回ほど参加したが,セミナーは系統立ててまとめられ,非常にわかりやすく,興味深い内容であった。それと同時に,受講者側が終始講師であるNeumann氏の気迫に少々押され気味になるほど情熱的にセミナーが進められたことも印象的であった。本書は,同氏がセミナーで熱く語った「観察による歩行分析」への思いが丸々詰まっている。
第1章は直立歩行の歴史が記載され,ヒトがどのような過程を経て現在の歩容に至ったかを知ることで,歩行機能の必要性・必然性を考えるところから始まっている。第2章は歩行に関する基礎的事項の確認と歩行の解釈について,本書に推薦の言葉を寄せているPerry博士を中心としたメンバーが築いた「ランチョ・ロス・アミーゴ分析法」をもとに述べられている。第3章では,観察による歩行分析を遂行するにあたってのポイントが記述されている。歩行分析を実施する際の手がかりのみでなく,システマティックに分析し解釈を統合するために重要と筆者が判断したクリニカルテストの他,歩行分析シートの利用方法も記載されている。第4章で計測機器を用いた歩行分析の概要が述べられ,第5章がいよいよ本書の主要部分「病的歩行-逸脱運動の原因と影響」である。
第5章は,身体部位別に計43の逸脱運動とそれに影響を及ぼすと考えられる要素が,わかりやすい図を用いて解説されている。臨床場面で歩行を観察し,問題を捉え,介入へと治療戦略を展開するにあたって参考となる有益な情報が満載である。記載されている内容を臨床で観察した現象と照らし合わせて考えることもできるし,さらに本章では臨床的推論の組み立て方も学ぶことができる。臨床的推論の展開には,やはり多くの知識と経験が役に立ち,優れた臨床家であればその展開が早く,そして明快かつ的確である。しかし,積んだ経験が浅ければ,うまくいかないことも少なくない。ましてや臨床実習中の学生など「経験をもとに考える」ことなど到底できないのだから,さらにつまずくことも多いはずである。実際,私も,私の周囲もそうであった。いったん迷路にはまってしまうと,その後どうやって思考を修正していけばよいかわからなくなる。特に,歩行や動作で観察された現象がどのように身体各部位の機能と関連しているのかについて整理できなくなってしまうことが多い。しかしながら本書の第5章の解説を読み進めると,そこで紹介されている現象がたとえ自分の観察したものと異なっていたとしても,現象を捉える思考過程を学ぶことができるので,大いに役立つのではないかと考える。
さらに所々に盛り込まれている「注目」と「臨床におけるヒント」にはNeumann氏が臨床経験で得た知見が記載されており,これもまた本書の魅力の1つであろう。また,歩行や動作といった動きには心理的因子も大きくかかわってくる。本書では,後半の第6章・第7章でその点についても触れている。
観察による歩行や動作の分析の重要性はこれまでにも十分認識されてきている。しかし,その方法と解釈を丁寧に説いている書籍は見当たらなかったように思う。本書は理学療法士のみならず,観察による歩行分析に携わる職域の方すべてにお薦めしたい。


高木 篤 著
《評 者》鶴田 修(久留米大助教授・第2内科)
基本手技をわかりやすく 理論的に説明
 本書の著者である高木篤先生とは,東京で月1回開催されている「大腸疾患研究会」で知り合って以来,10年以上の付き合いである。高木先生は一言でいえば“大腸オタク”であるが,一般にいう“オタク”とは異なり周りの人から尊敬される“美しい大腸オタク”である。大腸腫瘍を突き詰めて検討する姿は,傍らから見ていて恐ろしいほどの根気と迫力であり頑固でもあるが,本人の納得できる助言や意見に対しては素直に対応され,それをも自分のものとして吸収し,さらに真実に近づこうという姿勢を貫いていらっしゃる。これが美しく見え尊敬されるゆえんである。また著者は,大腸腫瘍のpit patternに関してもすばらしい業績の数々を残されているが,本書を読んでみて病変の解析と同様に大腸内視鏡挿入手技に関してもコツコツとその理論を構築されていたことに気づかされ,本当に大腸を愛している人であると感心したと同時に,まさに“大腸オタク”の名に相応しいことを再確認した次第である。
本書の著者である高木篤先生とは,東京で月1回開催されている「大腸疾患研究会」で知り合って以来,10年以上の付き合いである。高木先生は一言でいえば“大腸オタク”であるが,一般にいう“オタク”とは異なり周りの人から尊敬される“美しい大腸オタク”である。大腸腫瘍を突き詰めて検討する姿は,傍らから見ていて恐ろしいほどの根気と迫力であり頑固でもあるが,本人の納得できる助言や意見に対しては素直に対応され,それをも自分のものとして吸収し,さらに真実に近づこうという姿勢を貫いていらっしゃる。これが美しく見え尊敬されるゆえんである。また著者は,大腸腫瘍のpit patternに関してもすばらしい業績の数々を残されているが,本書を読んでみて病変の解析と同様に大腸内視鏡挿入手技に関してもコツコツとその理論を構築されていたことに気づかされ,本当に大腸を愛している人であると感心したと同時に,まさに“大腸オタク”の名に相応しいことを再確認した次第である。
次に,本書を読んでの感想を列挙させてもらう。(1)理論的でわかりやすい。ほとんどの挿入パターンがわかりやすく図説されており,非常に理論的である。私自身,何気なく操作してしまい,理論などあまり考えなかったことが本書では何か所も理論的に図説してあり大変ためになった。(2)基本的操作を十分に解説してある。挿入に関する基本手技がほぼ完璧に記載され,初心者にとってはこれ以上ないと思われるくらい懇切丁寧に説明してある。(3)すべての手法・理論を解説した後に部位別挿入法が記載されている。これにより,部位によりある程度の違いはあるが,挿入手技が複雑で難しいものではなくほとんどが基本的操作の繰り返しで盲腸への到達が可能ということが理解できる。(4)正直である。ループを形成せず,患者の苦痛のないように挿入するのがベストであり,実際ほとんどの症例でそれが可能であるかのように説明している解説書の多い中,少なからずループは形成されることを正直に述べ,どうしてもループを形成する症例において疼痛を最小限に抑えるコツを手技面やスコープの選択などから解説してある。これらの理由だけでも本書が優れていることは理解できると思われるが,「チョットひといき」,「大技小技」のコーナーでは著者の本音や経験談が記されており,さらに親切な内容になっている。
最後に,本書はこれまで私が読ませてもらった大腸内視鏡挿入手技の解説書の中で最も優れた内容に仕上がっており,これから大腸内視鏡検査を始めようとする初心者はもちろんのこと,中級者以上,さらには教育に携わる上級者にもぜひお勧めできる1冊である。


Lippincott's Illustrated Reviews
Pharmacology, 3rd edition
Richard D. Howland 他 編
《評 者》柳澤 輝行(東北大大学院教授・分子薬理学)
必要不可欠な薬物知識を コンパクトに凝縮
ダイナミックに変貌し続ける薬物治療や創薬の基礎として,医療人は薬理学を学び続けなければなりません。学習者への配慮で,米国の,いや世界の学生にインパクトを与えたLIRシリーズの『薬理学』第3版が8年ぶりに出版されました。第2版の翻訳を監修した者として,本書の改版が楽しみでした。統一性ある573枚ものイラストがフルカラーになり,内容も大いに刷新・改訂されているのに衝撃を受けました。平易な英語本文,病態に基づいた薬物の作用機序や動態,副作用のカラー図解は読者の理解と記憶を助けます。できたら抗菌薬のパイグラフや血栓形成・高脂血症の図を手にとって見てください。
章立てが旧版に比べ普遍化され構成が洗練され,薬理学と臨床系内容との対照がしやすく,コア・カリキュラムにも対処できます。読者の便宜を図ったクロスレファレンス(参照)の充実もありがたい。このシリーズの『生化学』『微生物学』との相互参照INFOLINKの脚注も統合的理解を深めてくれます。また各章にはCBTに相当するUSMLE Step1形式の主に臨床関連の設問が125題あり,発展的自己評価ができます。薬物の英語発音が示されているので,外国人と同じ音を操れ,コミュニケーションのギャップに苦しまないでしょう。索引が4段レベルで組まれていて,既習者もこれで頭の整理ができ,臨床医・薬剤師の方も薬物に疑問を持ったときに本書を大いに活用していただきたいと思います。
英語の教科書を一冊通読することは大いに自信を持たせてくれますが,細部や記憶作業にとらわれず,全体を読みきることが大切です。専門分野の英語をマスターするのに原書と翻訳書を並べて学ぶことも最も効率がよい方法です。薬物に関する必要不可欠な知識をコンパクトにイラストの助けで読みたい,臨床と基礎との関連を考えたいなどの多様な読者の要望に答えることのできる優れものとして本書を推薦します。
A4変・頁480 定価6,604円(税5%込)Lippincott Williams & Wilkins
