医学教育に期待されていることとは?
第37回日本医学教育学会ワークショップより
さる7月29-30日,第37回日本医学教育学会(大会長=東大医学教育国際協力研究センター・加我君孝氏)が,東京都文京区の東京大学において開催された。30日に行われたワークショップ「医学教育に今,社会が求めるもの」(コーディネーター=東京SP研究会・佐伯晴子氏,立命館大・松原洋子氏)では,医療における諸問題が各演者によって提起された後,医学教育関係者や医学生による活発な意見交換が行われた。
「患者」について考える
 松原氏は患者の意思決定について,本人が必ずしも常に自己決定できるとは限らないと指摘。たとえ事前に意思表示をしていても,症状の重篤化により考えが変わる場合はあり,その時にはすでに意思表示が困難になっている可能性もありうると述べた。
松原氏は患者の意思決定について,本人が必ずしも常に自己決定できるとは限らないと指摘。たとえ事前に意思表示をしていても,症状の重篤化により考えが変わる場合はあり,その時にはすでに意思表示が困難になっている可能性もありうると述べた。
また,一見「患者」としてはとらえにくくても,実際には医療行為を受ける患者であるケースとして臓器の提供者や胎児などをあげ,「“患者中心の医療”を進める前に,まず患者というものについて深く考える必要がある」と強調した。
岩本ゆり氏(N PO法人楽患ねっと)は実際に患者から寄せられた相談事例を紹介。トラブルになった事例においても,医療者に求められているのは決して特別なことではなく,1人の人間として相手の気持ちを尊重し,プロとしての適切な立ち居振る舞いを心がけることが大切であるとした。
続いて登壇した川口有美子氏(NPO法人ALS/MNDサポートセンターさくら会)は自身のALS介護経験を語るとともに,患者会の立場から発言。患者会には多くの患者から医療に対する悩み,苦情が寄せられていることに触れ,「現在医療者と患者のギャップを患者会が埋めているが,本来は制度で何らかの対策が行われるべき」と行政への要望を訴えた。
また,中島孝氏(国立病院機構新潟病院)は「QOLとは患者の“こうありたい”という期待と現実とのギャップの大きさで決まる」と指摘した。症状が改善しない難病患者の場合,そのQOLを評価することは難しいと述べ,どんな重症な患者でも尊厳は等しいというSOL(Sanctity of Life)を前提に難病のケアモデルを構築することを提案。「難病は治らないからといって,診療やケアする意味がないわけではない」と述べ,心理的サポートとスピリチュアルケアの統合や,緩和ケア技術も取り入れた機能低下に対するサポートの必要性を強調した。
当たり前のことができる医療者に
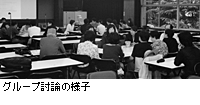 グループ討論の後,参加した医学生からは「子どものまま医師になっているような人が多い。まず社会人として当たり前のことができることが求められている」との意見があり,医学教育への要望として「医師として必ず向き合うことになる“人の死”について考えるプログラム」をあげた。これに対し松原氏は「“誠実な医療人”とは何かを常に考えてほしい。医療現場は理屈だけでは成り立たないところ。センシティブでいてほしい」と医学生への期待を述べた。
グループ討論の後,参加した医学生からは「子どものまま医師になっているような人が多い。まず社会人として当たり前のことができることが求められている」との意見があり,医学教育への要望として「医師として必ず向き合うことになる“人の死”について考えるプログラム」をあげた。これに対し松原氏は「“誠実な医療人”とは何かを常に考えてほしい。医療現場は理屈だけでは成り立たないところ。センシティブでいてほしい」と医学生への期待を述べた。
医学教育関係者からは「人間である以上相性もあり,最良の医師患者関係をすべての医師に求めるのは難しい。しかし,職業的人間関係の結び方はOSCEなどでも学ぶことは可能ではないか」との意見があり,また卒後ロールモデルの重要性も指摘された。
最後に佐伯氏は「もっと積極的に社会の目を医学教育に入れていき,いろいろな方面から“私たちの医療”を考えていきたい」と議論をまとめた。
