よりよい治療ネットワークをめざして
――第2回日本うつ病学会の話題より
さる7月14-15日,品川区立総合区民会館(東京)において,第2回日本うつ病学会が坪井康次会長(東邦大)のもと開催された。テーマは「良く“うつ”を制す-よりよい治療ネットワークをめざして」。うつ病の臨床・研究等の各分野における研究者同士が,臨床から最前線の研究結果まで幅広く討論した。また,うつ病になった時のサポートについて,市民公開講座が開かれ,患者-治療者間にとどまらず,家族・職場・地域に対する議論が行われた。
うつ病への取組み
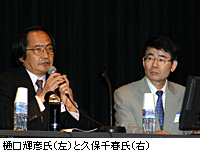 シンポジウム「うつ病研究最前線」(座長=国立精神・神経センター武蔵病院・樋口輝彦氏,九大・久保千春氏)では,初めに井田逸朗氏(国立病院機構高崎病院)が登壇。気分障害の神経内分泌学的研究について「うつ病時,内分泌系の調節がうまく機能しなくなり,ホルモンバランスが崩れる。それに伴い,脳の活動が低下もしくは過剰になっている部位がいくつか存在する。これらは,治療によりホルモンバランスの改善とともに,うつ病の症状もよくなった」と報告。
シンポジウム「うつ病研究最前線」(座長=国立精神・神経センター武蔵病院・樋口輝彦氏,九大・久保千春氏)では,初めに井田逸朗氏(国立病院機構高崎病院)が登壇。気分障害の神経内分泌学的研究について「うつ病時,内分泌系の調節がうまく機能しなくなり,ホルモンバランスが崩れる。それに伴い,脳の活動が低下もしくは過剰になっている部位がいくつか存在する。これらは,治療によりホルモンバランスの改善とともに,うつ病の症状もよくなった」と報告。
続いて高野昌寛氏(放医研)は,画像診断による抗うつ薬の臨床用量や用法の再評価の結果を発表。セロトニントランスポーターに選択的に結合する放射性薬剤を用い,健常者と未服薬・不服薬のうつ病患者の脳を測定・比較したところ,視床における結合能が有意に増大することを明らかにした。「抗うつ薬の脳内作用部位での動態を明らかにすることにより,臨床用量の再評価を行うことが可能になるのではないか」と強調した。今後PETを用いた新規抗うつ薬の臨床用量設定の治験など,さらなる応用・発展が期待されるとまとめた。
石郷岡純氏(東女医大)は治験を実施する立場から「新規抗うつ薬の開発動向」と題して口演。「抗うつ薬の開発は,効果の増強と早期発現の2つが目的の原動力となっている。薬剤開発は(1)モノアミン受容体仮説を進化させる,(2)非モノアミン受容体へ向かう,(3)細胞内情報伝達系へ向かうの3つの方向性で進められている」と語った。また開発を行う際,「どのような薬剤をうつ病の薬と分類するのか,そして今ある抗うつ薬を標準薬とし,開発のツールとして用いる危うさを常に理解していることが必要」と強調した。
最後に大野裕氏(慶大)が,年齢・性別・地域環境等を調査した「自殺防止研究をめぐって」を発表。保健師が積極的に地域と交流していった地域では,特に女性の自殺予防につながっていると報告。「自殺予防に限らずうつ病の治療を考えた場合,患者を支える家族,保健師・看護師などのコメディカル,地域・医療機関が連携していくことで,より効果があるのではないか。そういった面での研究において,今後エビデンスを積み重ねていくことが重要」と締めくくった。
