特集引継ぎに愛を込めて |
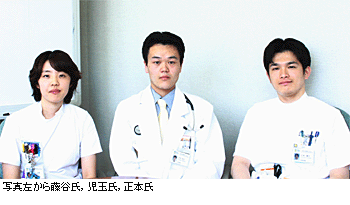
|
|
聖路加国際病院内科:
児玉 知之氏(卒後4年目,前・内科チーフレジデント) 藤谷 志野氏(2年目研修医) 正本 庸介氏(2年目研修医) |
初期研修のスーパーローテート化によって研修医の異動が活発化し,特に研修2年目は1か月単位のローテーションになることも多い。次の配属先に向けた準備も大切だが,その前に,研修医間の引継ぎはできているだろうか?
多忙な日々の中で引継ぎに時間を割くのは大変。だがここは,自分が受け持った患者さんのために,後任の研修医のために,さらには過去の診療を振り返る絶好の機会を失わないために,引継ぎに愛を込め,すっきりとした気持ちで次の研修先に飛び出そう。
伝統的に研修医の異動が頻繁な聖路加国際病院内科病棟では,引継ぎを「to next Doctor」と呼び,次の研修医へ申し送り事項を書くことを義務づけている。受持ち医として“患者のことをいちばんよく知る”研修医間の引継ぎは“文化”として定着しているという。
昨年度,内科チーフレジデント(内科病棟全体を管理する立場)として研修医の指導にあたった児玉氏と,その時に1年目研修医として引継ぎを経験した藤谷氏,正本氏に聞いた。
――研修医間の引継ぎでどのような工夫をされているでしょうか。
児玉 研修医が代わる時には「to next Doctor」といわれる,次の研修医に申し送る事項を書きます。どんな治療をしていて,どんな処方内容で,これからどんな検査をして,どんな方針でいくかということを詳細にまとめた紙ですが,それを書くことを義務づけています。
当院は伝統的に,研修医が病棟の患者さんの受持ち医として機能しています。内科の場合,治療方針や処方は主治医や病棟長(3-4年目の後期研修医)が決めますが,研修医は受持ち医として患者と密に接するぶん,責任も重いのです。申し送りを受けた研修医が患者さんを把握できていないと診療に遅滞が出る。研修医はそれくらい仕事を任されています。
カルテだけで 引継ぎはできない
――前任者のカルテを読むだけでは引継ぎができないのでしょうか?児玉 日々のカルテをすべて読み返すのは手間がかかるんですね。研修医が代わる時には,カルテをまとめたものを書かないと,後任者の労力が多大なものになります。
それに新しい受持ち医が患者さんのことを即座に把握できていないと,患者さんにも迷惑をかけます。上級医も,受持ち医と相談しながら診療を行うことが多いので,受持ち医になった段階で即座に患者さんのことを把握していないと,なかなか検査が進まないことがあります。
あと,カルテだけではわからないことも多いのです。たとえば患者さんの性格や,カルテに毎日記載はしていないけれども,引継ぎ時には言っておいたほうがいいということもあります。
――「to next Doctor」は,退院サマリーともまた違うのでしょうか?
児玉 サマライズされている点は同じですが,退院サマリーよりも具体的です。「今後どんな治療をしたほうがいいか」とか,「どんな検査を何日に入れていて,その検査の結果いかんでどういった方針になる」とか,そういうことも上級医と相談しながら,これまでの治療のエッセンスをまとめあげるということです。
研修医の立場で 心がけていること
――藤谷先生と正本先生は,患者さんを申し送る立場も,申し送りを受ける立場も経験されています。実際に引継ぎをやってみていかがでしたか?藤谷 患者さんを送る側は,1週間ぐらい前から「to next Doctor」を書き始めるのですが,どうしても日常業務に追われて,なかなか書きあがらないこともあります。そうなると引継ぎがうまくいかないので,期限には気をつけています。
あと,引継ぎを受ける立場としては,患者さんにとって交代がデメリットにならないように,受持ち医が代わったことでその前の状況を知らなかったということがないようにすることが,いちばん大切だと思います。それに加えて,1-2年目の研修医はずっと病棟にいるので,患者さんの性格や生活のことまでも含めて把握する必要があります。そこもきちんと引継がないと,難しいと思います。
正本 どんなに努力しても,受持ち医が代わることで連続性が失われるデメリットは多少あると思います。でもその反面,新しい医師が先入観を持たずに診ることによって,もう一度problemの洗い出しをして,これまで気づかなかった何かに気づくチャンスでもあると考えています。
ですから引継ぐ側としては,「to next Doctor」が書きあがる前に,カルテをみるなどして,その患者さんについてのアセスメントを自分なりに立てています。そのあと,「to next Doctor」で前任者の考えと自分の考えをつき合わせて,ディスカッションしながら患者さんに対する把握を深めるように心がけています。
藤谷 次の研修医の新しい視点で,私があげたproblemとアセスメントに対して質問を受けると,「違うアセスメントもあるんだな」と感じます。引継ぎで「to next Doctor」を書くのはすごく勉強になりました。
自分のレベルアップにも役立つ
児玉 「to next Doctor」は,彼らの研修のためにも,絶対に書くよう指導しています。「to next Doctor」の形で1回まとめると,今までのproblemの洗い出しができるし,日々忙しい中で深く考えていなかったこともレビューできるんですね。研修医が知恵を絞って,病棟長に相談しながら書きあげます。――患者さんのためでもあるけど,研修医のためでもあるということですね。
児玉 そうです。僕は3年目にチーフレジデントをやったのですが,その時に教えていた学年が彼らでした。3-4年目になると病棟長を任されるので,3年後にはそのレベルまで彼らが育たないと困る。そういう切迫感を持って教えました。だから,「to next Doctor」を書いてないと,僕が怒る(笑)。
正本 次に引継ぐ研修医にも怒られます(笑)。
児玉 次の日から後任者が診療しやすいように申し送らないと,クオリティの低い診療になってしまう。それでは同僚の研修医間の評判が悪くなりますから,彼らの間での責任感も出てくるでしょうね。
同期の研修医間で引継ぎをする場合は,「どうしてこれをやってないの?」とか,「これなに?」とアセスメントについて言いあったりして,それはそれで勉強になりますが,先輩に送る時はすごいプレッシャーなんですね。「あ,この検査やってない」って気づいたり,「これはどう説明しようか」と思うと,胃が痛い……(笑)。
藤谷 そうそう,書き始めると気づきます。
――研修医の勉強にもなるし,患者さんにとっては見落としがなくなるメリットもありますね。
児玉 そうですね。こうやって研修医間のリチェック機能が効くし,あとは主治医が朝夕2回診ているので,「患者の安全を守る」という点においては問題ないです。
患者さんのことを知っているのは研修医,という自負
――患者さんに対する研修医の責任感が,引継ぎをしっかりしたものにしているのですね。児玉 研修医間の引継ぎは「やってあたり前」というか,「文化」になっているので,もしやらなかったら,とても気持ち悪いと思うんです。
正本 「研修医は,医学的知識はともかく,患者さんのことをいちばんよく把握しているんだぞ」ということを入った時から教えられているので,引継ぐ時には,お互いがそのプライドを持って引継いでいます。
児玉 ちょっと申し送りが甘かったりすると,研修医同士でも“さむい”空気が流れ,上級医からもきつく指導されます。われわれスタッフも四六時中病棟にいるわけにもいかないので,本当に細かいところは彼ら研修医が担っているし,その自負心を持てるぐらいの仕事が与えられていると思います。
――ありがとうございました。
|
<Profile>
―――――略――――― <P. H>
<P. I>
<Problem list>
#1. sepsis due to aspiration pneumonia
#2. chronic infection
―――――#3から#7まで略―――――
以上,引き続き御高診をよろしくお願いいたします。 |
