MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


高階 經和 著
《評 者》山内 豊明(名大教授・看護学)
さらに完成度を増した完璧な心電図の教科書
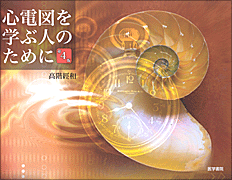 このたび,階經和先生の名著『心電図を学ぶ人のために』が約20年ぶりに改訂され,第4版となった。初版から数えること25年というロングセラーである本書は,第3版も第16刷を重ねており,すでにこれ以上改訂するところがないのではと思わせるほどの完成度の高い良著であった。
このたび,階經和先生の名著『心電図を学ぶ人のために』が約20年ぶりに改訂され,第4版となった。初版から数えること25年というロングセラーである本書は,第3版も第16刷を重ねており,すでにこれ以上改訂するところがないのではと思わせるほどの完成度の高い良著であった。
しかし,常に学問の進歩を見据え,ほんのわずかな妥協も許さぬ到達点を求め続けている階先生は,今回の改訂を敢行された。そして,今回の改訂でも初版から貫かれている「わかりやすい解説」という基本姿勢が徹底されている。
著者は謙遜して「この小書は,あくまでも心電図を学ぶ方々のための啓発書であり,専門書ではない」と記しているが,その実はこれ以上の追加文献を必要としない完璧な心電図の教科書である。
「動きをもって機能する臓器」を把握する
身体の各臓器やシステムはさまざまな情報の提示をするが,得られた情報とそれが意味することについての対応関係が緊密な臓器の代表格が心臓であろう。著者が提唱している「臨床の言葉(clinical language)」には,(1)患者さんの言葉,すなわち主観的情報である「日常語(spoken language)」,(2)我々の五感を通じて得られる身体所見,すなわち客観的情報である「身体語(body language)」,そして(3)さまざまな補助ディバイスを駆使して得られる検査所見である「臓器語(organ language)」,の3つがある。心臓という臓器の機能状況については,このうち特に心音聴取と心電図所見の把握をもってすれば,リアルタイムにほとんどの情報は得られるものである。心音は心臓の動きそのものを直接的に反映し,音を聴くことで心臓がどのように動いているかを正しくイメージできる。その心臓の動きをコントロールしている本態は電気であるが,残念ながら人間の持つ感覚受容器ではこの電気はなかなか把握できないものである。
この電気の働きを目に見える形に変換してくれたものが心電図である。であるから,心音所見と心電図所見を把握できたならば,「動きをもって機能する臓器」である心臓という臓器の「動き」とその「調整メカニズム」を把握できたことに他ならない。
「難解なものをやさしく書く」著者の力量が生んだ名著
心電図というものは,何やら難解なものではないかとの先入観も多いと聞くが,心電図の意味するところの本態をいったん理解し納得したら実は難しいものではない。しかし,複雑で難解にみえる事柄をわかりやすく書くことほど難しいことはなく,難しく書くことのほうが遥かに容易である。わかりやすく書くためには,難しいままで伝えることの何倍もの教育的能力を必要とすることは言うまでもなかろう。
その卓越した力量をお持ちである階經和先生であるからこそ,本書が生まれ,四半世紀にもわたって世の中で貢献してきたと考える。ここに改めて本書への全幅の信頼を寄せるとともに,多くの方々に本書を心より推薦したい。


李 啓充 著
《評 者》川島みどり(日赤看護大教授・看護学)
いま何をすべきか?看護師に深い示唆を与える1冊
 医療制度改革のあるべき姿は,「日常診療の場で,医療倫理に則った医療を達成することが容易となる法・制度の改革」であるとして,著者は,これまでにも胸のすくような歯切れのよい筆致で,米国の医療の実状を分析・紹介してきた。ともすれば,米国に倣いがちなわが国の医療の諸政策に対して警鐘を鳴らし続けるだけではなく,日本の医療の質を高め,患者本位に改革する方向性を示唆し,多くの読者を引きつけてきた。
医療制度改革のあるべき姿は,「日常診療の場で,医療倫理に則った医療を達成することが容易となる法・制度の改革」であるとして,著者は,これまでにも胸のすくような歯切れのよい筆致で,米国の医療の実状を分析・紹介してきた。ともすれば,米国に倣いがちなわが国の医療の諸政策に対して警鐘を鳴らし続けるだけではなく,日本の医療の質を高め,患者本位に改革する方向性を示唆し,多くの読者を引きつけてきた。
本書では,これまでの米国医療の批判的紹介にとどまらず,市場原理を持ち込むことによる医療そのものの崩壊の詳細について,具体的な事例をあげながら述べられている。なかでも,混合診療をめぐっては,わが国でも立場によってその受け止め方も一様ではない。だが,その解禁により,財力の差に基づく医療差別を制度化し,安全性と有効性の認められていない治療が,先端医療の名のもとに横行する危険性があるとしている。
なかでも,突然発症された実弟のくも膜下出血の治療をめぐるエピソードは胸を打つ。必要な治療の選択をできなかった肉親としての苦渋の思い,その思いを,「混合診療の解禁に向けるのではなく,安全で有用な治療薬が認可されない背景に怒るべき」だとの言葉は,相当の重みを持って迫ってくる。欧米では常識化されている治療薬の許認可のしくみ,その背景にも本書の主題である市場原理が見え隠れする。
一連の流れは,近年の米国における深刻な看護師不足,無資格看護職員の増加にも通じるものではないだろうか。また,世界の看護師らの憧れでもあった,ベスイスラエル病院の看護の崩壊劇の背景とも無関係ではないだろう。
近年声高に叫ばれてきた医療費の削減,経営の効率化が,ビジネスの論理への幻想を抱かせていると思われるが,行き過ぎると医療倫理に反することを合理化することにもなりかねない。昨今多くの医療機関に掲げられている患者尊重の理念を,言葉だけの上滑りにせず,日常診療・看護に具体的に実践されない限り,医療への信頼回復の道は遠いだろう。その意味で,巻末の対談には多くのヒントがある。医療の質を貧富によって差別しかねない市場原理・ビジネスの論理に惑わされず,「患者アドボカシーは看護師が適役」とのコメントを糧にして,いま何をすべきかを考える上で,多くの看護師らに一読をお勧めする。
四六判・頁280 定価2,100円(税5%)医学書院
