MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


J. W. Rohen,横地 千仭,E. Lutjen-Drecoll 著
《評 者》塩田 浩平(京大教授・解剖学)
写真による解剖学アトラスの最高峰
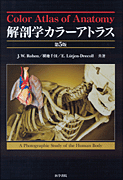 医学生,歯学生が解剖学実習を進めるうえでアトラス(図譜)はその羅針盤となる重要なものである。定評ある人体解剖学アトラスがいくつか出版されているが,その多くは写生図と模式図もしくは半模式図から成っている。もちろん描画のアトラスにはそれなりの利点があるが,多くの場合,構造物の形態や配置が理想的に描かれ着色されており,また余分な構造物が省かれている(例:しばしば動脈のみが描かれ静脈が省略されている)ため,学生が実際に目にする御遺体の状態とは異なることが多い。一方,解剖体の実写写真のアトラスは,よほどの剖出技術がない限り,各種の構造物を初学者にもわかりやすく提示するのは容易ではない。
医学生,歯学生が解剖学実習を進めるうえでアトラス(図譜)はその羅針盤となる重要なものである。定評ある人体解剖学アトラスがいくつか出版されているが,その多くは写生図と模式図もしくは半模式図から成っている。もちろん描画のアトラスにはそれなりの利点があるが,多くの場合,構造物の形態や配置が理想的に描かれ着色されており,また余分な構造物が省かれている(例:しばしば動脈のみが描かれ静脈が省略されている)ため,学生が実際に目にする御遺体の状態とは異なることが多い。一方,解剖体の実写写真のアトラスは,よほどの剖出技術がない限り,各種の構造物を初学者にもわかりやすく提示するのは容易ではない。
横地千仭,J. W. Rohen,E. Lutjen-Drecoll三教授による『解剖学カラーアトラス』は,芸術的といえるほど精緻に剖出された人体標本を,これも卓越した技術で撮影した比類のない美しい写真からなるアトラスであり,1983年の英文版初版刊行以来高い評価を得てきた。正確な写実,芸術的な写真の数々,行き届いた構成は,本書が写真による解剖学アトラスの最高峰であることをわれわれに再確認させる。
20年前の初版以来,版を重ねるたびに優れた写真や説明の図などが付け加えられて内容が充実し,このライフワークにかける著者らの並々ならぬ情熱が伝わってくる。全身の骨,筋,血管,神経などの極めて詳細な,かつ美しい写真はもとより,水晶体と毛様体冠を示す眼球の正面像(p.131),喉頭軟骨および靭帯の一体標本(p.159),心臓の刺激伝導系(p.251)など,見事としか言いようのない数々の写真が,何よりもこのアトラスを特長づけ他の追随を許さないものとしている。これまでの版が少なくとも16か国語で出版されているのもむべなるかなと思われる。
マクロ写真に加えてCTやMRの画像も豊富に取り入れられており,理解を助けるカラーの模式図も美しい。第5版では標本写真約40枚,CT,MR画像約10枚が新たに追加または古いものと差し替えられ,一段と内容が向上している。巻末にある心臓の3D立体アトラス,用語説明および付図は横地名誉教授自身の手によるもので,日本語版のみに付けられているようである。表紙と裏表紙の芸術的な写真も横地名誉教授自身によって作られている。このような素晴らしい書物をこの価格で提供した関係者の努力に敬意を表するとともに,本書に接することのできる喜びを多くの医学生,歯学生,コメディカルの学生諸君に享受してもらいたいと思う。
近年,医学部・歯学部で解剖学実習にあてる時間数が短縮される傾向にあり,十分細部までを剖出することが時間的に難しいことがある。そうした場合に,解剖を効率的に行うための指針として,あるいは自らの実習を補うすぐれたアトラスとして本書が価値を発揮するであろう。また,自ら人体解剖を行う機会がないコメディカルの学生にとっては,この優れたアトラスを活用して三次元的な人体の構造を視覚的に理解することが十分可能である。臨床医が必要に応じて人体の構造を確認する際にも,このアトラスが座右にあれば困らないであろう。そして,著者らが述べているように,人体というものが如何に精密に,美しくまた素晴らしく構成されているかということに,読者が等しく気付かされるであろう。
ヴェサリウスの『ファブリカ』(1543年)以来,人体の美しい構造は科学の対象であると同時に芸術の題材として様々に描かれ,名著といわれる多くの解剖学書や図譜が出版されてきた。Rohen,横地,Lutjen-Drecoll教授による「解剖学カラーアトラス」は,既に歴史的名著となるべき内容と風格を備えている。日本の解剖学者がそこで中心的な役割を果たしてきたことを,われわれも誇りとしたい。


菅野 健太郎,榊 信廣 編
《評 者》藤原 研司(埼玉医大教授 消化器・肝臓内科/日本消化器病学会理事長)
H. pylori研究の最先端を多面的に紹介
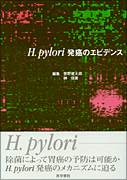 本書こそは今の臨床医に求められる医学書であろう。テーマをわが国の重点課題に絞っている。そして,示唆に富む臨床現場の観察を国内外から幅広く取り上げ,疾患に関連する最先端の基礎研究を多面的に紹介し,最新のトピックスへと内容を展開させている。その構成は,臨床医である編集者の医療にかける真摯な情熱を伝えており,わが国から胃癌を撲滅しようとする呼びかけともとれる書である。
本書こそは今の臨床医に求められる医学書であろう。テーマをわが国の重点課題に絞っている。そして,示唆に富む臨床現場の観察を国内外から幅広く取り上げ,疾患に関連する最先端の基礎研究を多面的に紹介し,最新のトピックスへと内容を展開させている。その構成は,臨床医である編集者の医療にかける真摯な情熱を伝えており,わが国から胃癌を撲滅しようとする呼びかけともとれる書である。
高齢社会では,悪性腫瘍の発生は避けられない。わが国における胃癌による訂正死亡率は,臨床医の長年にわたる努力により,50年ほど前から徐々に減少しつつあるとはいえ,未だに死因第1位である悪性腫瘍の首座の1つを占めている。H. pyloriが発見されてから20年余りが経ち,多くの研究成果が蓄積されてきた。今やH. pylori菌は胃癌発生や進展にどのようにかかわるのかを見極め,その防止に向けて,新たな方策を確立することが問われている時代を迎えている。
科学が新たな発展を遂げるには,研究者の目的を達成させようとする意欲と,試行錯誤を重ねながら偶然を見逃さない洞察力,視野の広さが要件となることは言うまでもない。しかし一方で,科学的認識には,観察と思考,経験性と合理性,帰納と演繹の二面性があり,そのため現代の科学では,絶対性はなく,蓋然的,確率的,統計的なものとして,その因果法則を立てざるを得ないとされている。
医学では,この点において,新たな知を創出する担い手は臨床医に他ならない。臨床医こそは複雑多様な病態の全体像が見えている唯一の観察者であり,問題解決に悩むほどにブレークスルーとなるアイデアの閃きも湧き得るのである。そのための知の醸成には,臨床と基礎医学にかかわる情報の共有が基本となるが,これを臨床医は,多忙な日常診療にあっても,効果的,効率的に習得しなければならない。
本書は,まさしくこれら医学・医療の特徴を捉えて臨床医に提供されたものであり,これからの医学書のあり方の見本としても高く評価される良書である。


RNAi
RNAi: A Guide to Gene Silencing
Gregory J. Hannon 編
中村 義一 日本語版監修
《評 者》渡辺 公綱(産業技術総合研究所・生物情報解析研究センター長)
ポストゲノム研究で注目を集めるRNAi発見の経緯がまとめられる
 本書はRNAiという現象の解明にかかわった研究者の1人であるG. J. Hannonの監修で,2003年にCold Spring Harbor研究所出版局より出版された原書を,文科省RNA特定領域研究の代表である中村義一・東大教授が監修し,日本の若手RNA研究者を結集して和訳したものである。
本書はRNAiという現象の解明にかかわった研究者の1人であるG. J. Hannonの監修で,2003年にCold Spring Harbor研究所出版局より出版された原書を,文科省RNA特定領域研究の代表である中村義一・東大教授が監修し,日本の若手RNA研究者を結集して和訳したものである。
RNAiは外部から二本鎖RNAを導入すると,それに相同な標的遺伝子の発現が抑制される現象で,1998年に線虫で発見されたが,その後植物や動物でも同様な仕組みの存在が明らかになり,多細胞生物に共通する遺伝子抑制機構として認められるようになった。2002年末のScience誌で,RNAiとそれに続いて発見された,RNAiと似た機構で発生や分化の制御に働くマイクロRNAに関する研究が,その年の最も重要なブレークスルーとしてトップにランクされたことはまだ記憶に新しい。
最近ではヒトの遺伝子の総数は22,000程度と見積もられているが,それらが20-30万種類もあるとされる多様な蛋白質をコードできるのは,mRNAの選択的スプライシングのためと考えられている。さらに,蛋白質をコードしないノンコーディングRNA(ncRNA)がヒトの全RNAの98%を占めること,ncRNA遺伝子の全ゲノムに占める割合は高等動物ほど大きくなること,などの最近の知見は,RNAこそが高等真核生物の複雑さを実現するための決定的要素であることを強く示唆しており,ポストゲノム研究におけるRNAの重要性が実感されつつある現在,本書の出版は時宜を得たものであると言えよう。
原書は,RNAiという現象の発見の経緯が関連分野の動向とともにまとめられ,さらに必要と思われる箇所には実験のプロトコルが適宜組み込まれており,総説と実験書を兼ね備えたユニークな専門書である。本書は原書に忠実に大変明快に訳されている。強いて欲をいえば,文章では懇切丁寧な説明がなされているが,それをよりわかりやすくする概念図や具体的な図表などがもっと多用されると,特に初心者にはいっそう理解しやすくなるのではないかと感じた。翻訳書では原著者との交渉でそのような工夫ができないものかとも思う。
原書出版後,本書が上梓されるまでの間にRNAiの研究はさらに急速に進展し,いくつかの新たな知見も得られているが,その基本的な仕組みや研究の方向は本書で十分解説されている。この分野に関心のある方やこれからこの分野に進もうとする学生,研究者のみならず,現在実際にRNAiに携わっている研究者にとっても,大変有用な参考書であり,ぜひ多くの方々に一読していただきたい本である。


《米国胸部学会ガイドライン》
結核・非結核性抗酸菌症診療ガイドライン
第2版
泉 孝英 監訳
《評 者》濱田 邦夫(市立千歳市民病院内科)
全身性疾患としての結核を学べる一冊
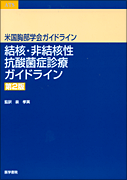 本ガイドラインには結核と非結核性抗酸菌症について,具体的な診断方法と治療方法に加えて,各治療薬剤の特徴,投与量,投与方法,血行動態,副作用,薬剤相互作用についても詳細な解説が記載されている。また,腎障害や肝障害がある場合や妊婦についても治療の実際が具体的かつ親切に説明されていて,結核・非結核性抗酸菌症の治療に従事している臨床医にとってはまさにバイブルとなるだろう。
本ガイドラインには結核と非結核性抗酸菌症について,具体的な診断方法と治療方法に加えて,各治療薬剤の特徴,投与量,投与方法,血行動態,副作用,薬剤相互作用についても詳細な解説が記載されている。また,腎障害や肝障害がある場合や妊婦についても治療の実際が具体的かつ親切に説明されていて,結核・非結核性抗酸菌症の治療に従事している臨床医にとってはまさにバイブルとなるだろう。
結核と診断されれば早急に専門施設へ移送して後は一任して終わり,という現在の医療体制では,一般呼吸器診療医の結核に対する理解はますます浅くなり,結核についての正しい知識の欠如と診断力低下(doctor's delay)は防げないのかもしれないし,今後ますますこの傾向が強まっていくことが懸念される。この傾向に少しでも歯止めをかけることができるものがあるとすれば,それは結核診療に日常携わっていない呼吸器診療医が,本書のようなガイドラインで知識を深めること以外にはないのではなかろうか。1人でも多くの呼吸器臨床医がこのガイドラインを座右の書に加えることを願ってやまない。ツベルクリン反応の意味と解釈について正しく理解するだけでも,日常診療がひと味もふた味も向上するのではないだろうか。
このガイドラインを一読する方は,結核は全身のどの臓器にも起こりうる感染症であることを改めて認識するだろう。そして,肺外結核の診断は,結核かもしれないという意識が念頭にないとますます困難になるということにも気づくに違いない。非結核性抗酸菌症も決して肺だけの疾患ではないことを初めて知る方も少なくないのではないだろうか。各科臨床医の皆さんにもぜひ結核や非結核性抗酸菌症について知識を持っていただきたいのはもちろんであるが,まずは呼吸器診療医が肺疾患としての結核・肺非結核性抗酸菌症だけではなく,肺外病変について各科臨床医に正しくアドバイスできるだけの力量を持ちたいものである。
監訳者であり私の恩師でもある泉孝英京都大学名誉教授の本来のご専門は間質性肺疾患であり,本書の姉妹編にあたる「米国胸部学会ガイドライン 間質性肺疾患診療ガイドライン」の共同監訳者でもある。先生は現在の京都大学呼吸器内科の前身である胸部疾患研究所がまだ結核研究所であった頃に結核診療に従事されていて,結核にも造詣が深い。欧米の知見をいち早く取り入れて持ち前の自由闊達な発想で意見されるので,先生のお考えは学会ではなかなか受け容れられなかったと聞いている。そんな先生の主張されてきたことが標準化されつつあるのを目の当たりにすると,今更ながら泉先生の先見の明に深く敬服するのである。


精神医学講座担当者会議 監修
山内 俊雄,小島 卓也,倉知 正佳 編
広瀬 徹也,丹羽 真一,神庭 重信 編集協力
《評 者》山口 成良(松原病院院長,金沢大名誉教授)
精神科専門医が習得すべきminimum requirementを明示
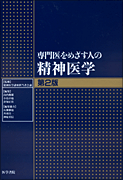 1998年に西園・山口・岩崎・三好編集の「専門医のための精神医学」第1版が発行されてから6年にして,このたび第2版が刊行された。名前も「専門医をめざす人の精神医学」と改められ,執筆者も第1版の54名から115名と倍増してわが国の精神医学の各分野の第一人者を配している。頁数も索引を除いて521頁から752頁と大部のものとなり,一読するのに約30時間を要した。
1998年に西園・山口・岩崎・三好編集の「専門医のための精神医学」第1版が発行されてから6年にして,このたび第2版が刊行された。名前も「専門医をめざす人の精神医学」と改められ,執筆者も第1版の54名から115名と倍増してわが国の精神医学の各分野の第一人者を配している。頁数も索引を除いて521頁から752頁と大部のものとなり,一読するのに約30時間を要した。
各版の序文にあるように,第1版では精神科医としての専門的知識・技能を体得していただくことを願って「専門医のための」という言葉を使ったが,今回の第2版では専門医として習得すべきminimum requirementsを明示し,精神科研修医の学ぶべき指針を示すようにと意図して編集されたもので,「専門医をめざす人」たちの必携の書として発行されたものである。
内容は第1版では,従来の教科書のように第1章総論,第2章診断および治療計画,第3章治療,第4章各論としてあったが,第2版では20に章立てしており,1.精神医学を学ぶための基本的な知識と態度,2.精神症状とその捉え方,3.診断および治療の進め方,など精神科専門医をめざす人たちの態度の導入に,250頁という三分の一の紙数を使っているところからも,精神科専門医としての素養をしっかり身につけてほしいという編集者の並々ならぬ意図が切実に感じられる。
4.症状性を含む器質性精神障害から,13.小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害までは,大体ICD-10の疾患分類に従った各論的記載であり,次いで14.乳幼児,児童および青年期の精神医学的諸問題,15.コンサルテーション・リエゾン精神医学,サイコオンコロジー,16.精神科救急,17.自殺の問題,18.生物学的治療,19.精神療法,20.社会的治療,社会復帰を援助する治療と続き,専門医として習得すべき知識・技能のminimum requirementsを網羅している。
さらに新しい項目立てとして,精神医学を理解するための神経科学,精神医学を理解するための認知行動科学,脳死判定基準,サイコオンコロジー,成年後見制度,介護保険とケアマネジメントなどがあり,また定型・非定型抗精神病薬,性同一性障害の項では詳しい説明がなされており,精神医学・医療における時代の趨勢を読み取ることができる。
毎日の忙しい診療の終わったあとで一読するのに通算して1週間以上を要したが,各項は要を得て簡潔に書かれており,理解しやすく,非常に勉強になった。日本精神神経学会でも長年の懸案であった精神科専門医認定試験を行うことになった今日,この第2版が発行されたことは甚だ時宜を得たものであり,専門医をめざす人のみならず,精神科医としての経験の深い方にも,生涯学習のための必読の書としてお奨めしたい。
B5・頁752 定価18,900円(税5%込)医学書院
