[ 寄稿 ]
英国とフランス,そして日本の緩和ケア
その共通点と相違点からわれわれは何を学ぶか(前編)加藤恒夫 かとう内科並木通り診療所(岡山市)
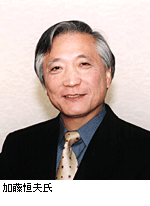 フランスにおける緩和ケアについては,これまで日本ではあまり紹介されたことがない。筆者は今回,緩和医療教育についてヨーロッパ緩和ケア学会(EAPC)のドキュメントを点検中,フランスと日本との類似点がかなり多いこと(緩和ケア施設が病院から出発した点や在宅ケアの仕組みがまだ整備途上であることなど)に気付き,訪仏の機会を得てフランス第2の都市リヨンにおける緩和ケアの実態を取材した。
フランスにおける緩和ケアについては,これまで日本ではあまり紹介されたことがない。筆者は今回,緩和医療教育についてヨーロッパ緩和ケア学会(EAPC)のドキュメントを点検中,フランスと日本との類似点がかなり多いこと(緩和ケア施設が病院から出発した点や在宅ケアの仕組みがまだ整備途上であることなど)に気付き,訪仏の機会を得てフランス第2の都市リヨンにおける緩和ケアの実態を取材した。
紹介の労をとっていただいたのは,EACP初代会長のGoeffrey Hanks教授(英国ブリストル大学緩和医療学)である。ご無理をお願いして,リヨン市を拠点にフランスにおける緩和ケアの指導的役割を果たしているDr. Marilene Filbet氏を紹介していただいた。
なお,訪仏に先立って英国も訪れて取材した(9回目)ので,今回は2回にわたり英国の最新動向とフランスの動向,そして英仏比較を記し,日本への若干の提言を行いたい。
英国の新たなジレンマ
今回の英国訪問にあたっては,(1)専門的緩和ケアとプライマリケアとの連携(在宅緩和ケアの促進),(2)緩和ケアの対象をがん以外の疾患に拡大する,の2つをテーマとした。訪問・取材先は,(1)Macmillan Cancer Relief(以下MCR),(2)St. Christopher's Hospice,(3)National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services(以下NCSPCS)本部の3か所であり,訪問日程およびインタビュー対象者は表に記した。
|
緩和ケアの専門特化とその負担の増大
英国におけるホスピス・緩和ケアは,よく知られているように,非営利団体(Voluntary Sector)の牽引により今日まで発展してきた。最近では,国民健康保障政策局(NHS)の政策転換により,非営利団体とNHSの協調政策がとられているものの,PCUベッド数の80%はいまだに非営利団体が提供している。
しかしながらそれらPCUの多くは,非営利団体としての経営体質(ある意味で放漫経営)ゆえに現在では財政的困難に陥り,その他にもさまざまな面で体質改善を余儀なくされている。あるいは,次のような言い方もできよう──各地域が非営利事業として競ってPCUをつくったがために,結果として経済的にも質の面でも転機を迎えている,と。
セントクリストファーズホスピスも例外ではなかった。Barbara Monroe氏(Chief Executive)によると,5年前に財政的困難に陥り,急ぎ統括管理組織の変更を図る一方,大幅赤字だった高齢者施設の閉鎖や人員整理,人事評価の徹底などによるホスピス経営の効率化を急いでいるという。創設者ソンダース氏は代表権のある職から退き,現CEOの言葉によれば「よりビジネスライクなモデルをめざしている」というのである。
プライマリケアチームに能力と権限を
同ホスピスの転機についてはもう1つ,地区サービスとの関係で見過ごせない理由がある。同ホスピスには1968年,英国で初のコミュニティサポートチームが編成されたが,このスペシャリストの組織がいつのまにか,ゼネラリストであるGeneral Practitioner(GP)や地区看護師が担う在宅緩和ケアの分野を取り込んでしまい,余分な負担増加による財政的なトラブルを抱え込んでしまう要因になっていたという。非営利団体でも,対費用効果を無視することはできない教訓といえよう。
現在では,サポートチームにナースコンサルタントをおき,地区のGPや看護師からなるプライマリケアチームにアドバイスする業務と緩和ケア教育に徹している。ナースコンサルタントはNHSが推進している新しい職位であり,非営利団体のなかでの存在はまだ数少ないが,「緩和ケアの普及・教育はゼネラリストに日々接する中でしかあり得ない」との結論から導き出された職位である1)。
緩和ケアを他の疾患に拡大する
対費用効果といえば,従来の施設ホスピス(デイセンターなどを含む)の在り方も見合わないことがわかってきたという。その要因の1つは,患者の高齢化に伴って患者のニーズが多様化し,がん以外の疾患(アルツハイマー,パーキンソン病,心臓病など)にも対応せざるを得ないなど,問題が複雑化しているからである。非営利PCUを支える財団の立場は
こうした点についての対応はすでに,非営利団体を支えるトラスティー(信託財団)の代表格MCR(正式名称は別表に)や,英国のほとんどのホスピスと緩和ケア関連の団体を統括する組織NCHSPCSでも,転換を促すべく新たな方針が打ち出されている。まず,MCRの活動方針から紹介しよう。
MCRはその名称にあるように,「誰もが何処ででも不安なく必要で最適ながんケアを受けることができるように」と憲章に謳っている。この憲章を変更するつもりはないとしたうえで,がん緩和ケアの他の分野への応用,あるいはがん以外のケアから学ぶことを妨げるものは何もないという。実際,MCRの代名詞であるマクミランナースには,がん以外の疾患,たとえば難治性の心筋症や終末期の腎不全などに対しても,現場でその分野の専門家や組織と共に積極的に関わるよう奨励されている。
利用者の立場に立ったサービスのあり方の研究
「がん患者の闘病のすべての旅路」をサポートするMCRにとって,患者のニーズがどこにあるかなどの,より良い臨床実践のための研究が,実際の患者を交えて(consumer's involvement)医療サービスの利用者の立場から,いくつかの大学(リーズ大学とリバプール大学)と提携しつつ,常に行われている。研究資金は決して多くはないとのことだが,それでも最近は年間250-300万ポンドという。
そうした研究の中から,がんの患者のニーズの多くは医療以外のところ,例えば通院手段や経済的問題などソーシャルサービス分野にあることがわかった。がんは慢性病化しつつあることを裏付けるニーズといえようか。
緩和ケアの概念の拡大をめざして
本来はがん緩和ケア専門のマクミランナースが,現場レベルでは実質的に心臓病患者への対処も始めているのは,理由がある。NCHSPCSがすでに5年前に「心疾患にも緩和ケアサービスを提供していくべきだ」との文書を発行しているからである2)。 NCHSPCS代表者Peter Tebitt氏(National Palliative Care Development Adviser)(写真)はいう。「緩和ケアをがん以外の疾患に拡大する方針は,NHSの健康政策として実現されたわけではないものの,政策の枠組みとしては取り上げられています。英国で緩和ケアを利用できることは,がんであろうとなかろうと,衡平でなければなりませんから」。読者諸氏には耳慣れない言葉と思われるが,衡平(equity)とは,だれもが平等に権利を享受できるチャンスがあることであり,英国の慣習法から生まれた国民の立場にたつ平等概念の言葉である。
NCHSPCS代表者Peter Tebitt氏(National Palliative Care Development Adviser)(写真)はいう。「緩和ケアをがん以外の疾患に拡大する方針は,NHSの健康政策として実現されたわけではないものの,政策の枠組みとしては取り上げられています。英国で緩和ケアを利用できることは,がんであろうとなかろうと,衡平でなければなりませんから」。読者諸氏には耳慣れない言葉と思われるが,衡平(equity)とは,だれもが平等に権利を享受できるチャンスがあることであり,英国の慣習法から生まれた国民の立場にたつ平等概念の言葉である。
緩和ケア利用状況では,この運動がはじまった後,とりわけ心臓病の患者が増えたというデータは今のところなく,一見何も変わっていないというが,「この2-3年,がん以外の慢性疾患に対する緩和ケアサービスはとくに発展してきたと実感しています」という。そして,前述の5年前の文書が発端になって,NICE3)が行った勧告に基づき,2003年NHSは5000万ポンドの臨時支出を組んだ。心疾患に対する緩和ケアのモデルづくりが,実質的な健康政策として一歩を踏み出したのである。
団体名から「ホスピス・専門的」の削除
続いてTebitt氏が何気なく述べた発言に,筆者は驚かざるを得なかった……。「私たちはたぶん,当協議会の名称から『ホスピス・専門的』という字句を削除して,『緩和ケア全国協議会』というような名称に変更することになるでしょう。まだ議論段階ですが」。ホスピスという言葉が除かれようとするのは,この取材を通じて感じていたが,専門的サービスという言葉まで削除する意図は何なのか。
「緩和ケアを改善する,最善で最も安く効果的な方法は,緩和ケアの知識と技能を専門化させないこと,つまりゼネラリストの知識と技能を改善していくことです。緩和ケアの枠組みを標準化することが重要なのは,このためです」
筆者は,日本における緩和ケアサービスが,本来は個々人に応じた全人的ケアを目指さなければならないにもかかわらず,そのための教育を医療全般に普及するのではなく,徒に認定医制度作りを急ぐことを危惧するものである。英国では,緩和医療専門医の資格取得のためには,一般医療の研修が義務図けられていることは数年前に見聞してきていたが,すでに新たな地平を切り拓いて走り出していたわけである。そして,次の言葉には救われた思いがした。
「NCHSPCSとしては,緩和ケアの提供は誰が担ってもよいと考えています。非営利であろうと,完全な民間営利ベースであろうと,NHSであろうと。個々を支援し発展を促すのは,私たちの役割ではありません。もちろんスペシャリストの役割は,まれな複雑な問題を抱えるケースに対して欠かせない存在であり,ケアのバランスをとる上で必要であり続けます。私たちの役割は,思想的にも実践的にも異なるさまざまな緩和ケアの在り方を促進していくことであると確信しています」
(参考文献)
1)NCHSPCS刊行/加藤恒夫訳「提携関係の促進:地域における緩和ケアの管理と計画策定(1998)」(緩和医療研究会「緩和医療」第9巻2号,2001年所収)。
2)“Reaching Out: Specialist Palliative Care for Adults with Non-Malignant Diseases", NCHSPCS 1998.
3)National Institute for Clinical Excellence 英国における医薬分野についての有効性,安全性および経済性を評価する機関。英国ではNICEから推奨されたものだけが市場活動ができる。
