MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


長い研究の流れを整理し,今日の脳研究の知見と問題点を明らかに
神経科学-形態学的基礎間脳[1]視床下部
佐野 豊 著
《書 評》藤田恒夫(新潟大名誉教授・解剖学)
研究者の道しるべとなる重厚な1冊
 20世紀のドイツでは,医学のあらゆる分野においてHandbuchといわれる叢書が出版された。これは1冊を担当すべく編者から指名された将来有望な若手著者がその領域の世界の文献を捗猟し,その時点で得られている知見を詳細に記述したもので,ドイツ語文化圏の研究者の羅針盤のような役割を果たしてきた。
20世紀のドイツでは,医学のあらゆる分野においてHandbuchといわれる叢書が出版された。これは1冊を担当すべく編者から指名された将来有望な若手著者がその領域の世界の文献を捗猟し,その時点で得られている知見を詳細に記述したもので,ドイツ語文化圏の研究者の羅針盤のような役割を果たしてきた。
組織学もご多分にもれず,神経系から内分泌腺,骨や軟骨に至るまで,あらゆる器官をカバーするMollendorffのHandbuchとよばれる重厚な数十冊があった。私たち解剖学者は,顕微鏡で未知の事象に遭遇するたびに図書館に駆けこんで,それがすでに誰かによって記載されているかどうかを,MollendorffのHandbuchで確かめたものである。Handbuchはドイツ人の性格とドイツ学界の風土に根ざした特異な所産で,他の国には存在しない。
ところが,わが国の神経科学の泰斗,佐野豊先生が畢生の大作として著しておられるシリーズは,まさにHandbuchの規模と格調をもつ叢書であり,研究者の道しるべとして頼りがいのある参照源といえる。第I巻「ニューロンとグリア」(1995,金芳堂),第II巻「脊髄・脳幹」(1999,金芳堂)に続いて今回の第III巻(2003)は医学書院から出版され,間脳の第1部:視床下部に当てられている。各1000ページを超えた前2巻よりは薄いが,560頁の重厚な1冊で,200ページにわたる膨大な文献表だけでもその価値(研究者の利用度)は計りしれない。
「読みもの」として楽しめる本文
本文を読んでみよう。この巻の冒頭で説かれるのは,間脳の構成である。間脳がどのような形態単位から成立し,機能に対応しているか。著者は,19世紀末のHisやKupffer以来,多くの形態学者が「個体発生」と「系統発生」を鍵に積み重ねた研究を整理する。その中で,(1)Herrick(1910)は縦走性細胞柱による縦の区分を詳細にし,(2)Baer(1928)以後は横の区分(分節性)の研究が進み,Bergquist(1952-55)は分節性の研究をさらに発展させ,これが神経上皮の局所ごとに存在する細胞増殖域に対応すると提唱した。そして近年(3)Akam(1982),Wilkinsonら(1989)以後,胎児脳における遺伝子発現(hoxとKrox20に相同の遺伝子など)が検索されるようになると,これら縦割り・横割りで生じる脳の格子状の区分に,遺伝子発現パターンが対応することが明らかになる。こうして遺伝子発現を鍵にすることで,古典的な形態学の知見が生き返り,間脳の格子構成のパターンが確実で詳細になったばかりでなく,従来未解決だった前脳までもが,6分節に分割されることになった経緯が語られる。たくさんの適切な図が理解を助けてくれる。著者の流儀はこのように,複雑な今日の知見と問題点を,長い研究の流れを整理することで解き明かそうとする。それによって読者は,重要な業績の生まれた経緯とその意味を鮮明に理解できるばかりでなく,問題解明に取り組んだ研究者たちの労苦と栄光を知って,深い感銘を覚えるであろう。冒頭でやや礼賛調で紹介したドイツのHandbuchとこの本とは,そのような点で大きく趣きを異にする。Handbuchは詳細な記述の集積で,研究者が折にふれて開いてみる参照源であることが一般だが,本書は拾い読みしても通読しても興味の尽きない「読みもの」になっている。学問というものは面白い,奥が深いと感動を与えてくれ,さらに読み進みたくなる。
「神経分泌」や「視床下部下垂体系」などの章は,著者自身がその研究の歴史の中心にいたことから,ストーリーが(おそらく現在世界の誰が書くより)豊富で鮮明で,読む者は血湧き肉踊る心地を覚える。
本書の内容は形態学の枠を越えて,関連領域にひろがり,まさに形態学を「基盤」にした「神経科学」の書となっている。事実,ペプチドおよびアミン性伝達物質やそのレセプターについては生化学的な解説に,概日リズムでは生理学や動物学に,多くのページを用いている。「ステロイドと脳」についても,大きな章を設けて新しい研究の流れを解説している。
本書は本文が「読みもの」になっていることはすでに強調したが,さらに随所に設けられた囲み記事が読者をくつろがせてくれる。「余滴」のコーナーでは,本文に関連するさまざまな問題について,著者自身の長い研究体験からにじむ蘊蓄を傾けたり,研究者たちへの貴重な示唆を与えたりする。また人物コーナーでは大きな功績をあげた解剖学者や生理学者のミニ伝記を,貴重な肖像写真とともに楽しむことができる。ここにも学問の先達たちへの著者の敬愛の念が溢れている。
日本の脳研究の「Handbuch」
著者佐野豊先生は,青年のような情熱と気力をもって,この叢書の執筆に励まれ,今後引き続き脳幹から小脳や大脳に攻め昇ろうとしておられる。世界の学界にも稀な快挙というべきであろう。ところが仄聞するところによれば,このシリーズの売れ行きは期待ほどでなく,前2巻を出版した書店が手を引いたので,医学書院がこの第3巻からの出版を引継ぐことになったという。採算を無視して学問に貢献しようとする医学書院に満腔の敬意を表したい。
しかし本来,佐野先生の意気に感じその偉業を支援すべきは,出版社よりも,その本の恩恵を受ける研究者であるべきであろう。自国の学者が成しとげた価値ある仕事を正当に評価し,その営為に共感し,その本を購うことで支援の気持ちを表す,という気風というか習慣が,日本の学界には足りないのではないだろうか。そういうアカデミックな土壌がなければ,舶来尊重主義から脱した独創的な日本の学問は育たないであろう。
そこまで大上段に振りかざさなくとも,ともかくこの1万8000円という破格の安さの本は,脳の研究者が個人で購入して座右に置いて楽しめる1冊である。まして,医学生物学系の図書館には,そして研究室の書架にも,日本の脳研究の「Handbuch」として必ず備えてほしいとねがうものである。


精神科を専門としない医師の疑問に答える
内科医が知っておきたい向精神薬の選び方・使い方
中河原通夫 著
《書 評》森脇龍太郎(埼玉医大講師・高度救命救急センター)
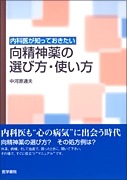 わが国の自殺既遂者は1998年より年間3万人を超えている。そして自殺未遂者は少なくともその10倍以上存在するといわれている。このような自殺企図患者の治療の中心的役割を果たしているのが救命救急センターであるが,自殺手段としては向精神薬を中心とした薬剤の大量摂取を選択することが多いようである。したがって,救命救急センターに長く勤務していると,向精神薬の薬理作用にも自ずから詳しくなるものである。
わが国の自殺既遂者は1998年より年間3万人を超えている。そして自殺未遂者は少なくともその10倍以上存在するといわれている。このような自殺企図患者の治療の中心的役割を果たしているのが救命救急センターであるが,自殺手段としては向精神薬を中心とした薬剤の大量摂取を選択することが多いようである。したがって,救命救急センターに長く勤務していると,向精神薬の薬理作用にも自ずから詳しくなるものである。
なまじ詳しくなると,内科外来でうつ病らしき患者にたまに出会うと,向精神薬を処方したくてうずうずしてくる。かねてより坑不安薬や睡眠薬はときどき処方していたが,SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)の登場以来,現在は坑うつ薬も含めて頻繁に処方するようになった。しかし,向精神薬の選択に当たって十分な根拠と自信をもって処方しているわけではない。効果がなかった時の第2選択薬は?効果があった場合はいつまで続ける?などなど,さまざまな疑問が湧いてくる。おそらく一般内科医も同じような疑問を持ちながら向精神薬を処方しているのではないかと思われる。
研修医も含めたすべての医療者に推薦する
このような折,まさにタイムリーな本が上梓されたものである。第1章「内科医がよく出会う精神疾患とその治療法」では,日常内科外来で遭遇する代表的な精神疾患について言及しているが,各々の疾患の特徴,治療の手順(専門医に任せるかどうかについても言及),処方例,第2選択薬,副作用とその対策,病気の経過,薬剤の減量法などが簡潔にかつ明瞭に述べられており,上述した疑問が氷解した思いである。第2章「身体疾患に伴って現れる精神症状とその治療法」,および第3章「薬剤によって起こる精神症状とその治療法」では,精神症状を起こしやすい内科疾患および薬剤を取り上げて,各々の内科疾患や薬剤服用中に起こりやすい精神症状の特徴からはじまって,第1章と同様の切り口で治療の手順(専門医に任せるかどうかについても言及),処方例,第2選択薬,副作用とその対策,病気の経過,薬剤の減量法などが述べられている。
さらに第4章「向精神薬の効果と副作用」では漢方薬も含めた代表的な向精神薬について簡便にポイントを押さえて述べられており,精神科を専門としない一般医にとってはたいへん便利であろう。また処方例が具体的に商品名でも提示されているのも実用的で,小生は外来診療に当たってポケットに入れて,必要に応じて参照している。
「内科医が知っておきたい」という前置きがあるが,一般内科医のみならずすべての医療従事者にも推薦したい良書である。本年度から研修制度が変更になり,精神科研修も必須となったようであるが,その研修前に必読の書として研修医の方々にも強く推薦したい。


眼科学において最も高い人気を博す教科書
標準眼科学 第9版大野重昭,他 編
《書 評》三宅養三(名大教授・眼科)
今年もこの教科書で決まり!
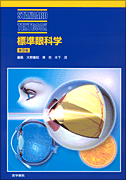 「標準眼科学」の第9版が出版された。この教科書の歴史は長く,初版は23年前の1981年に出版され,その後約3年に1度の間隔で改訂版がでているという実に息の長い教科書である。常に改訂を続けてこられた編集各位に敬意を表する。
「標準眼科学」の第9版が出版された。この教科書の歴史は長く,初版は23年前の1981年に出版され,その後約3年に1度の間隔で改訂版がでているという実に息の長い教科書である。常に改訂を続けてこられた編集各位に敬意を表する。
本書は初版の序で強調されているように,総論を習得した後に各論に進むという形をとらず,現実に出会う眼疾患の具体像にまず重点を置いており,病気の臨床像を理解した後,その背景の病態生理を考えるという,非常に読みやすくあきない体裁をとっている。現在,学生に考えさせる教育方法としてチュートリアルという手法が多くとりいれられているが,この教科書はこの方法にもマッチしているように思われる。さらに,全科にわたって昔とは比べ物にならないほど多くの知識習得を求められる現在の学生諸君の頭脳がパンクしないよう,重要事項を中心に簡潔にまとめられていることも,本書が学生に最も高い人気を博している理由であろう。
もう1つの本書の特徴は図が多く写真の質が極めてよいことである。視覚に訴えることは読者の興味を倍加し,かつ内容が簡潔にまとめられていることで,ついついマイナー分野として片づけられがちな眼科学に学生が興味を持ち,入局のきっかけになるのではと期待もしたくなる。さらにこの教科書は講義の折りの基本資料としてもよくまとまっているように思う。毎年学生の最初の講義で推薦する教科書を示すことになっているが,今年もいつものようにこの教科書で決まりのようである。
『眼科用語集』との符合が課題
ただ1つ,病名で気付いたことを述べておく。最近の多くの教科書で「眼科用語集」に沿わない病名が記載されていることがある。本書でも“眼底白点症”という病名が記載されているが,「眼科用語集」には“白点状眼底”という呼称が示されている。たしかに長年われわれは“眼底白点症”と呼んできたので,「眼科用語集」でこのように勝手に変えられては困るのだが,眼科用語集の病名は日本眼科学会が認める正式の呼び名であるとすると,国家試験や専門医試験では“白点状眼底”のみが使用されることになる。すなわち“眼底白点症”という眼疾患はもう存在しないことになる。次回の改訂で修正していただきたいと思う。

さらに進化したマンモグラフィ検診精度管理における指針
マンモグラフィガイドライン 第2版(社)日本医学放射線学会/(社)日本放射線技術学会 マンモグラフィガイドライン委員会/乳房撮影委員会 編
《書 評》中島康雄(聖マリアンナ医大教授・放射線医学)
 本書は1999年に日本医学放射線学会が中心となって発行した,わが国初のマンモグラフィガイドラインの改訂版である。初版は2000年から導入されたマンモグラフィ検診精度管理における指針の役割を果たし,検診マンモグラフィに携わる医師,診療放射線技師すべてのバイブルとして広く利用されてきた。今回の改訂では現在広く受け入れられている撮影法,所見の記載はそのままの形で,“マンモグラフィの読影の実際”が改訂され,新しく“画像評価”の章が加わり,“精度管理”にはデジタル撮影の管理について追加されている。
本書は1999年に日本医学放射線学会が中心となって発行した,わが国初のマンモグラフィガイドラインの改訂版である。初版は2000年から導入されたマンモグラフィ検診精度管理における指針の役割を果たし,検診マンモグラフィに携わる医師,診療放射線技師すべてのバイブルとして広く利用されてきた。今回の改訂では現在広く受け入れられている撮影法,所見の記載はそのままの形で,“マンモグラフィの読影の実際”が改訂され,新しく“画像評価”の章が加わり,“精度管理”にはデジタル撮影の管理について追加されている。
早期の乳がん診断に必要な要素を網羅
マンモグラフィが早期の乳がん診断に役立つためには,“診断に適したよい画像の提供と十分な知識と能力を持った読影者の存在”があってはじめて実現できる。本ガイドラインは初版からこの点を強調し撮影機器の性能評価,撮影方法,読影の基礎となる乳腺の解剖と乳腺疾患の病理,そしてメインパートであるマンモグラフィ所見用語とその記載方法,カテゴリー分類の読影方法,さらに画像の評価方法とマンモグラフィ精度の具体的品質管理方法が記載され最後に被ばくについて述べられている。第2版で改訂された読影の実際では“局所的非対称陰影”のカテゴリー分類が表の形で簡潔にまとめられた点と“構築の乱れ”について図を示して説明されている。この2つの所見は従来からマンモグラフィ講習会で受講者に伝わりにくい概念であった。このテキストを見ながら講師の説明を聞けば多くの方が納得いただけるようになるのではないかと期待される。また石灰化についての記載が充実し,病理像との関連がわかりやすくなりマンモグラフィの理解が深まるであろう。掲載されているマンモグラフィは初版と同じものだが,今回の写真のほうが高コントラストで画質が鮮明である。こだわりのある著者と出版社に敬意を表したい。新しく加わった画像評価の項はファントムと臨床画像の両者について現在精度管理委員会が行っている画像評価方法が説明されている。特にわが国で普及しているデジタル画像についても具体的に記載されているので施設評価を受けようとしている方には必読である。
以上のように本書は初版発刊後普及してきたマンモグラフィ検診や各地で行われてきたマンモグラフィ講習会での経験を生かして進化した形で提供された最新のバイブルである。また今後のデジタル撮影への展望も読み取れる。マンモグラフィに携わる医師,技師はもちろんのこと,マンモグラフィ検診を計画している事業者およびマンモグラフィ製造企業およびフィルム関連企業など,すべての方に必携の書である。わが国が誇るガイドラインとして自信を持ってお薦めする好著である。


呼吸器科医が座右に置く最善の書の1つ
胸部のCT 第2版村田喜代史,上甲 剛,池添潤平 編
《書 評》貫和敏博(東北大教授/遺伝子・呼吸器内科)
CTは現代呼吸器病学に不可欠
 胸部CT撮影は現代呼吸器病学には不可欠の情報源である。約20年の臨床での展開は,肺癌における縦隔進展,胸腔内隣接臓器進展,さらには早期肺癌検診としてはじまった。現在では正確なCTガイド下肺生検,また,PETとの組み合わせによるリンパ節転位診断と,その重要度はますます増加している。
胸部CT撮影は現代呼吸器病学には不可欠の情報源である。約20年の臨床での展開は,肺癌における縦隔進展,胸腔内隣接臓器進展,さらには早期肺癌検診としてはじまった。現在では正確なCTガイド下肺生検,また,PETとの組み合わせによるリンパ節転位診断と,その重要度はますます増加している。
一方,びまん性陰影の鑑別診断では,HRCT技術の進歩,マルチスライスによる撮影時間短縮により,高解像度画像で典型的な蜂巣肺の存在は肺生検を経ずに特発性肺線維症(IPF)の診断を可能なものとした。さらにlow attenuation area(LAA)としての気腫肺,破壊肺のCT像も検出への感度が向上した。ここにようやくHRCT像による線維化肺,気腫化肺の疫学的調査が可能になった。
日本呼吸器学会,厚生労働省「びまん性肺疾患」調査研究班,「呼吸不全」調査研究班は共同でこの作業に着手した。胸部CT撮影の臨床展開でさらに考慮すべきものとして「胸部CT呼吸器家族歴」を筆者は主張している。神経変性疾患における原因遺伝子の特定はその特徴的神経症状の家族集積からはじまる。呼吸器における変性,炎症疾患の臨床症状は長くsilentであり,罹患患者家族の胸部CT撮影による肺影像としての家族歴とその追跡は,疾患原因遺伝子解析への道を開くと期待される。
将来さらに重要な位置を占める分野
こうした呼吸器病学におけるニーズの中で日本語のCT教科書は少ない。今般『胸部のCT』(村田,上甲,池添編)改訂2版が出版された。マルチスライス撮影,被曝線量の説明,また進展固定肺における病理組織像との対比,基礎となる正常解剖の説明も完備している。疾患としてはMRI所見を含む肺癌など腫瘍,肺感染症,びまん性肺疾患と続くが,初版以来の特徴であるCT所見をまとめたBox化箇条書きは,臨床医にとって整理の助けとなり有用である。今回新たに加わった,急速に技術革新が進むマルチスライス撮影の1章,さらに肺機能評価との連携,細葉まで識別可能な超高分解能CTの紹介など,この分野が将来さらに呼吸器病学の中で重要な位置を占めることが理解される。おそらく次版においては付録DVDによる連続CT断層の動的映像やPET情報とCT情報の同一画面表示の試み,吸呼気で動的に理解できる肺機能評価の応用などが加わり,さらに呼吸器科医の興味を掻き立てることであろう。ノックアウトマウス肺のCT像などが加われば,臨床では困難なmolecular変化と画像変化の直接理解も次の課題となる。本書は呼吸器科医が座右に置く最善の書の1つである。
B5・頁642 定価14,700円(税5%込)MEDSi
