短期集中連載 〔全4回〕
ボストンに見るアメリカの医学・
日野原重明(聖路加国際病院理事長)
ボストンに見るアメリカの医学・
看護学・医療事情の現況〔3〕
日野原重明(聖路加国際病院理事長)
【12月30日(月)】 Part.I
Katz准臨床教授室を訪れて
私の今回のボストン訪問の目的の1つは,医学生のためのプライマリ・ケア医学の臨床教育が,どのようにされているかを調べることであった。最近では3年前(2001年)の12月末にも,ハーバード大学の「Primary Care and Preventive Medicine」講座の主任教授であった日本人二世のInui教授を訪れたことがあるが,現在この部門の医学教育担当であるHanvey Katz准臨床教授が,私をオフィスに迎えてくださったので,午前10時に訪問して,詳しい説明をうかがった。
Katz准教授はジョンズ・ホプキンス大学の出身だが,ニューヨーク市立大学で卒後研修を終え,軍隊に服務している間,ハワイに駐在して小児科を専攻し,後にジョンズ・ホプキンス大学の医学部小児科の内分泌学を専攻した方である。
ハーバード大学医学部の「プライマリ・ケア・クラークシップ」
彼の話では,入学1年の後期には患者の「インタビュー」と「診察技術」を教える。医学生3-4学年の1月から9月まで,「プライマリ・ケア・クラークシップ」のカリキュラムが学生に提供されているとのことであった。このコースにはKatz准教授の下に,ベス・イスラエル・ディーコネス・メディカルセンター,プリガム・ウィメンズ病院,ハーバード・バンガード・ケンモア・センターの内科医,または小児科医の7人の教官がいる。そして,その指導のもと,医学生にはそれぞれ9か月連続して,患者や家族の健康上の問題の処理を担当させている。医学生とはいえ,家庭医のように患者や家族に付き添って外来診療や訪問診療を行なう。入院すれば病棟医とともに,その患者を担当させるのである。そして,その患者や家族にどんな健康上の問題が生じても,まずその担当の医学生が関与し,健康保険加入か否かに限らず,また貧富を問わず,医学生が患者や家族のケアに参与するのである。
もともとハーバード大学では,将来,教職や研究者になる人材を養成することをめざした教育が行なわれてきた。しかし10年ほど前からは,医学生の半分は女性となり,しかもまたその半分はアジア系や,その他の外国人となった。そして,ハーバード大学出身者もプライマリ・ケアに携わる医師が少しずつ増してきたのである。
そのために,このような長期の「プライマリ・ケア・クラークシップ」のカリキュラムが医学生にはじめられたのである。
「プライマリ・ケア」について
「プライマリ・ケア」,または「総合診療」は,そもそもアメリカ合衆国の西海岸のワシントン州のシアトル市にあるワシントン大学医学部で,40年前から先進的にはじめられたものである。ワシントン州には立派な医学校があるが,この州の周囲のアラスカ,モンタナ,ネバダ州などでは無医村が多く,医学校もないことから,40年前から家庭医学講座が開設されていた。先に述べたInui教授は,約10年前にハーバード大学のプライマリ・ケア医学部門の責任者としてシアトルから移られたのである。
私は自治医科大学が開校された頃,この大学の家庭医学部門の客員教授に招聘されたことから,それ以後も自治医科大学とシアトルのワシントン大学の家庭医学部門との連携を構築する努力をしてきた。
「プライマリ・ケア・クラークシップ」の7つの到達目標
さて,このハーバード大学のプライマリ・ケア・クラークシップの到達目標は次の7か条とされている。(1)何か月にもわたって,患者の疾病と臨床面での人間関係を作る。
(2)患者の臨床上の質問に,できるだけ上手に答える。
(3)疾病を予防し,健康増進を図る。
(4)臨床上のあいまいな点に上手に対処する。
(5)ある場合には,制限されたお金や事情の枠の中でその資源を最高に活用する。
(6)ヘルスケアチーム(保険診療)の中で働く。
(7)家族の間や,その患者の持つ文化的背景の中で,患者と相談して上手な意志決定をして患者を支援する。
「プライマリ・ケア・クラークシップ」の具体的内容
医学生は3学年の1月までには,内科や小児科の病棟でのクラークシップは終わっている。そこで,3学年から4学年までに行なわれる9か月のクラークシップの最初の3週間は,プライマリ・ケア医の指導下で外来診療に出る。つまり,市中や市外の住民の文化や言葉の違う人の中で働くのである。また,ホームレスや同性愛者にも触れる。指導医は,学生の病歴作り,診察術,検査結果を正しく判断し,うまく対処するプランを立て,学生の成長の段階で,時々(少なくとも月に1日は)すべての学生と指導医が集まって討議する。
一方,学生の指導医のための訓練のセッションを実施した後,4月と9月の2回にわたって,学生の臨床能力の評価が指導医によって行なわれる。学生はこの期間中,止むを得ない事情のある場合には,4回までに限り休むことが許されるが,他は出席が厳守されるとのことである。
なお,学生は患者の診療にあたる際に,守らなければならない倫理的,対人的姿勢や,患者の守秘義務,患者とのラポール,同業の医療従事者とのよい人間関係を作ることなどの指導がなされる。
このグループの教室での学習テーマとして掲げられているのは,筋肉,骨の訴え,保険医療に関すること,HIV,青春期の問題,小児の症例,婦人の健康,医学生による症例発表などである。
また,「プライマリ・ケア・クラークシップ」の基本としては,下記のものがあげられる。
(1)症例を通して学習する。
(2)一方的な教壇的教育でなく,教える者と学ぶ者が双方に学ぶ体制を作る。
(3)患者の問題中心に研修がされる。
(4)学生はスプーン・フィデーングでなく,生涯を通しての自主的学習法を学ぶ。
そして,最後に学生の診断能力の評価が行なわれる。
以上がKatz准教授によって示されたカリキュラムの大要である。
ハーバード大学における「代替医療」教育
ところで,Katz准教授にハーバード大学における「代替医療」の教育の状況をうかがったが,10年以上前から代替医学として,針や灸,ホメオパチー,その他,漢方薬による治療などの「代替および総合医療」に関する教育や研究がDavid Eisenberg教授を中心に広く行なわれているとのことである。また,学生は希望すれば,そのコースを取ることができるという。Katz准教授は,長い臨床経験と健康保険システム(HMO)についての深い知識があり,ハーバード大学系の諸機関の保険診療管理の仕事も担当されているとのことであった。なお,ハーバード大学や教育病院とは少し離れた建物の中に,この部門の教授のオフィスがある。古い歴史を持つハーバード大学としては,まだ歴史の浅い部門と言えよう。
|
『New England Journal of Medicine』の編集会議に出席する
この日の正午は,Jeffrey M. Drazen教授とLee教授に招かれて,ハーバード大学医学部のGate Way図書館の6階にある『New England Journal of Medicine(NEJM)』の本部で催されるこの雑誌の編集会議に出席した。Drazen教授はハーバード大学医学部の呼吸器科の教授で,喘息の新薬開発で有名な学者であるとともに,『NEJM』誌の編集長である。私は長い間,日本での数多くの医学雑誌の編集に従事してきたので,内科の専門雑誌として,世界で最も有名で,なおかつ格調の高いこの雑誌の編集方針と,その編集作業に大変強い興味を持っていた。
実は,昨(2003)年7月に京都で開かれたプライマリ・ケア研修会に,たまたまDrazen教授とLee教授が,講師として来日された。そして,その際にお話しする機会を持ち,その年の暮れに私がボストン訪問を予定していることを告げたところ,「年末に開かれる『NEJM』誌の編集会議に招待する」と言われ,今回,その約束が実現されたわけであった。
『NEJM』誌の編集体制は,Drazen編集長,Lee副編集長以下,20名の編集委員(ハーバード大学外から6名)からなるが,残念ながら日本人の医師は参加していないとのことであった。定例の編集委員会は年に8回ほど開かれる。
本部では専任の職員(多くはPH.Dを持ち,編集の専門家である)が数名おり,論文の査読を援助して,図表や文章のチェックを行なう。統計学者も参与しているということを知り,さすがに天下の専門誌だと思った。内科医のほかには,ハーバード大学小児科のJ. Ingel Finger教授も編集長代理として参加されていた。
査読は専門分野別に,あらかじめ外部の専門家に依頼してある。1論文に2人の専門医師が担当し,査読期限は通常2週間とのことであった。しかし,例えばSARSなどのように,医学上の緊急事態が発生した時の論説は,発表が急がれるので査読は2日間に制限される場合もある,という厳しい条件で行なうと話されていた。この会議は軽い昼食ではじまり,そのあと2時間会議が続けられる。
今回のボストン訪問で,このような長い歴史を有する(ちなみに,創刊は1812年である),この名門専門誌の編集会議に出席できた僥倖を,あらためて感謝したのである。
ハーバード大学医学部の現状
現学部長のJoseph B. Martin博士は,今回はあいにく故郷のカナダに帰っていて不在であった。しかし,幸いこの編集会議の席上で私は,Lee教授から最近のハーバード大学医学部の動向がまとめられたMartin医学部長による報告書『Harvard Medical School Dean's Report(2003-2004)』を入手できた。ハーバード大学の医学部長について触れると,3年前に退官されたTosteson前学部長は,その前はデューク大学医学部の生理学教授であった。私が興味を持ってきたカリウムの代謝の専門家だったこともあって,後にハーバード大学医学部長になられてからも,ボストンを訪問した時には,時々お会いして医学教育についての意見をしばしばいただいたのである。
現学部長のMartin教授は,カリフォルニア大学サンフランシスコ医学部長,そして後には,同校の学監(Chanceller)をされていた。
数年前に,この大学病院をサンフランシスコの近郊にあるスタンフォード大学病院と統合することによって,病院経営の経済的負担を少なくさせることを発案され,かつ実行されたのであった。その直後の1997年に,Martin博士は母校のハーバード大学医学部長に招聘されたのである。
|
ハーバード大学医学部の関連病院および研究所
次に,先に述べた『Harvard Medical School Dean's Report(2003-2004)』に拠って,ハーバード大学医学部の関連する教育病院および研究所を下の表に示す。ハーバード大学医学部はもともと大学自体に病院を持たず,教育病院として下表のブリガム・ウィメンズ病院とMGH,さらにベス・イスエラエル・ディーコネス・メディカル・センター,その他の関連病院を持っており,大学の臨床教育のためにはそれらの施設が提供されているのである。
ベス・イスラエル病院はユダヤ人系の古い歴史のある病院であった。私は「(財)ライフ・プランニング・センター」を東京で発足させた1973年以来,当時の院長Rabkin先生と親しくなり,彼の30年にも及ぶ院長経験から多くのノウハウをいただいてきたのである。
Rabkin先生が病院長を辞された後,ベス・イスラエル病院とその向かいにあるプロテスタント派のディーコネス病院とが統合し,「ベス・イスラエル・ディーコネス・メディカル・センター」となったのである。
しかし,これは当初の期待通りにうまく統合されず,多額の負債を強いられた。Rabkin先生が院長を辞任された後,2人の医師が院長になったが,病院の経営が困難になったので,今年は医師でない病院管理者が院長になられたとのことである。
いずれにしてもハーバード大学医学部は,これらの異なった系統の病院群と密接な連携をとり,それらの病院の自立的な経営の下に,学生の医学教育や研究が行なわれているのである。
したがって,同じハーバード大学の内科の教授といっても,別々の病院で診療・教育・研究が行なわれているのである。もちろん,ハーバード大学直属の数多くの研究所もあって,そこにも多数の教授や准教授,助教授,助手が所属している。
ハーバード大学医学部の経営内容
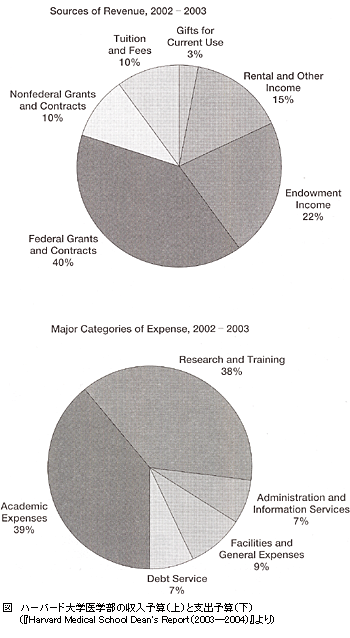 私立大学であるハーバード大学医学部の総予算額は不明であるが,最近の収支予算の実績は図に示すごとくである。
私立大学であるハーバード大学医学部の総予算額は不明であるが,最近の収支予算の実績は図に示すごとくである。
これによると,学生からの授業料は総予算の10%,連邦政府からと民間からの寄付収入は40%,ハーバード大学の財産投資からの収入が22%となっている。
これに対して支出は,医学部経営のために教育費が39%,研究費が38%で,合計76%が研究ならびに教育に支給される。事務費と情報費には7%,設備,その他運営費には9%支払われる。日本の多くの私立の医学校とは大きな差があり,いかに政府や民間からの寄付や財産運用からの収入が大きいかが一目瞭然である。
なお,NIHからの研究費については,例えばこの大学の教授およびその研究チームに,年間10億円の研究費が約束されるとすれば,ハーバード大学のごとき名門校にはその80%近くがoverheadとして大学側に上乗せされて支給されるのである。学問的業績があまりめだたない大学のoverheadは50%位のものになるという。
アメリカでは教授の転職が多いが,有能な研究者を大学がスカウトすれば,その教授が政府や民間から獲得する研究費に上乗せされてその大学に給付されるので,よい教授を招くことによるメリットは大学として大きいのである。
ハーバード・メディカル・インターナショナルの活動
ハーバード大学医学部は,ボストンでの医学教育・研究・診療を行なう以外にも,国内各地の実地医家のためのセミナーを単独,または他の地方大学と共催で企画している。日本に関しては,聖路加国際病院が持つ公益財団法人「聖ルカ・ライフ・サイエンス研究所」と,ハーバード・メディカル・インターナショナルとの共催で,日本の実地医家のためのフォーラムが2002年以来毎年1回,「Harvard Primed」の名前で東京もしくは京都において開催され,日本におけるプライマリ・ケアの普及に貢献している。なお,ハーバード大学はインド,中東,ドイツ,オランダなどの医学校にも働きかけ,Problem solvingを中心として,前述した「New Pathway」の自己学習を中心とする医学教育の普及に努めている。また,中国やインドの大学病院の教育,研究を支援しつつ,将来の各国のヘルスケア・システムの発展にハーバード大学が参与できるように努力している。
ハーバード大学医学部の学内の研究活動として2003年に特記されることは,NIHからの研究助成が前年度より9%も増したことである。これらの研究資金とともに有能な学者が外から数多くスカウトされたためであり,2003年度はBiological Chemistry(生化学)とMolecular Pharmacology(分子薬理学)の研究所,さらにNeurology(神経学)研究所の陣営が大変充実されたと学部長は報告されている。
