新春随想
2004
医療と仏教
河合隼雄(文化庁長官) 医療と仏教,などというと「縁起でもない」と顔をしかめられるかも知れない。もっとも,その「縁起」という言葉は仏教の言葉であるのだが。
医療と仏教,などというと「縁起でもない」と顔をしかめられるかも知れない。もっとも,その「縁起」という言葉は仏教の言葉であるのだが。
医療現場と宗教家
アメリカの病院では,病気を本人に告知することがはじめられてから,患者の要求を満たすために多くの宗教家を病院に来てもらうようにした。病床において,患者と心の問題について話し合うためである。ところが,日本で,もし墨染めの衣を着たお坊さんが,病院に多く出入りしていたら,患者さんたちは嫌に感じる人が多いのではないだろうか。日本ではお坊さんといえばすぐにお葬式を連想するのではないだろうか。しかし,本来の仏教は,死に対してはもちろんだが,生に対しても教えてくれるものである。あるいは,人間にとって幸福とは何か,幸福に生きるにはどうすればいいか,などということにも関連してくる。仏教は生きるための哲学や心理学にも大いに関連してくるのだ。
仏教には多くの生きるための知恵が語られている。しかし,残念なことに,日本人は仏教のことを知らなすぎる。と,偉そうに言っている私自身も,子どもの時から長い間,仏教に関して無関心であった。しかし,心理療法という仕事をするようになり,人間がいかに生きるか,そして,いかに死ぬか,ということに深くかかわるようになり,迷い迷いしながら仕事を続けているうちに,だんだんと仏教に心を惹かれるようになってきたのである。
心理療法を行なううえで,私は西洋のユングの心理学に助けられることになったのだが,フロイトやユングなどの深層心理学の考えは,二千数百年も以前に,仏教においては考えられていたことと言ってもよいだろう。
科学技術の進歩と仏教の役割
ただ,問題は今日,現代人が大きい頼りとしている科学技術は,仏教国からではなく,キリスト教国から生まれてきた,という事実である。このこともわれわれは忘れてはならない。科学技術の発展の恩恵を,現代人は多く受けており,医療の分野においても,もちろんである。生命科学の近年における発展は目覚しいものがあるし,医療器械や薬物の進歩発展によって,医療はどんどん発展している。しかし,どんなに医療がよくなっても,結局,人間は死ぬことに変わりはなく,医療はそのことを不問にできない。
アメリカのNSF(National Science Foundation)の長官,Rita R. Colwell氏が,科学が今後に究明してゆくべき課題として,「宇宙,生命,現実,心」の4領域をあげたという。これは,科学と宗教との関連性が深くなることを意味しているし,医療がこれに深くかかわっていることは明白である。医療においては生命,現実,心,すべてが大切である。現実というとどうして,と思う人がいるかも知れない。しかし,患者の体験している現実と医療関係者の体験している現実のズレなどを考えると,よくわかるだろう。
このような科学と宗教とのかかわりのなかで,仏教の果たす役割は大きい,と私は考えている。今後の研究が待たれるのである。
漢方医学・最近の話題
寺澤捷年(富山医科薬科大学副学長・附属病院長) 1868年に誕生した明治新政府は近代国家への施策の一環として医学教育の近代化に取り組んだ。1874年(明治7年)医制を定め,その範をドイツに求めた。これ以降,それまでわが国の医療を支えてきた漢方医学は公的な医学教育の場から排除されたのである。
1868年に誕生した明治新政府は近代国家への施策の一環として医学教育の近代化に取り組んだ。1874年(明治7年)医制を定め,その範をドイツに求めた。これ以降,それまでわが国の医療を支えてきた漢方医学は公的な医学教育の場から排除されたのである。
漢方医学が前近代的なものと見なされた最大の理由は,医学の基礎となる解剖学・生理学が実態からかけ離れたものであったことであろう。気・陰陽・五臓六腑の宇宙論的な哲学を墨守することはまさに中世の蒙昧であった。また薬物療法の根幹をなす生薬の成分も当時の技術力では分析不可能な領域であった。事実,長井長義が麻黄(マオウ)から塩酸エフェドリンを抽出することに成功したのは1892年(明治25年)のことである。
このあたりの事情は日本近代化の推進者であった福沢諭吉の著述『学問のすすめ』や土屋雅春著『医者の見た福沢諭吉』(中公新書)などに詳細に記されおり,当時の知識人の漢方医学に対する嫌悪の情がどの様なものであったかを知ることができる。
そして,繊維・鉄鋼・石炭・鉄道の諸産業の発達を目の当たりにして,医学・医療も西欧化へと,正に怒涛のシフトを成し遂げたのである。国民大衆が伝統文化を捨てて,近代化をとげて行った姿は司馬遼太郎著『明治という国家』(NHKブックス)から伺い知ることができるが,医療界の地滑り的な大変革が極めて短時間のうちになされたことは私にとっては驚きであり,今後の研究課題でもある。
一方,大変に興味深いことには,漢方薬についての国民のニーズは連綿として続いた。特に家庭配置薬や各種の婦人薬の分野にその足跡を見ることができる。そして大正末期から昭和の初期には漢方医学そのものの価値を再認識する動きが出てきた。最近,たまたま幸田露伴著『努力論』(岩波文庫)を手にしたが,露伴が漢方医学の本質について明晰な分析と評価を与えていたことを知ったのである。
漢方医学とEBMの融合
さて,いよいよ本論に戻って「最近の話題」について述べたい。その第一は漢方薬を取り巻く世界の情勢が大きく変化したことである。これは欧米諸国における相補代替医療の勃興と連動している。その最大の価値基準の変化は漢方薬をはじめとする天然薬物を「1つの薬物単位」として見なそうという動きである。もちろん,薬物としての品質を担保するためにHPLC(高速液体クロマトグラフィー)による成分分析や,NMRによる化学構造の決定は必要であるが,どの成分がどのような薬理作用を持つかを個別に探索することはひとまずおいて,その多成分系の薬物が総体として有用なのか,安全なのかを評価しようとする考え方である。この考え方を土台として,漢方医学とEBMの擦り合わせが可能になった。私どもの仕事を例に取ると,「釣藤散」は11種類の生薬で構成されているが,この水性エキス製剤を1つの薬物単位とし,プラセボを用いて脳血管性痴呆に対する二重盲検臨床比較試験を実施し,その有用性を明らかにした。近年,この考え方に基づく漢方製剤についてのエビデンスが集積しつつあり,日本東洋医学会が高いレベルのものについて『漢方治療におけるEBM』(日本東洋医学会雑誌53,2002)を公表した。また私どもは10症例以上の症例集積研究まで範囲を広げ,『EBM漢方』(医歯薬出版)として公刊したところである。
医学教育への導入とCOEプログラム採択
第2の話題は,医学教育コア・カリキュラムに「和漢薬を概説できる」という項目が取り入れられたことである。疾病構造の変化に伴って漢方医学に対する社会のニーズが高まっている。これに対応するために,医学部教育においても漢方医学の基礎知識を修得することになった。歴史的に見て,130年ぶりの画期的な動きである。さらに喜ばしいことに,医学教育コア・カリキュラムに呼応して,薬学教育のコア・カリキュラムにも東洋医学とこれに関連する漢方製剤あるいは生薬についての教育が大きくとりあげられたことである。第3の話題は,東洋医学のパラダイムを評価しようとする動きである。私どもが提案した21世紀COEプログラム「東洋の知に立脚した個の医療の創生」が採択された。これは東洋医学のパラダイムと西洋医学のパラダイムの融和を提案したものである。具体的には糖尿病性網膜症,アトピー性皮膚炎,関節リウマチと更年期障害を対象として,東洋医学のパラダイムでこれを亜群に分け,血液中に出現する蛋白質をプロテオーム解析し,DNAチップによるパターン解析と併せてその亜群の妥当性を検証しようとする試みである。このプログラムをとおして,東洋医学とその薬物研究に関するオールジャパン・コンソーシアムの形成をめざしている。
疾病の予防と治療に当たって,洋の東西はない。東西医学の融和はわが国において可能な研究領域であり,その成果はわが国のみならず広く世界の人々の幸福に連なる道であると確信している。
4+4または(4)+4構想
齋藤宣彦(日本医学教育学会会長,聖マリアンナ医科大学教授・内科学)今どきの医学生たち
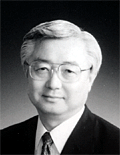 医学部・医科大学の入学試験で,どのような能力・資質を測定すべきかを若い医師たちと討論したことがある。話が佳境に入ってくると,卒後3-4年の若い医師でさえ「今どきの医学生たちは……」などと年寄りじみた言葉を遣う。そして「先生から見ると,僕らも若い連中とたいして変わらないじゃないかと思うかもしれませんが,いやあ,違うんですよ……」となる。
医学部・医科大学の入学試験で,どのような能力・資質を測定すべきかを若い医師たちと討論したことがある。話が佳境に入ってくると,卒後3-4年の若い医師でさえ「今どきの医学生たちは……」などと年寄りじみた言葉を遣う。そして「先生から見ると,僕らも若い連中とたいして変わらないじゃないかと思うかもしれませんが,いやあ,違うんですよ……」となる。
彼らによると,学力や知識は今の入試でよい,合格スレスレでも入学してからマジメにやれば,余程のことがないと落伍はしないだろうという。
「じゃ,“今どきの医学生たち”にないものは,なに?」と聞いた。
曰く,協調性がない,マニュアルがないとできない,地道な仕事を嫌がりすぐに結果を出したがる,日本語が話せない,文章が書けない,ちゃんとコミュニケーションができない,奉仕の心がない,幅広い知識や文化を身につけようとしない……など,出るは出るは。
そして「学力試験だけじゃなしに,こういったことのチェックを入試に反映させてもいいんじゃないですか」と。
入学者選抜法の問題か?
「じゃ,どうやって?」と問い返すとすぐには妙案は出ない。しばしの沈黙後,「ボクたちもそうだったんだよな,きっと。そんな試験があったらパスできなかったかも」なんて殊勝な発言も出る。そして突然「だからなんですよ。医療事故が多いのは!」と。なるほど,そうきたか。確かに,協調性がなくって,マニュアル人間で,地道な仕事を嫌がって,すぐに有名になりたがり,患者さんや同僚などともちゃんとコミュニケーションがとれないとなれば,ことは医療安全教育カリキュラム整備以前の問題である。とすれば,医学部入試に,アメリカのMCAT,オーストラリアのGAMSAT,韓国のMEETのような総合試験をすべきか。それを行なうことで果たしてチェックできるのか。かつてはわが国でもMCATを改変したタイプの試験を実施した大学もあったが……今後の検討課題山積である。
18歳で医学の道に進むことの可否を決めるのは,かなり勇気の要ることだ。本人が,自分が医師に向いているかどうかと自問しても,医師の姿はテレビドラマか小説くらいでしか知らない受験生が多い。入試担当教員だって,わずかな面接時間で医師向きの資質の有無なんか判断できるわけがない。そして入学してしまえば「君は,どうも向いていないようだね」などとは迂闊にはいえない。「教員の教育能力が低いせいでしょ! educationのeduceってのは,学習者の潜在能力を引き出すことだっていいませんでしたか?」と切り換えされたら「グー」程度はいえるがそれ以上は無理。
もちろん,18歳という若さでも,こういう人が医師になってくれればボクが診てもらいたいと思う人材はたくさんいるし,昨今,取り沙汰されている4年生大学卒業者を医学部に入学させて医学教育を行なう“メディカルスクール”構想もよい制度だと思う。となると,わが国の80医学部医科大学のうち,すべて自大学で4+4の8年生をとる大学と,前半の4年は他大学で学習し学部卒業生用を採用する(4)+4年制メディカルスクールとが共存してもよいのではなかろうか。
小児医療と自治体病院
小山田 惠(全国自治体病院協議会会長) 新年おめでとうございます。医療改革が叫ばれてから久しく,小泉内閣の聖域なき構造改革が声高く騒がれてからでさえ3年が経つというのに,国民が望む改革は何一つ進展せず経済優先の医療費抑制だけが先取りされております。
新年おめでとうございます。医療改革が叫ばれてから久しく,小泉内閣の聖域なき構造改革が声高く騒がれてからでさえ3年が経つというのに,国民が望む改革は何一つ進展せず経済優先の医療費抑制だけが先取りされております。
自治体病院の危機
平成14年度の診療報酬マイナス2.7%の影響はどの病院にとっても大きな打撃だったと思いますが,私ども自治体病院では,特に300床以下200床を持つ中小病院の約7割が赤字経営を余儀なくされ,累積赤字がさらに増えることが予想されています。自治体病院が一般会計から多額の繰り入れがあっても,なお赤字になることについては,これまでも各方面から批判され経営の悪い自治体病院は不要だという議論が各地で起きていることを私どもも深刻に受けとめております。病院経営に不馴れな病院長,事務長の資質,経営責任の不明確さといった基本的欠陥のほかに年功序列型の公務員給与体系による人件費の高騰,建設設備から物品購入すべてが入札で決められ,さらに情報公開法によってすべて購入価格を公表しなければならないから高く買わされる,というようなことが経営改善の大きな障害になっています。しかし病院の経営悪化が病院を抱える自治体の財政破綻を招くようになれば病院そのものの存立が危機に立たされます。
小児科医も病院も限界
ということで,今私たちは開設者である自治体の首長と一体となって健全経営に向けて取り組んでいるところであります。しかしどんなに工夫しても採算が取れない,苦労すればするほど赤字が増える部分があります。それは自治体病院に課せられた政策的医療ですから国にそれ相当の負担をしてもらわなければやっていけません。が,実態はちがいます。その1つが小児医療であります。もともと小児医療は病院に嫌われる診療科ではなかったのですが,この10年来小児の入院が敬遠されるようになったのです。1990年小児病床を持つ病院が全国で4110あったのが1999年には3528に減少,この一年間で200の病院が入院をなくし外来だけにしました。少子化,医師不足という背景もありますが,現在の診療報酬では小児入院は病院経営を強く圧迫するからです。これは公的病院小児科勤務医の会がまとめたデータですが,2003年全国にある小児病床は3万6189床で,経営主体別でみると自治体病院が最も多く36.5%,大学16.9%,国立9.2%,日赤5.6%,済生会2.1%で民間は9.3%であります。
自治体病院は,たとえ不採算でもその地域が必要とする医療はしなければならないのが設立の基本理念ですから,小児病床をなくすわけにはいきません。問題は経営だけではありません。小児科医にかかる労働荷重も放置できない限界にきています。小児科医12名で365日24時間小児救急をやっている病院でのこれら医師の当直回数は1人月8回とのことであります。
小児医療を自治体病院にしわ寄せしていく状況の打開に,全医療界のご理解とご支援をお願いして年頭のご挨拶といたします。
いよいよはじまる新医師臨床研修制度
大谷藤郎(国際医療福祉大学総長,新医師臨床研修制度施行準備有識者会議委員) 今年4月からいよいよ新医師臨床研修制度がはじまる。
今年4月からいよいよ新医師臨床研修制度がはじまる。
厚生労働省のワーキンググループの一員として新制度創設の一翼に参加してきた者として,諸機能がスムースに作動して所期の目的が達成に近づくことを切に希望する。
インターン制廃止から新制度創設へ
私は今から40年近く前,昭和40年(1965)末から44年(1969)まで,旧厚生省医事課でインターン問題担当官として,戦後のインターン制度廃止とそれに代わる任意の臨床研修制度創設の仕事にかかわった。その頃,厚生・文部両省共同の審議会の座長を務められた樋口一成慈恵大理事長はとっくに死去され,副座長を務められた懸田克躬順天堂大学長も15年11月7回忌の偲ぶ会が開催されたようなわけで,当時の事情を知る関係者も少なくなった。そのような次第で老齢を省みず,ワーキンググループに参加させていただいて,当時の関係者が果たせなかった理想に一歩でも近づけたいと念願した。ワーキンググループに参加して,40年前の騒動の時と決定的に違うのは,前回は国による義務化を否定し,ただちに廃止せよの声が大勢を占めていたのに対して,今回は義務化の法律が既に通過していることもあり,必修義務化に反対の声は少なく,前回の大衆運動のような激しい抗議行動も認められなかった。それだけ政府やワーキンググループ,各団体の責任者など創設の議論に参加する関係者の責任はきわめて大きいと考えられる。
実際今回の関係者の討議はきわめて熱心で,前回に比べて実務的項目についての検討は建設的に着々と進んだという印象を受けた。研修医については,「臨床研修の必修化」,「研修の到達目標(必修7科の研修による基本的診療能力の修得)の達成の義務づけ」,「研修プログラムによる病院の自由な選択」,「研修専念義務等の項目」,また臨床研修実施病院については,「指定基準の見直し(地域医療実践病院の臨床研修への参入拡大)」,「新スーパーローテート方式の実施」,「研修の質の確保のための指導,評価体制の確立」,「研修医に対する適切な処理の確保(アルバイトを原則禁止)」,「研修プログラムの公開と研修医の公募(マッチング)」などの項目が専門家の熱心な討議を経てそれぞれまとめられた。それはそれで画期的な成果をあげられたと評価する。
依然残る問題群
継続した取り組みが必要
しかしながら,それで問題はすべて解決したとは言えない。40年前にももっとも問題視された次のような課題については今回も必ずしも明確な解決がなされなかった。したがって引き続き医学界も行政当局もこれにフォーカスをあてて取り組まなければ,新臨床研修制度が完成したことにはならない。
第一には財政問題である。臨床研修制度に必要な経費は600億円とも700億円とも言われる。これに対して筆者がこの記事を書いている11月の時点では,厚生労働省事務当局は国プロパーで212億円,残余は健康保険法による診療報酬に財源を求めたいとの考えを示した。前者は12月の財務省との折衝,後者は2月の中医協の審議を待たなければならない。臨床研修の実をあげるためには財源確保を明確にする必要がある。
第二には指導医の指導が質的量的に担保できているかという点について不安がある。
第三にはプライマリケアを中心とした新臨床研修が終了した時点で,その後に連結されるべき専門医研修についてのシステムはどうなっているかという心配。このシステムについては,医学界において,あるいは大病院においてそれぞれ独自にお立てになればよいのではないか,と考えるが,その代わり,その内容はしっかり開示されて,誰もがその権威と公平性を認めるものであってほしい。
いずれにしてもよい医師を育てるための制度について,今回の発足をもって論議を終わらせてしまうということにしてはいけない。
春は今どのあたり
久常節子(慶應義塾大学看護医療学部教授)靄がかかって見えない
 この歳になって日本画を習いはじめた。
この歳になって日本画を習いはじめた。
3-4時間の間で,描くことに集中するのは30-40分ほど,後は食べたり,飲んだり,しゃべったり。2人で習っているが1人は先生のおしゃべりの相手をつとめ,もう1人はお茶の入れかえや軽食づくりを担当する。今まで体験したことのない時間の使い方だ。しかし,妙に癒される。先生の褒め上手に感心しながらも素直にうれしい。プロの絵? と見間違うほどに加筆,修正された成果物に対する満足感とともに,もう1年も続いている。
暮れには,翌年の干支の猿の土鈴をモデルに,白麻紙ボールドに金箔を貼り,その上に描いた。年賀状にもこの白い猿の絵を使うことにした。右手を額にかざし遠くを見ている。何を見ているだろう。いつの間にか白い猿と話をしていた。
「何を見ているの?」
「看護の春はどのあたりか見ているんだよ」
「看護の春は近いの?」
「それがね,靄がかかってはっきり見えないんだ」
取り残された看護制度改革
10数年前,役人になってはじめて「法律や制度でこう決まっているから,仕方がない」という捉え方から「法律や制度は変更したり廃止したり,新しく創ったりすることができる」ことを実感した。私が在職した頃,医療提供体制の抜本改革が検討され,医療関係職の教育や配置の問題点も取りあげられた。例えば医学教育は研修が義務化され実質8年教育に,薬剤師は4年教育から6年教育に,栄養士は2年教育から4年教育に時代の要請に答え,通常の手続きを経て改善されたのだ。
しかしそんな中,看護の制度改革は十分ではなかった。医療はいろんな職種で構成されるものだが,医療提供体制は看護の質に左右されると言われる。しかし,にもかかわらず看護教育の改善や急性期の看護の配置は,診療所経営者の利益を代表する医師会の反対にあい,つぶされてきたのである。皆保険体制をとらない米国の配置の豊かさは別として,全国民をカバーする公的保険や公的医療提供体制をとる国,例えばドイツやイギリスでは急性期病床での患者対看護師の割合が1対1であるのに対し,わが国では3:1となっている。これは準夜や深夜の看護師数は50人の変化の激しい急性期や手術したばかりの患者に対したった2人しかいない状況である。寝がえりすらできない患者が排尿したくてナースコールを鳴しても,看護師がすぐかけつけることはとてもできない配置なのである。
薬の種類は他の国々の1.5-2倍使い,入院期間は4倍ほども長いにかかわらず,上述のような経緯の中,看護の配置だけは3:1と決まったのである。
春よ,早く来い!!
この頃,年のせいか入院する機会がある。そんな時,看護師の患者あたりのあまりの少なさが回復を遅らすことを気にしてきた。看護師が医療事故を心配し,それが患者の行動の抑制につながってきている様子が見てとれた。看護教育や数の改善を抑えることは,患者にとっては病のつらさに加え,きびしい看護環境とあいまって逃げ帰りたい入院体験につながるだろう。
こうした状況は,看護者120万人の政治や政策決定過程の関心の薄さが招いたことだと,情報提供体制の整備や教育が必要不可欠であることを訴えてきた。それに向けて看護協会や連盟は一歩を踏み出しているだろうか,踏み出し方の方向を間違うと事態は停滞したままである。
一看護職の立場から何ができるだろう。干支の猿さえ靄のなかの状況は見えないようだが……。
春よ,早く来い!!


