〔寄稿〕
在宅排泄ケアの処方箋を求めて
地域医療在宅排泄ケアセミナーを開催して
奥井識仁(横須賀市立うわまち病院低侵襲手術センター副センター長)はじめに
 在宅医療において排泄は大切な項目の1つです。近年,都市部を中心とした在宅排泄介護についてのセミナーなどが行なわれるようになっています。しかし,まだまだ全国には排泄ケアの講習会や勉強会の機会がない地域が多くあります。
在宅医療において排泄は大切な項目の1つです。近年,都市部を中心とした在宅排泄介護についてのセミナーなどが行なわれるようになっています。しかし,まだまだ全国には排泄ケアの講習会や勉強会の機会がない地域が多くあります。
在宅医療における排泄の問題は深刻で,僻地などでは本当に苦労の連続です。そんな中,本年8月31日,社団法人地域医療振興協会の全国集会のテーマの1つとして,『地域医療排泄ケアセミナー』を東京の都道府県会館において開催しました。
地域で排泄ケアを担っているのは看護師や介護士であり,そうした人たちが現場においてひとりで迷わずにケアの方針を立てられるようになることを目的としました。僻地でがんばる看護師・介護士をはじめ,内科医・泌尿器科医・婦人科医などさまざまな職種の人が集まり,おむつやカテーテルなどいろいろな商品を紹介しつつ,実践的に排泄の理論・知識を身につけることをめざしました。
ここでは,セミナーに参加した皆さんと交流したなかで得られた在宅排泄ケアに求められるエッセンスを報告します。
おむつの利用
おむつを考えるには,「費用」「交換回数」「製品選び」などいろいろなポイントがあります。今回は「おむつの種類」「夜間おむつ」「むれと細菌数」「海外のおむつ事情」などさまざまな観点から発表がありました。また実際に日本で入手可能なおむつすべてを会場に集め,水を吸わせたりして検討しました。参加者からは以下のような意見が聞かれました。- おむつの構造を具体的に検証できた。水を吸収させる時は,尿道があたる部分へ水を染み込ませて,その後よく手で押してみる。こうすることによって,患者が実際に排泄し,その上から体重が乗った時の様子がよくわかる。全体的に水を吸収させるだけではわかりにくいおむつ個々の特徴が理解できた。
カテーテルの利用
留置カテーテル・導尿用カテーテルともに,数社からいろいろなカテーテルを用意してもらい,実際に触ったり,導尿の練習をすることで体験学習を行ないました。各テーブルに桶と水と全国のカテーテルを用意して,水で濡らしながらの感覚を確かめました。- 留置カテーテルは,親水性のもののほうが表面がぬるぬるしていて挿入時の痛みが少ない。疎水性との違いは短期ではEBM差はないが,長期になると親水性のものがよいとの患者の声が多い。
- 自己導尿カテーテルには,使い捨てタイプと反復使用タイプがあるが,後者については数社からさまざまな種類のものが出ているので,患者にあったものを選ぶことが大切である。
便失禁とストーマ
便失禁は大変重要な問題です。ストーマかぶれなどについて,メーカーの製品説明を担当している荻野泰彦氏にいろいろなスライドを用意してもらい,解説してもらいました。- 硬い便の次には下痢便が待っていることが多い。そのため摘便をすると,その後数日間の下痢が継続することがある。
- 最近発表された肛門の栓(アナルプラグ®)は二分脊椎など神経の病気がある患者さんには有効だが,高齢者の便失禁には向く人と向かない人がいる。いずれにしても腸の動きがよくなるように注意することが大切。
- 尿・便いずれのストーマでも,皮膚の発赤や感染が起こるので,注意が必要。
研究会セミナーを終えて
このほか,看護師の立場から吉田久美子氏が,医師の立場から倉澤剛太郎氏が,実際の経験を紹介しつつ,現場の問題を発表しました。排泄にかかわる知識を身につける機会を地域の看護師・介護士さんの多くが望まれていることを感じたセミナーでした。
僻地で在宅ケアを担っている人は,ひとりで考えてしまう機会が多いので,研究会やセミナーを行なうことはよいことです。難しく考えず,皆さんの目の前の患者さんを,今ある道具と知識でどうしたらケアできるか考えるために,引き出しをたくさん用意しておくことが重要だと思います。
この研究会は新年に横須賀市立うわまち病院(連絡先:総務課046-823-2630)および来年8月に行なわれる第3回地域医療学術集会(Tel:03-5212-9152)でも予定していますので,どうぞご参加ください。
●推薦文献
1)名古屋大学排泄情報センターほか『排泄ケアマニュアル』:無料。インターネットでもダウンロード可能(http://www.m-haisetsu.info)。排尿についての基本的な知識をおさえたい人にはお勧め。
2)老人泌尿器科学会『高齢者排尿障害マニュアル-より適切な対応をめざして』,メディカルレビュー社,2002年(2000円+税):流れに沿って要点を押さえるのに有効。コンパクトにまとまっている。
3)地域医療振興協会監修『在宅でみる排尿介護のコツ』,南山堂,2002年(1700円+税):上記2冊のサイドリーダー的存在で,基礎からかなり詳しい知識が書いてある。排尿日誌の読み方が豊富。排尿と婦人科・肛門科とのかかわりなど,勉強をすすめたい人にお勧め。
| ●地域医療排泄ケアセミナープログラム | |
|
| 奥井識仁氏 1965年名古屋市生まれ 99年東大院修了(医学博士)。01-03年ハーバード大ブリガム&ウイメンズ病院クリニカル・フェロー 03年より現職。94年より排泄の訪問ケアをはじめる。主な著書に『在宅でみる排尿介護のコツ』『内科のための排尿のみかた(共著)』(南山堂),『婦人泌尿器科へようこそ』(保健同人社) | 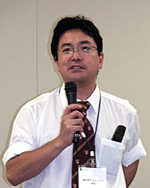 |
