C型慢性肝炎の治療とケア
第29回日本看護研究学会ランチョンセミナーより
| <講 演> | 林 紀夫氏 | (大阪大学大学院医学系研究科教授) |
| <司 会> | 江川隆子氏 | (大阪大学医学系研究科保健学科教授) |
| <質問者> | 峰 孝子氏 | (大阪大学医学部附属病院看護部) |
| 渡辺あや子氏 | (聖路加国際病院看護部) |

さる7月25日,第29回日本看護研究学会ランチョンセミナー企画「C型慢性肝炎の治療とケア」が,大阪国際会議場において行なわれた。看護系学会としては初のランチョンセミナーとなった本企画には,200人を超える参加者が訪れた。
セミナーではまず,林紀夫氏(阪大教授)によってC型慢性肝炎の病態や治療法,ケアのポイントについての講義がわかりやすく行なわれた。後半部では,「質問者」である看護師2名のほか,会場からもC型肝炎のケアに関する質問が相次ぎ,この領域におけるケアの難しさと,関心の高さをうかがわせた。
今回はセミナーの様子をレポートする。なお,本セミナーは第29回日本看護研究学会と中外製薬(株),医学書院の共催で行なわれた。
■講義編「C型慢性肝炎の治療とケア」
林 C型慢性肝炎の治療では,ご存知のようにインターフェロン(以下:IFN)治療が,肝癌への進展を防止するうえで重要な治療法となっていますが,その投与中にはいろいろな副作用が生じます。それにどのように対処していくかが,治療を行なううえで一番難しい点であり,看護師さんの協力が必要となってくるところです。本日は主にC型慢性肝炎の治療が現在,どのように行なわれているか,また今後,どのように変わっていくかということをお話ししたうえで,看護上の問題についてのご質問にお答えしたいと思います。
C型肝炎の特徴
わが国は肝疾患が非常に多い国です。肝疾患というと,アルコールが原因だと一般に思われがちですが,日本の肝疾患の80%以上は肝炎ウイルスによるものです。肝炎ウイルスには現在,A,B,C,D,E型の5種類が見つかっていますが,日本で問題になるのは,慢性疾患を起こすB型とC型です。表1に肝炎ウイルスの種類を示します。
C型肝炎ウイルスというのは約9500塩基のシングル・ストランド(single strand)のRNAウイルスであり,肝臓の細胞で増殖します。本来,こうしたRNAウイルスは増殖能力が高いわけではありませんので,普通は免疫能力でウイルスを排除できます。しかし,C型肝炎ウイルスはヒトの免疫系を抑制することによって体から排除されない特殊なウイルスなのです。
このウイルスは今,日本だけでなく,世界的に大きな問題になっています。アメリカを例にとりますと,15-25年後には日本と同様に肝癌が急激に増えるといわれており,エイズよりもC型肝炎ウイルスの研究費を増やしている状況です。ただ,日本が他の国と少し違うのは感染者の年代層がかなり高齢に偏っていることです。
感染経路は,血液から血液です。表2はB型肝炎との対比です。B型肝炎の感染経路で一番の問題は,母児感染ですが,C型肝炎には母児感染がほとんどありません。輸血,あるいは血液製剤による感染が約50%。それ以外の50%については感染源を同定できていませんが,おそらくC型肝炎ウイルスに汚染した血液の付着物による感染であり,例えば針治療や刺青などによるものが考えられます。
性行為感染はB型に比べると圧倒的に少なくなっています。肝炎患者の配偶者を調べますと,結婚してから30年ぐらいの間でもほとんど感染は起こりませんので,配偶者間の感染はほぼ起こらないと考えてよいでしょう。
ウイルスの遺伝子型について表3に示します。各国で少しずつ塩基配列の違うウイルスが存在しており,日本では1b型と2a型,2b型の3種類がほとんどです。1b型が圧倒的に多く約70%。残りは2a型が20%,2b型が10%ぐらいです。患者さんの数が多い1b型ですが,IFN治療の効果については圧倒的に低くなります。遺伝子型によって治療効果が大幅に変わるということで,患者さんからよく質問を受けるポイントです。
| 表1 肝炎ウイルスの種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 表2 HCVの感染経路 | ||||||||||||||||||
|
| 表3 本邦でのHCVサブタイプ | ||||||||||||||||||||
|
C型肝炎の経過
このウイルスに感染すると,30-40年という非常に長い経過をとって病気が進行していきます(図1)。まず,急性肝炎を起こしますが,その80%が慢性化します。その後一時的に肝機能は正常化し,持続感染が続きます。慢性肝炎になると10-20年という単位で肝硬変に進行していきます。肝硬変まで進行すると,年率5%程度の割合で肝癌を発症することになります。その間,ウイルスは持続感染が続きます。治療せずにC型肝炎ウイルスが体から排除される確率は1%以下といわれていますので,治療しない限り,ウイルスの持続感染は続くと考えてよいでしょう。
このような経過から,C型慢性肝炎の治療の目標は,肝癌まで病気を進展させない,あるいは慢性肝炎や肝硬変の初期の段階で,ウイルスの持続感染を断ち切って病変の進展を止めることになります。
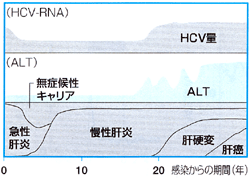 |
| 図1 C型肝炎の自然経過 |
C型慢性肝炎の治療法
C型慢性肝炎の治療法で最も重要なのはウイルスの排除ですが,ウイルスの排除を起こせるのは,今のところIFN治療だけです。IFN治療がうまくいかなかった場合は,できるだけ肝機能を正常値に近づけて病気が進展するのを防ぐ治療となります。現在日本で普及しているのは胆汁酸産生剤で,ウルソ(Urso)という薬と,強力ミノファーゲンCという注射薬です。どちらも肝機能のGPT値を下げる働きがあります(表4)。ウルソの注意点としては用量依存性があります。一定量(600mg/日)を飲まないと効果がないわけですが,患者さんはどうしても副作用のことが気になり,飲む量を自分で減らしてしまいます。しかし,例えばこれを300mgに減らすと,GPTを下げる作用はあまりなくなってしまいます。
強力ミノファーゲンCも,ある程度用量依存性です。1アンプル20mlですが,1日最低3アンプル以上使わないとあまり効果がありません。1,2アンプルでも効果があると考えている方もいますが,それはその他の要因で自然にGPTが下がっただけだと考えていいと思います。
もう1つ,強力ミノファーゲンCの注意点としては,1週間に最低3回以上打たないと効果が少ないということです。1週間に3回注射に通うのは大変だと,1-2回しか注射に見えない患者さんがいますが,それではあまり効果がないと考えていいと思います。
| 表4 C型慢性肝炎の治療 | |
|
IFN治療の現在
IFN治療は現在でもかなり有効な治療法ですが,日本では厚生労働省によるIFNの投与量と投与期間の制限があり,現状では欧米とは少し異なった治療法となっています。この点については後で詳しく述べることにして,ここではまずIFNの6か月投与による治療効果を見てみましょう。IFN治療において,IFN投与中にGPTが正常化し,投与を止めてもGPTの正常化が持続する方を「著効」といいます。それに対して,IFNを投与してもまったくGPTの正常化が起こらない「無効」の方がいます。それから,投与中はGPTが正常化しますが,止めると再燃が起こってしまう「再燃」の3つのタイプに分かれますが,これらはだいたい1:1:1の比率です(図2)。
著効になる因子としては,年齢が若い,肝臓の繊維化が進展していない,できるだけ肝硬変に近づいていない,それからウイルス側の因子としては,ウイルス量が少ない,それから,先ほど述べたウイルスの遺伝子型が2型の場合に,著効となる確率が高くなります(表5)。
例えば,遺伝子型が1型で,ウイルスの量が10meq/ml以上という方に6か月間治療しても,実際にウイルスの排除が起こる確率は1%しかありません。他方,2型の方には50%以上の治療効果があるということで,遺伝子型によって治療効果には非常に大きな差が出てきます。
IFN治療によって,実際に肝癌になることが防げたかどうかということが,最近,明らかになってきています。図3は,IFN治療後の,累積の肝癌発症率を調べたものです。IFN治療を終了後3か月ごとに超音波検査で肝癌が発症したかどうかを見たところ,IFN治療をしなかった方や,IFN治療をやったけれども無効であった方は,3年を過ぎたところから肝癌を発症しています。それに対して,IFN治療で著効になった方では,明らかに累積の肝癌の発症率が下がっています。再燃の方も発症率の低下を見ています。
また,実際に生命予後が大幅に改善しているということもわかってきました。図4は,IFN治療後の生存率を見たものですが,未治療群と無効群は5年を過ぎると,肝蔵関連の病気で亡くなられる方が出てきます。それに対して著効群と再燃群では亡くなる方はほとんどいないということで,生存率が向上することもわかってきています。
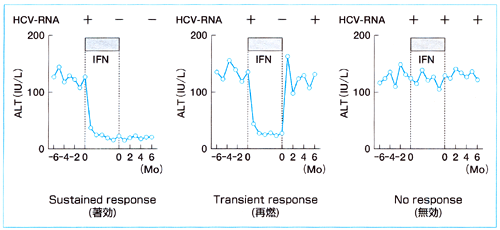 |
| 図2 IFNの治療効果 |
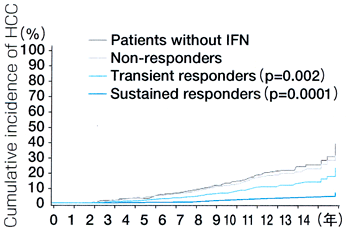 |
| 図3 IFN治療後の累積発癌率 |
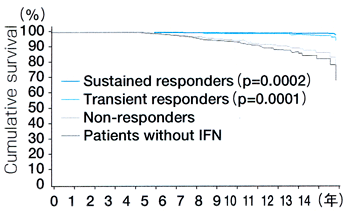 |
| 図4 IFN治療後の生存率 |
| 表5 IFN治療効果(著効)に影響を与える因子 | ||||
|
国際標準の治療について
ここまで見ていただいたのが,6か月間のIFN治療の治療効果ですが,かなりの治療効果があがっていることがわかると思います。しかし一方で,この治療法ではウイルスの排除が起こらないという人がいるわけです。そういう方たちへどのような治療を行なっていくのかが問題となるわけですが,実は国際的には,方向性は明らかとなってきています(表6)。
| 表6 難治性C型慢性肝炎の治療法 | |
|
投与期間(註)
まず,投与期間を長くすることで治療効果があがることがわかっています。日本でも1年半ほど前に,厚生労働省によるIFN投与期間の制限(6か月)がなくなりました。ですから今ではIFNを1年でも2年でも投与することができます。図5は,6か月間と1年間のIFN投与の比較試験です。著効率が33%から54%に上がっています。このことから,現在私どもでは,C型慢性肝炎患者のIFN投与期間は1年間をベースにしています。
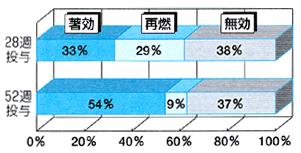 |
| 図5 C型慢性肝炎症例に対するIFN長期投与による再燃率の低下 (Hepatology, 21, 291-297, 1995) |
リバビリン併用療法
次に,リバビリン併用療法があります。リバビリンは現在,保険診療で使われています。
図6は欧米での成績です。6か月のIFN治療では著効率は6%ですが,それを1年にすると16%となります。それに対して6か月のIFN治療にリバビリンを併用すると33%の著効率で,さらにその併用療法を1年間行なうと41%になることが示されています。
このように,IFNにリバビリンを併用して1年間治療するというのがよい治療法だということは明らかとなってきましたが,日本の保険診療ではリバビリンは半年間しか使えないことになっています。そこで,現在は1年間のIFN治療の前半6か月にリバビリンを使用するという方法を取っています。これによって,ウイルスの排除率を30%ぐらいまで上げることができました。この治療法によって,1b型の高ウイルス量の方でもウイルスの排除を起こすことが期待できます。
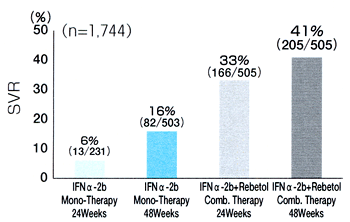 |
| 図6 投与法・投与期間別ウイルス陰性化率(投与終了24週時) (T. Poynard, et. al.: Hepatology, 211-218, Vol. 31(1)2000.) |
ペグIFN・リバビリン併用療法
また,欧米では現在,ペグIFNとリバビリンを併用するのがスタンダードの治療法になっています。ペグIFNとは,従来のIFNにポリエチレングリコールというものを共有結合させたものです。分子サイズを大きくして消失率を下げ,血中濃度を維持するようになっています。原則的には従来のIFNと抗ウイルス効果が変わるわけではありませんが,投与が1週間に1回でよいため,患者さんにとって非常に楽な治療法となっています。
従来のIFNを週3回投与した場合とペグIFNを投与した場合の,血中のインターフェロン変動を比較します(図7)。ペグIFNですと,1回の投与でこのように1週間の間,血中濃度を維持できるということです。
実際にどの程度のウイルスの排除率になるかというと,ペグIFNとリバビリンの併用療法を1型の患者さんに1年間投与した場合,46%の方でウイルスの排除が起こることが欧米の研究で明かになっています。これは,ウイルス排除が起こりにくい1型での数字ですから,全体では50%以上の方にウイルスの排除を起こせるということになります。
このペグIFNは現在日本で臨床治験中で,ペグIFN単剤ではおそらく2003年12月から,リバビリンとの併用療法については1-2年後に日本で実際の治療で使えるようになると思います。
ペグIFNの1年間投与の日本での成績は,例えばペグIFN180μgでは,すべての治療タイプで36%の方にウイルス排除が起こっており,1b型でも19%と,従来のIFNよりもウイルスの排除率が高くなっています。
このようにインターフェロン治療はどんどん新しくなってきており,おそらく今,保険の制約がなければすべての治療タイプで60%,1b型の高ウイルス量の方だけでもだいたい40%くらいの方にウイルス排除を起こせるということになります。
現在の日本でのIFN治療について整理すると,遺伝子型が1型でウイルス量の高い方はリバビリン併用6か月からIFN単独治療への移行,あるいは,IFNを1年以上投与するということになります。2型の方はリバビリンを併用した6か月の治療法が基本となります。また,低ウイルス量の方についてはIFN単独で長く投与しています。ペグIFNが使えるようになれば,1年間治療する患者さんの負担も軽くなるので,IFNで長く治療するケースも多くなるでしょう。
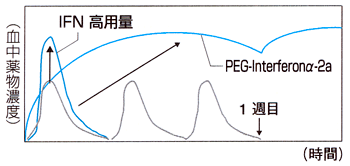 |
| 図7 PegIFNの薬物動態 |
IFN治療と副作用
このように進歩してきたIFN治療ですが,実際の治療をやるうえでは,IFNが引き起こす非常に多くの副作用が問題になってきます。表7はIFN治療に伴う副作用です。風邪をひいた時の何ともいえない身体のだるさは,内因性のIFNによるものですから,そこから想像してもらえればよいでしょう。
全身倦怠感と食欲不振,発熱はほぼ必発で,投与直後から起こります。また,白血球,血小板の減少が起こりますので,あまりひどい減少が起こった場合には投与量を減らすことになります。
甲状腺機能の異常も,かなり高率に起こってきます。対処できる範囲の症状であれば,IFNの投与を継続する場合もあります。
IFNの有名な副作用に精神神経症状がありますが,これはIFN治療がはじまった頃に,うつ病によって自殺者が出たという新聞報道があったために有名になったのだと思います。実際には,IFN投与者と,同年齢の自殺率を比べるとIFN治療患者のほうが自殺率は低かったということがわかっています。臨床的にも,うつ病による治療中断はそれほど多くはありません。
ただし,そうはいっても,IFNを投与するとうつ傾向,あるいは少し気分が落ち込むといった症状はでてきます。うつ病の既往歴がある人については,必ず精神科の先生と一緒に診ることが重要です。
新聞報道ではこのほか,IFNの副作用として間質性肺炎が注目されたことがありました。しかし,これも,小柴胡湯という漢方薬を併用しなければ,ほとんど生じることはありません。
注意してもらいたいのは,糖尿病がかなり高率に起こるということです。IFNによるものというよりは,C型肝炎ウイルスに感染すると,糖尿病が起こる確率が高くなるということが,最近いわれています。それにプラスして,IFNを使うと糖尿病が誘発されてくる確率は高くなるので,このことは必ずご注意いただきたいと思います。
また,脱毛については,特に女性の方が嫌われますので注意してください。5%を超える率で起こると思います。投与後2か月後ぐらいから起こります。脱毛についてはIFN治療終了後に必ず元にもどりますときちんと説明すると,たいがい納得してもらえると思います。IFN治療で毛根がダメージを受けることはありませんので,必ず元に戻ります。
リバビリンについては,溶血性貧血と催奇形性が問題となります。リバビリンを服用すると,必ず溶血性貧血が起こります。そのため現在,リバビリンは投与前のヘモグロビンが12グラム以上ないと投与しませんが,投与後2週目,4週目に必ず高率に起こるので要注意ということになります。また,リバビリンは催奇形性がありますので,本人および配偶者に妊娠の可能性がある時には投与しません。
| 表7 IFN治療に伴う副作用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
IFN治療中の日常生活の注意
表8はIFN投与中の患者さんだけではなく,C型肝炎患者さん一般への日常生活上の注意です。従来,われわれ医師は,肝臓疾患の日常生活についてかなりまちがった指導をしてきました。
まず,いまだに肝疾患の方に対して,高タンパク,高カロリーの食事指導が行なわれることがありますが,これはぜひやめていただきたいと思います。「肝臓が悪くなると高タンパク,高カロリー」という考えが普及した理由は,以前,肝硬変の末期の患者さんについての欧米のデータで,高タンパク高カロリーにすると,生命予後がよかったというものがあったためです。しかしこれは,食事摂取がかなり悪くなった患者さんのデータであり,現在の日本人のように食生活がよい場合は,むしろ肥満をどう防ぐかということのほうが大事になります。普通のバランスのよい食事をしてもらい,絶対に高タンパク,高カロリーにならないようにしてもらいたいです。
また,鉄分の多い食材を取り過ぎないようにすることが重要です。C型肝炎で肝病変が進行する大きな理由として,体の鉄分のリザーブが増えるということがあります。実際に,治療法として「瀉血療法」をして貧血にすると,肝臓の病変の進展が止まるということがすでに明らかになっています。肝炎の感染率は男女で差がないのに,肝癌の死亡率は圧倒的に男性が高いのですが,その理由の1つとして,女性は貧血傾向の人が多いということが大きくかかわっていると考えられています。
禁酒については励行してもらいたいと思います。C型肝炎の人が常用飲酒すると,病変の進行が早いことがわかっています。ただ,例えば1週間に1-2度,ビールを1本飲まれても影響はありません。でも,毎日日本酒1-2合以上飲むといったことは,絶対にやめていただいたほうがいいと思います。
運動については,肥満と関係してくることになりますが,非常に重要です。C型肝炎の患者が肥満を伴いますと,病気の進行は早くなります。現在,欧米ではIFN治療する前にダイエットをやってもらってから治療をしているぐらいです。肝臓が悪い方は安静にする,というのがかなり広く信じられていますが,私たちは逆に,肝硬変がかなり進行している人以外には,運動制限しないようにしています。
また,食後,横になるということも,かなりの患者さんに信じられているようですが,これも肥満の元になるのでお薦めできません。食後横臥で肝臓が治ることはまずありません。逆に食後は血糖を上げないために動いていただくほうがよいと思います。
以上のように,一般に信じられている肝臓疾患の養生法の多くはかなり間違っているということを,IFN治療の有無にかかわらず,肝炎の患者さんには知ってもらう必要があるでしょう。
| 表8 日常生活上の注意 | |
|
■質問編「ナースの疑問に答えるC型肝炎Q&A」

司会(江川) それでは,前半の講演を踏まえて,看護の立場からケア上の注意や問題点について質問していきたいと思います。最初に病棟で看護なさっている峰さんにお願いしましょう。
薬を忘れても大丈夫?
峰 C型肝炎の方は6か月,1年という長期間にわたる治療を覚悟のうえで来られており,治療に対して認識度の高い患者さんだと思いますが,やはり長期間の治療ということで,日常生活に戻りますと,いろいろなアクシデントがあると思います。退院指導時などに,リバビリンを飲み忘れたり,仕事の都合などでIFNを週3回受けられなかった場合,どうしたらいいのか,治療効果がなくなってしまうのではないかといった不安を訴えられる患者さんが少なくありませんが,どのようにお答えするのがいいでしょうか。
林 リバビリンは丸1日投与が抜ける,あるいは1日3錠飲むのが2錠になったとしても,実際の効果はまず維持できます。投与を止めてからだいたい1-2か月は効果が残っていますので,飲み忘れがすぐに治療効果に影響することはないと説明してよいでしょう。
ただIFNについては,週3回投与するタイプのIFNが週2回になるくらいならともかく,週1回では,効果がかなり落ちると考えられます。最低週2回は打ってもらいたいと思います。
IFNと妊娠・出産
峰 ありがとうございました。もう1点,催奇性についてなのですが,若い方で,今後の結婚や出産育児ということに関して,非常に不安を抱えながら治療に挑んでいる患者さんもみえますので,そうした方へのアドバイスのポイントをお聞かせください。林 これも非常に難しい問題です。リバビリンの併用中についてはかなり厳密に,お子さんをつくらないように指導しています。
薬を服用した後にお子さんを作る場合ですが,私はリバビリンでもIFN単独でも,治療後最低1年間はお子さんを作らないようにという指導をしています。それを守っていただければ,まずお子さんへの問題はないでしょう。
認可が待てない
江川 ありがとうございます。会場からもご質問をいただければと思います。女性(会場) わかりやすくご講演いただきありがとうございます。私は看護師でもあり,C型肝炎の患者でもあります。自分自身で,先生が話された治療をほとんど受けてきました。
去年6月にリバビリンとIFNの併用療法をしたのですが,リバビリンの貧血はものすごく強くて,失神して倒れたりなどの経験もしてきました。いまはウルソとIFNを週3回やっています。1型ですので,ウイルスをゼロにするのはもうあきらめて,炎症を抑え,安定させるという方向になっており,ペグIFNの日本での解禁を待ち焦がれています。
IFN投与については,6か月間の制限があった時,IFN終了後すぐに肝機能が悪化してしまった経験をしています。ずっと使ってよいという制度のほうが肝硬変や肝癌が抑えられて,保険の財政としてもよいのではないかと思い,うらめしく感じていました。ペグIFNについても,どのような形で認可がおりるのか,ということが心配です。
もう1つは,リバビリンとIFNの併用療法は1年間を中心にしているというお話だったのですが,たぶん,私のような場合にはIFNを打ち続けないとまた再燃ということになると思うのです。そのあたりについてご意見をお聞かせください。
林 ペグIFNの認可については,まだ正式に決まっていませんので,どういう使用範囲で,どういう制限がかかるかについて,今のところお答えができません。ただ,認可されれば従来のIFN3回投与を週1回投与で置き換えていく形になると思います。ですから,今のお話のように,低用量で長期にIFN治療するケースはおそらく,ペグIFNに変わっていくと思います。
再燃については,IFNを長期に投与されているということなので,ウイルスが陰性になっているかどうかが分かれ道だと思います。
例えばIFN単独でウイルスが陰性化していなくても肝機能が正常化しているのであれば,そのまま長期投与すれば,ある程度病気の進展は抑えられると思います。また,投与中だけはウイルス陰性であるという状態であれば,おそらく2年間程度続けていればウイルスの排除は起こると思います。それ以外にもある程度,ウイルスを特異的に抑えるような薬も開発にかかっていますので,今のうちにある程度,病気の進展を止めておけば,そのうちにウイルスの排除を起こせる可能性は高くなってくると思います。
肝臓病に健康補助食品は?
江川 次に外来の看護という面から,渡辺あや子さん,お願いいたします。渡辺 副作用についてですが,IFNを続けていると,どうしても食欲不振が起こります。食事がとれないと,体力も落ちてきますし,気力も落ちてくる。そのなかで何とかウイルスの排除をめざしてがんばっているというのが多くの患者さんの状況です。単なる食欲不振だけではなく,味覚の異常を訴える方も非常に多く,何か対策はないのかと思うのですが。
林 非常に難しい問題で,食欲減退や食事の摂取量が減るというのはほぼ必発の副作用です。半年間のIFN治療で,だいたい体重が3-4kgは減ります。
投与中にウイルスが陰性化した方は,それでも治る期待感がありますので,何とかそこを乗り越えられるのですが,ウイルスが陰性化しない方が一定期間治療を続ける気力を持つのは,難しい問題ですね。
実際,食欲を増やすよい方法はありませんので,私は好きなものを食べてもらう以外ないと思っています。味覚異常が起こる理由もよくわかっていませんし,口内炎が起こる場合もありますが,それについてもいい対策がありません。
ただ,そのうえで一言付け加えるなら,日本では現在,かなり肥満傾向の人が多くて,体重が3kgぐらい減るとちょうど標準体重になるんですね(笑)。ですから,私はむしろ,IFN治療を終わった後に,元の体重より増えてしまわないようにと注意しています。投与をやめると一気に食欲が出てきますので,それに合わせて食事をとると,元の体重よりも増えてしまうのです。これは病態を悪くしますので,かなり注意して指導しています。
少し貧血気味ということと,体重を減らすということは,病気の進行を止めるうえにはよいことなので,「たいへんでしょうけれど,体重が減るのはいいことなんですよ」ということは伝えています。
渡辺 ありがとうございます。マイナス面をプラス面に変えて,患者さんに説明して励ましていきたいと思います。
女性(会場) 食欲がない時期もあったからだと思うのですが,主治医から勧められて,健康保助食品を寝る前に1パックずつずっと飲み続けています。
先ほどのお話では,高カロリー高タンパクはむしろ害があるということでしたが,私の栄養状態からみると,それを補ってもマイナスにはならないかなと思って飲み続けています。専門家から見て,そういった補助食品についてはどう思われますか。
林 病気がどれ程度進行しているかによって,考え方が大きく変わると思います。肝硬変で病気が進展していない例に,栄養治療をやって実際に生命予後がよくなるという報告はいまのところありません。
肝臓の繊維化が進展してきて,血中のアミノ酸バランスが狂ってきた場合に,それを食事で補助するのはいいかもしれませんが,あまり病気が進行していないのに,アミノ酸で負荷をかけることは,意味はないと思います。
また,食事については,鉄分の摂取を抑えることも重要です。講演で瀉血のことに触れましたが,私たちも最初は「何でこんな治療法をやるのだ」と疑問に思ったぐらいなのですが,その後,国際的な研究で確証がとれています。そして,その時に瀉血で鉄分を減らすだけではなく,食事から摂る鉄分の制限をすることが重要であることがわかっています。
いずれにしても,肝臓が悪いというと食べるというのが従来の考え方でしたが,最近は,どうも逆だということが明らかになってきたということをご理解いただきたいと思います。
注射のタイミング
渡辺 もう1つ,いつ注射をするかという問題についてお聞きしたいと思います。ちょっと前に,夕方に注射をすると効果が高いということを聞いたことがあるのですが,いかがでしょうか。林 いいと思います。体内の日内リズムとも関係がありますが,基本的には午前中にIFNを打つよりも,夕方,打ったほうが効果が高いという報告がありますし,副作用も少ないという報告もあります。
副作用については,発熱と全身倦怠感が,投与後3-5時間ぐらいに必発で起こってきますので,その時に寝てしまうというのがいちばん楽なんです。可能であれば夕方に打ってもらうのがいいと思います。
峰 私ももう1点だけ,お願いします。大学病院ということもあって,IFN治療は通常に行なっているのですが,患者さんは,退院前に日常生活をしながら治療を続けていくため,近医で治療可能な病院を探されるのですが,診療所や病院のネットワークのようなものはないのでしょうか?
林 非常に重要な問題ですね。阪大病院では,実際に病院まで注射に来ていただいていません。日常のIFN治療はご自宅近くの診療所あるいは病院を探して,紹介するようにしています。
本当はご指摘のように,投与してもらえる病院のリストがきちんとあると,患者さんがそこから選べばいいので,非常にいいことなのですが,現在,日本ではそこまでうまくできていません。
昨年からC型肝炎の検診が各都道府県実施ではじまりましたので,その陽性者を紹介する病院のリストはそれぞれの市町村である程度できてきています。原則的にはそういう病院では投与してもらえる可能性は高いと思います。
江川 ありがとうございます。こういったネットワークは,外国ではしっかりしているのでしょうか。
林 そもそも外国では,自己注射ができるのです。
江川 なるほど。とすると,日本でもこれからは自己注射を認可していく方向になるのでしょうか?
林 われわれも,今,それを厚労省に働きかけています。糖尿病でインシュリン自己注射が行なわれているのだから,IFNについても自己注射ができて当然だと思っています。しかし,日本では今のところ針による感染が問題になっていて認められていません。針の安全性の問題がクリアされれば,認可される可能性はあると思います。
民間療法と肝臓病
江川 ありがとうございます。先生,何か追加なさることはございますか。林 私がケア上で問題だと思っているのは,日本では肝疾患の民間療法と称するものが,ものすごい数あるということです。私もビックリするぐらいで,こんなものがあるかなと思うような治療法が山ほどあるのです。患者さんの指導をする時に,治療効果が明らかでない治療法をやっていないかどうか,必ず注意してもらいたいと思います。
何も副作用がなければいいのですが,中にはかなり副作用のあるものがあります。漢方薬に副作用がないというのは嘘で,効果がある漢方薬については当然,副作用があります。
これほどたくさん民間の治療法が広まってきた理由は,根本的な治療法がなかったということだと思います。原因がウイルスだとわかってきた今,私たち専門家は,患者さんに指導していくべきだと思います。
細胞性免疫を上げるものについては,原則的にある程度の効果があると考えられますが,単独でウイルスの排除を起こすものは専門家の目から見てほとんどありませんから,肝炎に特異的に効く民間療法はまずないと考えてよいでしょう。
そういった相談は,ドクターよりも看護師さんにしますよね。よろしくご指導いただければと思います。
江川 ありがとうございました。あっという間に時間が過ぎてしまいました。もっともっと林先生にお聞きしたいところですが,時間がきましたので,これでランチョンセミナーを終了させていただきたいと思います。林先生,渡辺先生,峰先生,ありがとうございました。(終了)
註:IFNを長期で使用する場合,投与期間は臨床効果および副作用の程度を考慮しながら慎重に決定するが,投与12週で効果が認められない場合には投与を中止すること。
| 林 紀夫氏 1972年大阪大学医学部卒業,第1内科に入局。79年から米国テキサス大学医学部生化学教室研究員を経て,81年より大阪大学第1内科勤務。現在,大阪大学大学院医学系研究科分子制御治療学教授として,日本消化器病学会近畿支部支部長,日本肝臓学会理事,日本アルコール薬物医学会の評議員,臨床分子医学会の評議員などを務める。2000年,日本肝臓学会織田賞受賞。 |  |
 |  |  |
| 江川隆子氏 | 峰 孝子氏 | 渡辺あや子氏 |
