| |||||
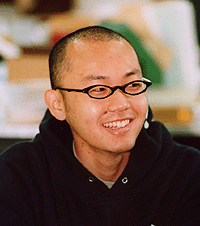 <聞き手>稲葉 俊郎氏 東京大学医学部6年 |  川村 敏明氏 浦河赤十字病院・精神科医 | ||||
| 川村氏は自称「治さない医者」である。べてるの家を訪れた人が驚かされるのは,自主的に活動する精神病者たちの姿だけではない。薬の量,入院期間まで患者さんと相談して決める。多少暴れたくらいでは薬は使わない。幻覚や妄想の話を患者さんから聞いては大笑いしている。およそこれまでの精神科医のイメージや常識にそぐわない川村氏の姿に驚かされる人は少なくない。2003年度べてるの家総会が終わった翌日,5月18日に,川村氏にお話をうかがった。 | |||||
■「非援助の援助」への歩み
文句が出る医療,出ない医療
稲葉 昨日の総会ではお世話になりました。べてるのメンバーは歌ったり,舞台で挨拶したり,概ね饒舌な方が多いなという印象を受けます。しかし,一般的な精神科の患者さんだと,まったく何もしゃべらない方も多いですよね。川村 病院という場が,そういう患者さんをつくってきたのだと私は思っています。
例えば,向谷地さん(注1)のところに行って「幻聴が強いんです」と言っても,薬は増えないし,外出も止められない。退院も延びません。逆に感心されたり,感謝されたりしますから,患者さんは「ああ,話してよかった」,「私の話が伝わる人がここにいる」と,いくらでも話せるんです。
しかし,精神科医の前でそんなことを話したら,「幻聴か。大変だね。じゃあ,ちょっと薬を変えておくからね」と薬を出されて,次の日から薬が効いて,話もできない,ぐたっとした状態になってしまいます。それを患者さんもわかっているから,ものを言わなくなる。「無口な精神病患者」というのは,そういう環境に適応しただけなんですよ。
べてるに来て,例えば向谷地さんと話していると,誰でも腹が立ってくるんですよ(笑)。思わず文句のひとつも言わないとやっていけないのが,べてるです。「三度の飯よりミーティング」というキャッチフレーズがべてるにはありますが,それもわざわざ「ものを言いましょうね!」というプログラムを設けているわけではなくて,それくらいたくさん,何かしら文句があるということなんです。
べてるのメンバーが饒舌なのは,文句を言う人がいっぱいいた,ということです。精神病の人が,このさびしい浦河という土地で生きていこうという時に,文句が出なかったらおかしいです。日々の生活や将来のことを考えれば無理もありませんよ。
稲葉 健常者だろうと精神病者だろうと,文句があって当たり前,饒舌になって当たり前,ということですね。
川村 医療相談室で患者さんが向谷地さんに文句を言う。向谷地さんは「そういう文句が言えるあなたが素晴らしい」という評価を返します。しかし診療室では,文句を言うと薬が増やされる。まったく逆のことが,どちらも精神医療とされていることへの疑問をずっと持っています。
今,自分がやっていることが本当の医療なのかどうなのか。医者がやっていることだからといって「医療」と言ってしまってよいのか。少なくとも,文句も言えないくらいぐったりした患者さんをつくることが,どうして医療と言えるか,と思っています。
ですから,向谷地さんを通して,相談室から伝え聞いた患者さんの文句や,幻聴などのエピソードが持つ,ある種の温かみみたいなものが,私の原点とも言えるものだと思います。それが,どんな精神科医療をしたいのかを私に考えさせるきっかけになりましたね。
| 注1)向谷地生良氏 元浦河赤十字病院ソーシャルワーカー。川村氏とともに20年にわたってべてるの家の実践に取り組む。現在は北海道医療大学助教授。 |
「3年間でゼロ」
稲葉 今,原点というお話が出ましたが,そのことを詳しくお聞きするためにも,先生が今の職業を選ばれるまでの経緯をお聞きしたいと思います。川村 私は大学紛争世代で,よくも悪くも,皆が自分のことを悩んだ世代でした。私も親孝行のつもりで入った水産学部を辞め,自分をこの世の中でどう活かそうかといろいろ考えた結果,医学部に入ることにしたんです。でも,入ってからがまたうまくいかなくて,ほんとうに,何をやってもうまくいかないヨレヨレの20代を過ごしたと思っています。
でも,そういうヨレヨレの医学部生活の中で,精神科の実習に行った時,私はすごくそこに不思議な世界を感じたんです。泣いたり笑ったりしている患者さん相手に,先生は「うんうん」とうなずくだけ。しばらくしたら「じゃあ,2週間後ね」と送り出す姿に,私は非常にショックを受けました。
一見,何もしていないようにしか見えないけれど,きっとそこにすごい意味がある世界なんだろうな,と考えました。また,ここなら自分も受け入れられるかもしれない,という思いもあって,「行ってみたいな」と思うようになったんです。
それで,卒後研修に行った大学病院での1年と,浦河日赤に赴任しての2年を合わせた最初の3年間,精神科でアルコール依存症の患者さんを中心に診たのですが,治療成績は「ゼロ」でした。3年でゼロって医者はあんまりいないんですよ(笑)。その後,札幌でアルコール専門病棟に行ってからは,治療成績は上がっていくんですが,やはり最初の「3年間でゼロ」という事実の重みは大きかったです。
稲葉 それは,医者として無力感を感じたということでしょうか?
川村 不思議なもので,治療成績がゼロでも,落ちこんだりはしませんでしたね。これが精神科の奥の深いところというのでしょうか,よくならなくても,「治療法は正しいけれど,病気が重かったからしょうがない」という受け止め方を一般的にするでしょう? 私もそういうふうにプライドを守っていたわけですね。「悪いのは病気だ」みたいにね。
でも,やはりゼロという結果は,重かったんです。それは失望とか諦めではなくて,逆説的ですが,そこを出発点とすれば何とかなるんじゃないか,といった希望に近い感覚でした。
後に気づいたことは,要するに「ゼロだったのは,余計なことをいっぱいしていたからだ」ということです。最初の3年間のほうが今よりもはるかに熱心でしたし,妙に,いやらしいほどの思いやりがありました。「患者さんのため」「病気のため」って,いかにも医者らしかったんです。
「医者は何もしないほうがいい」
稲葉 医者は余計なことをしないほうがいい,というのは,現在のべてるでの実践につながるものかと思います。そのことに気づいたのが,その後赴任された札幌のアルコール専門病棟に勤務された時だったということですね。川村 そうですね。札幌の民間の精神病院にアルコール専門病棟があって,そこで4年間働きました。専門病棟ですから,専門のスタッフがおり,彼らはアルコール治療の経験をたいへん豊富に持っていました。そして,そこでの私の役割は,私がそれまでやっていたものよりもかなり限定的な役割だったんです。
ほんとに,こんなに一線を引いていていいのかな? と思うほど何もしていませんでしたが,現実にはそれでどんどん酒をやめていく人がいたんです。最初は偶然だと思っていたんですが,繰り返し,繰り返し,患者さんが酒をやめていくわけです。「あんなに一生懸命やっていたのに,酒をやめた人はゼロだった。それがどうして何にもしていないのにやめていくんだろう?」と悩みましたね。
その時に初めて,医者は何をすべきで,何をしちゃいけないのかという,「自分の役割の使いどころ」ということを考えるようになりました。こちらの熱意を出すばかりではなくて,少し立場を引いてみると,「この人たちも酒をやめたいんだ」と気がつくようになったんです。そして,そういう思いを大切にしたいな,と思うようになりました。
私の治療意欲が満々の時には,患者さんたちは「先生がなんとかしてくれるだろう」と考えていたと思います。患者さんが退院すると心配で,退院直後の患者さんの様子をバイクに乗って見にいったこともありました。そうすると,「先生が来てくれた!」という感動で,その日から飲んじゃうんですよね。「これで安心だ。俺には川村先生がついてる」って(笑)。
今思うとバカバカしい話ですが,そういう関係を,医者も患者もなかなかやめられないんですよ。でも,これは治療的な関係ではありません。患者さんを助けるといいながら,実は医者が患者さんに「見捨てられたくない」と依存している状態なんです。アルコール専門病棟に来て私が学んだのは,そういう関係から一歩引くことでした。
正直なところ,最初は「彼らを主役にしていいんだ」ということが信じられませんでした。「あの駄目な人たちを,この熱意にあふれた,思いやりにあふれた私が,どうやって救いあげるか」ということしか頭になかったですから。
また,精神科に来る患者さんというのは,そういう思いのあふれた医者の目から見ると,ほんとうに駄目に見えて,格好の「餌食」なんですね。駄目に見える患者さんを相手にしていると,自分が本当に「いい人」「いい医者」であるように錯覚してしまう。そういう意味で精神科というのは危ないところです。「いい人」役がやれて,とても居心地がいいんですが,それは本人が気づかないうちにどんどん落し穴にはまっていく状態なんですね。
稲葉 たしかに,医者が過剰にすばらしい,いい人と思われすぎる現場には違和感を覚えます。医師を1人の人間として素直にありのままに見てほしいなあと思うことがよくありますね。
医療相談室の空気
稲葉 アルコール専門病棟での4年間の勤務の後,現在の浦河赤十字病院に再度赴任されたわけですね。川村 思い出すと,浦河でも最初の頃は,患者さんが精神科医をとても権限のある権威者として位置づけていましたね。退院から外出まで,あらゆる許可を与える権限が医者に集中するという権威的な構造があって,皆が医者の顔色をうかがっていました。
そんな中,相談室の向谷地さんから伝え聞くエピソードが,ほかの診療場面と明らかな「温度差」みたいなものを持っていることに気づいたんです。そこにはなんとも言えない温かみがあったわけですが,まあ,内容が生活問題のエピソードだけなら,医者もそういう違いがあって当然だと受け止めるわけです。しかし,例えば精神分裂病の人が幻聴の話を医療相談室でしている,という話を聞くと,医者としては「どうしてその話を僕の前でしてくれないんだろう?」と,ちょっとがっかりしますよね。しかし,当時の診察室の雰囲気では,患者さんから幻聴の話を聞くことはとても無理な雰囲気でした。
ぼくはまだ若かったので,そのことでプライドが傷つくというよりも,「相談室っておもしれえな」と思える時期でした。それと同時に,精神病に対するそれまでの否定的イメージとは違う,あったかくて,可能性を感じるイメージを,相談室の現実から受け取ることができました。それは,医者として目の当たりにする現実とは対極に位置するものでしたが,その2つをトータルに見ることで,精神病に対して「やりようがあるな」という希望が見えてきたんですね。
最初に浦河にいた2年間でそれを感じていたので,2度目に浦河に赴任してくる時は,私と向谷地さんがパートナーシップを持ってやっていけば,状況を変えていけるという思いはありましたね。
■医療には「わきまえ」が必要
「川村先生ありがとう」では駄目なんです
稲葉 その後20年余り浦河赤十字病院に勤められ,今日に至るわけですが,ここまでの経緯を踏まえたうえで,べてるの現在の実践についても少しずつうかがいたいと思います。例えば今の精神医学の分野では脳の研究がされていて,統合失調症についても「なぜ起きるのか」といった研究を行ない,そこをターゲットにした薬を開発していこうという方向性が盛んです。べてるの実践とはある意味では対極にあると思える,そういった方向性については,どのように思われますか。
川村 私は,精神病に限らず,分子レベルでの医学研究が,狭い意味での医学的なアプローチにおいてはとても大切だと思っています。現実に,私たちはこれまで,薬物医療を含めた医学の恩恵を大きく受けてきていますし,それはこれからも変わらないでしょう。
しかし一方で,病気の世界には,決してそういう取り組みだけでは超えられないものがあると思います。精神病に限らず,病気にはある意味で人間が根源的に抱えている,人間としての弱さなりから生まれてくる,とても大切な安全装置みたいな意味をもった部分があります。そんなものまでなくしてしまうような技術というのは,少し行きすぎているのではないか。「病気になってはいけない」という,否定的な捉え方に基づいた治療方法は,人間の存在を妙なかたちでコントロールするものになるのではないかと思います。
医療者として大事なことの1つは,自分が無力なこと,限界があるということを知ることです。私たちはそこから始めることを大切にしています。だから,薬物療法が進歩し,新しい治療法が出てきたとしても,それは課題にアプローチする道が増え,進歩したということではあっても,その道だけが大きな,あるいは唯一の道では決してないわけです。その意味で,限界,分際をわきまえる部分がないと,精神科医や精神医療というのは,大きな過ちの世界に入っていきそうな気がしますね。
稲葉 先生は「治さない医者」と自称されるように,薬など,医学的なアプローチを極力使わない方向性をめざされていると思うのですが,それも分際をわきまえる,ということなのでしょうか。
川村 私は,世間と正面切って戦うようなタイプではありませんが,常識的なこと,本流的なところからちょっと斜めに逸れていく傾向がもともとあるんです。例えば,常識的にいわれる治療法がある場合に,「この人の場合はこの薬をどこまで減らしてやっていけるだろうか?」ということが頭に浮かぶんです。
「川村先生のおかげでよくなった」「薬のおかげでよくなった」というきわめて治療的なイメージよりも,「早坂さん(注2)と話をしたら楽になりました」というほうが好きなんですよ。つまり,「治された」という実感が患者さんにないほうが好きなんです。非専門的な,ある種普遍的なやり方で,1人の人間が誇りを取り戻したり,人間関係が復活してきたりすることが好みなんです。
稲葉 薬だけで治るのはよくない?
川村 医者にだけ礼を言うような治療は,治療ではないです。それでは,医者とか薬しか見えていない。患者さんが治療という1本の糸でしか,社会とつながっていない。そんなことで,実際に社会に戻って暮らせるわけがないと思うわけですよ。
医療というのは社会ではすごくでかい顔をしていますが,実はかなり限定された世界です。もう少し,自分たちの大きさにふさわしい役割を取らないといけないと思いますね。
| 注2)早坂潔氏 べてる設立当初からのメンバー。「べてるうまいもん事業部」販売部長。解離性障害(自称「精神バラバラ状態」)の発病で数々のエピソードを残す「ミスターべてる」。総会での早坂氏の様子は取材記事を参照のこと。 |
「自分を助ける方法」は患者さん自身が知っている
稲葉 総会では,それほど切羽詰った状況が見られなかったのですが,普段のべてるには精神疾患による急性的な問題は頻繁に起こっているのだと思います。心配な患者さんには,やはり薬を出すのですか?川村 患者さんが暴れるという状況に対して,事前に薬を増やしておくという方法がもっとも有効だと,皆思いこんでいるんでしょうね。この町でもそういう時代がありましたが,私たちが学んだのは,それが少しも有効な方法じゃないということです。だから,あまり薬を出さないのは,そのほうがいいからです。状況に応じて有効な方法を選択しているだけなんですよ。
べてるでは,よくイメージされるような精神病院の暴れる患者さんっていうのは,意外とありません。暴れるといっても,「強い主張」が中心で,「ああ。文句がたまってるんだな。わかる,わかる」って,放っておけるような爆発なんですよ。押さえつけて入院させる,なんていう場面はまず年に何回かしかありません。決して病状そのものは軽くはありませんが,決定的な爆発にならないのは,彼らがちゃんとSOSを出してくれているからです。
「精神病の人は,自分を自分で助ける方法を身につけられる」。これが,べてるが長い間かけて見つけたことの1つです。逆に言うなら,暴れたら誰かが助けてくれる,抑えてくれる,そういう関係性でやってると,遠慮なく,思いっきり激しく暴れてしまうわけですね。
暴れている人がいたら,私はべてるのメンバーに相談します。彼らが,精神病の人たちはどう生きられるかということを研究しているから,私は医者として研究テーマを発注するんですよ。「こういう人が,こういう問題をもっている。どうすればいい? 皆で研究して」って。それがべてるで行なわれている当事者研究です。実際に社会生活するのは本人ですから,また社会に出て,失敗しては戻ってきて,試行錯誤するわけです。
もちろん,私だってまったく心配していないわけじゃありません。でも,心配だったら,薬を使う前に心配なことを誰かに相談しますね。相談室に行って,向谷地さんに「心配だなぁ」ってつぶやくんですよ(笑)。そうやって,自分の抱えている心配や不安を,自分だけで抱えずにキャッチボールしているあいだに,薬で抑える以外の選択肢が生まれてきます。
そういうことでいうなら,普通,精神科医は「心配だなあ」とは口にしませんね。逆に,何も言わずに薬を出しておけば,専門家として,責任感をもって未然に対策をしたと受け取ってもらいやすいですよね。もちろん,薬を出すという選択肢もあると思いますが,それを安易に選ぶ精神科医になりたいのかというもう1つの問いかけが私の中にはあるんです。だから,私は,他の人に相談するんです。
怖かったら逃げましょう
稲葉 去年,外部の精神病院で実習していた時に出会ったある女の子への対応で,いまだにひっかかっていることがあるんです。僕にノートを見せに来るんですが,書いてあることはまったく意味が不明で,どうすればいいのかわからなかったけれど,とりあえず何とか対応してたんです。そして実習が終わって帰る時,彼女がずっと遠くのほうからものすごい勢いで走ってきたんです。見ると,まるで僕の首を締めてくるような体勢だったので,その瞬間どうしていいのかわからなくなって,僕,逃げちゃったんですよね。ああいう時にどう対応したらいいのか。もう薬とかそういう次元ではなく,とっさに,急性的に何かが起きた時にはべてるではどうしているんですか?
川村 逃げたほうがいいです。
稲葉 逃げるのがいちばんいいですか。
川村 逃げたのが間違いだったら,謝ればいいんです。
稲葉 正直に。
川村 そうですね。彼女が本当にしたかったことは誰にもわからないじゃないですか。何か伝えに来たのかもしれないですよね。だからあとで,「恐かった」とか,怯えていること,恐がっていることをメッセージとして伝えればいいんです。稲葉さんが何を感じているかわからなければ,患者さんからは単なる正体不明な人でしょう?
私たちは,治療的,医学的であることの前に,うれしかったり,恐かったりということが多少とも自然に伝わるようにしていければと思っています。精神的にも,肉体的にも,まず自分が安全であることがあってはじめて,余裕のある会話ができるわけで,相手の正体がわからないまま安心した会話なんて,まずできないじゃないですか。
稲葉 こっちも,感じたことを素直に言うのが大事ということですね。恐かったら「恐い!」と。
川村 そう。それでいいと思います。私は,年がら年中そうやってきてて,何も問題なかったです。特別何かをしてなければいけない,こうあっちゃいけないというよりも,感じたとおりにするしかないですよ。もちろんいつも正解はできません。例えば,彼女だって襲ってきたわけじゃなくて,親しくなりたかったのかもしれない。そういうことを後から理解して「悪いことしちゃったなあ」と後悔することもあるでしょう。
そういう誤解はこれからも,精神病の人だけじゃなくて,いろんな場面で起きてくるわけですよ。稲葉さんはもうすぐ「東大出のお医者さん」になるわけですが,そうなったら,「ごめんなさい」と言う場面よりも,「ごめんなさい」なんて絶対に稲葉さんに言わせないような場面のほうがいっぱい考えられるわけです。そういう意味では,とても危ない世界に入っていくと覚悟したほうがいいですね(笑)。
■「べてるで医療者を育てたい」
医者の役割って何ですか?
川村 稲葉さんが今話してくれたように,若い医療者がべてるに来て,いろんなものを見て,自分のあり方を考えてもらうことはとても大切なことだと私は思っています。最近,べてるで医者を育てていくということをよく考えるんですよ。例えば,昨日の総会を思い起こしてもらえばわかりますが,私をはじめ,精神科医はまったく存在感がないでしょう? ああいう場で何より私が心地いいのは,患者さんたちが誰も私の顔色を見ないということです。たまに気遣ってくれて,私もステージにあげてもらいましたが,他の2人の精神科医はステージにも呼んでももらえない。今回の総会で精神科医がやった仕事は椅子運びとか,実に地味な雑用だけです。
私はよく精神科の若い先生に「べてるという場所は,現実をいろいろ見せつけられる,厳しいところだよね。先生はここで,精神科医としての自分の役割をどんなふうに考えますか?」って聞くんです。
そういう風に,自分を支える基盤について考えてもらわないと,浦河では,医者の存在感がなくて(笑)危なっかしくてしょうがない。相手を治すのではなくて,自分を支える技術,自分の役割を見出すことを大事にしてもらいたいと思っています。
医者というのは実は,批判にたいへん弱い存在です。この弱さ,もろさを自分でなんとかしないと,過剰に治療したり,過剰に親切になったりで,いつも過剰になってしまいます。薬を過剰に与えるのは,量が過剰なだけじゃないんです。医者の「思い」が濃すぎるんですよ。治療成績がゼロだった,私の3年間のように,過剰にかかわらずにはいられない。
稲葉 たしかに,医者も自分のアイデンティティを守ろうとして過剰に治療し,安心してしまいがちかもしれませんね。一方通行になりがちです。
川村 医者は本来,周囲から期待されること以上に自由で,非常に可能性もある存在だと思いますが,周囲の期待どおりに「医療」をやって,期待に応えることだけをやってると,とても窮屈な仕事になってしまいます。だから,周囲に目を向けるのではなくて,自分に目を向けて,自分がやりたい医療というのを真剣に考えてほしいんです。
周囲の期待を裏切って,自分のやりたい医療を行なうというのは,単なる“裏切り”とは違うんです。期待どおりではないかもしれないが,「私はこれができますよ」ということをいつも用意しているわけです。私も,やっていること自体はかなり科学的なんですよ。周囲からはぜんぜん科学的に見えないだけで(笑)。
最近は医学部の学生だけじゃなくて,卒業後の医者もちらほら訪れてくれています。彼らも何かを求めてここに来ているわけだけれど,それはきっと,医者としての自分を支えていくものだと思うんです。だから,べてるが,自分たちの患者としての経験をもとに1人の医者をつくっていくお手伝いができるといいな,と思っています。べてるでは最近「健常者を支援する」が1つのテーマになっているんですが,その一環として,医者作りに貢献できればと思いますね。
川村先生でなくてもできる?
稲葉 べてるが医者を育てるというお話は,総会に参加して皆さんのお話をうかがった僕には実感があります。しかし,一般的には,先生の実践というのは,先生の気さくなキャラクターと結びついたもので,普遍的なものではないと誤解されがちだと思います。川村 うん。たしかによく「川村はキャラで仕事してる」って言われます。しかし私自身は,自分のやっていることを自分のキャラだとは思っていませんよ。きわめて醒めた感覚でやっています。
私は,日頃からかなり自分自身に好奇心を働かせています。例えば「いま自分が迷っているのは医師としてのプライドの問題なのか」とか,「だとすればどっちに重きをおけばいいのか」といったことを日頃からよく考えています。医師としての専門性で推し進めるべきか,あるいはプライドを下ろして患者さんに任せればうまく進むんじゃないかとか,場面によっていろいろ選択しているわけです。だから,医師としての専門性もないわけじゃないし,プライドがないわけでもないんです。こだわっていないだけです。
これを使ったほうがいいのか,捨てたほうがいいのか,使って厄介なものから,使い応えのあるものまで,医学的な方法も含めていろいろなものを自分なりに用意しています。もちろんそういう中では,「これはまずい」と思いながらも,それにすがるしかないこともあるんですが。
稲葉 どういう時ですか。
川村 例えば私が,頭の中では「こうするのが一番いい」と思っていても,それが力がないとか,理解力がないとかいろんな理由でできない時があります。そしてそれは,向谷地さんなら簡単にやっていることだったりします。向谷地さんならできるが,私にはできないということがわかった時どうするのか。私はそういう時,2番目,3番目の方法で,自分を満足させることをやるしかないわけです。他のやり方のほうが優れているのはわかってますから,無力感は感じますが,そういう時に,相手のやり方を潰すのではなく,一歩引く方向に自分をコントロールするようにしています。
だから,トータルでいえば,いろんな人の可能性,役割を生かす役割をやっているということは言えるかもしれません。「場」全体に対する安心感を提供する,ということですね。そういうふうにやらないと,医者が何でもナンバーワンでなきゃならなくなりますから。医者がナンバーワンになると,患者さんも医者ばかり頼ります。最初の権威的な構造に逆戻りしてしまうわけです。
私にも駄目な,弱いところがあり,できないことがあるということを受け容れていなければいけないし,それができないと,私は「治療者」になれないんですよ。だけど,これは断じて私のキャラではないですよ。そういうふうに自分をコントロールしているだけです。
誤解も大歓迎
川村 べてるの実践を私のキャラで片づけてしまう人は,そこしか見えないというよりは,そういうものであってほしいんだと思うんですね。もちろんそれは誤解だと思っています。しかし一方で私は,べてるに来た人が,自分のいちばん欲しいものを持って帰ればいい,とも思うんですよ。焼き魚しか食べたことのない人に,フランス料理を勧めてもしょうがないと思いますから。
べてるもそうですが,私自身,誤解されないようにといった努力を何もしてこなかったんです。正直なところ,誤解した人はした人で,お客さんとしてこの町に何度も来てお金を落としていってほしい(笑)。それで町は潤うわけだし,私たちもその誤解を,きちんと受け止めて,それを笑っていくようなスタンスでいたいですね。
稲葉 誤解すらも飲み込んでいくということですね。
川村 そう。かつては,マイナスのイメージの誤解がいっぱいあったわけですよ。いまは逆にバブリーな誤解が蔓延しています。べてるを見る時の周囲の人のほうが妄想化してるんですよ。「べてるって金持ちなんだな」とか。私たちは,それを笑いながら,否定しないというスタンスです。
もちろんいまは,情報がものすごい勢いで伝わっていく時代ですから,そこにはとんでもない誤解もあるでしょう。しかし,メッセージを正確に受け止める人たちがいるということは,いままでの経験から確信してるんですよ。
精神医療だけでいえば,100年の歴史があって,その100年を,われわれが一気に根元から覆すというようなことは考えてません。方向性が変わるきっかけにはなるかもしれませんが,そこにはいろんな人たちの役割が必要だと思いますよ。それを,必要以上にべてるを持ち上げて,「べてるが何かした」という話にはしたくないなと思っています。
医者にだけ礼を言って退院する人がいるのを私がまずいと思うように,「べてるが,べてるが」ということだけが語られていくことはあまりいいことだと思いません。べてるは聖地でもなんでもありませんし,変われたとしたらそれはその人たちの実践です。私たちがいろんな人との出会いから考えはじめて,さまざまな活動を行なってきたのと同じように,べてるを訪れた人が,その中身に触れて得たものを,それぞれの場所に持ちかえり,それが具体的な成果につながっていけばいいと思っています。
■べてるから何を持ち帰る?
べてるは不親切なところですよ
稲葉 しかしながら,妄想であれ誤解であれ,これだけメジャーになると,入所希望者も増えて混乱をきたすということはないのでしょうか。川村 どう見られるかということについては,過去も今も同じで,私たちの問題じゃないですからねえ。町の人から非常に否定的に見られてきた長い歴史があって,それはすぐにはどうにもならなかった。同じように,メジャーとして見られることについても,私たちは影響を受けようがないんですよ。
だから,たくさんの希望者が来ても,別に困らないですよ。今回は総会だったので,たくさんのお母さん方から声をかけられましたが,私たちから言えるのは,「来たい人はどうぞ,べてるに果敢にアタックしてください。熱意しだいです」,「あなたが,なぜ浦河を求めるのかということを,一生懸命言ってください」ということだけなんです。私たちに強烈な印象を残すようなアタックをやってもらうこと,それがいわば,私たちの「治療的な援助」です。
稲葉 自主的に動いてもらうことそのものが「援助」となるということでしょうか。
川村 病気の人はそこまで自分の希望を表現することも今までなかったでしょうし,なぜ自分にはこんなにべてるが必要なのかということも,考えたことがなかったでしょう。親子で来た人に対して私は「親が勝手にワアワア言ってるあいだは,浦河では精神科といわずに小児科というんです」と答えています(笑)。
実際,お母さんの相談には乗れますが,お母さんが「うちの息子を……」といっている段階では無理なんですよ。浦河は,残念ながらたいへん不親切な町ですし,べてるというのは絶望的に非協力的なところなので無理ですよ,ということを伝えます。
親や病院がその人の尻拭いを続けてきた,それまでの関係をそのままべてるに肩代わりしてもらうことを期待しているのなら,それはとんでもない勘違いで,べてるにはそんな力はないし,絶望的なくらい,誰も何もしてくれないんですよ。
だから,よくべてるを観察して,ここでは何をしてくれて,何をしてくれないのかよく見極めてください,それまでに何回でもいらしてくださいと,「何回も来てくれると,この町も潤うな」と内心思いながら伝えるわけです(笑)。
キャパシティを含めて,べてるの現状を変えるのはぼくたちじゃなくて,新たに来る人たちなんです。浦河を一生懸命希望する人自身がまた,浦河を変えてくれるんだと思います。とにかくべてるに来たい,という人が集まってくれば,「それじゃあ住居も必要になってきたね」と考えて,それを準備するのであって,べてるが積極的に入居者のために場所を用意して,そこにどんどん人を呼ぶということは,今までもなかったし,今後もないと思いますね。
失望の中から立ち昇る「希望」
べてるは常に「不充分」です。私たちがやってきたのはいわば期待を裏切ることの歴史です。昔は浦河という町の期待を裏切り,いまは世間の期待を裏切っています。それは,取りも直さず私たちの力の限界がいつもある,ということです。こういう状況のほうが,かえって浦河を希望する人たちも,浦河に行く前に地元でやれることは何かと考え,その試行錯誤の中で,やっと現実感が生まれるのではないでしょうか。「遠く離れたところにべてるというところがあるらしい」と理想郷のように憧れて,べてるに行くと奇跡が起きるかのように思ってしまうのはよくないし,実際何も奇跡なんか起きないですから。
すごく熱心な人がいるかと思ったら,熱心な人なんて誰もいないし,深刻に相談しているのに「アハハハ」と笑われて,えらく傷ついて帰る人もたくさんいます。「べてるに来て傷つきました」って,外来に来る人がいるんですよ(笑)。訪れた人の大きく膨らんだ希望が,べてるの現実を見た瞬間,ペシャッと潰れてしまうのが常なんです。しかし不思議なことに,その後,何かをつかんで帰る人もまた,たくさんいるんですよ。
何十年も苦労してきた人,空回りをしてきた人,長い時間苦しんだ人ほど,べてるでショックを受けながらも,何か大事なものをつかんで帰っていきます。私は,そういう苦労話を聞くと,「べてるに来てがっかりしたかもしれないけれども,私はあなたの話を聞かせてもらえてよかったな」といつも思うんですね。そして,そのことを伝えると,「また,来ていいですか?」となる。がっかりしたはずの人が,少し元気になって帰っていく。そんな経験をよくしています。
べてるは,期待ばかりしてくる人には,本当になんもしてくれないところですが,入院前の苦労なり,切実感を持ってくる人には,学びになるプログラムや人材は豊富だと思います。その人の見方,べてるに何を期待するかということによって,さまざまに見えるところだということでしょうね。(了)

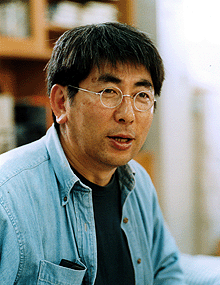 | 川村敏明氏 (かわむら・としあき) 1949年,北海道道森町に生まれる。北海道大学水産学部を3年で中退,その2年後に札幌医科大学入学。卒業後大学病院を経,81年から浦河赤十字病院に2年間勤務。札幌旭山病院アルコール専門病棟勤務後,88年に再び浦河赤十字病院に勤務。精神神経科部長。ソーシャルワーカーの向谷地生良氏とともに,べてるの活動に携わってきた。 |
●インタビューを終えて
 | 稲葉俊郎氏 (いなば・としろう) 1979年,熊本県生まれ。東京大学医学部6年。趣味は山登り,沢登り,ロッククライミングなど大自然の中で戯れることと,油絵,写真などの芸術行為全般。こよなく愛する人はPicasso,Gaudi,Gogh,John Lennon,Reinhold Messner,岡本太郎,三島由紀夫,手塚治虫,植村直己,松本人志など。 |
べてるのメンバーや川村先生と話してもっとも感じたのは「自然だ」ということだ。べてるでは,メンバー同士の友情があり,喧嘩があり,恋愛があり,喜怒哀楽があり,すべてのものが当たり前に詰まっていた。
べてるを聖地のように思って訪れる人は期待を裏切られるだろう。べてるにいる人々は,自己中心的で目立ちたがり屋で,不満がたまると暴れたりと,僕らとまったく同じである。聖地と誤解して訪れる人は,川村先生もおっしゃっていたように,べてるの「当たり前の現実」に幻滅するかもしれない。
また,べてるを恐ろしい精神障害者の人がいる所だと思って訪れる人も期待を裏切られるだろう。彼らは幻覚や妄想を持っていたりするものの,ごく普通である。彼らは,幻覚や妄想という「特殊能力」を持った普通の人間として自然に扱われている。足の速い人はかけっこで表彰されるように,幻覚や妄想で表彰されている。実際,今年幻想&妄想(G&M)大会のグランプリを受賞した早坂潔さんも全員から祝福され,誇りに満ちた表情だった。
医学部の学生というのは非常に宙ぶらりんな存在である。実習で病院にいると,看護師さんからは邪魔もの扱いされ,医者からは医者扱いされ,友人からは医学部の友人として扱われる。つまり,医学の素人でもあり,プロでもあるわけだ。僕ら学生はその微妙な扱いの間をのらりくらりと生活している。
この期間,僕ら学生はすごく貴重な時間を過ごしていると言える。医師の視点からカルテを見たり手術を見たりもできる一方で,患者さんの視点から医療の現場を見ることもできるからだ。しかしそこで感じた疑問などを表現する場所や手段に僕らは恵まれていない。
だからそういう思いは,個々人の趣味に昇華されていくのかもしれないし,とことん医学を勉強して学問によって昇華させる人もいるかもしれない。
しかしこういう思いは,別に僕ら医学生に限らない。人々は皆,さまざまな思いを抱え込み,日々を生きている。それを溜め込みすぎて苦しんでいる人も少なくないだろう。
「降りていく生き方」という,べてるでよく出てくる表現は,このような苦しみへの1つの答えなのかもしれない。
つまり,「僕らは思いを溜め込み,その重い荷物を背負ったまま,さらに遠くへさらに高くへと飛ばなければいけない幻想に陥っているけど,実はその荷物はもっと軽くできるし,そんなむやみに遠くに高くに飛ばなくてもいいんだよ」といっているのかもしれないと思うのだ。
それは,自分をありのままに見つめてありのままに生きるということであり,実際べてるの人々は,みんな自分というものをよく知っていた。そして,自分の不満や喜びをそのまま表現しており,その姿はとても自然で普通だったのだ。
べてるの人々は喧嘩もし,わがままも言い,とても手がかかる。しかし,みんな笑って楽しそうな表情をしていることも多い。僕らは,あそこまで楽しく笑えているだろうか。自分の思いを下手であっても表現してみたり,うまく人に伝えたりして,体や頭の中に貯まっている膿をうまく吐き出せているだろうか。
べてるから学ぶことは多いが,それらはすべて,とても当たり前の普通のことばかりである。べてるの人々は,患者さんだとか,健常人だとか,そういう言葉で括ることがあまり意味をなさないほど,ごく普通に自然に生活しているのである。


