第38回日本理学療法学術大会開催
科学的根拠に基づく理学療法を提唱
第38回日本理学療法学術大会が,5月22-24日の3日間,中澤住夫大会長(長野医療技術専門学校)のもと,長野市ビッグハットで開催された。
今回のメインテーマは「科学的根拠に基づく理学療法」。経験主義的要素が強いとされる理学療法にEBMは浸透するのか。海外の臨床研究データベース管理者による特別講演のほか,シンポジウム1題とワークショップ7題もすべてEBM実践に関するものとなり,臨床につながるEBMのあり方が検討された。また役員選挙では,奈良勲氏の勇退に伴い,中屋久長氏が協会長に選出された。
●EBMは理学療法の実践に寄与するか
 大会長基調講演「理学療法の臨床研究とEBPTの課題」では,中澤氏がEBMの概略と課題,EBPT(Evidence-based Physical Therapy)が求められる社会的背景を説明。EBMの限界や理学療法の特徴からEBPTの課題は多いとしながらも,「組織的に取り組むことで理学療法の科学性が前進する」と,本学会の意義を述べた。
大会長基調講演「理学療法の臨床研究とEBPTの課題」では,中澤氏がEBMの概略と課題,EBPT(Evidence-based Physical Therapy)が求められる社会的背景を説明。EBMの限界や理学療法の特徴からEBPTの課題は多いとしながらも,「組織的に取り組むことで理学療法の科学性が前進する」と,本学会の意義を述べた。
臨床研究データベースPEDroが描く未来予想図
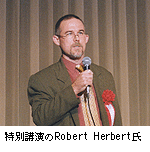 続いて,Robert Herbert氏(シドニー大)による特別講演「Evidence-based Physical Therapy」が行なわれた。氏は,理学療法の必読書のここ数年における変化を例に出して,理論や経験だけでなく臨床研究に基づいて治療が行なわれるようになってきた世界的な潮流を紹介。もっとも偏りが少なく最高の治療効果の根拠が得られるのは,RCT(randomized controled trial:無作為化比較対象試験)と系統的レビューだとした。そしてこれらデータの探し方として,氏みずからが管理するウェブサイト,PEDroを紹介した。
続いて,Robert Herbert氏(シドニー大)による特別講演「Evidence-based Physical Therapy」が行なわれた。氏は,理学療法の必読書のここ数年における変化を例に出して,理論や経験だけでなく臨床研究に基づいて治療が行なわれるようになってきた世界的な潮流を紹介。もっとも偏りが少なく最高の治療効果の根拠が得られるのは,RCT(randomized controled trial:無作為化比較対象試験)と系統的レビューだとした。そしてこれらデータの探し方として,氏みずからが管理するウェブサイト,PEDroを紹介した。
PEDroは理学療法における科学的根拠のデータベースで,調べたい用語で検索をかければ,収録された論文の要約などが無料で閲覧できるもの。これら研究論文の信用度は,10点満点で評価されている。
また,「理学療法の臨床研究の量は過去数年間で急速に増えている」と,1955年以来の研究論文数の伸びをグラフを用いて説明。現在収録されている3500以上のRCTと600以上の系統的レビューが,臨床での意思決定に必要な土台を提供していると述べた。最後に,「熟練した治療者は,情報管理の熟練者になる必要がある」「現在広く使われているいくつかの治療法は淘汰されて,新しい治療法が採用される」と,EBPTの未来への展望を語った。
PEDroは,下記アドレスで無料閲覧できる。
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/
また,長野県理学療法士会のウェブサイトでは,PEDro指導書の和訳や検索手引きなどが日本語で解説されている。
http://www.dcn.ne.jp/~ptnagano/
臨床での応用を考えたEBPTの創出を
シンポジウム「理学療法におけるEBMの実際」(司会=国際医療福祉大・丸山仁司氏)では,エビデンスをつくる(研究)・使う(臨床)・伝える(教育)のそれぞれの立場でシンポジストが発言した。伊橋光二氏(山形県立保健医療大)は,EBPTの発展のためにはRCTを推進する体制整備が必要だと強調。昨年度の本学会発表のうちRCTを用いたものは5題のみという大会長講演での報告を例に出し,倫理的問題や対象者と資金の確保など今後の課題をあげ,個人や一施設の研究だけでなく,協会レベルで「臨床研究支援センター」の設立を提唱した。これについて,会場からは「EBMは研究者のためでなく,大部分の現場で働く人のためにある。PEDroのようなデータベースをつくるなどのアイディアがあるといい」との声があがり,荻島久裕氏(富山医療福祉専門学校)も,「現場と研究者がネットワークをいかにつくるかが重要」と同調した。
大峯三郎氏(産業医科大)は,「臨床でエビデンスをどう使うか。まわりに相談できる人がいない状況のなかでは頭を悩ますところ」とし,多職種で問題を討議する福岡県医師会の試みを紹介した。また学会評議員間での検討事項として,「査読の際に,論文のクオリティは発表者に責任を持たせて,今後は臨床的な面での査読を進めようということが現在話し合われている」と報告。大量の論文をデータベース化したうえでPEDroのようにランクづけし,臨床の場で引き出せるシステムが必要だと述べた。
最後に丸山氏は,症例報告論文のデータベース化や「臨床研究支援センター」での倫理審査委員会の設置,疾患のガイドラインや評価項目の統一などの課題を整理し,「実際に応用するのがEBMだという心構えを持っていきたい」とシンポジウムをまとめた。
●中屋久長氏が協会長に就任
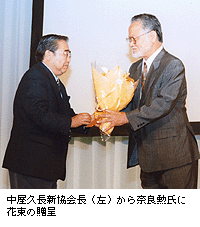 大会2日目の選挙結果発表では,奈良勲氏(広島大)に代わり,中屋久長氏(高知リハビリテーション学院)が協会長に選出された。新協会長挨拶で中屋氏は,学会員の若年化への対応や,急増する養成校での教育内容と臨床実習,学生の就職先など,今後の課題をあげ,「1つひとつに対して,政策的に実践的に運営することが新しい執行部に課せられた命題だ。足腰の強い,学術と職能,両面のバランスの取れた協会を目指したい」と決意を語った。
大会2日目の選挙結果発表では,奈良勲氏(広島大)に代わり,中屋久長氏(高知リハビリテーション学院)が協会長に選出された。新協会長挨拶で中屋氏は,学会員の若年化への対応や,急増する養成校での教育内容と臨床実習,学生の就職先など,今後の課題をあげ,「1つひとつに対して,政策的に実践的に運営することが新しい執行部に課せられた命題だ。足腰の強い,学術と職能,両面のバランスの取れた協会を目指したい」と決意を語った。
奈良氏は,就任当時まだ小規模だった協会を盛り上げるために最初の理事会でマスタープランを打ち出した頃を振りかえり,「課題も残ったが,7-8割は実現できたと思う。協会員みんなが目標を共有し集結できた。反省すべき点もあったが,14年間のなかで私自身も成熟した」と感慨を込めて語った。大きな拍手のなか,中屋氏から花束が贈呈され,7期14年にわたる協会長任務にピリオドを打った。
