| 連載(7) | 新医学教育学入門 | 教育者中心から 学習者中心へ |
| カリキュラムって何だ(後編)-現実と理想の違い | ||
| 大西弘高 国際医学大学(マレーシア)・医学教育研究室上級講師 | ||
初めての外来実習
天野ヒカリさんは医学部5年生。今回,循環器内科臨床実習で初めて外来実習に出ることになりました。グループの8名は朝8時半に集合し,教授から15分間「外来診療の特徴」という小講義を受けました。「外来は病院の表の顔だから,特に共感的,かつ患者中心的に接しなければならない」
「外来では病棟よりも病歴と診察の占める役割が大きいし,病歴と診察だけでも7-8割の診断がつくというデータがある」
といった内容に,天野さんは感銘を受けました。9時から各自指導教官に割り振られることになりましたが,天野さんはたまたまこの教授の外来を見学することになったため,「どんなすばらしい診療がなされているんだろう」と緊張感をみなぎらせました。
最初の患者は,33歳女性の憂子さんで,「最近ときどき胸がドキドキする」という主訴でした。憂子さんは悩ましげな表情をしながら,手足のしびれ感や息苦しさのようなことも言い始めましたが,教授は「その動悸は,いつから,どんなふうに起こったの?」とややぶっきらぼうな尋ね方をして遮りました。
さらに,少し答え方に悩んでいるところで,「じゃあ,そのドキドキは脈が飛んだような感じか,それともトットットッという速い感じかどちらですか」と矢継ぎ早な質問が続きました。天野さんは(あれっ,これだったら全然共感的じゃないぞ。こんなのOSCEだったら不合格だよ~)と思いながら黙ってみていました。憂子さんは,速い感じの動悸で規則正しいと答えました。すると診察に移りました。
「じゃあ,診察しますから服を上げてください。ブラジャーは外してください。心臓の音を聞きますので」という教授の言葉はとても威圧感がありました。天野さんは(自分だったら,あんな風に言われたらかなり恥ずかしいな。どこでも外来ってこんななの?)と思っているうちに診察は終了。心電図で異常のないことが確認され,憂子さんは「おそらく精神的なものでしょう。心配いりません」という説明を受けて,悩ましげな表情のまま帰っていきました。
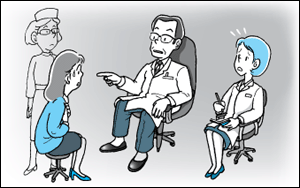
教授の言葉に感じた疑問
教授は,「ああいうのは,心臓神経症というか,まああまり心配ないね」と言いながら,Brugada症候群について少し解説しました。そして,納得いかない表情をしている天野さんに対し,「3時間待って3分診療って言うだろ。理想どおりにいかないのは医療行政の問題だね」と言うと,次の予約患者を呼び入れていました。天野さんは,“教授は精神的なものと説明していたけど,憂子さんの精神的な悩みを聞こうともしていなかったんじゃないのかな”と大いに疑問を感じました。さらに,教授の小講義の内容を振り返り,“理想と現実の違いというだけの問題じゃなさそうな気がするなあ”と改めて感じました。
ロールモデリングと潜在的カリキュラム
医療教育の場面では,見学という方法が用いられることが少なくありません。プロの技を見ることは,学習者の行動に大きな影響を及ぼすでしょう。これは“ロールモデリング”と呼ばれ,指導者が演じる役割を学習者に見せたり経験させたりすることを通じて学習させる教育方法です。ロールモデリングをより一般化したものに観察学習がありますが,これはBauduraが提唱した社会的学習理論の枠組みで出てくる用語です。“人のふり見てわがふり直せ”と言うことわざもありますが,ほかの人の行動を見ることは自分の行動に変化を与えやすいのです。しかし,ロールモデリングや観察学習は,積極的にこれを教育に用いようとした時に限定されるわけではありません。むしろ,この循環器内科教授のように,教えようとしなかったことのほうが影響力を持つということは教育現場でしばしばみられることです。理想的な行動を言葉で示し,同時に現実には大学病院ではそれが不可能であることを行動で示したとすると,学生は「制度が変わらない限り,同様の外来を続けることは仕方ない」という意味にとるでしょう。前編で述べた“潜在的カリキュラム”の多くは,“言葉では理想を語り,行動では現実を示す”ことによって生まれるのかもしれません。
天野さんの例では,教授は憂子さんの「精神的な症状」について十分話を聞いていなかったことの理由を,3分間診療という病院管理上の問題に帰しようとしているようにみえます。しかし,教授が「精神的なもの」というあいまいな説明をしていることは,精神科的診療という観点からは分析が不十分なようにも思えます。天野さんの「理想と現実の差だけじゃないのでは?」という違和感はこの部分にあたるのでしょう。
この場合,教授が教えようとした内容は診療における理想と現実の差でしたが,天野さんが受け止めた内容は,「精神科的な面接は忙しい内科外来では困難であり,教授のような人ですら不十分になりがち。患者中心の医療とは言っても“心”にも焦点を向けた診療は難しいもの」であったと考えられました。
“患者中心”に隠れたメッセージ
最近,マスコミに“患者中心の医療”という言葉がちらほら見られるようになってきました。全人的医療,心身医学,生物心理社会モデルなど時代の変遷に従ってさまざまな言葉が使われてはいますが,「医療者に救いを求める人に対し,特定の臓器や,特定の病理変化だけに焦点を当てるのではなく,悩みを抱えた人間全体を癒すべきである」という主張は一貫しているでしょう。ところが,実際の医療現場では「患者中心」という言葉だけが一人歩きし,個々の医療者がその言葉を吟味せず,実行しないままになっているということが多いように思われます。本来,医療は患者のニーズから生まれた職業であり,「患者中心」であることは取り立てて言う必要のない本質的な考え方なのですが,それを改めて言葉にしなければならないほど現代の医療には根深い問題があると言えます。
憂子さんは何らかの心理的問題を抱えていたのでしょうが,それを話す機会すら与えられなかったのであり,この教授の言う「精神的なものでしょう」は,正しくは「診察の結果,身体的問題はありません」という意味であり,心理的問題は診ていないことを暗に示しているようです。ロールモデル医師が「患者中心の医療」を実行できないのであれば,それを口にすることによって“患者中心の医療というのは理想であって現実には不可能なこと”と言う潜在的カリキュラムを引きずってしまうことになるでしょう。
これらの理由から,教育者は,“自らの行動を振り返り,言行一致を心掛ける”ことが重要であると言えます。教育に関わる医師が「患者中心」という言葉の響きのよさを笠に着ることにより,必ずそれを見ている学生や患者がいると思った方がよいでしょう。
(この記事に登場する人物,科等はフィクションであり,実在のものとは関係がありません)
(この項つづく)
