コスト意識がないと驚かれた日本の医学教育
世界の医学教育の流れはポートフォリオ評価の時代へ
英国ダンディー大学医学教育研修セミナーの体験から
吉田一郎(久留米大学医学部医学教育学教授) スコットランドの小さな町ダンディーでは,毎年世界中から参加者が集う医学教育学Faculty Development(FD:教師の意識改革)セミナーが開催される。ダンディー市は,英国最初の南極探査船ディスカバリー号が出航した町であり,「Discovery city」とも呼ばれている。筆者は新しい医学教育の「発見」のため,2002年9月後半の2週間,同市に滞在した(セミナーの内容は表参照)。わが国では,このFDに匹敵するものはない。厚労省と文科省が,日本の医学部教師の意識改革をめざし企画されている富士医学教育ワークショップ(WS)も1週間のみである。富士WSは,わが国の医学教育への貢献が大きく,多くの日本の大学の医学部がいわゆる富士方式とその関連資料で各大学ごとのFDを行なっている。ダンディーも富士も人里離れた美しい自然の中でFDセミナーが開催されており,「ヒトは魂が高揚した時に最もよく学ぶ」というリトリートの教育原理をみる思いであった。
| 表 2週間のスケジュール | ||||
|
求められる医学教育の専門分化,必要な医学教育学の専門家
今回のFDセミナーは筆者の参加のためか,ダンディー大学医学教育センター長Harden教授による日本庭園の紹介でスタートした。同教授は,螺旋カリキュラム,SPICESモデル〔1984年に提唱されたカリキュラムの方向性を明確に示したモデルStudent-oriented(学生中心),Problem-based(問題志向),Integrated(統合),Community-based(地域基盤),Elective(選択),Systematic(系統的)をさす〕,OSCE(Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験),BEME(Best Evidence Medical Education),ポートフォリオ評価(註)など新しいコンセプトを次々に提案している医学教育の巨人で(写真1),本年7月に佐賀で開催される日本医学教育学会で特別講演をされる。Harden教授は,「医学教育でも日本庭園でもプリンシプルやコンセプトが一番,大切なのは従来の医学教育でのPHOG(Prejudice,Hunches,Opinion,Quesses)アプローチではなく,根拠のあるBEMEに変えることが必要」と強調された。
また,「医学教育の分野はあまりにも広く,専門分化が必要」とも強調された。
このセンターには,アジアの大学医学部から3名が留学しており,タイの名門チュラロンコン大学から留学中の医師は,帰国後母校に医学教育センターの開設を予定している。ふりかえってわが国の医師で医学教育学の研修に4年も5年も留学する者が,きわめて少ないことに不安を感じた。
 | 写真1 医学教育で世界をリードするダンディー大学医学教育センター長Harden教授。医学教育におけるコンセプト,プリンシプルの重要性を強調している。 |
発言増す医学教育における消費者としての医学生
学生の立場に立つ医学教育は,Harden教授が提唱したSPICESモデル(最初のSは,student centredすなわち教師中心ではなく学生中心)は,富士WSでも毎年,強調されている。しかし,わが国では,なかなか現場には反映されていない。英国で生まれた「コアカリキュラム」と「選択のカリキュラム」は,欧米やアジアの先進校では2000年で導入を終了しているが,わが国では,現在導入中である。Harden教授は,学生側に立つ配慮,例えば学生のニーズに応じ,学習を援助する,「Study guide」を供覧され(写真2),その重要性を強調された。「Study guide」で重要なのは,TRACKER(Target,Route of study,Assessment activities,Core information,Key tips,Educational opportunities,Readable material)である。なお,米国では医学教育の消費者としての学生重視から,卒前のカリキュラムを作成する地域委員会(医師会と医学部で構成される民間団体)には,すでに医学生が数名構成メンバーに入っている。
また,学生は教師をよく観察していることも述べられた。グラスゴー大学では教育に熱心な外科教授の影響で,他大学の10倍以上もの外科医志望の学生がいることを紹介し,学習促進者としての教師の役割の重要性を強調された。
2日目はダンディー大学の誇るスキルスラボで,SP(模擬患者)やシミュレーターを用いた実演があった。Harden教授によれば,10年後の医学教育はシミュレーターとCD-ROM全盛の時代が到達するだろうという。
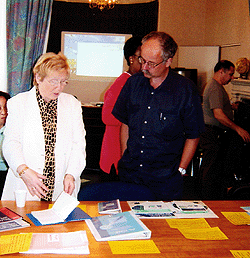 | 写真2 会場では,医学生のためのStudy guideが供覧された。参加者に説明するダンディー大学のLaidlaw女史(左),ドイツから参加の新生児科医(右) |
ダンディー大学のOSCE
OSCEの本家であるダンディー大学では,ステーション数は25-35,1ステーションは4分半である。以前はこれを1日がかりで行なっていたが,昼休みに学生同士の情報交換が入るため,現在は列を増やして午前中だけで終了している。なお,ダンディー大学では,SPは点をつけない。「米国では,一般化可能性理論が重視されているが」との筆者の質問に対し,Harden教授は,「ステーション数を20以上にすれば,難しい理論を使わなくてもよい評価は可能」と答えられた。また,「心電図や画像をOSCEに導入することに異論があるが」と質問してみたら,Harden教授は,「Case-basedのセッティングにして,2つ目のステーションで使用すればよい」と回答された。
さらに,チェックリストやレーティングスケールについても活発な討論がなされた。筆者にとっては,OSCEの意義について,北米とはやや異なる英国流の考え方が興味深かった。OSCEが,医学以外の領域にも応用されているOSPRE(Objective Structured Performance Related Examination)のことも紹介された。
本音が出るコーヒーブレークでの情報交換
この種のセミナーのコーヒーブレークは,各国の医学教育の情報交換の場になっている。今回仏伊からの参加者はいなかったが,「フランスは他の国々を見下しているが,しだいに孤立して遅れつつあると思う。イタリア人には最初からよい医学教育をやろうなどという気持ちがない」,「EUはヨーロッパ全体の共通医師免許証を計画しているが,問題は南ヨーロッパの医学教育のレベルの低さだ」,「オックスフォードとケンブリッジは英国の名門医学部であるが,ケンブリッジの医学教育は最低で学生が気の毒」,「医学教育の先進校がすべての面ですぐれているわけではない。マックマスターやマースリヒトはPBL(問題基盤型学習)では頑張っているが,臨床教育は非常にお粗末」,「英国の卒前教育は大変すぐれているが,卒後教育では米国に遅れをとっている」,「ヨーロッパの医学教育で,英国に追いつこうと,がんばっているのはオランダとデンマークだ。ドイツはやっと,新しいスタートを切った」などなど参加者から本音の発言が飛び出してきて興味が尽きない。この席で筆者は,日本が近く卒後研修必修化を開始することを話したら,「このスピードの時代に,学生時代と同じことを,卒後にもう1度やるなんて,日本には『時間が何よりも大切』というコスト意識がないのか」と驚いた表情を示した。先進国の多くは,ストレート研修の時代になっている。筆者は,日本の新しいモデルコアカリキュラムの医学生の臨床実習期間が,最低2年間という先進国レベルに達していないことを非常に残念に感じた。医学教育における質の重視-アウトカムの評価
世界でも一様に医学部の教師は,誰もが自分の講義や教育方法がベストだと信じている。これを修正するために英国では,医学部長が新任教授の就任直後に授業風景を参観するという。そのため医学部長は,よい教育をしている医師をリクルートしてくることが重要な任務となっている。医学部におけるよい教師とは,教育をよい内容,よい方法で行なうことで,“QUESTS”(Quality,Utility,Extent,Strength,Target,Setting)のクライテリアを考慮すべきという。医学部全体の査察は,GMC(General Medical Council)が5年ごとに,徹底したチェックを施行する。スコットランドではさらに,3年ごとの同地方特有のチェックが重なる。この査察は厳しく,英国では医師不足にもかかわらず,数年前にはスコットランドの医学校が廃校に追い込まれた。
Outcome-Based Medical Education(OBME)は,ダンディー大学からスタートし,スコットランドの全医学部に波及し,さらに欧州や米国に拡がりつつある。OBMEでは知識,技術だけではだめで,態度に重きが置かれる。つまり,「The doctor as a professional」が強調される。よい医師づくりのためには,それぞれ「どんなCBT(コンピュータ・ベースド・テスト)」,「どんなOSCE」,「どんなPBL」がよいのかを絶えず検討する。12のOBMEが定められ,これには「How the doctor approaches their practice」における3つのアウトカム,「What the doctor is able to do」の7つのアウトカムが含まれている。わが国のカリキュラムでも医学部6年生の終わりに何ができるようになっているか,というアウトカムを学生に示すことは重要であろう。
医学教育における新しい評価-MCQの終焉とポートフォリオ評価の時代
教育は,そもそもその評価がなければ,「Teaching without testing is like cooking without tasting」と言われる。よい評価は,学生にとり,学習へのよい動機づけになる。わが国でも医師国家試験や共用試験でMCQ(多肢選択試験)やOSCEが導入されているが,英国ではすでにMCQの時代は終わりつつある。英国のロイヤルカレッジは,MCQの不使用勧告を出し,今後はEMI(Extended Matching Items=MCQのRタイプともいう)を勧めている。その理由は,(1)MCQは問題作成が難しくよい問題が得られにくいこと,(2)MCQは断片的すぎて,統合型教育の評価には不適切である。これらの点でEMIの方が優れているという。米国からの参加者は「米国でもMCQを中止する方向で努力しているが,まだAタイプとワンベストが残っている」と述べた。
現在欧米のカリキュラムで強調されていることの1つは,プロフェッショナリズムである。プロフェッショナリズムは,CBTやOSCEでは評価できない(図)。そのため,英国では5年間の医学部(内,3年間が臨床実習)で4年生の終わりにEMI,OSCE,CRQで評価し,卒業試験ではポートフォリオ評価を外部よりの評価者とともに施行している。そのため,医師国家試験は行なっていない。米国でも医師国家試験にCBT,OSCEに引き続き,ポートフォリオ評価の導入を準備中であるという。
OSCEとポートフォリオ評価の医学教育への導入は,Harden教授の考案によるもので,ダンディーが世界の医学教育を牽引していることを実感した2週間であった。
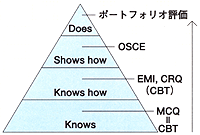 | 図 米国のDr. Millerが1990年に提案した能力ピラミッドとその評価を示したもの。ピラミッドの上を評価するほど,より本物の評価となる(Miller GE. :Acad. Med, 1990を修正)。単に知っている(Knows),どのようにするかを知っている(Knows show)はCBTで,どうするかを示す(Shows how=competence)はOSCEで,実際に行なっていること(Does,パフォーマンス,プロフェッショナリズム)はポートフォリオで評価する。 |
(註)ポートフォリオ評価:ポートフォリオとは元来「紙ばさみ」のこと。ポートフォリオ評価とは,紙ばさみに挟み込む資料(期間中に学習者が作成した学習記録だけでなく,例えば学生が学会などで発表したポスター展示やメモなど,一切合切が含まれる)を用いて,学習者の自己評価,教師から学習者への評価を行なう。また学習者にどのようなポートフォリオを作らせたかという点で教師への評価も可能である。知識はCBTで,スキルはOSCEで評価できるが,1回きりの試験という限界があり,実際のパフォーマンスの実力はポートフォリオでしか評価できない。医師国家試験に導入する場合にポートフォリオの客観化,コンピュータ化が必要であろう。
