MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


これこそ待望のWeb検索・活用のガイドブック
保健・医療者のためのWeb検索・活用ガイド中山和弘 著
《書 評》坂本直弘(米子医療生協弓ヶ浜診療所)
この1冊で,インターネットが自由自在
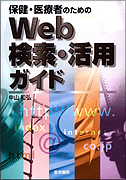 できる限り容易に理解できるよう,わかりやすく過不足なく説明した良書である。特筆すべきは,入門者にもわかりやすい「上級書」だと言うこと。
できる限り容易に理解できるよう,わかりやすく過不足なく説明した良書である。特筆すべきは,入門者にもわかりやすい「上級書」だと言うこと。
膨大な情報の中から自分に必要な部分を整理する,このノウハウのすべてを著者は本書内にさらけ出している。
乱雑になってしまった情報の山は,この本があればきれいに整理できる。皆さんは,こんな思いはないだろうか。わが家を放り出して,自分にとっていいものだけを集めた別宅がほしいと。Web検索において,本書があれば可能なのである。
盲点をついた内容であるがゆえ,ヘビーユーザーはもちろん初心者でも,最短でWeb検索上級者になれる。今やすべての人が,コンピュータ(インターネット)を自由に使いこなすことが可能なのである。
本書は,すべての人が待望していたものだろう。この1冊で,インターネットが使いこなせ,読み終えればなんでもできる!そんな1冊だ。
Web検索・活用の裏技がバッチリ
病院運営の日常業務上,Web検索に頼る機会が頻繁にある今日では,本書に挿入された画面の絵だけでもさらなるひらめきがある。さらに,本文中にカギ・コツがたくさんある。日々進歩,あるいは変化する保健・事務・医療において,本書はぜひ必要である。著者の本文より偲ばれる優しさと情報収集アンテナが高性能だというとこから,本書が完成できたのだと思う。医学書も包括したWeb検索・活用ガイドだ。本書名は「保健・医療者」とあるが,その範囲にとどまらない。それ以上にもったいない気さえする(出版社には申し訳ないか)。
読み終えた本書を眺めてみると,目次がいかにも初心者向け風(?)でよくない。ところが,本文は裏技集である。
第2章の「役立つWebサイトはあるのか」は,論文を書こうとしている時,さらに日々の日常業務でも役立つ。
第3章のC「さらなる検索テクニック」は,必需品として活用させていただいている。
第4章は圧巻である。インターネットをするすべての人に役立つ。
本書の案内について進んでいくと,1日で検索の達人になれ,保健・医療者なら,著者のリンク集がそのまま即活用できる。著者のサイト収集力に脱帽だ。
半日で本書にそってインターネット環境が完成し,Web検索の技術が飛躍的に進歩した今後,今日の半日の何倍もの時間が私の余裕の時間となるだろう。著者に感謝する。
A5・頁144 定価(本体1,800円+税)医学書院


初期臨床研修の取り組み方について懇切に解説
君はどんな医師になりたいのか「主治医」を目指して
川越正平,川畑雅照,松岡角英,和田忠志 著
《書 評》市村公一(東海大附属病院・研修医)
必修化される卒後臨床研修
 卒後臨床研修必修化が,いよいよ2004(平成16)年度から導入されます。これにともない,「年間入院患者100人に対し1人の研修医,または病床10に対して1人の研修医」という制度上の制約と,昨年実施された厚生労働省のアンケートでも明らかな医学生側のプライマリ・ケア医,家庭医志向の高まりから,これまで大半の研修医を受け入れてきた大学病院から大量の研修医が市中の研修指定病院にシフトすることが予想されています。しかし,個々の医学生にとって肝腎なことは,「全体の流れはさておき,自分はどこで,どんな研修を受けるか」でしょう。今までは,「外に出るといっても様子もよくわからないし,研修後の進路も不安だから」と母校の医局に入局するのが大勢だったものが,ストレート研修が禁止され,大学に残っても外に出てもスーパーローテーションで,プライマリ・ケアの基本的診療能力を身につけることが求められます。
卒後臨床研修必修化が,いよいよ2004(平成16)年度から導入されます。これにともない,「年間入院患者100人に対し1人の研修医,または病床10に対して1人の研修医」という制度上の制約と,昨年実施された厚生労働省のアンケートでも明らかな医学生側のプライマリ・ケア医,家庭医志向の高まりから,これまで大半の研修医を受け入れてきた大学病院から大量の研修医が市中の研修指定病院にシフトすることが予想されています。しかし,個々の医学生にとって肝腎なことは,「全体の流れはさておき,自分はどこで,どんな研修を受けるか」でしょう。今までは,「外に出るといっても様子もよくわからないし,研修後の進路も不安だから」と母校の医局に入局するのが大勢だったものが,ストレート研修が禁止され,大学に残っても外に出てもスーパーローテーションで,プライマリ・ケアの基本的診療能力を身につけることが求められます。
「どこで,どんな研修を受けるか」――卒後臨床研修必修化にともなって研修先の選定という問題に直面し,医学生は従来よりも一層真剣に将来進むべき方向を考えることになるでしょう。それも必修化の大きな副次効果かも知れません。
その研修先の選定について,しかし,現状では各病院の研修内容が情報として十分に提供されておらず,また医学生も日本では参加型臨床実習がやっと導入されはじめたばかりで,卒前において臨床現場に主体的に関わることが少ないため,ともすれば有名研修病院にいくことがすなわちよい研修を受けることだといった短絡的な見方も少なくないように感じます。
医師としての1つの理想像(「主治医」)を提言
ここにご紹介するのは,『初期プライマリケア研修』,『学生のためのプライマリケア病院実習』(ともに医学書院)を著し,多くの医学生の研修相談にのってこられた「若手医師の会」の川越正平先生らが,これまでの経験をふまえて,全国の医学生・研修医に「主治医」という医師としての1つの理想像を提言するともに,卒前に体験すべきことを説き,初期臨床研修のあり方とそこで研修医が学ぶべきポイントをまとめられた本です。ここで「主治医」とは,「人と人とのつながりを大切にし,疾患の種類によらず心身各部の診療の求めに応じ,継続して患者さんの生命と生活に責任を持ち続ける医師」と定義され,家庭医やプライマリ・ケア医にも共通し,かつその本質をなす概念であるとしています。私個人としては,「家庭医」,「プライマリ・ケア医」,「かかりつけ医」そしてこの「主治医」と,そのめざすところの大半はオーバーラップするであろうに,あえて別の旗印をかかげることには,広く市民の理解を得てその輪を拡げる上でマイナスだと考えるのですが,本書に説く「主治医」のあり方に強い共感を抱く医学生が少なくないことは,容易に想像されます。
本書は,第2章から第4章で卒前に臨床現場を経験することの重要性と卒後研修のポイント,そして臨床の場に出る者としてわきまえておくべき常識や心得を説き,第5章「どこで,どんな初期研修をするか」で大学病院と一般病院の特徴,その長所・短所と,きたるべき研修システムの理想像を説いています。プライマリ・ケア医志向か専門医志向かにかかわらず,これから臨床研修を受けるすべての医学生に,最低限この第5章だけは読んで心得ておいてほしいと思います。研修先選びで後悔しないために。
A5・頁184 定価(本体1,800円+税)医学書院


これからの解剖学教育に一石を投じた教科書
一目でわかる解剖学山内昭雄,桜木晃彦 訳
《書 評》足立和隆(筑波大体育科学系・応用解剖学)
医学部や歯学部の学生,さらにコメディカル分野の学生にとって,人体解剖学はかなり難物の専門科目である。とにかく暗記しなくてはならない解剖学用語がたくさんあり,さらに人体の基本構造や機能に関しても詳細に理解し,学習する必要がある。ところが医学の発展にともない,ほかにも覚えなくてはならないことが急激に増え,解剖学に費やす時間も現在は一昔前とは比べものにならないほど限られてきている。このような状況の中では,効率のよい解剖学の学習法の確立が学ぶ側にとっても,また教育する側にとっても重要な課題となっている。しかし,これに対して思い切った取り組みがなかなかできないのが現状である。本書の原著者はこの課題に果敢に取り組み,本書はこれからの解剖学教育のありかたについて一石を投じた最初のものといえる。
本書のオリジナルである英語版は,昨年刊行されたばかりの新しいもので,著者は外科医と解剖学者である。そのため,一般的な臨床外科の視点がかなり考慮されているが,それとは関係ない他の部分,例えば脳の解剖などといった内容は,バッサリ落としているというのも特徴である。
気楽に読めて,文字通り「一目でわかる」解剖学教科書
本書は184頁しかないが,内容は薄っぺらなものでは決してなく,一般臨床外科に関する解剖学分野の国家試験対策用テキストとしても十分な内容をもっている。もちろん,一般外科以外の整形外科やコメディカルのOT,PT,鍼灸,マッサージ,柔道整復,カイロプラクティックなどを専攻とする学生にもオススメである。また,これらの臨床家にとっても知識を整理するのに役立つであろう。構成は,解剖学の教科書としてはめずらしい臨床に適した局所解剖学となっており,全部で72章ある。各章は基本的に見開きの左頁が図,右頁がその説明となった2頁構成である。図はカラーを多用してたいへん見やすくなっている。例えば,上・下肢の血管分布や神経分布の説明は,カラーの図と明確な説明文によって大変わかりやすい。まさに原著のタイトルにもあるが,「一目でわかる(at a glance)」内容である。しっかりとした訳にかんしても,監訳者,訳者の努力がうかがわれ,気楽に読める解剖学の教科書として推薦できる。
A4変・頁184 定価(本体3,800円+税)MEDSi
