| 連載 第22回 | 再生医学・医療のフロントライン | ||
再生医学の倫理的側面
| |||
ヒトES細胞の倫理問題
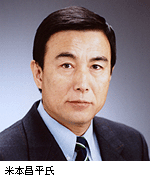 1990年代以降に,急速に発達した再生医療はまた,生命倫理の問題に新しい課題をもたらした。その中で現在,議論の核心にあるのは,「ヒトES細胞(embryonic stem cell)」の問題である。この問題を理解するには,欧米におけるヒト胚研究の論争をふり返ってみる必要があり,さらにそれはキリスト教圏における人工妊娠中絶(中絶)の賛否という大きな政治問題に連なっている。
1990年代以降に,急速に発達した再生医療はまた,生命倫理の問題に新しい課題をもたらした。その中で現在,議論の核心にあるのは,「ヒトES細胞(embryonic stem cell)」の問題である。この問題を理解するには,欧米におけるヒト胚研究の論争をふり返ってみる必要があり,さらにそれはキリスト教圏における人工妊娠中絶(中絶)の賛否という大きな政治問題に連なっている。
70年代は中絶の自由化が進む一方で,生命倫理学の成立期であり,伝統的に「どこから人間が始まるか」は,生命倫理の最重要課題の1つとなってきた。78年に初めて体外受精児が産まれると,女性の体外に存在する受精卵は人間か否かという問に直面することになった。この問題に対して欧州主要国は,90年代初めに生殖技術法を制定した。ヒト胚研究とその延長線上にあるES細胞の研究規制はこの枠組みの下で行なわれてきている。これに対して米国は,中絶の賛否で国論が二分し,国として生殖技術規制法を成立させることができず,連邦研究費助成を認めるか否かが唯一とりうる政策となっている。
ES細胞の倫理問題は,樹立のためのヒト胚の破壊を許すか,研究目的での体外受精によるヒト胚の作成を許すか,人間のクローン作成に直結しかねない治療的クローン胚の研究を認めるか,が当面する課題である。これをすべて国の厳格な管理下で進めようとしているのがイギリスであり,米国は厳格な倫理基準を満たしたES細胞株を用いる研究にのみ連邦研究費助成をつける政策をとっている。フランスは関連する法律の見直し中でモラトリアムの状態にあり,ドイツは原則禁止で,ES細胞の輸入を例外的に認める法律を成立させた。日本は,不妊治療で使われなかった胚から得られるES細胞の樹立と輸入を認め,個別に認可を始めている(表)。
| 表 ES細胞研究の規則 | |||||||||||||||||||||||||
|
再生医療一般の倫理的課題
ただしES細胞や治療的クローン胚の研究成果が,実際に再生医療として応用されるまでにはまだ時間が必要である。当面する再生医療の倫理問題として重要な点は,20世紀に確立した生命倫理の基本原理に対して,再生医療の進歩が修正を迫る事態をもたらしているところにある。そもそも生命科学における倫理規制は,74年に米国で成立した国家研究法が事実上のモデルとなってきた。この法律の成立は,人体実験の被験者の保護を目的に国家が研究現場に法介入する歴史的な事件であった。この法律によって,各研究施設は施設内審査委員会(IRB)を置き,人体実験やこれに準ずる研究は事前にIRBで審査されることになった。そしてそこでチェックを受けるのがインフォームド・コンセントの手続きである。
だがここまで肉体が細分化され,また再生医療のようにその一部を取り出して操作し肉体に戻す事態が常態化してくると,伝統的なインフォームド・コンセントだけに力点を置く倫理規制では意味をなさなくなってくる。日本での再生医療の議論は,本人の幹細胞を体外で培養する自家移植のイメージが強い。この場合ですら安全性がきわめて重要であるし,操作や培養条件によっては異種移植に近づくことになる。加えて,さまざまな人体組織の治療利用が急速に普及してきており,再生医療の実用化のためには,人体組織全体をどのようなものと解釈し,どう扱うのかについて,国際的な共通ルールを確立する必要が出てきている。
日本が抱える課題
この点でわが国が抱える問題は小さくない。ES細胞問題に限ってみても,これまで日本では,ヒト胚の扱いについて大規模な議論をしてきてはおらず,その規制方法や倫理的議論そのものが米国のコピーに近いことであることである。米国での議論には,中国やインドなど発展途上国からのES細胞の供給に対する問題意識が希薄であり,南北間の価値観の落差という問題に,いずれ日本も直面することになる。しかしさらに重大なのは,日本には臓器移植法に定められた主要臓器以外の人体組織の扱いに関する法律がなく,治療や研究への利用についてのルールが未整備であることである。再生医療の領域では,組織幹細胞の利用が先に実用化されるのは確実であり,であるならば臓器移植法の対象とならない皮膚・骨・軟骨・腱・血管・心臓弁などの扱いを包括的に定めた人体組織法の制定が不可欠である。現在米国では,人体組織を加工して医療や研究用に提供する企業が多数存在し,そのカタログが日本に入ってきている。われわれは,人体という「内なる自然」をどう意味づけ,その利用をどこまで認め,国内調達をどこまで考えるのか,という巨大な問題に直面している。
| ●本連載は,今回をもって終了いたします。ご愛読ありがとうございました。
(週刊医学界新聞編集室) |
