21世紀に求められる「生命科学の知」を語る
『医学書院 医学大辞典』発刊によせて
 井村裕夫氏 (京都大学名誉教授) |  伊藤正男氏 (東京大学名誉教授) |  高久史麿氏 (自治医科大学学長) |
■20世紀から引き継いだもの
前半は感染症,後半は加齢に伴う疾患の時代
伊藤<司会> 前世紀の末には,新しい世紀を迎えるに当ってさまざまな反省や総括がなされましたが,21世紀を迎えてすでに3年が過ぎようとしており,今日,われわれの予想もつかなかったことも縷々見受けられます。そこで本日は,「21世紀に求められる『生命科学の知』を語る」と題しまして,改めてもう一度20世紀を振り返り,その上で21世紀を展望してみたいと思います。
申し上げるまでもなく,私どもの学生の頃から比べると,現代の生命科学は大きくさま変わりしました。まず最初に,いかに20世紀後半の進歩が激しかったかということを,先生方の体験を踏まえて振り返ってみたいと思います。いかがでしょうか。
井村 私と高久先生が医学部に入学したのはちょうど20世紀の真ん中で,1950年です。伊藤先生はその少し前でいらっしゃいますね。
伊藤 私は1949年です。
井村 当時は卒業して医師になっても,現代と比べると診断面もまだ比較にならないほど曖昧でした。
高久 当時,私は冲中内科に入りました。その頃の冲中内科は神経が主流でしたから,カンファレンスで「脳卒中か脳梗塞か」ということについて侃々諤々と議論していました。今ならば,CTを撮ればすぐにわかることですが……(笑)。
当時は,もちろん超音波もなく,X線写真だけです。
井村 そういう点では,画像診断というものも臨床的に決定的に大きな要素になりましたね。また,画像診断と同様に,生化学的診断も格段に進歩して,精確度が増しました。
高久 私たちが卒業した頃には,まだ中央検査システムがなかったですね。
伊藤 ご指摘のように,検査や診断の技術は格段に進歩しました。ただ,治療面の進歩は,最近になって追いついてきましたが,相当ペースが遅かったですね。
高久 私の専門の血液学の分野で言いますと,私が入局した頃は,急性白血病に対する有効な治療薬はほとんどなく,現在のように完全寛解になる例はきわめて稀でした。
井村 実は,私は医師になって2例目の症例が糖尿病でした。当時はインスリン以外にないのです。軽い糖尿病ですと,メゾ蓚酸カルシウム,メゾキサンをやりましたが効かないのです。
経口糖尿病薬は出ていましたが,日本にはまだ入っていませんでした。まもなく,「ラスチノン」が入ってきて,初めて血糖が下がるということがわかり,その頃から糖尿病治療もやや本格的になってきたわけです。それまでは,中等度以下の糖尿病には治療法は食事療法だけでした。
高久 運動療法は行なわれていたのですか。
井村 あまり行なわれていませんでした。むしろ当時は,まだ糖尿病そのものがめずらしかった状況でした。急激に増えてきたのは,1970年代頃からですね。
伊藤 現在はアルツハイマー病が大きな問題になっていますが,それと同様に糖尿病も,昔はあまり問題にならなかったような気がします。
高久 アルツハイマー病と言えば,昔から日本にはアルツハイマー病の患者さんは少なく,血管性の痴呆がほとんどと言われていましたね。
井村 そうですね。そういう面では,20世紀の医学を大雑把に振り返ってみますと,前半は感染症の時代で,後半は加齢に伴う疾患の時代だと言えそうですね。
前半と後半では,病像がすっかりさま変わりしてしまいました。
高久 当時は,まだ結核病棟がたくさんありましたね。
伊藤 実は,私は高校生の頃に肺浸潤を体験し,大府の療養所に半年おりました。
それがきっかけになって,医学部へ入学する気になり,そして最初は結核研究会というグループに入って,ツベルクリンやBCGを手伝ったりしました。
「要素還元主義」を超えて
 伊藤 井村先生のおっしゃるように,前世紀の前半は感染症の時代,後半は加齢に伴う疾患の時代と言えそうですが,とにかく大きな変化のあった世紀でした。
伊藤 井村先生のおっしゃるように,前世紀の前半は感染症の時代,後半は加齢に伴う疾患の時代と言えそうですが,とにかく大きな変化のあった世紀でした。
現代はとりわけ遺伝子が象徴的ですね。「ヒトゲノムプロジェクト」が遺伝子を読み終えたわけですから。
井村 2001年は高峰譲吉のアドレナリン発見100周年ということで,アメリカで「Hormone Discovery」というシンポジウムがありました。
そこで,高峰譲吉のことを調べてみましたが,彼の研究はアジソン病あたりから始まるのです。アジソン病とは色が黒くなり,やせ衰える病気で,副腎がやられて起こるということがわかり,間もなく動物で副腎摘出実験が始まりました。副腎を取ると死ぬので,副腎に何かあるのではないかと考えられてきて,やがて副腎から昇圧物質が見つかるのです。
高峰先生はその頃研究に入り,あっという間に結晶を取ったのですが,運がよかったのは,エフェドリンとアドレナリンが似ていることです。ほとんど同じような方法で結晶化できたわけです。
私には,この高峰先生の研究がかなり象徴的に20世紀の学問の流れを語っているように思います。というのは,生理現象や病気を起こす物質を追究して,分子レベルへ入って行き,さらに遺伝子へ進むという要素還元主義で研究を推進してきたわけです。伊藤先生がおっしゃった,ヒトゲノムプロジェクトというのはまさにその極致とも言うべきことで,人間の身体を造っている要素をすべて洗い出そうということです。ところが,これが意外と言ってよいほどわかりませんね。
高久 むしろ本質的にはタンパクですね。
井村 そうですね。ですから,今度はもう一度遺伝子から組み立てていかなければいけない。遺伝子からRNA,タンパクにいき,そのタンパクが糖や脂肪の修飾を受けて最終的に細胞ができ,細胞からシステムになっていくわけです。
21世紀の生命科学は,ある程度20世紀の生命科学の逆方向を進むのではないかという気がします。
伊藤 たしかにそうですね。
日本人の功績
伊藤 ところで,あらためて日本人の功績を考えてみますと,20世紀に大きな貢献をしたのは野口英世と,先ほど井村先生からお話のあった高峰譲吉,そして北里柴三郎だそうです。高久 タールを使って癌を作った山極勝三郎先生のお仕事は,生きておられれば当然ノーベル賞を受賞してもおかしくない業績だと思いますね。
井村 そうですね。ノーベル賞を受賞しても不思議はありません。化学発癌を実験的に証明されたのは初めてですから。
高久 「藤波肉腫」の発見で有名な,藤波鑑先生もそうですね。
井村 藤波肉腫の発見はラウス(Peyton Rous)とほぼ同じ頃で,両方ともニワトリから発見された肉腫です。
ご存知のように,ラウスはがん組織を磨り潰し濾過した液によって,ニワトリにがんを感染させることができるのを発見したのが1911年で,ウイルスによってがんが起こることを示唆した最初の実験でした。
この年1911年には,先ほどお話が出ました,野口英世が梅毒スピロヘータの培養を発表しています。野口英世の研究が世間の華やかな脚光を浴びたのに対し,同じロックフェラー研究所にいたラウスの研究は誰にも認められず,次第に下火になったのです。
ただ,ラウスの肉腫の原因は,1970年代に明らかにされ,「src(サーク)」と呼ばれるがん遺伝子が発見されました。ラウスはこのため,発見してから50年以上経った1966年にノーベル賞をもらっています。藤波さんはその頃には亡くなっていますから,対象にもなり得ませんでした。
「藤波肉腫」と文化の保存
井村 藤波先生は東大を出てから京都大学に教授としていらしたのですが,出身は愛知県です。愛知は名古屋コーチンで,ニワトリの本場でしょう?(笑)。藤波肉腫に関してはおもしろいエピソードがあります。そのsrcが見つかってから,藤波肉腫の原因遺伝子は何かを追究しようということになったのです。
これは花房秀三郎博士が中心になってやろうとしたのですが,藤波肉腫が手に入らない。というのも,日本にはもう残っていなかったのです。そこでいろいろ手を尽くして探してみると,遥か遠くイギリスのミルヒルの研究センターで見つかった。これを花房先生が取り寄せて調べてみると,fps(フプス)というsrcとは異なる癌遺伝子だということがわかったのです。
高久 fpsというのは,藤波先生の名前からでしょうか。
井村 そう思います。このおもしろいエピソードを京都で開催された日本癌学会の時に初めて聞きました。
高久 花房先生がご自身で話されたのですか。
井村 いえ,花房先生は来られませんで,豊島久眞男先生に話してもらいました。
生物資源も大事にしておかなければいけないですね。イギリスに保存されていたから良かったものの,そうでなければまったく不明になってしまうところでした。
伊藤 思い出しましたが,湯川秀樹先生が仙台へ来た時,本川弘一先生が日本で最初に脳波をとったのですが,その増幅器を見せろと言われて,お弟子さんがないと言うと,「なぜとっておかんか!」と怒られたというエピソードがあります(笑)。
やはり,そういうものを大事に保存する精神がないのですね。
井村 そのへんはやはりイギリスはたいしたものですね。
高久 イギリスは特にそうですね。
伊藤 それから,サイエンスというのはおもしろいもので,どこかで新しいものの発見が起こると,周りにも同じような気運があるのですね。
その点では,日本は情報の側面においても大変に損をしてきました。
高久 情報の受信ということだけでなく,発信・発表面でも損をしています。
「科学-終りなきフロンティア」
 井村 アメリカという国がすごいと思うのは,第二次世界大戦の終わる1年前に,戦後の科学研究をどうするかということをルーズベルト大統領が諮問しているのです。
井村 アメリカという国がすごいと思うのは,第二次世界大戦の終わる1年前に,戦後の科学研究をどうするかということをルーズベルト大統領が諮問しているのです。
戦争に科学者を動員して,すでに勝利を確信したのですね。そこで,ヴァネヴァ・ブッシュというMITの教授が委員長になって「科学-終りなきフロンティア」という報告書をまとめたのです。これがその後のアメリカ政府の科学技術政策の指針となりました。
その報告書は,日本が敗戦する1か月ぐらい前に大統領に渡っているのですが,それが「戦後もアメリカの科学研究は引き続き政府が投資すべきである」と言っている。科学は果てしないフロンティアだから,投資すれば,それが社会にも産業にも役立つという主旨の有名な報告書です。
NSF(National Science Foundation)は,それを受けてできたわけですが,NIH(National Institute of Health)の予算もそれから増えていますね。
高久 NIHを作ったことは,アメリカの生命科学を推進する大きな原動力になりましたね。
井村 NIHは,もとはニューヨークの検疫所でした。港ですから検疫をしていたのですが,それを研究所にして移転したのです。1950年からずっとアメリカは,基礎研究に投資してきたので,それが生きてきて70年代から80年代になって大きな業績が出てきたのですね。
伊藤 それは今でも一貫していますね。ヒトゲノム研究におけるHUGO(The Human Genome Organisation)などがそのよい例でしょう。
生命科学の研究方法の変化
井村 HUGOができた頃から,生命科学の研究方法が相当変わってきたように思います。従来とは異なって,大きな工場のようなものを作り,そういうところで推進しなければ到底成果が上がらないようなプロジェクトが出てき始めました。
ヒトゲノムプロジェクトは,まさにその最たるもので,イギリスのサンガーセンターも,アメリカのセントルイスのヒューマンジェノムセンターも,300-400人のテクニシャンが働いており,機械が100台ぐらい動いています。まさに工場そのものです。日本では,そういうシステムがはじめにうまくできなかったですね。
伊藤 HUGOができた時,日本が拠出金を出さないので,当時の委員長のワトソンが怒って「日本の技術者には情報を出さない」と言って大騒ぎになったことがありました。
松原謙一先生が相当困っていましたが,今から考えると,それほど多額の資金でもないのですが,そういうことに政府資金を拠出する仕組みがなかったですね。
井村 外国より立ち上げが2-3年後れていると思います。それが最後まで尾を引いて結局6%しか貢献できなかったのです。
■21世紀に求められる生命科学の「知の統合」
「ポストゲノム」と「再生医療」
伊藤 21世紀初頭の現代の生命科学は複雑な様相を呈しているわけですが,今後どのように発展していくのか。今日のテーマでもある「知の統合」という話をしたいのですが。
高久 やはり,ゲノム医学と再生医療が最も大きなテーマになるでしょうね。
井村 そうですね。ポストゲノムの医学と再生医療。これが2本柱でしょう。
高久 最近は,再生医療とゲノムを組み合わせた研究が動物実験のレベルでは行なわれていますね。
井村 人間の遺伝子の数は比較的少ないわけで,結局,1つの遺伝子を多様に使っているのです。そうすると,発生の過程で思わぬ遺伝子が重要な役割をしていることになります。
例えば,発生の過程でどういう遺伝子がどう働いているのかを追いかけていかないと,ある目的の組織を作りたいといっても不可能になります。今は,偶然できているにすぎません。そうではなく,例えばある幹細胞から血管や神経を作る時に,どのような遺伝子を発現させればできるのか,というロードマップを作らなければいけないと思います。
それによって再生医学は,大いに発展するでしょう。そうなるとやはりゲノム研究が大事です。発生の過程でどういう遺伝子が発現しているかということを追いかける仕事が急速に広まっています。例えば骨髄の細胞とか,胚性幹細胞から血管ができるとか,血球ができるまでにどういう遺伝子がどのように変わっていくかというステップを追いかけていく。したがって,ゲノム医学と再生医療は深い関係にあります。
高久 それから,幹細胞の中に遺伝子を入れますと,いろいろなファクターを出します。骨髄中の細胞に骨形成蛋白(bone morphogenetic protein:BMP)の遺伝子を入れると骨ができるから,脊椎の障害に利用できます。
井村 ご指摘のように,遺伝子治療を組み合わせた再生医療は,今後の大きな領域の1つでしょう。
高久 幹細胞は重要なファクターですね。
井村 そうですね。どのようにして幹細胞を増やすか。そして,どのようにして望む細胞に分化させるのか。その辺りが重要なポイントになります。その面で,ゲノム研究が役立つだろうと思います。
先端医療とインフォームド・コンセント
高久 そうですね。ヒトの胚性幹細胞の場合,イギリスはかなり積極的に進めていますが,アメリカでは宗教的な背景があってなかなかできません。一方,日本では宗教的な背景とは別に,反対する人たちがいます。井村先生は総合科学技術会議でご苦労されておりますが,いかがでしょうか。
井村 そうですね。抵抗は強いです。それとは別に日本ではなかなかインフォームド・コンセントが取れないので困っているという話を聞きますね。
伊藤 それが一番難しいでしょうね。
高久 日本人は一般に,科学に対する理解が少し乏しいように思います。新しいサイエンスに対する過剰なアレルギーがあるようにも思います。
井村 そこまでに至る過程は異なりますが,臓器移植の問題とよく似ています。
ES細胞も余った受精卵を使うわけですが,なかなかインフォームド・コンセントが取れないと言います。
日本には今までそういう習慣が日常生活にはありませんから,「サインしてください」というと身構えられてしまいます。
高久 現在は,新薬の治験などでもすべてサインが必要ですから,やりにくくなっているようですね。
「再生医療」と「統合」
伊藤 再生医療と従来の医学,生命科学との相違点をひと言で言うとどのようになるのでしょうか。井村 例えば,心筋梗塞で死んでしまった心筋を再生させようというもので,局所で傷害された臓器を再生することが中心になると思います。
ただそれ以外に,体外で障害した臓器を造って元に戻してやることができないかということが課題になっています。
高久 動物では膀胱や血管など簡単なものはできますが,複雑なものはまだまだ無理でしょう。
井村 再生医療の開拓者の1人であるバカンティというハーバードの教授が昨年の日本外科学会に来て講演しました。
私も講演を頼まれていたので聴きましたが,彼は現在,心臓をまるごと造るというプロジェクト進めています。
もちろん再生医学を使ってですが,まず冠動脈を造り,冠動脈ができたら,その冠動脈の間に心筋を植えるそうです。
「これは月へ人が行くよりも難しい」と言っていました(笑)。
高久 心膜も造る必要があるので大変でしょうね。
井村 彼の話に沿って言いますと,そこで「統合」ということが必要になってくるのだそうです。
というのも,数学者の助けが必要になるわけです。つまり,どのような血管が一番血液がよく流れるのか,ということを数学を使って計算し,それに合うように造っているわけですね。
将来的には,そういう方法で臓器が造れるようになることも,決して夢の話ではないかもしれませんが,まだ先のことだろうと思います。
「再生医療」の現況
 高久 現在実用化されているのは皮膚,軟骨,骨ですね。
高久 現在実用化されているのは皮膚,軟骨,骨ですね。
井村 あとはまだ実験段階です。しかし,脳などが再生できるようになれば,それを行なってよいのかということが新しい問題になるでしょうね。他人の幹細胞を脳に植えるのがよいかということはまた難しい問題でしょう。
高久 脳で対象になっているのはアルツハイマー病やパーキンソン病ですね。
パーキンソン病に対しては以前からドーパミン産生細胞の移植をしていましたね。
井村 そうですね。胎児の神経細胞や副腎髄質細胞を使っていました。
高久 現在話題になっているのが,日本で行なわれた治療ですが,本人の骨髄細胞を局所に注射して末梢血管の閉塞を治す治療法です。それから心筋梗塞の後,バイパスの手術をする時に本人の骨髄細胞や骨格筋の細胞を入れることも行なわれています。動物実験ではなく,すでに人間に対しても行なわれていて,これで血管ができたと報告されています。
それから,人工補助心臓を入れる時に,一緒に本人の筋肉を入れることも行なわれています。骨格筋の筋肉と心臓の筋肉が抗体で区別できるので,患者さんが亡くなった後に調べてみると,骨格筋の筋肉が心筋の中に入り込んでいたということも報告されています。
井村 アメリカで,女性の心臓を移植した男性を調べた報告がありました。
染色体で簡単にわかりますが,亡くなってから調べてみると,10%弱は本人のものになっている。それが骨髄から出てくるのか,あるいは大動脈あたりから連続的にくるのかわかりませんが,移植された心臓の中に本人の心筋ができている。血管はもっとよくできるそうですから,条件によっては一定の再生能はあるのでしょう。
高久 肝移植でも,そういうことがありました。骨髄からきているのでしょうね。
そのような点から考えて,人間には再生能力がかなりあるのですね。
井村 ある程度ありますが,今のところは限界があって,心筋では数%ぐらいです。
「老化」をめぐって
伊藤 ところで,高齢化社会という切実な状況がありますが,老化を遅らせるという問題に関してはいかがでしょうか。例えば,100歳になるとアルツハイマー病になる確率は90%以上と言われます。アルツハイマー病に関する研究で,その発症を抑えるとしても,自然老化によって脳は100年で3分の1ずつ減っていくので,計算上は300年経つとゼロになるわけです。
しかし,以前は神経細胞は減ると言われましたが,最近の新しい研究ですと,数は減っておらず,大きいものが小さくなるだけだそうですね。
高久 C. elegans(線虫)を使っての研究ですが,筋肉のほうが早く老化して神経は意外と長く残っているそうです。
もしも,人間にも同じことがあてはまるなら,加齢によって歩く力のほうが考える力よりも落ちるはずです。
井村 そうですね。ただ,不思議なことにC. elegansは同じ条件で育てても寿命には個体差があるそうです。ということは,偶然の要素が寿命にはかなり影響することになります。
高久 それもあるでしょう。しかし,逆にいわゆる「長寿家系」と言われるように,100歳まで生きた人の子どもは長生きするという報告もありますね。
伊藤 ひと頃,長寿地域というので,沖縄の高齢者の遺伝子を調べていましたね。
井村 老人研で100歳老人を調べた人の話では,どうも遺伝ではなくて,偶然ではないかという話でした。
環境因子とか,感染がたまたま起こらなかったという要素もあるのではないかと報告していました。
「アルツハイマー病」について
高久 アルツハイマー病に関して言えば,そもそも早期診断ができない。現在は症状が出てから初めて診断がついて,その後はただ進行を遅らせるだけですね。伊藤 そうですね。早期診断に関しては,画像法の進歩による診断が期待されているようです。発症の前段階で,少し記憶障害が起こるプロセスを把握することができ始めたようです。
高久 アルツハイマー病の発症頻度は,日本とアメリカは同じぐらいですか。
伊藤 年齢が同じなら頻度は同じです。ただ,日本では平均寿命が伸びるにつれて,爆発的に増えていくのが恐いですね。
特に,女性のほうが長生きだから,アルツハイマー病による痴呆患者は3分の2が女性で,アメリカでは100万人を超えているそうです。
今まで人類が遭遇したことのない状況ですので,そういう意味では,21世紀というのは,よいことばかりでもなくて,疾患の診断・治療・予防が進んでいく一方で,新しい問題がでてくる世紀であるのかもしれませんもね。
井村 特に高齢者の問題が大きいです。永久に生きることはできるはずはありませんし,また仮にそれが実現できたら,逆に人類は破滅するでしょう。最後の一定期間にどのように対応するのか,医学にとっても社会全体にとっても大きな問題ですね。
高久 そうですね。社会全体の問題です。
井村 しかも,少子化が並行して進んでいますからよけいに深刻ですね。
「工学」との融合
伊藤 突飛な発想だと叱られるかもしれませんが,最近,ロボットに期待するということを一生懸命言っているのです(笑)。お話を伺っていますと,「再生医療」という問題も,ある意味では「工学」との融合ですし,高齢化という社会全体の問題を考えるにしても,あながち的外れではないと思うのですが,いかがでしょうか。
高久 病院でも,患者さんに直接接するところ以外の部分では,ある程度ロボットを導入して対応しなければ難しい状況も生れるのではないでしょうか。
ダヴィンチという手術機械がありますね。心臓などもロボット手術でできるようですね。また,ロボットとは多少異なりますが,最近は内視鏡によって低侵襲の手術が可能になりましたから。
井村 私もダヴィンチを1度操作させてもらったことがあります。
こちらを相当動かしても,先端は1ミリか2ミリしか動かないから,細かい技術を必要とする手術には適していますね。遠隔手術も可能でしょうが,いまは細い血管の吻合などに使われているようです。
それから,センサー類の機能の開発が進んでいますので,例えば患者さんにセンサーをつけておけば,夜間の情報も集められます。何か異常が出たらすぐにブザーが鳴るようなしくみでできるから,ロボットを使わなくても,ある種の自動化が進むのではないでしょうか。
最近,「バイオニクス」という言葉が使われるようになりました。これは,バイオロジーとエレクトロニクスを融合させることですが,そういう分野はこれから相当発展していくと思います。
高久 日本人が得意とする分野ですね。
井村 それから,例えば,糖尿病の患者さんが家で血糖を測って,電話やインターネットで相談してインスリンの投与量の指示が得られるようになると,患者さんはわざわざ通院しなくても済むようになります。
「知の統合」を語る
井村 「知の統合」とよく言われますが,今世紀はさまざまな学問分野が一緒になって,いろいろな「統合」を試みる必要があるのではないでしょうか。ロボットやバイオニクスというのは,まさにエレクトロニクスの分野の人たちとの統合です。それ以外にも,最近言われだした「バイオ・インフォマティクス」もそのうちの1つです。例えば,タンパクとDNAの自動分析器と合成器の両方を作って,昨年の京都賞を受賞したフッド(L. E. Hood)は,現在は「システム・バイオロジー」を研究しているそうです。これは,マクロファージなどもコンピュータの中で再現する研究です。こういうことは,数学とコンピュータサイエンスとバイオロジーとの統合ですね。
それから,やはり昨年の京都賞を受賞したグロモフ(M. L. Gromov)という幾何学者は,現在はDNAの構造を数学で決定する研究を行なっているそうです。このようにして,数学,物理,工学,医学などさまざまな学問分野が一緒になって発展すると思います。
高久 そうなりますと,統轄する人が必要になってきますね。
井村 フッドは「統轄するのは,バイオロジストでなければいけない。なぜならば最も広い視野を持っているからだ」と言うのです。
高久 「バイオ・インフォマティックス」という言葉からしてそうですね。両方を知っていないと困りますから。
伊藤 「ニューロ・インフォマティックス」になるともっと複雑で,究極はヴァーチャルブレインのモデル,つまり人工的に脳を造ることをめざすことになります。これは大変ですね(笑)。
「統合」と「言語」:科学のインタープリター
伊藤 ところで,そうなりますと「共通言語」と言いますか,異分野の間を仲介する言語が必要とされるのではないでしょうか。井村 そうですね。医学の世界だけでも,分野が異なると使われている言葉がわからないことがあります。ましてや異なる分野の人たちの間では非常に難しい問題が生ずることがあると思います。
伊藤 特に発展の速い分野は,新しい言葉を次から次へと生み出します。
井村 しかも,最近はあまり意味のない符号のようなものがたくさんありますね。
分子の名前についても,P53やP73はまだいいとしても,やがて遺伝子分子の名前が大きな問題になってくるでしょう。
ところで,分子の数はタンパクレベルでは10万はあると言われています。遺伝子が3万余なのに,10万のタンパクができるのは,「オルタナティブ・スプライシング」があるからです。例えば,サイクロオキシジェネスでも,cox-1,cox-2の他に,最近,cox-3が見つかりましたが,それがオルタナティブ・スプライシングです。
そのようにして同じ遺伝子を使ってタンパクを3つほど造り得るので,3万余の遺伝子から10万のタンパクが造れるわけですが,それにそれぞれ違った名前がついているから,遺伝子の名前がもうわかりませんね。
高久 日本人が関係した研究がありましたね。私の記憶に間違いがなければ,確か脳に特有だけれども,他の部分にもある遺伝子を見つけて,その遺伝子を「nda」と名づけたのですが,これは「脳はどこにでもある」という日本語の略だと言うことだそうです(笑)。
もちろん動物のケースですが,最近のアメリカとの共同研究で,日本人に敬意を表してそういう名前をつけたそうです。
伊藤 学会などで若い人の発表を聴くと,最初からそういうものが出てきます。聴いている側がわかっていることを前提にしているから。
井村 特に若い人に,その分野のことを研究している人にしかわからない言語ばかりを,平気で使っている人が増えましたね。
高久 そういう状況を考える意味からも,これからは,いわば「科学のインタープリター」,科学の諸分野の間の架け橋となると同時に,社会との間の「通訳者」となる啓蒙者的な人の存在が必要になるのでしょうね。
伊藤 ご指摘のように今後は「科学のインタープリター」という存在が切望されることでしょう。
本日は長時間にわたり,幅広い,かつ貴重なご意見・知見をお聞かせいただきましてありがとうございます。
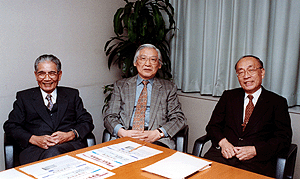
(おわり)


